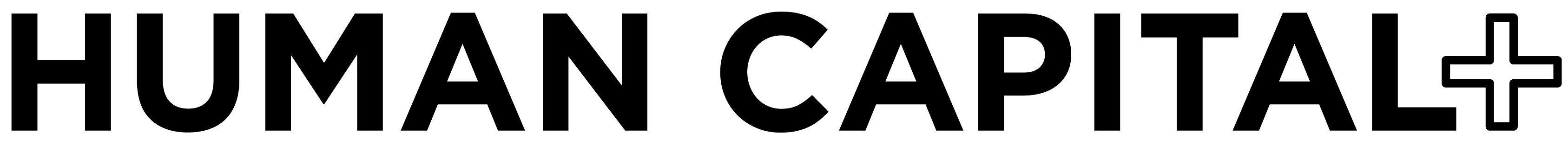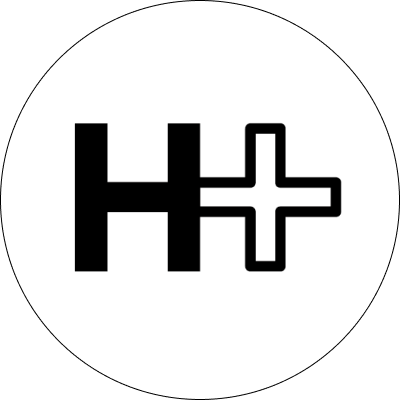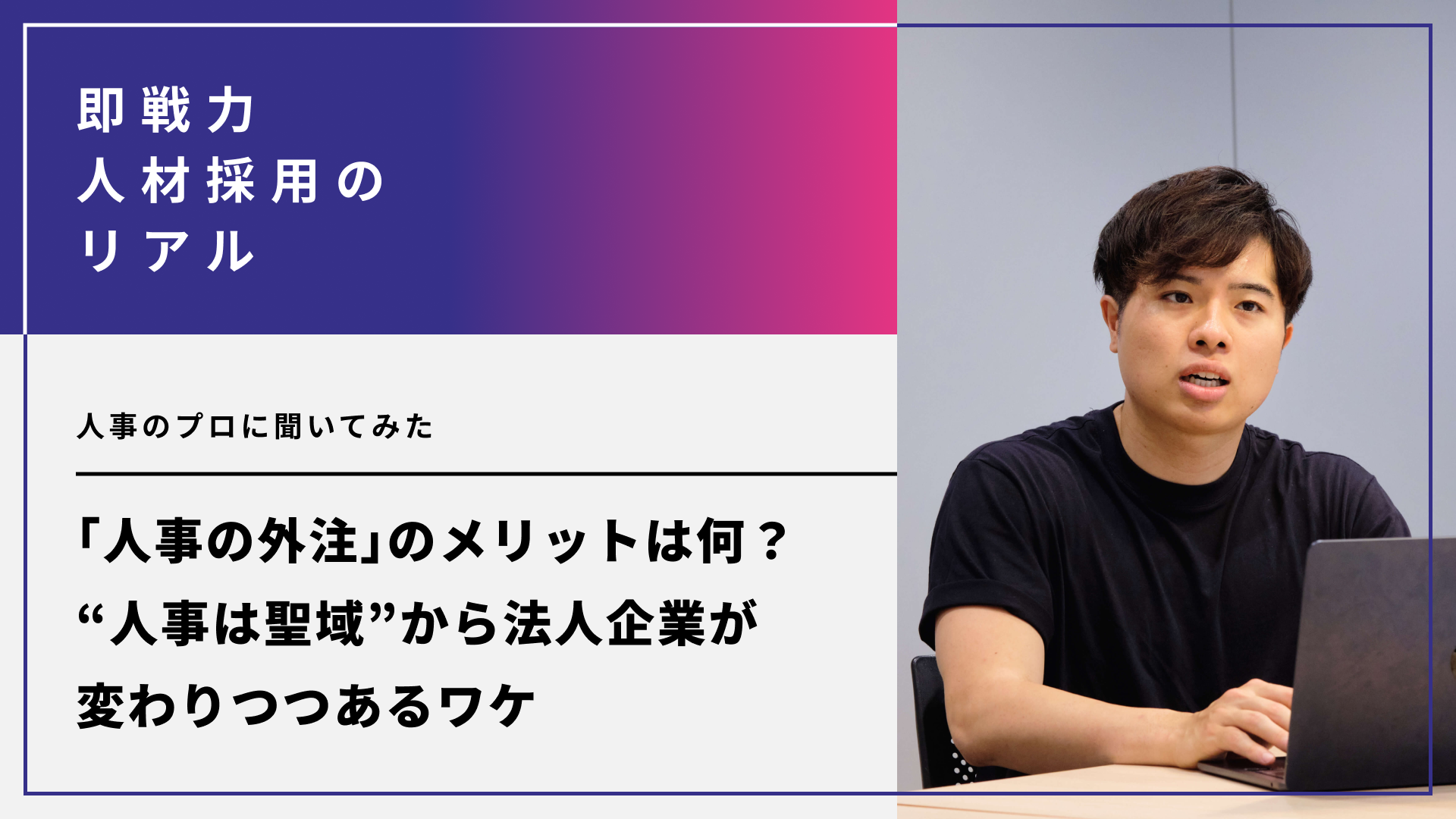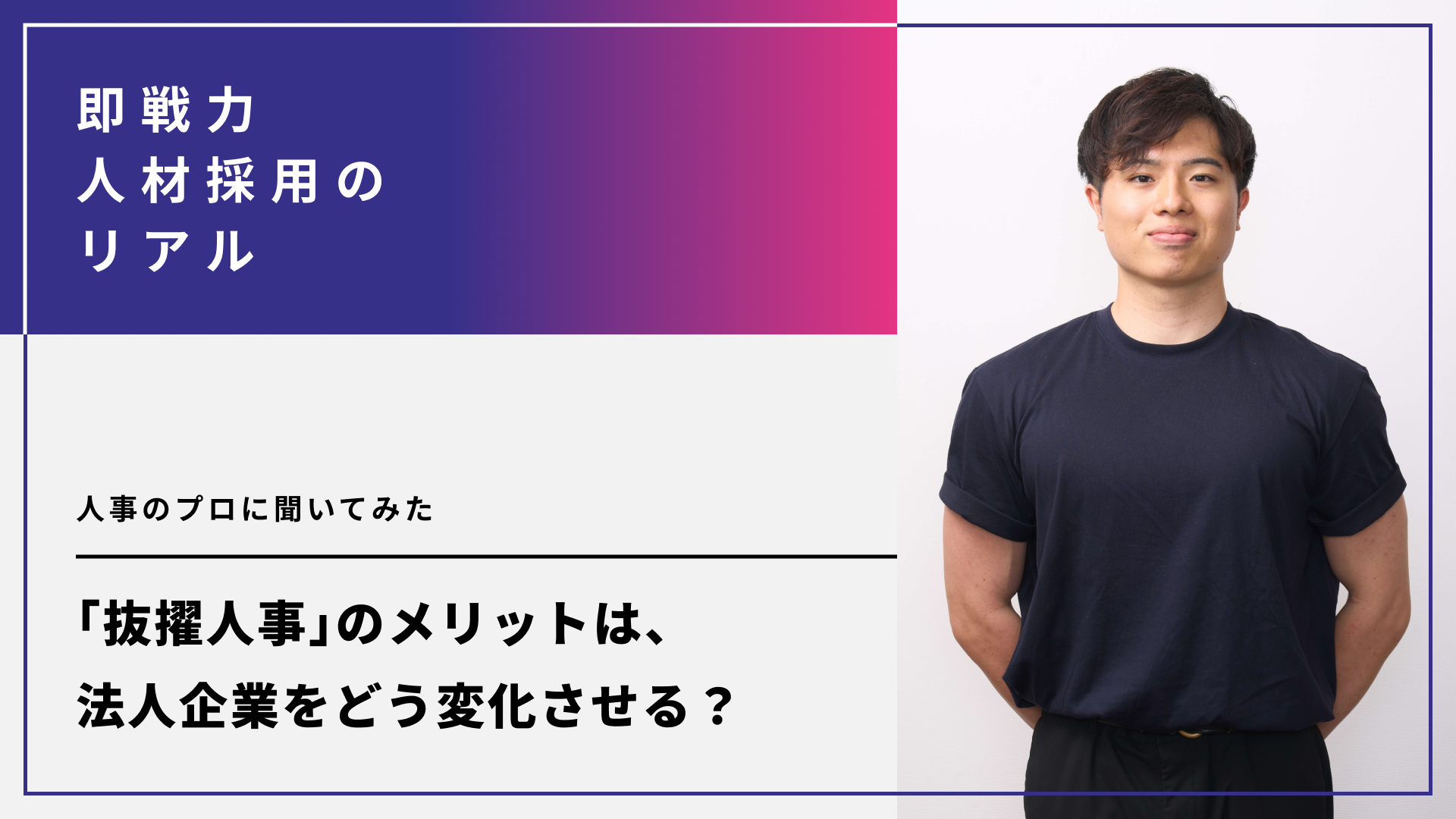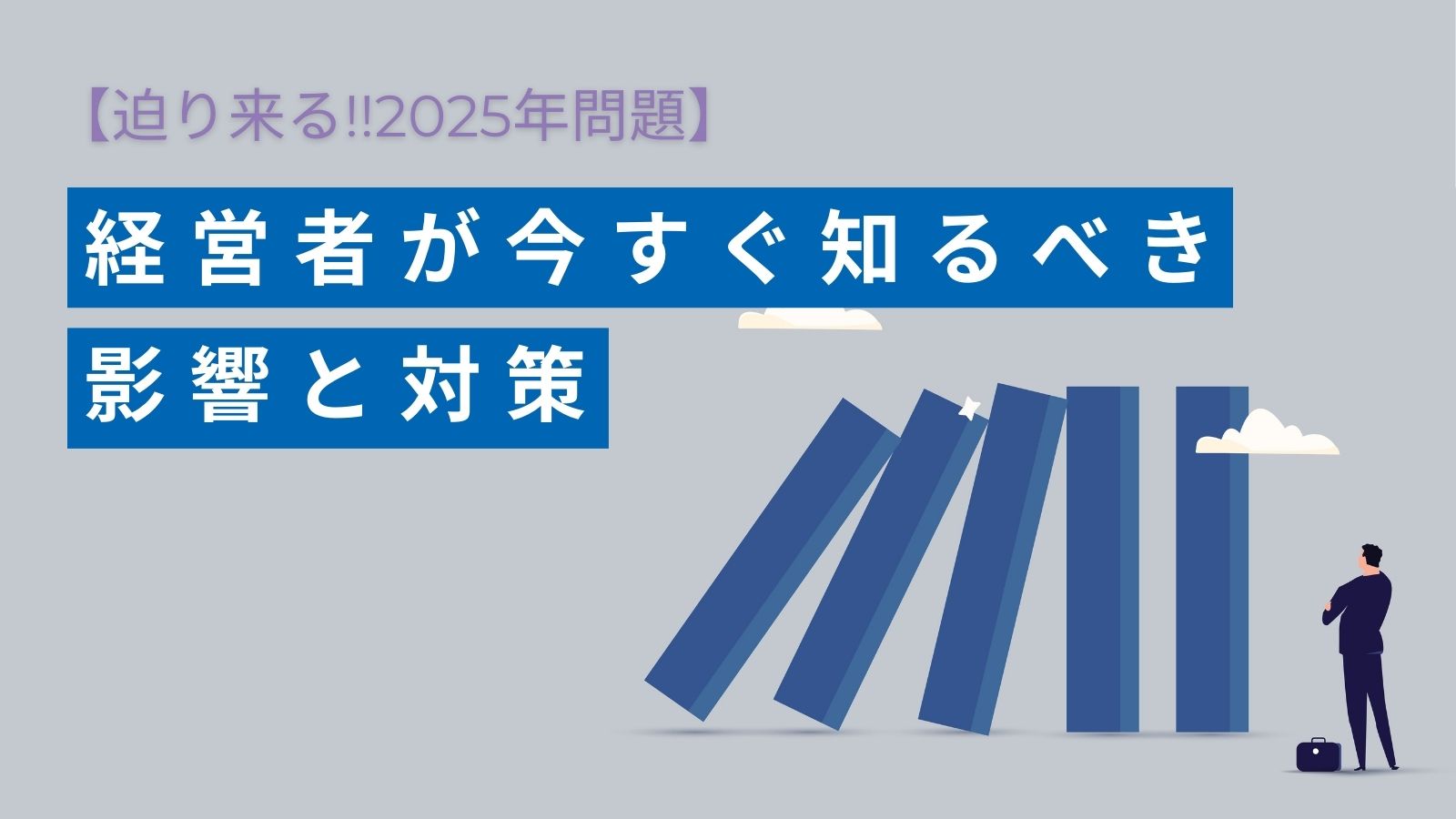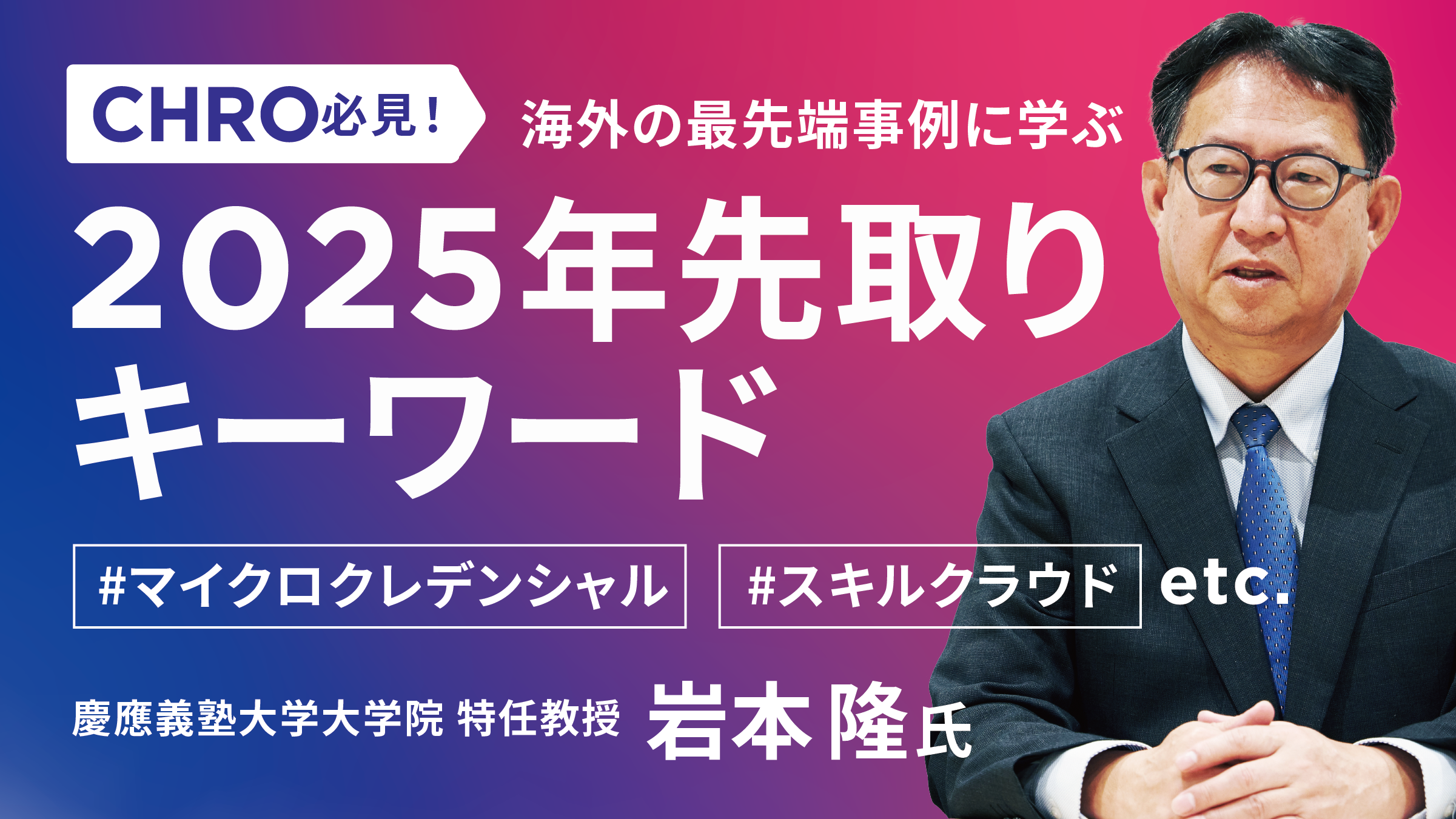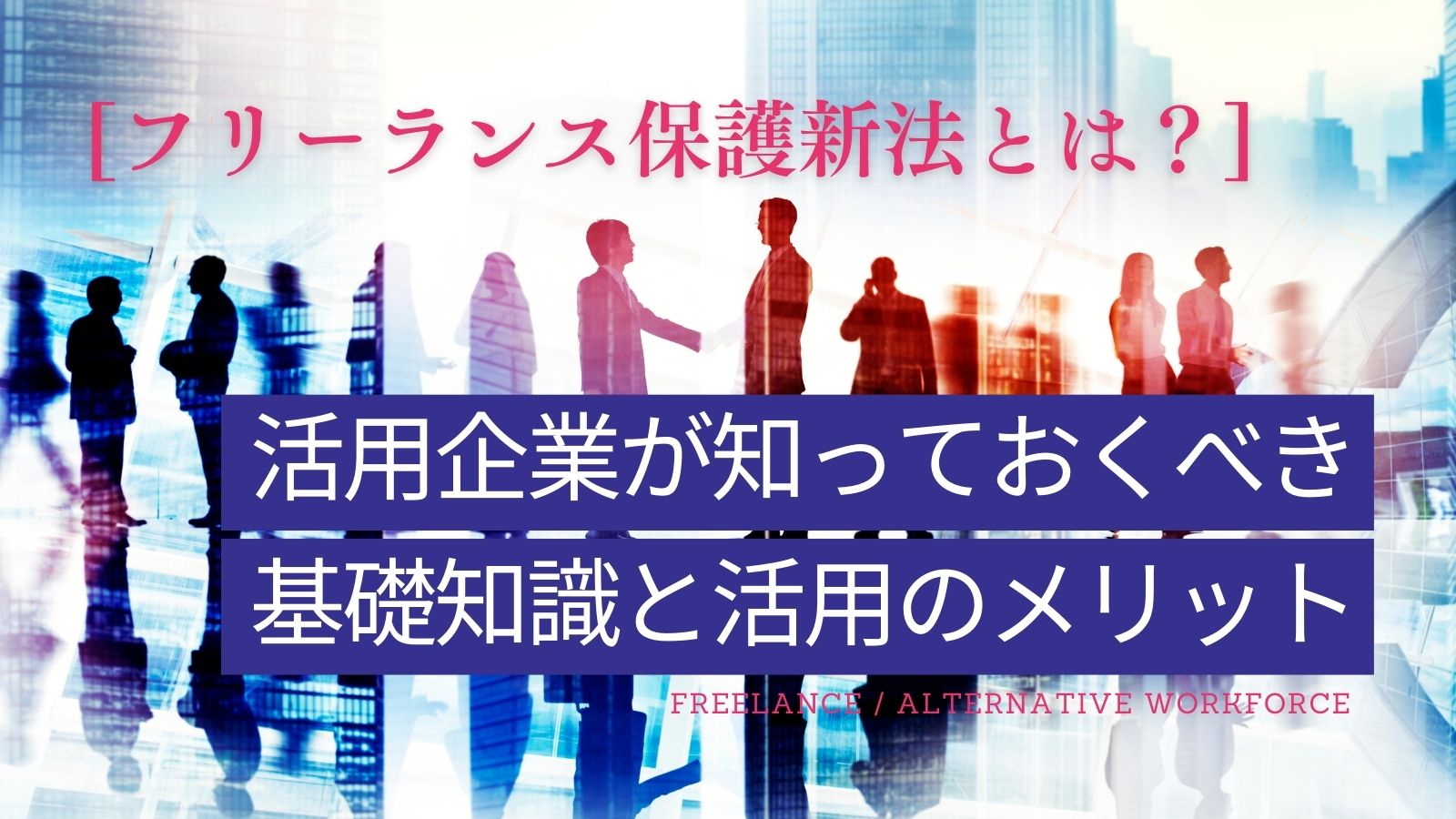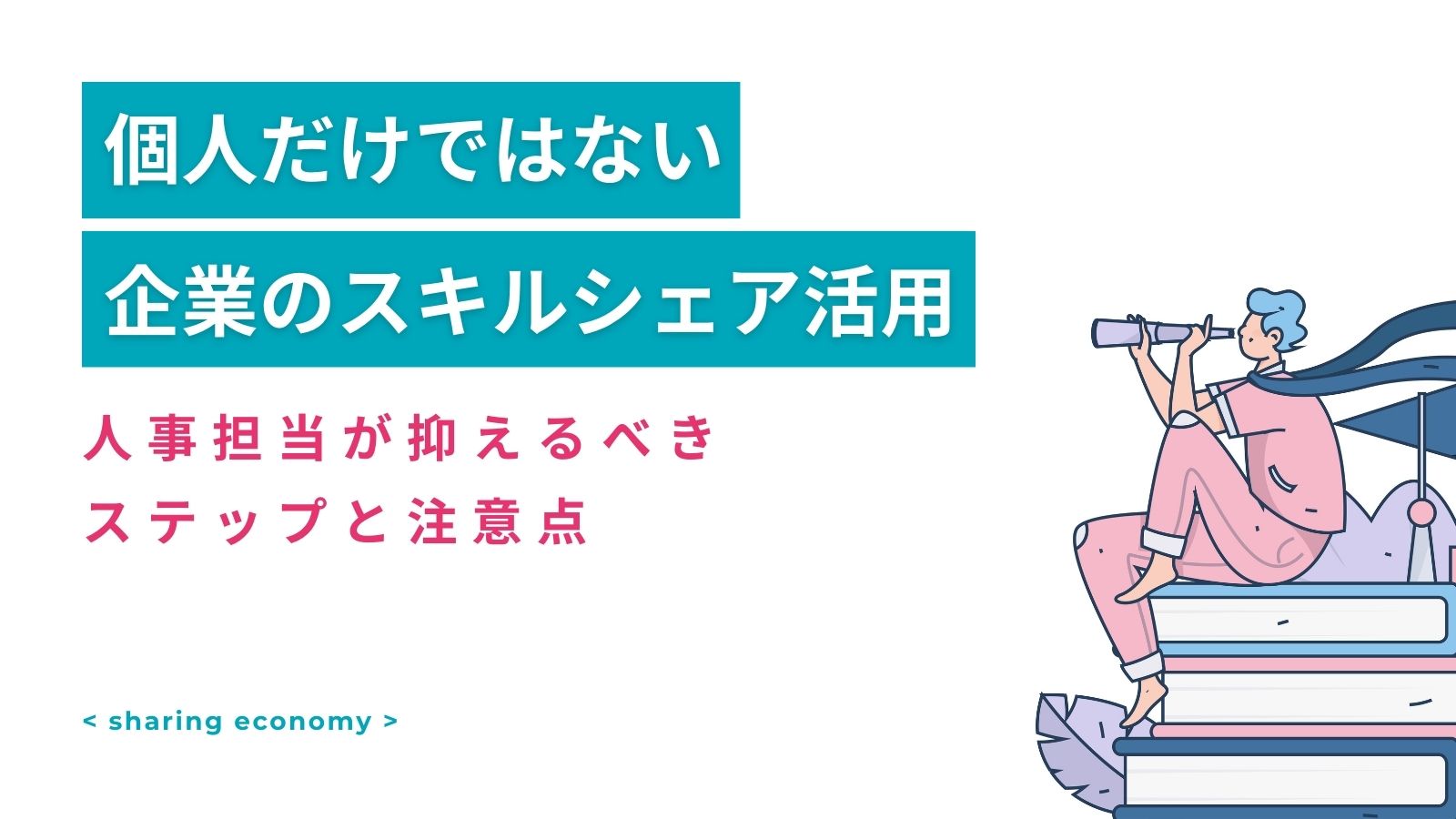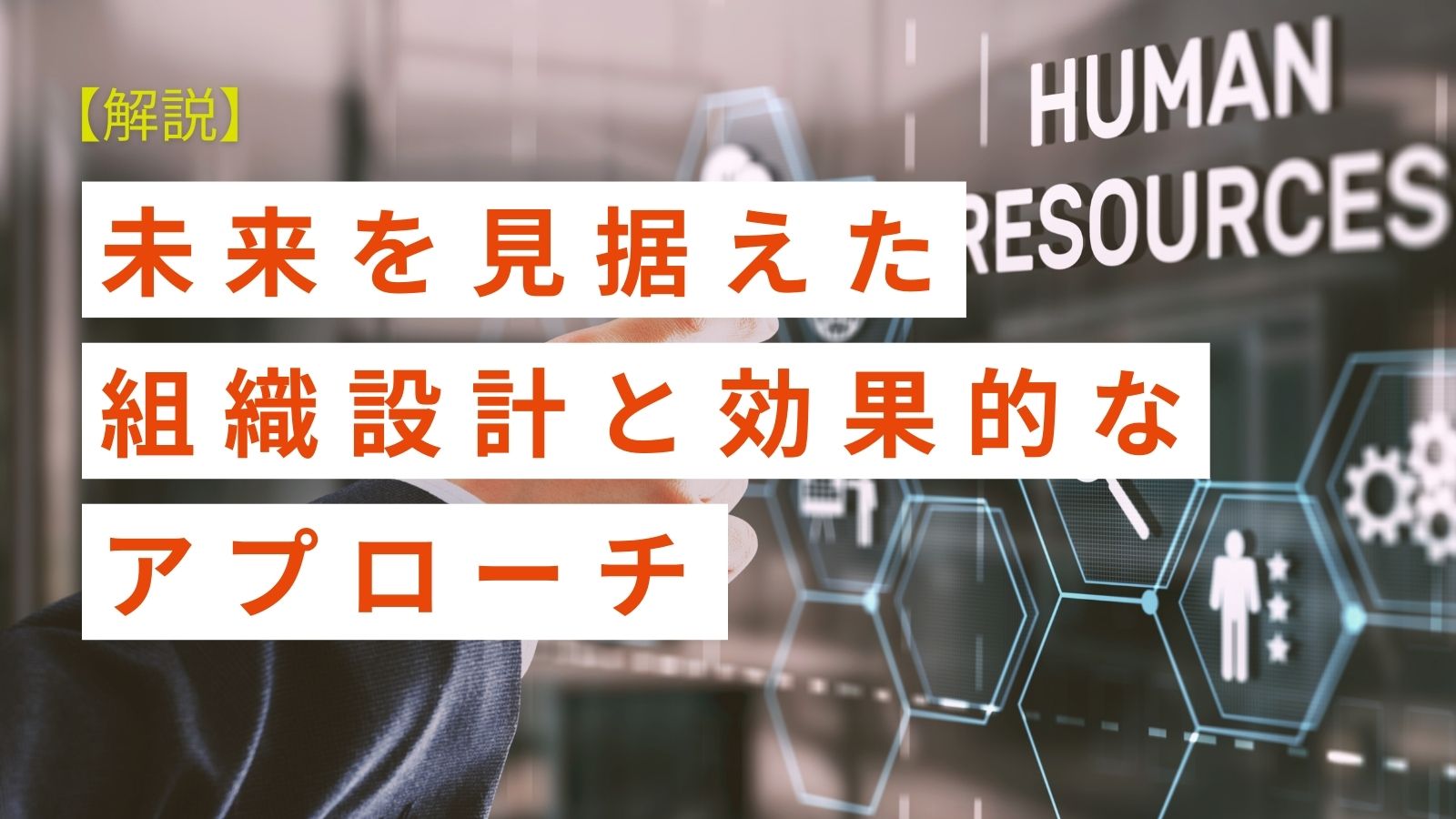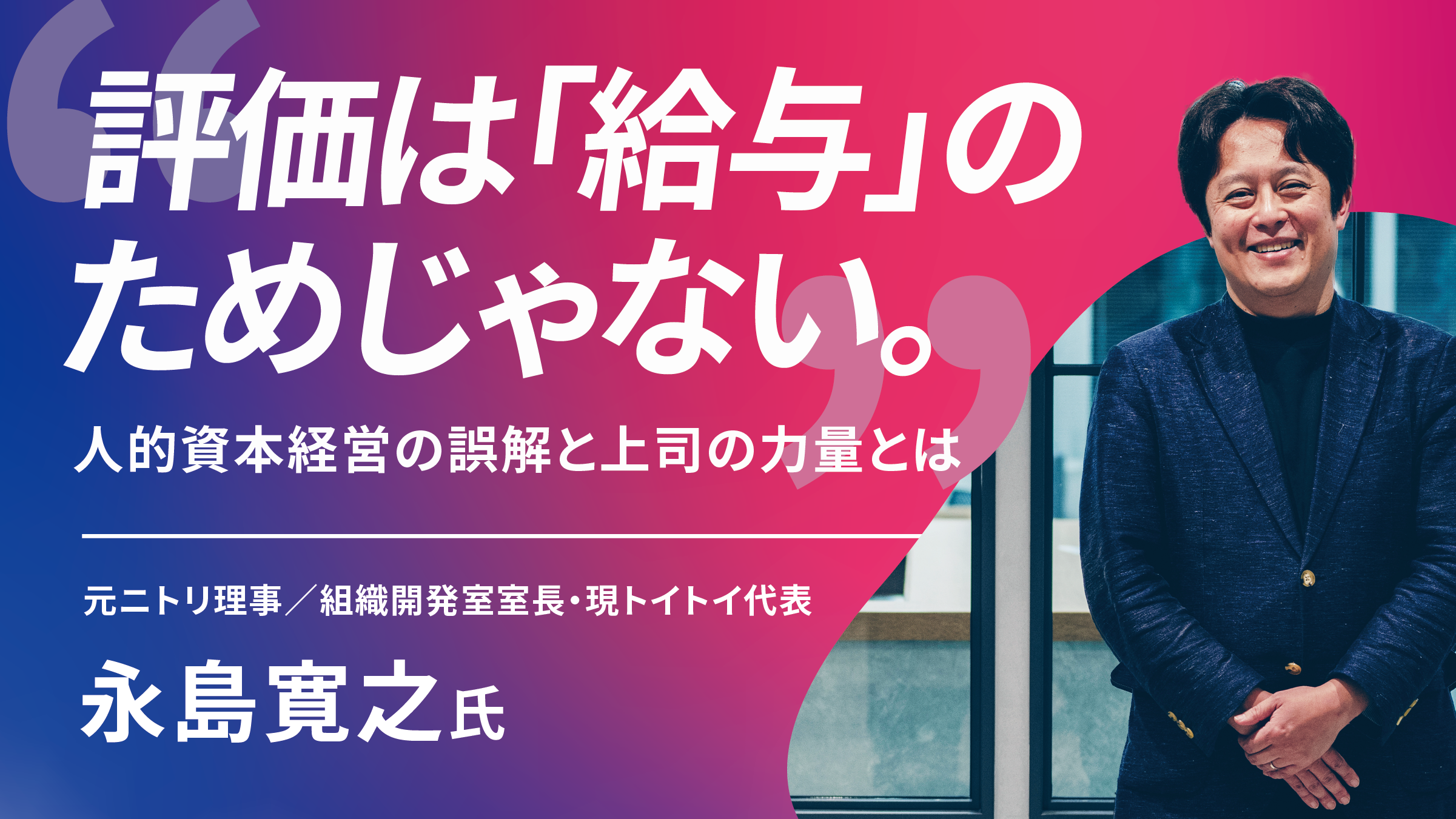リモートワークの普及により、都市部だけでなく地方在住のエンジニアを採用する企業が増えています。しかし「成果が見えない」「チームに馴染みにくい」「キャリアの未来が描けない」といったフルリモート特有の課題が、定着や活躍を阻む要因になりがちです。本記事では、3つの”見える化”をキーワードに、地方エンジニアが安心して力を発揮できる環境をつくるための実践法を紹介します。
エンジニアのマネジメントでお困りならHRBIZのプロ人事に相談
採用から定着まで、実績豊富なプロ人事がサポート。【無料】お問い合わせはこちら
地方エンジニアのマネジメントが難しい理由
リモートワークが定着した今、首都圏や大都市圏の人材だけにこだわらず、地方在住のエンジニアを採用する企業が増えています。採用難が続く中で、地方人材を活用することは企業にとって大きなチャンスです。
しかしその一方で、「フルリモート」という環境特有の難しさが浮かび上がってきました。とくにマネジメントの面では、都市部の出社前提のマネジメント手法をそのまま適用すると失敗しやすいのが実情です。
よくある失敗例としては:
- 稼働実態が不透明で、プロジェクト進捗や成果が掴みにくい
- 評価の不公平感が生まれ、不満が溜まりやすい
- 孤独感から組織文化に馴染めず、帰属意識が育たない
- キャリア感や将来像が見えず、エンゲージメント低下→離職率上昇
こうした『見えない課題』を放置すれば、せっかく採用した地方エンジニアが短期間で離職してしまい、再び採用・育成コストが発生するという悪循環に陥ります。
そこでこの記事では、実務経験と企業支援の知見をもとに、地方エンジニアをフルリモートで定着・活躍させるための”型”を整理しました。それが 『3Vフレームワーク』です。
- ✔ Visualization of Performance: 成果の見える化
- ✔ Visualization of Collaboration: つながりの見える化
- ✔ Visualization of Future Career: キャリアの見える化
本記事では、この3つの観点から、地方エンジニアをマネジメントするための具体策を紹介します。
🔎関連記事:リモートワークの普及
フリーランスが選ぶ「リモートワークしたい都道府県ランキングTOP20!」約8割が居住地以外でのリモートワークに関心
44.9%が中長期滞在志向、4人に1人が二拠点生活への関心で新たな関係人口創出の可能性が明らかに
① Visualization of Performance:成果の見える化

フルリモートで地方エンジニアを活用する場合、最初に直面する課題が 「稼働実態が見えない」 という問題です。オフィス勤務であれば「席にいる」「声をかければ反応がある」といった些細なサインから進捗を推測できますが、リモートではそれが完全にない状態でマネジメントしなければなりません。
結果として、プロジェクトの進行度が把握できずタスクの遅延に気づくのが遅れる、実際の成果よりも「オンラインにログインしている時間」で評価してしまう、などといった問題が発生しやすくなります。
また、エンジニア側も「頑張っているのに伝わらない」という不満を抱えやすく、こうした“お互いに見えない状態”は、不信感やモチベーション低下につながり、最悪の場合は早期離職の原因にもなります。
実践策1:三点報告ルールで進捗をシンプルに可視化
まずは毎日の稼働報告を「三点」に絞って共有してもらいましょう。
- タスク進捗(今日やったこと・進んだこと)
- 障害(詰まっていること・困っていること)
- 相談事項(助けが欲しいこと)
これをSlackやTeamsで簡潔に共有するだけで、日単位での状況を把握でき、エンジニアも「余計な監視感」を持たずに済みます。
例:
- ✅ タスク進捗:ログイン機能のユニットテスト完了(進捗80%)
- ⚠️ 障害:一部ライブラリのバージョン競合あり
- 💬 相談事項:明日の定例でレビュー依頼したい
このように形式を揃えることで、情報の抜け漏れがなく、マネジメント効率が一気に向上します。
実践策2:アウトプットベースのKPIを設定する
フルリモートでは、勤務時間ではなく アウトプット(成果物) を基準に評価する仕組みが不可欠です。
具体的には:
- GitHubのPR数(Pull Requestの提出件数)
- レビュー応答時間(他メンバーのコードにフィードバックするまでの時間)
- テストカバレッジ率やデプロイ成功率
などをチームKPIとして導入します。
これらの「定量化されたアウトプット」を評価指標に組み込むことで、エンジニアからの納得感が高まり、評価に対する不満を軽減することに繋がります。
実践策3:OKRを階層化して”自分の貢献”を可視化する
成果の見える化は、単にアウトプットを数値化するだけでは不十分です。重要なのは 「自分の成果が組織の成果にどうつながっているか」 を理解できることです。
そこで有効なのが、OKR(Objectives and Key Results)の階層設計です。
- 個人のKey Result を
- チームのObjective に紐づけ、さらに
- 事業全体のゴール と接続する
この設計をすることで、地方エンジニアでも「自分の1コミットが事業の成長に直結している」という実感を得られます。
例:
- 事業Objective:新規プロダクトのリリースを予定通り達成する
- チームKey Result:主要機能10件のテストカバレッジを90%以上にする
- 個人Key Result:ログイン機能のテストを今週中に完了させる
メンバー全員を定期的にオンラインで集めて「定例報告会」を実施するのも良いでしょう。会社の定量目標をもとにチームKPIを設定し、それらを担当ごとのKey Resultに落とし込みます。これにより、タスクの位置付けと目的が明確になったり、他のメンバーがどのような活動をしているのか理解が深まったりします。
② Visualization of Collaboration:つながりの見える化

フルリモート環境で軽視されがちなのが、組織としての一体感です。オフィスであれば、ちょっとした雑談やランチ、会議前後の会話が自然に発生し、組織文化の醸成や心理的安全性の確保につながっていました。しかし地方エンジニアがフルリモートで参画する場合、この非公式なコミュニケーションがほとんど失われます。
結果として、組織文化に馴染めず孤立感からエンゲージメントが下がる、相談やヘルプをためらい成果やスピードに影響する、などといったソフト面・ハード面への悪影響を及ぼしかねません。
こうした「見えない断絶」を埋めることが、定着率と生産性を両立させる鍵になります。
実践策1:定期1on1と心理面チェックシート
地方エンジニアに限らず、リモート人材の定着には1on1の定期実施が不可欠です。
ただし「進捗確認」だけで終わらせてしまうと効果は限定的です。そこでおすすめなのが「心理面チェックシート」を併用する方法です。
- 今の仕事の満足度(1〜5)
- チームとの関係性(孤独感があるか?)
- 今後のキャリアに関する不安
といった項目をスコア化してもらい、面談時に共有。言語化が苦手なエンジニアでも、数字で自己開示できるので不安の早期発見につながります。
実践策2:カジュアルミーティングを設定する
リモート環境では、意図的に「会う時間」を設計する必要があります。
- デイリースタンドアップ(朝会):進捗と予定を短時間で共有
- 定期オンライン雑談会:テーマフリーで交流(雑談専用の時間と位置づける)
- 隔週の全体共有会:会社の動きや方向性を共有し、地方メンバーも巻き込む
ポイントは「仕事の話」と「仕事以外の話」の両方を仕組み化すること。業務の接点以外でも、横のつながり・縦のつながりを意識的に醸成することで、エンジニア個人の孤独感解消のみならず、組織としての一体感やカルチャーの強化が期待できます。
実践策3:離職予兆の3サインを数値化する
フルリモートの地方エンジニアをマネジメントする際は、「離職予兆の3サイン」を指標化し、早期解決に取り組みましょう。例えば、
- 稼働量の急変:作業時間や成果物が急に増減していないか
- レビュー遅延:Pull Requestのレビューや応答が遅れがちになっていないか
- 雑談不参加:カジュアルな交流の場から姿を消していないか
これらのは孤立やモチベーション低下の初期サインの可能性が高いです。メンタル面の数値管理は一見難しいですが、タスク量・スピード感・カジュアルミーティングへ不参加率などを定量把握することで、早めに手を打つことができます。
③ Visualization of Future Career:キャリアの見える化

フルリモートで地方エンジニアを活用する上で、最も大きな離職要因の一つが 「将来が見えない」 という不安です。
- 今の業務が自分のキャリアにつながっているのか?
- 都市部のエンジニアと比べて成長機会を失っていないか?
- プライベート(家庭や地域での生活)とキャリアを両立できるのか?
これらの不安を放置すると、エンゲージメントが低下し、早期離脱しやすくなります。逆に「未来が見える」状態をつくることは、地方エンジニアのモチベーションを高め、長期定着につながります。
実践策1:キャリアルートと評価基準を明確にする
採用したエンジニアを長く定着させるためには、単に働きやすい環境を整えるだけでは不十分です。エンジニアが「この会社で成長できる」「キャリアを描ける」と感じられることが最も大切です。
エンジニア層が転職を考える理由には「キャリアパスが見えない」「自分の成長が止まっていると感じる」が挙げられます。つまり、キャリア形成に対する支援は、エンジニア定着の核心なのです。エンジニアのエンゲージメントを向上させるために、具体的には以下のような取り組みが有効です:
- キャリアパスの明示
「シニアエンジニア → テックリード → マネージャー」といった昇格ルートを明確に提示する。 - 業務配分の調整
ルーチン業務ばかりを任せるのではなく、新技術や新規プロジェクトにも関わらせ、挑戦の機会を与える。 - エンゲージメントサーベイの実施
定期的に従業員の満足度や意欲を数値化し、早期に離職リスクを把握する。 - キャリア面談の仕組み化
評価面談とは別に「キャリア形成に関する面談」を実施し、本人の希望を尊重しながら配置や育成方針を決める。
地方にいても「自分の未来は閉ざされていない」「キャリアはここで積み上げられる」と実感できる環境を提供することが大切。エンゲージメントを高める視点からキャリア支援を設計することが、離職を防ぐ最大の施策といえるでしょう。
🔎関連記事:イベントレポート『今さら聞けないエンゲージメントのきほん』
リファラル×認知科学で描く!新時代の組織デザイン
組織づくりにおけるリファラル採用と認知科学という、一見異なる領域を掛け合わせたテーマ。講演や対話を通じて、“自律的に成長する組織とは何か”を参加者とともに考える場となりました。
実践策2:会社と個人の未来を「ありたい姿」で重ねる
キャリア支援で見落とされがちなのが、会社の目指す方向と個人のキャリア目標が同じベクトルを向いているかという視点です。そのために有効なのが「ありたい姿」の共有です。
- 個人に「3年後・5年後どうなっていたいか」を言語化してもらう
- 会社の中期ビジョンと重ね合わせ、交わるポイントを探す
- 具体的な役割やプロジェクトに落とし込む
例えば、会社が「プロダクトを海外展開したい」と考えており、個人が「グローバル案件に挑戦したい」と望んでいれば、海外顧客案件のチームに早期から参加させる、のような、まさにWin-Winの関係を築くことが大切です。
実践策3:成長機会をリモートでも公平に提供する
都市部のエンジニアと比べ、地方在住のエンジニアは学習やネットワーキングの機会に恵まれにくいのが現実です。都市部では勉強会やコミュニティが豊富に存在しますが、地方ではそうしたイベントに物理的に参加しにくいため、情報の格差が生まれやすくなります。
企業が意識すべきなのは、技術のアップデートを組織的に仕組み化することです。
- 社内勉強会や輪読会の開催
月1回の技術共有会や、最新の技術書をテーマにした輪読会をオンラインで実施し、社員全員が参加できる場を設ける。 - 外部カンファレンスや研修への参加支援
交通費や参加費を補助し、地方在住者でも最新のカンファレンスに参加できるようにする。 - 育成と評価を結びつける
新しい技術を習得したエンジニアを正当に評価し、昇給や役割拡大に反映する。
「ただ勉強の機会を与える」のではなく、マネジメント側がエンジニアの成長を「育成計画」として組み込みましょう。
まとめ|地方エンジニア活用を成功させるために必要な視点とは

地方エンジニアをフルリモートで活用することは人手不足を打開する有効な選択肢ですが、成果やつながり、キャリアといった「見えにくさ」がマネジメントの大きな壁となります。
だからこそ、企業はこの“見えないもの”を意識的に可視化し、安心して働ける仕組みを整える必要があります。「3Vフレームワーク」は、そのための実践的な型です。人材が自分の力を発揮し、組織とともに成長できる環境をどう設計するか——それを考える出発点として、ぜひ自社に当てはめてみてください。
そして、ここまでをすべて自社の人事部門だけで完結させるのが難しい場合は、エンジニア採用に特化した外部パートナーを活用しましょう。
株式会社テックビズが運営するHRBIZには、エンジニア採用・マネジメントに精通した人事フリーランスが多数在籍しています。採用戦略の立案からスキル要件の整理、選考プロセスの設計、さらには採用後の評価制度や育成・定着支援まで、一気通貫でサポート可能です。
- フルリモート人材のマネジメントが思うようにいかない
- エンジニアを正しく評価できているか自信がない
- 採用してもすぐに離職してしまう
といった課題に心当たりがある場合は、ぜひ一度HRBIZにご相談ください。御社の採用課題を整理し、優秀なエンジニア人材の確保から定着まで、伴走型でご支援いたします。
エンジニア採用にお困りならHRBIZのプロ人事と解決
即戦力の人事プロを、柔軟かつスピーディーにご紹介!【無料】お問い合わせはこちら
即戦力人材の採用にお困りではありませんか?ハイスキルなHR人材をスムーズに採用できる【HRBIZ】
HRBIZでは優秀なHR人材をご紹介しています。スキルのみならず人柄も踏まえ、企業様にマッチした人材を、最短で即日ご紹介できます。即戦力人材の採用にお困りの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。