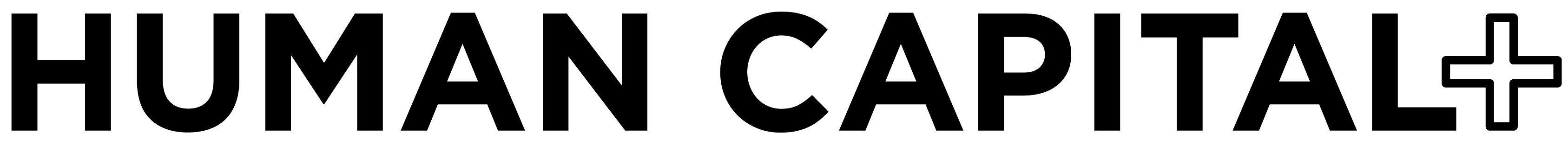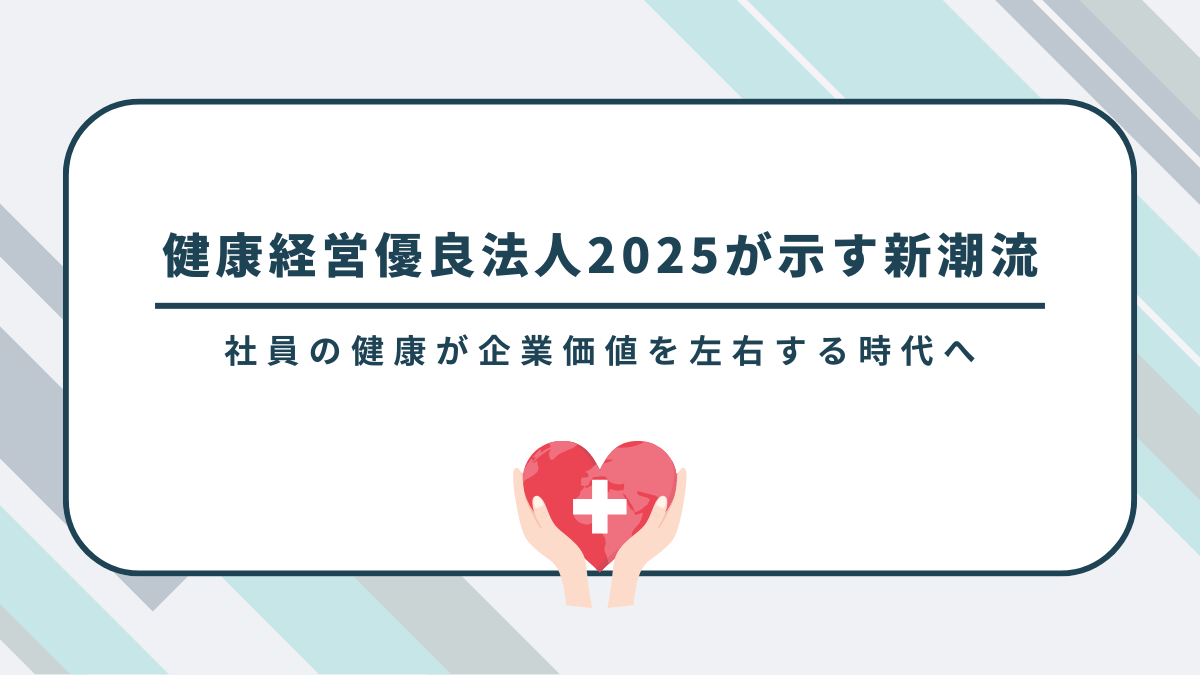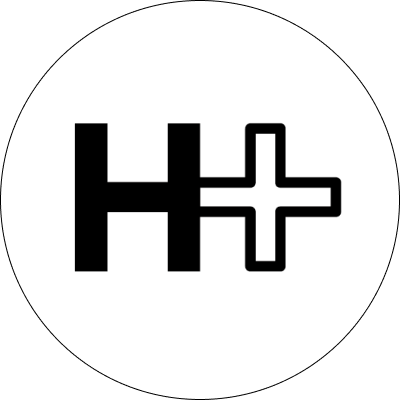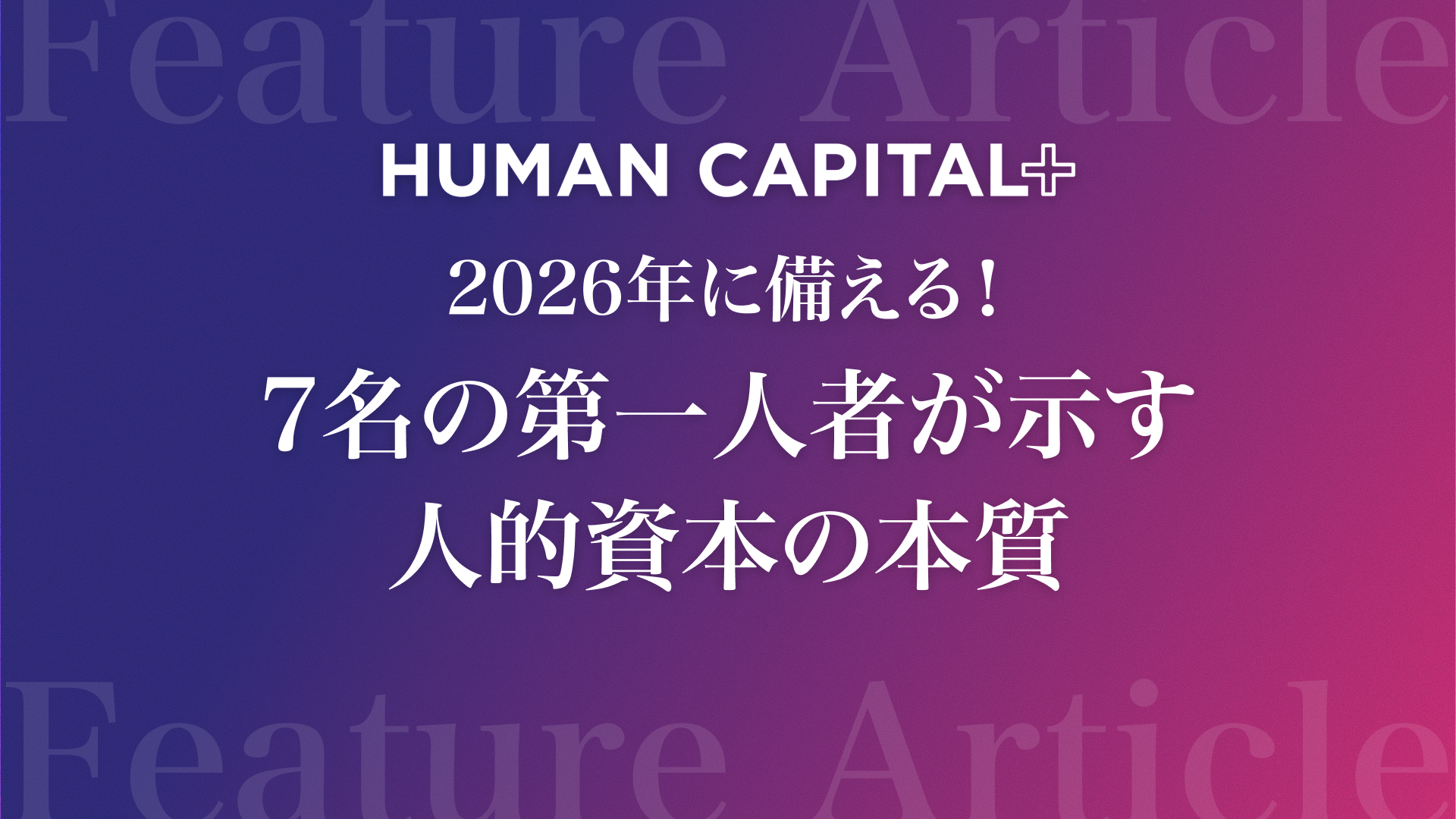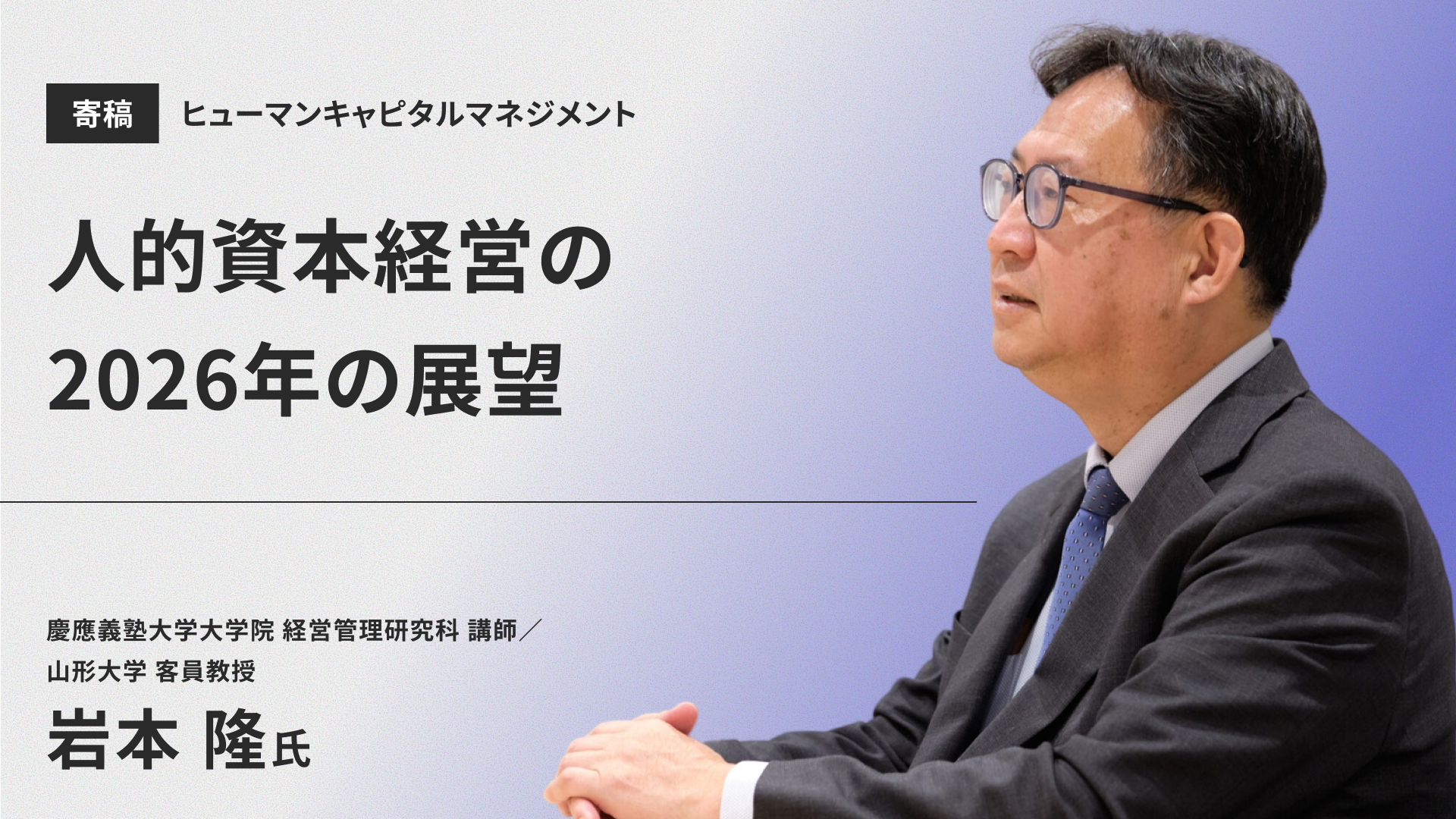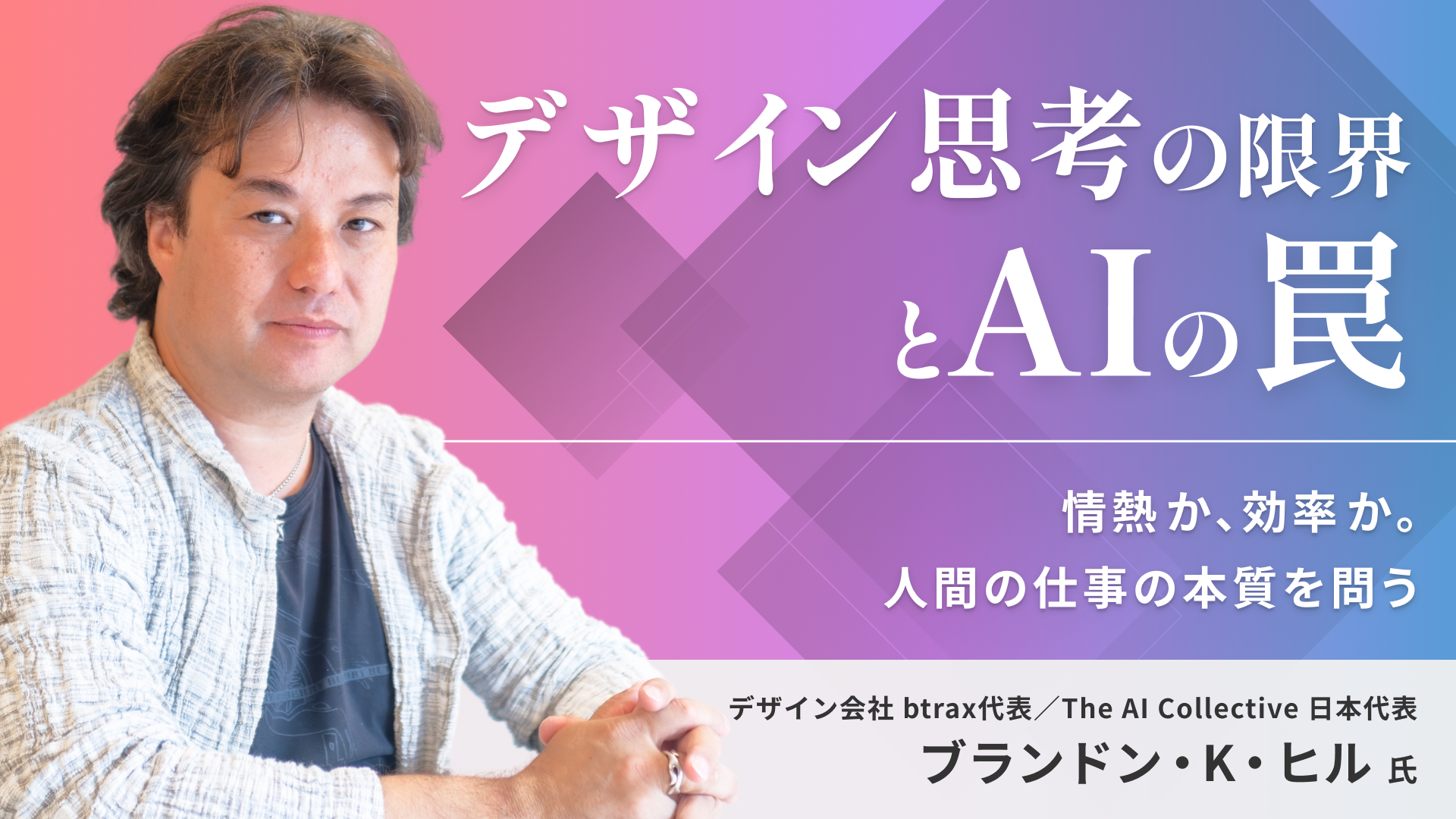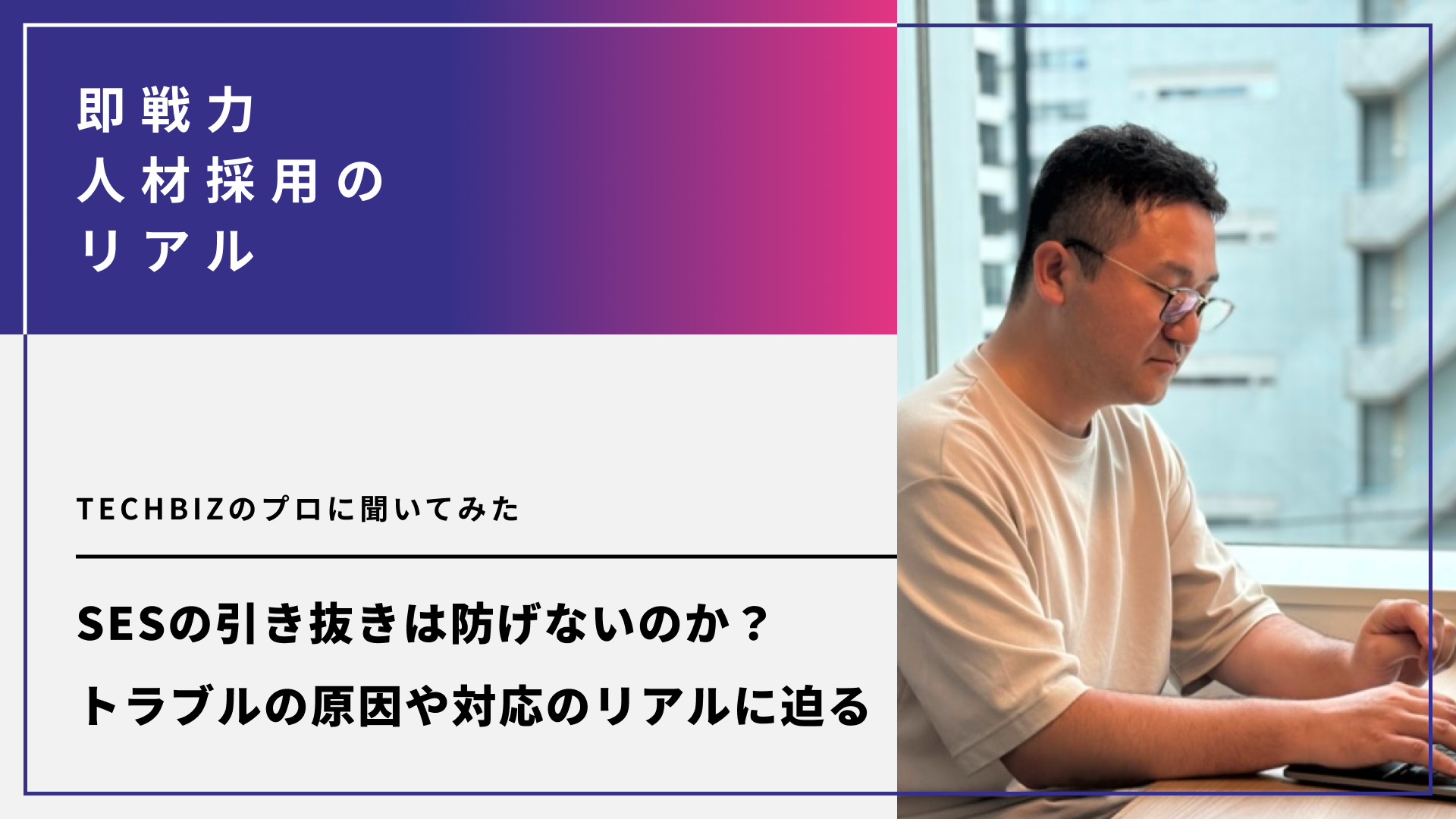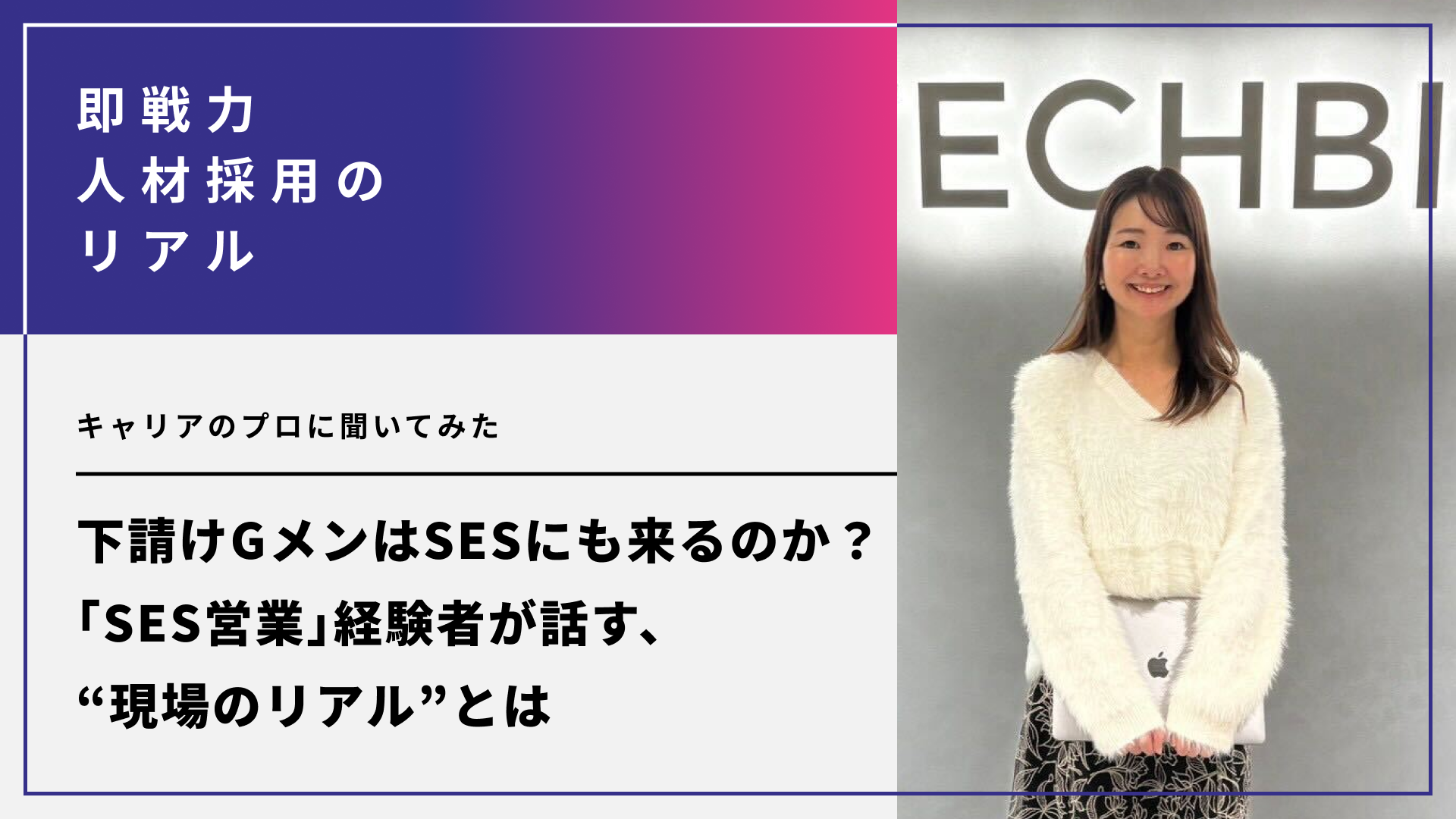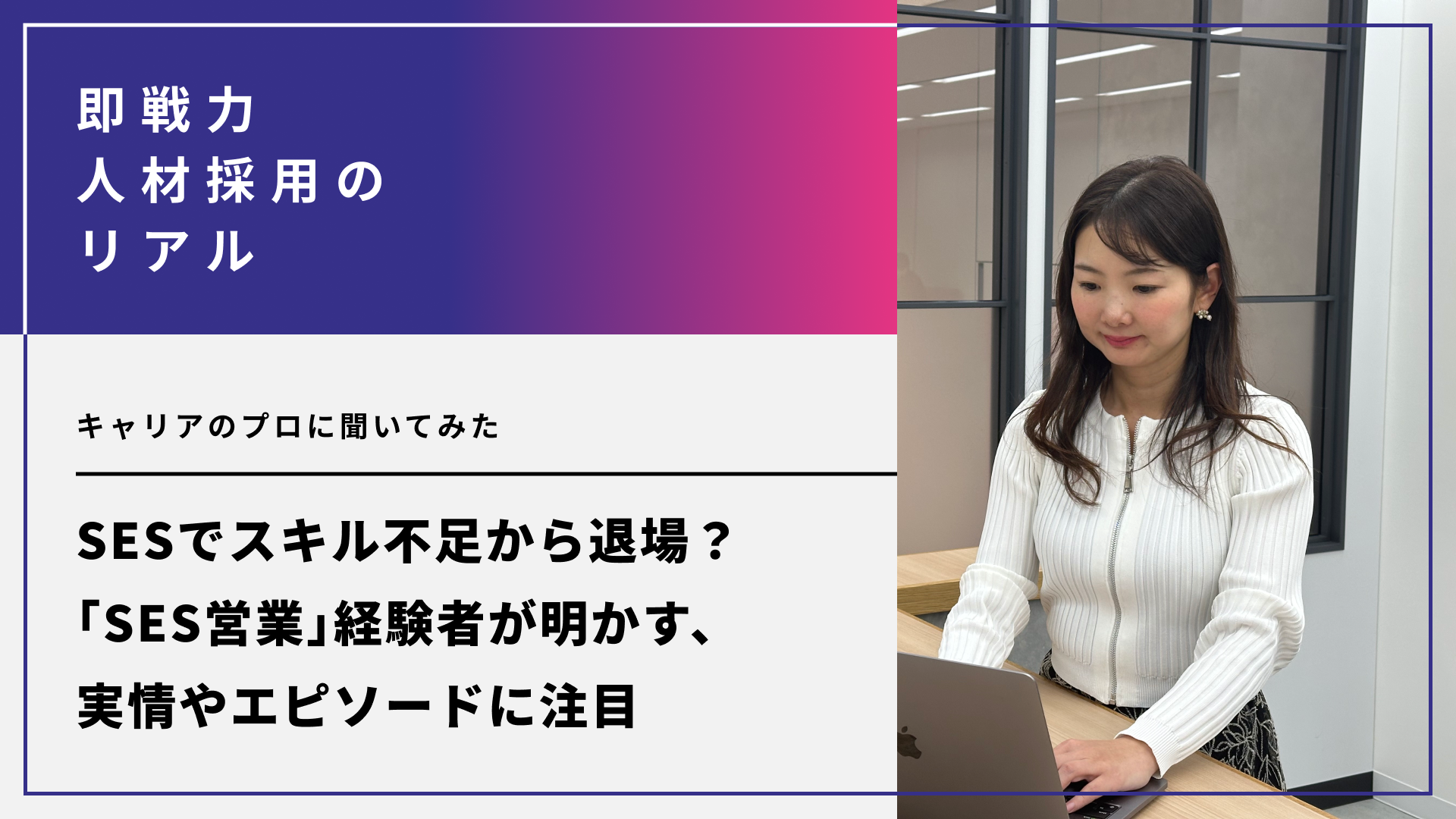2025年3月10日、経済産業省と日本健康会議は「健康経営優良法人2025」の認定企業リストを公表しました。認定の総数は2万社を超え、大企業から中小企業まで過去最多を更新しています。HR担当者や経営層を中心に、「健康経営を無視しては企業価値を高められない時代が到来した」との声が高まっているようです。
健康経営という言葉を耳にする機会は増えましたが、その背景には「人的資本」への注目がますます高まっている現状があります。社員一人ひとりの健康と生産性が、企業の長期的な競争力や魅力に大きく影響するようになってきました。では、なぜここまで注目されるのでしょうか。
本記事では、健康経営優良法人の制度概要から具体的な企業事例まで、ニュースの観点を押さえつつ読み解いていきます。
健康経営優良法人とは?――制度の狙いと背景
健康経営優良法人は、経済産業省と日本健康会議が共同で実施している認定制度です。社員の健康を「コスト」ではなく「将来への投資」と捉え、組織として積極的に取り組む企業を顕彰しています。
大企業部門では「ホワイト500」、中小企業部門では「ブライト500」といった上位認定があるほか、認定企業の数は年々増加傾向にあります。
この仕組みを支えているのが、経済産業省による健康投資推進の国家戦略です。超高齢社会といわれる日本において、社員の健康を守ることは、医療費の削減や労働力不足の解消だけでなく、企業の生産性やイノベーション創出力を底上げするカギとして期待されています。
ポイント
• 健康経営優良法人の認定総数は毎年増加し、認知度が高まりつつあります。
• 社員の健康を重視する企業姿勢が見える化されるため、社内外の信頼獲得につながると考えられます。
• 大企業だけでなく、中小企業にも門戸が広がっており、地域金融機関や自治体の支援事例も増えています。なぜ社員の健康が“企業価値”を左右するのか
「人的資本」としての健康
近年、ESG投資や統合報告書などのトレンドにより、企業の人材マネジメントや組織風土といった「人的資本」が注目されています。人的資本とは、企業に所属する人材の専門性やモチベーション、組織がもつ無形資産の総体です。社員が健康かどうかは、その無形資産を100%活かせるかどうかを左右します。
• 健康であればこそ、高い集中力を発揮できる
• メンタル・フィジカルの両面が安定していると、イノベーションが生まれやすい
• 健康経営がしっかりしている企業ほど離職率が下がり、組織力が蓄積されるこのように、社員の健康を守る取り組みは、企業が長期的な成長エンジンを確保する上で重要な要素といえます。
事例1:ストレスチェックの“見える化”がもたらす変化
健康経営優良法人に認定されたあるメーカー企業は、ストレスチェックの結果を部署やチームごとに細かく分析し、課題を洗い出しています。
一般的にストレスチェックは個人のメンタル状態を把握する目的で行われますが、この企業では残業時間や有給取得率などと組み合わせて数値化している点が特徴です。
• 残業が慢性的に多い部署→業務改善プロジェクトを立ち上げ、短期的に要員を増やす
• 有給取得率が極端に低いチーム→上司のマネジメントスキル向上研修を実施し、取得促進を呼びかけるこうした取り組みを続けた結果、メンタル不調による休職数は前年比で2割以上減少し、仕事へのモチベーションに関するサーベイのスコアも上昇したそうです。人事責任者は「データを見ながら具体的に手を打つことで、問題が深刻化する前に対処できる」と話しています。
事例2:エンゲージメントサーベイの活用でチーム力を高める
通信業界大手のKDDIなど、エンゲージメント(貢献意欲や愛着度)を定期的に調査する企業も増えています。全社員にアンケートを実施し、得られたスコアを経営会議で共有。特に数値の低い部署には、専任チームを派遣して問題の原因を探り、改善施策を立案するという流れです。
• 1on1ミーティングの頻度
• リモートワーク環境の整備
• 管理職へのフィードバック研修これらをバランスよく導入することで、社員の「会社は自分たちを大切にしてくれている」という実感が高まり、結果的に生産性や定着率も上がったという報告があります。人事担当者は「エンゲージメントをしっかり把握し、組織全体で改善サイクルを回すことが、健康経営にも直結する」と指摘しています。
「見える化」と迅速なアクションがカギ
健康経営が企業価値に影響する要因として、社員の健康データの“見える化”に基づいた迅速なアクションの重要性が挙げられます。
1.早期発見
• ストレスチェックやエンゲージメントサーベイで、課題を迅速に把握
• 個別ではなく組織単位の問題点を洗い出すことで、広範な不調を防ぎやすい
2.ピンポイント対策
• 部署別のデータをもとに、過重労働やコミュニケーション不足など特定の課題に適切に介入
• 効率的にリソースを投下でき、改善効果を早期に実感しやすい
3.社員のエンゲージメント向上
• 組織が自分たちの声を拾い、動いてくれるという体験が「働きがい」に直結
• 心理的安全性が高まり、新しいアイデアやチャレンジが生まれやすい雰囲気にこうしたプロセスを回していくことで、外部からも「人を大切にする企業」と認知され、採用面や投資家からの評価にも良い影響を与えます。
今後の展望と課題
中小企業への波及
健康経営優良法人の認定は、中小企業でも獲得しやすくなっています。しかし、人事部が整備されていなかったり、リソースが限られたりするため、導入に二の足を踏む企業も少なくありません。近年は地方銀行や自治体が支援策を打ち出す事例が増えており、中小企業の裾野にどう広げていくかが今後の課題になりそうです。
国際基準とのすり合わせ
欧米では人的資本開示に関するルールが日本より先行しており、健康管理の情報も投資家への開示対象に含まれる流れがあります。日本企業も今後はISO30414など国際的なガイドラインに即して情報を整理し、グローバルスタンダードで評価される準備を進める必要があるかもしれません。
テクノロジーの活用
ウェアラブル端末やAIを活用した健康データの収集・分析が進むにつれ、より個人に合わせたサポートが可能になると期待されています。プライバシーや個人情報の保護と両立する仕組みづくりが重要ですが、うまく運用できれば“いつでもどこでも社員の健康を見守る”体制が実現しそうです。
健康経営は“人を大切にする経営”の象徴
健康経営優良法人2025の発表を受け、改めて「従業員の健康が企業価値の源泉になる」という認識が広がっています。かつては“福利厚生の一環”とみられがちだった健康施策も、今では“戦略的な人的資本投資”として捉えられるようになりました。
キーポイント
• 社員の健康データを見える化し、課題を特定して迅速に改善することが大切です。
• 社員が「大切にされている」と感じれば、エンゲージメントが高まり、生産性や定着率も上がります。
• 健康経営の充実度は企業の社会的信用や投資家評価につながり、長期的に企業価値を押し上げる要因になります。今後は中小企業へのさらなる普及や、グローバル基準に対応した人的資本開示など、健康経営を巡る取り組みがさらに広がっていくでしょう。
従業員を大切にする企業が社会から選ばれ、そこに投資や人材が集まる――そんな新たな時代は、すぐそこまで来ているといえます。
参考情報
- 経済産業省「健康経営優良法人認定制度」
- 日本健康会議の活動報告やイベント案内
- ISO30414など人的資本開示の国際ガイドライン
- 各企業の統合報告書や健康経営レポート
即戦力人材の採用にお困りではありませんか?ハイスキルなフリーランス人材をスムーズに採用できる【テックビズ】
テックビズでは「ITエンジニア」「人事HR」「経理ファイナンス」領域にて優秀なフリーランス人材をご紹介しています。スキルのみならず人柄も踏まえ、企業様にマッチした人材を、最短で即日ご紹介できます。即戦力人材の採用にお困りの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。