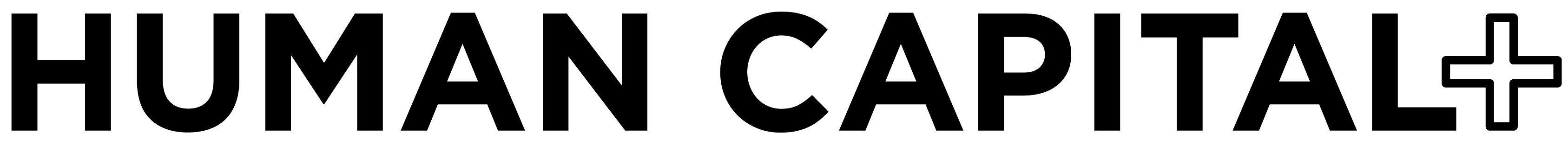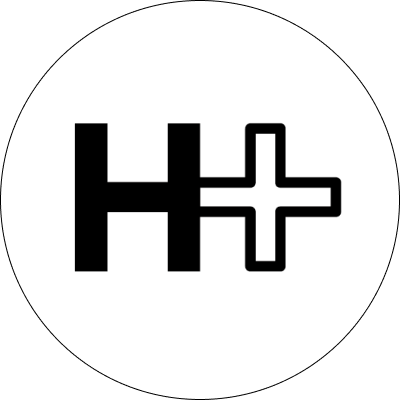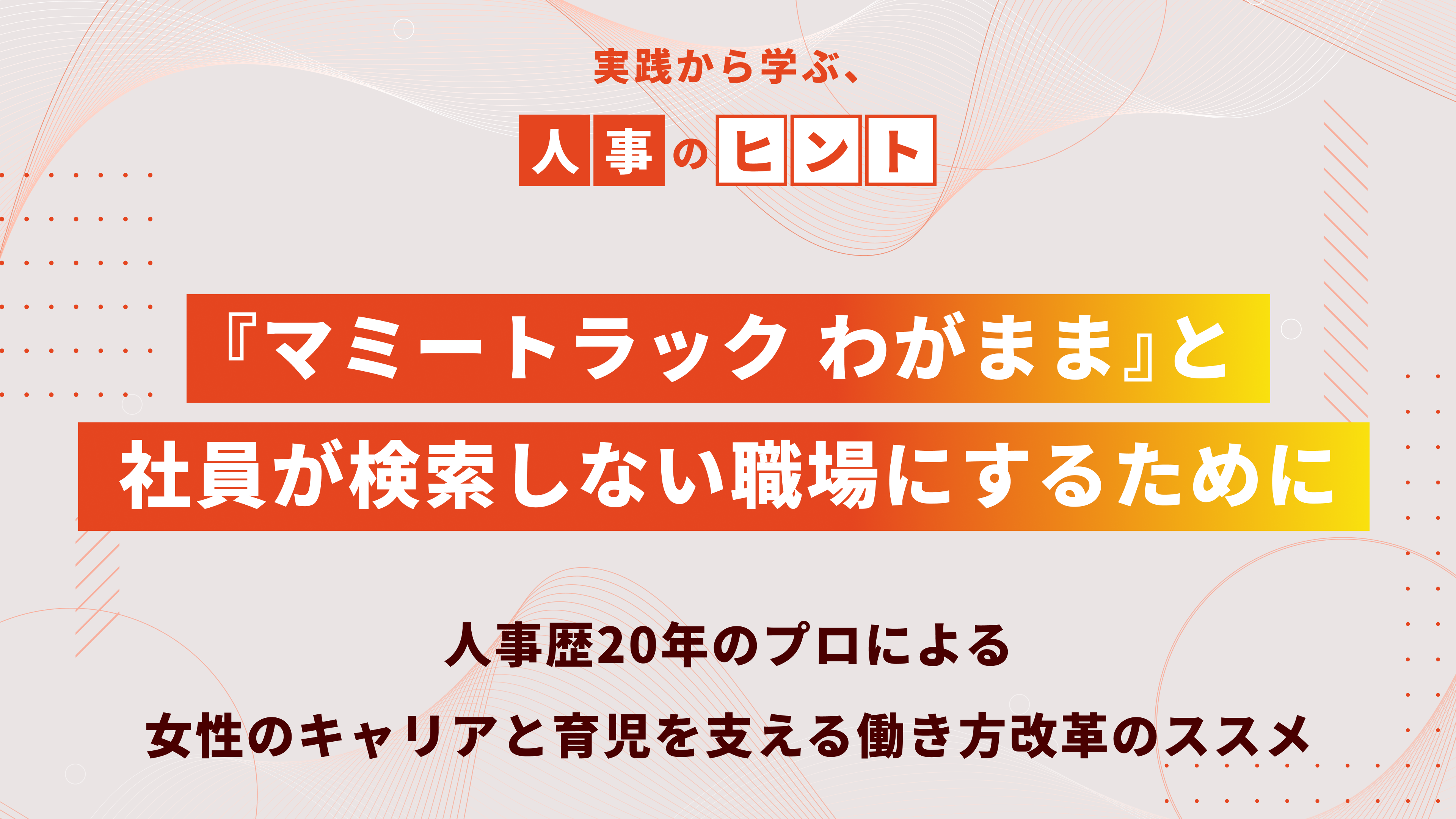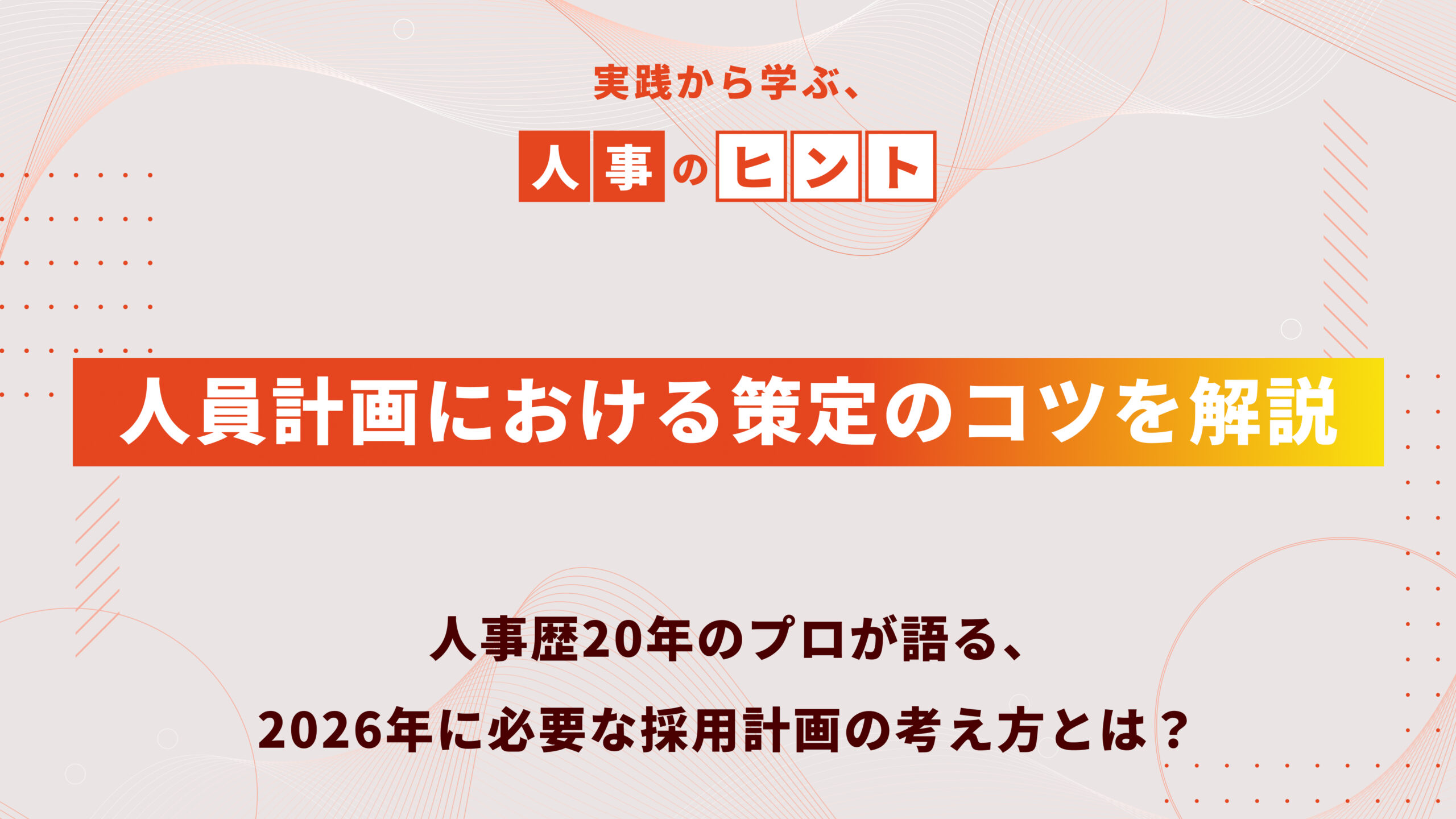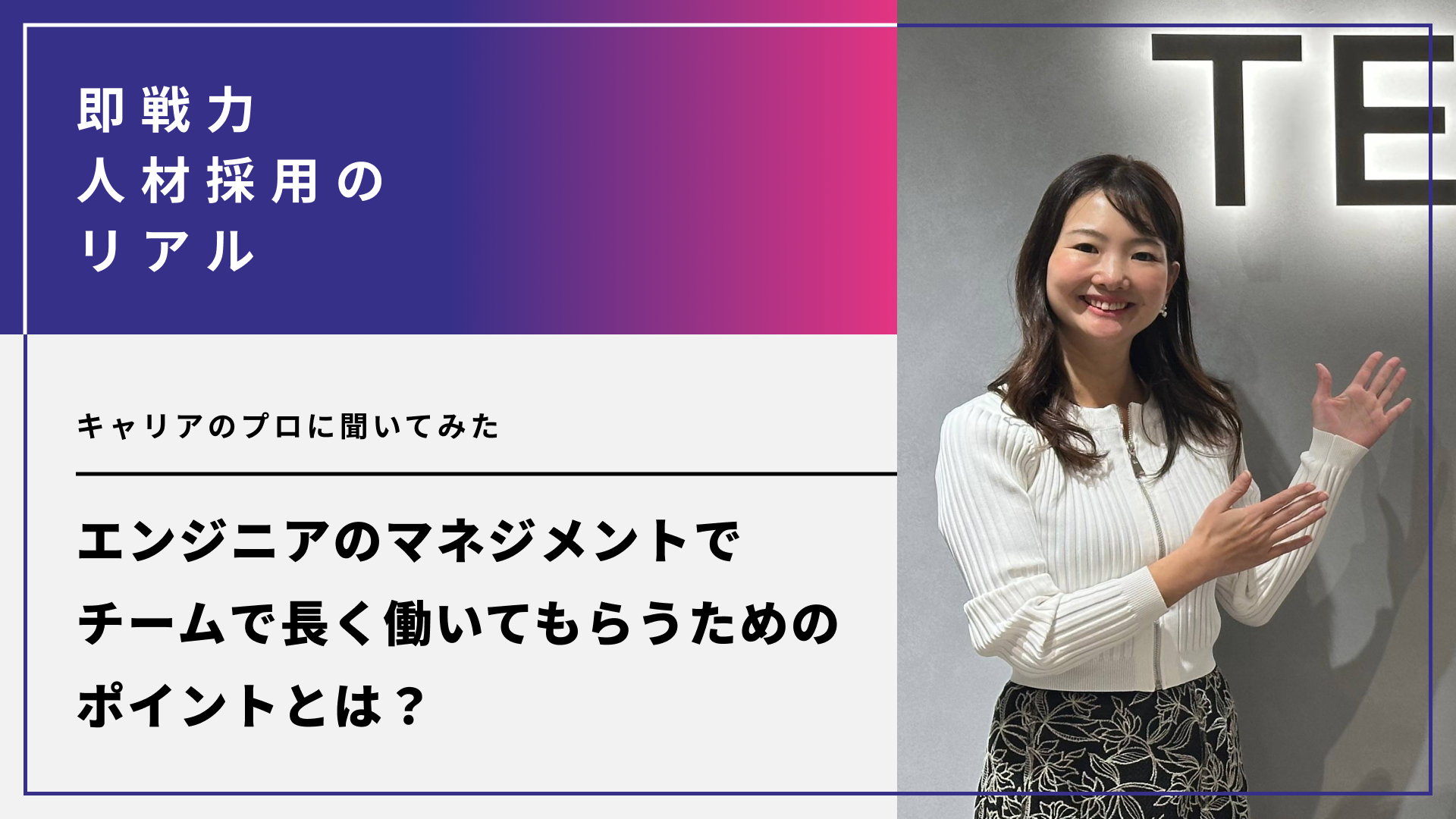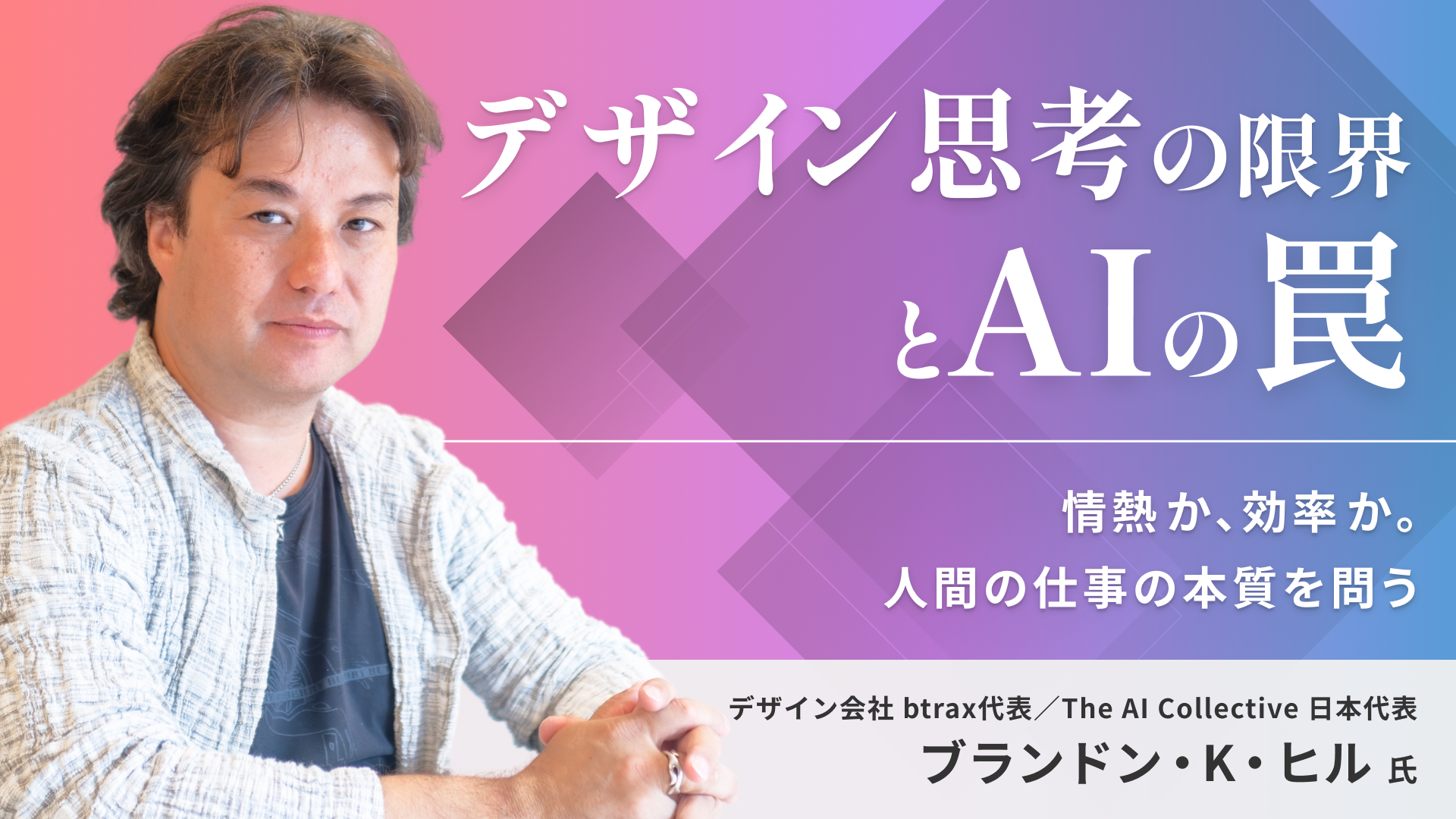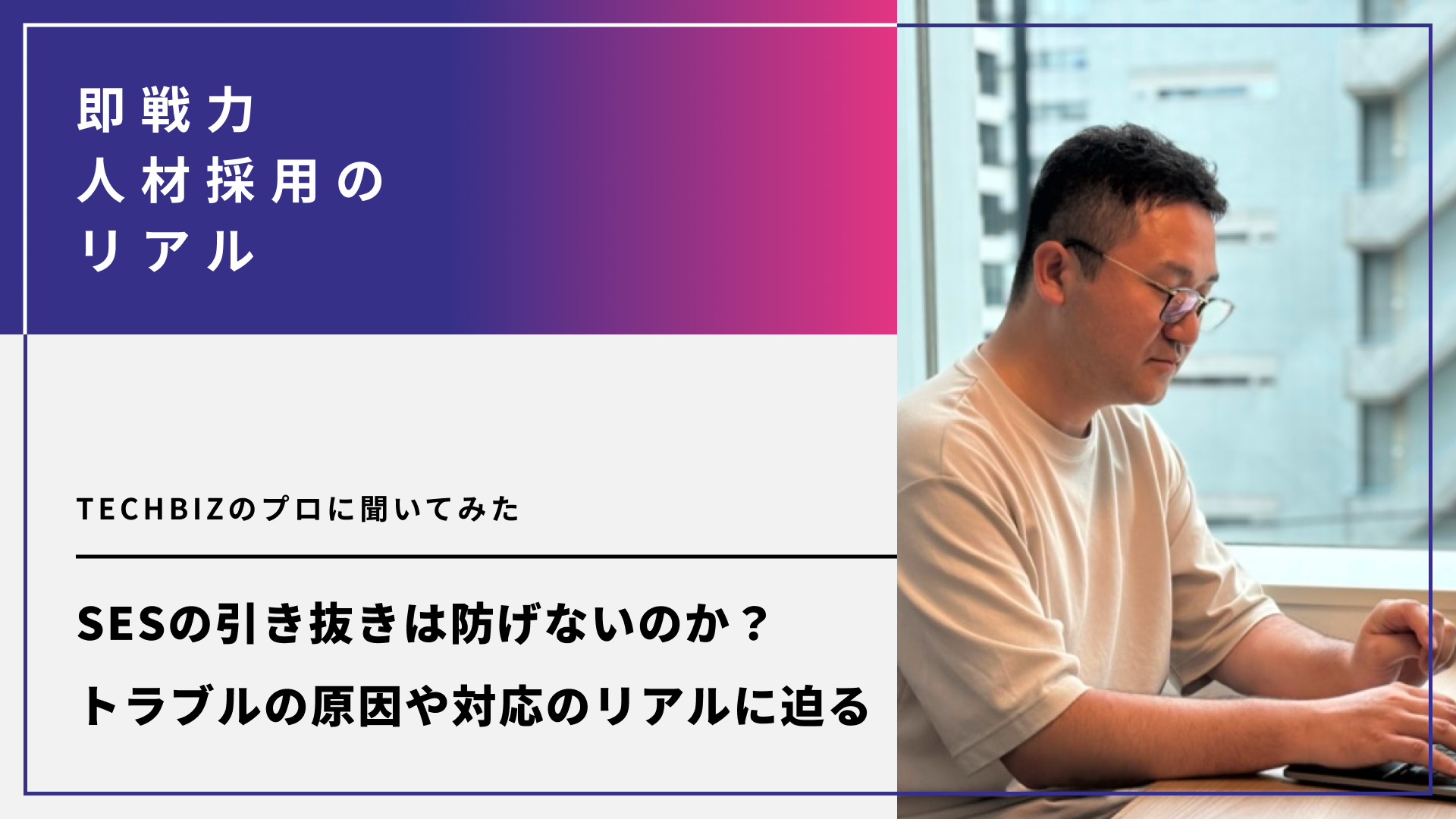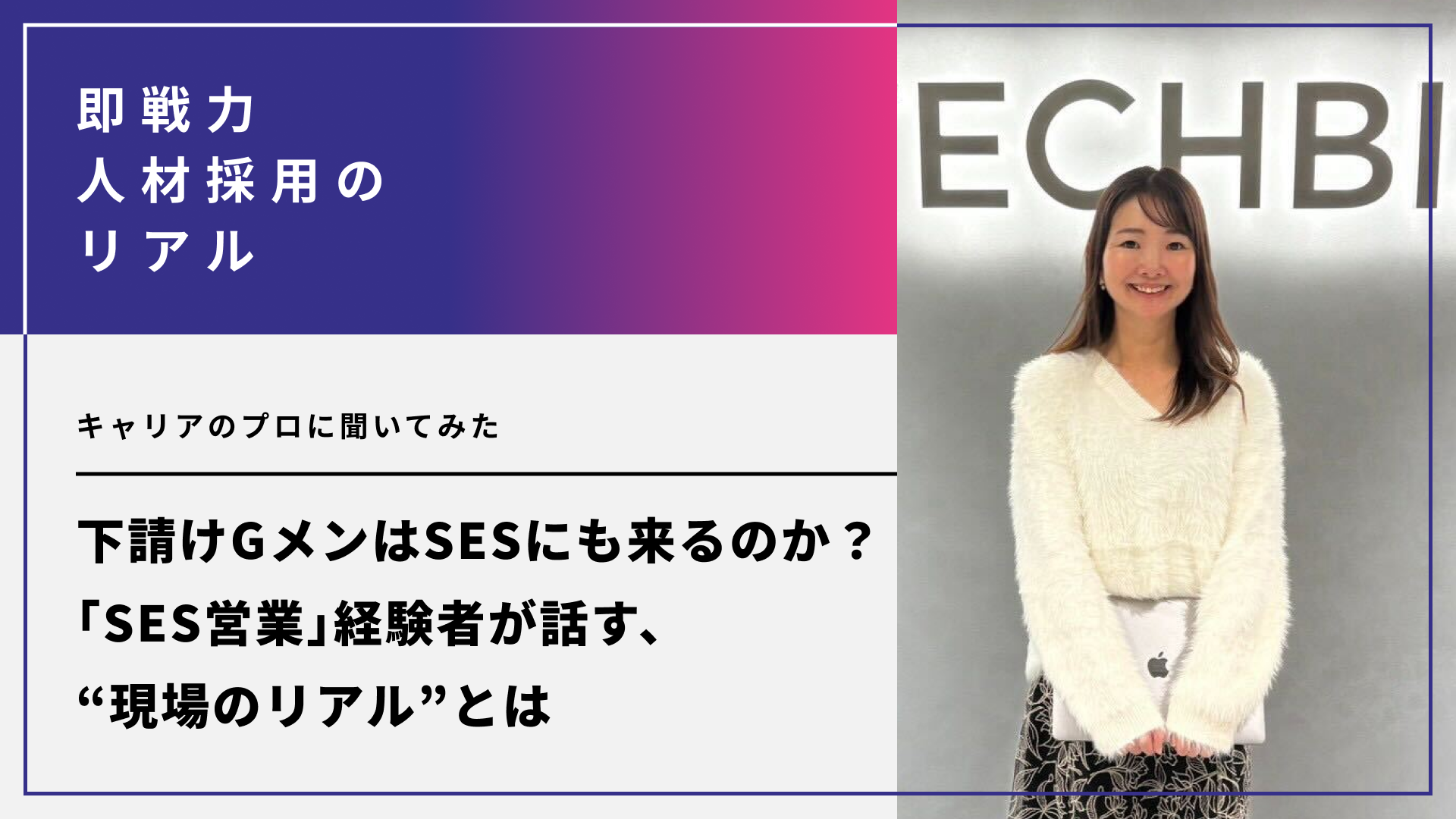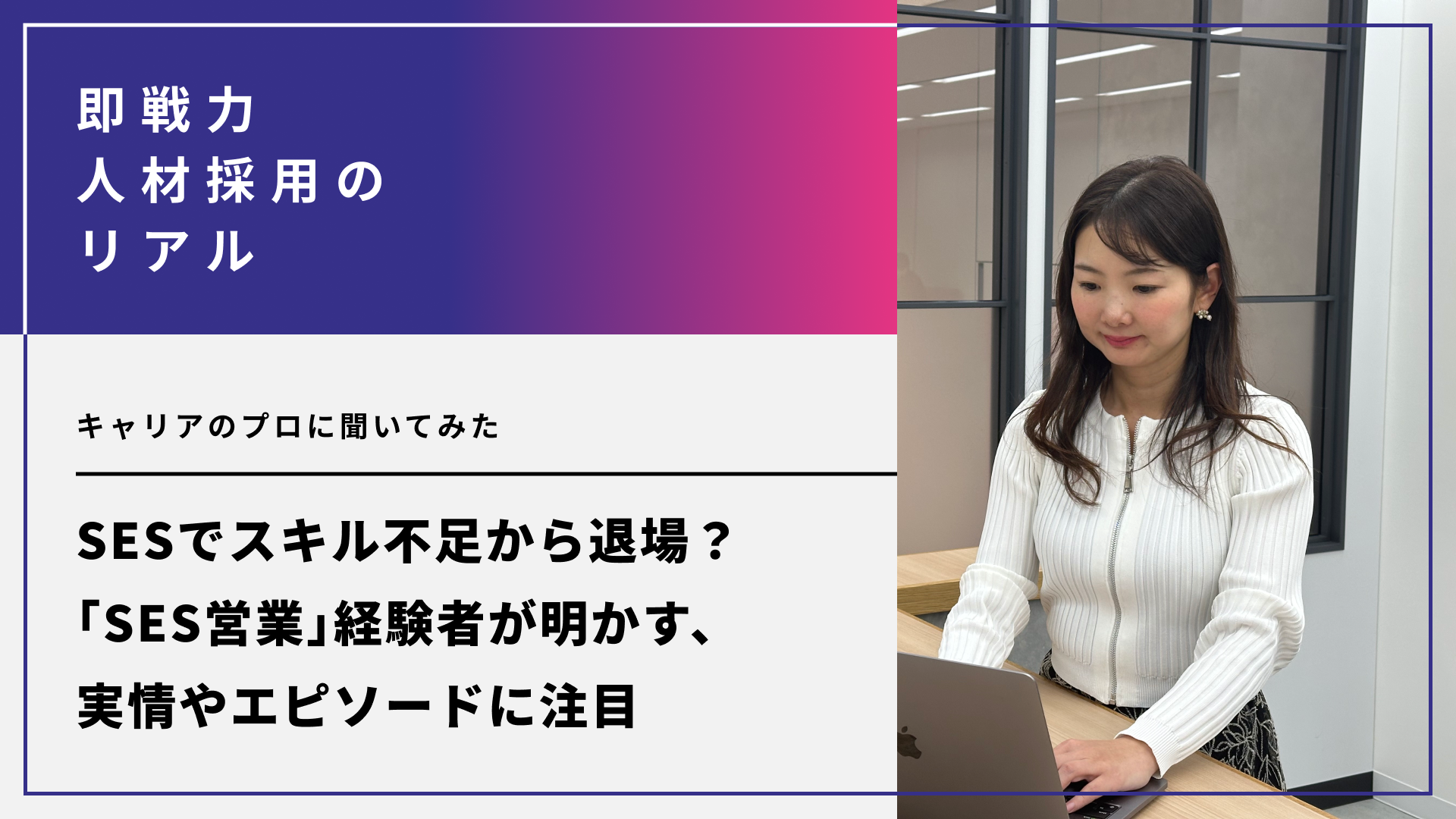人的資本経営への注目が高まる中、多くの企業が外部人材活用や情報開示に取り組んでいるが、なぜ期待した成果が得られないのか。
ビジネスリサーチラボ代表として、アカデミックな知見をビジネス現場に橋渡しする活動を続ける伊達洋駆氏に、真の変革を生む組織変化の本質と、人的資本経営の落とし穴について聞いた。
伊達洋駆氏プロフィール

神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』(すばる舎)等。
アカデミックな知見をビジネスに橋渡しする挑戦

— まず、ビジネスリサーチラボの事業について教えてください。人事データ分析が中心とのことですが、そもそもなぜアカデミックな知見をビジネスの世界に届けようと思われたのでしょうか。
私はもともと学部時代は心理学、特に教育心理学を専攻していました。そこでデータ分析や人間の心理を測定する方法といった基礎を学んだ後、大学院では経営学に進学したんです。
経営学に進学したきっかけは、教育心理学と比べて経営学の方が実践との距離が近いだろうという期待を持っていたからです。ところが、実際に大学院に入ってみると、あまり距離が近いわけではないということに気づきました。学問とその実践との距離に問題意識を抱くようになったんです。
論文を書き終えた後に、原点的な自分のモチベーションや問題意識として思い出したのは、研究と実務の距離が少し遠いのではないかということでした。そこで大学院在籍中に、現在のビジネスリサーチラボの原型にあたる活動を始めました。研究の知見や研究で培った技術を使って、市場に対して価値を提供する。そのことによって様々なデータや知見が得られるので、それをまた学術界に還元していく。
研究室は大学の中に作られるというのが一般的だと思うんですが、市場の中に研究室を作れないかなと。それがもともと考えていた問題意識だったんです。そのような経緯もあり、アカデミックな知見を産業界で活用していくということを事業として始めました。
オーダーメイド型の価値とHR事業者との共創

— 事業の内容が単なるコンサルというよりも、クライアントの内製化支援に重点を置かれているように見えます。このスタイルについて詳しく教えてください。
大きく分けると、この業界のサービスはオーダーメイド型かパッケージ型かの2つに分かれると思います。オーダーメイド型は、クライアントに応じてゼロベースから作り上げて、そのクライアントに寄り添って最適なソリューションを提示していくやり方です。一方でパッケージ型は、知識を標準化させた手続きに落とし込んで、それをプロダクトとして提供するものです。
弊社はオーダーメイド型を得意としています。特に企業の人事向けにオーダーメイド型のサービスを提供していて、例えばデータ分析や組織サーベイなどのサービスを提供するにあたって、それぞれの企業に応じてゼロベースで分析を立ち上げたり、調査を設計したりしています。
一方で、HR事業者(企業人事を顧客としてサービスを提供している企業)からご相談いただき、パッケージ型のサービスを構築する支援も行っています。
とはいえ、パッケージ型のサービスもオーダーメイドで設計することになります。このようなオーダーメイド型のサービスをひたすら提供している会社というのは、実は非常に少ないんです。このノウハウを持っている会社はほとんどありません。
外部人材活用の二つの価値:補完型と変革型

— 現在、多くの企業は人手不足をはじめとする様々な課題に直面しており、その解決策のひとつとして外部人材活用への期待が高まっています。こうした状況の中で、外部人材活用の価値をどのように再定義すべきでしょうか。
外部人材を活用する際に分岐点になるのが、自社の仕事の進め方やルーティン、習慣、実践の方法を変えるのか、変えないのかという点です。
変えないという方向性に行くと、そこにおける外部人材の価値は「労働力の補完」になります。例えば1から10のステップがあって、このうち7から9の部分が今不足しているので、そこをおこなってくれる人を探しています、といった形です。
もう1つの方向性は、自社のルーティンや実践、考え方、習慣を変えることを前提とした関わり方です。例えば、フリーランスの技術者の方から、仕事の進め方について「他社ではこのように進めていて、この方が便利ではないでしょうか」という提案を受け、それをもとに自分たちの仕事の進め方を見直して修正を加えていくようなケースが考えられます。
前者の補完的な要素で得られる価値は、マッチングのプラットフォームが機能していれば、ある程度うまくいきますが、変革的な価値を得ようとすると、自分たちのルーティンを意識して、変革に対応していく必要が出てきます。
組織学習と変化への抵抗
— 組織は一朝一夕で変わらないという認識は多くの人がもっているものだと思います。変化への抵抗ということもできると思いますが、ここについてもう少し詳しく教えてください。なぜ変革型の価値実現は困難なのでしょうか。
自社を変えていくという方向性は、とても難しいんです。なぜ難しいかというと、基本的に変えたくないからです。「うちにはうちのやり方があって、今までこのように進めてきており、今更変えることはできない」といった形で、ダイレクトに反発されるか、あるいは無視されて終わってしまうことが多々あります。なぜならある組織が現在当たり前に行っている実践や考え方は、学習の産物なんです。その組織にとって、突然現れたものではなくて、自分たちが仕事を進めたり、外部の人と関わったり、それから内部で統制を効かせたりするために、様々な試行錯誤をしながら学習してきた産物だということです。
逆に言うと、外部の人が何かしら知識やアイデアを提供した際に、何も抵抗が起きないと、それは何も学習してない組織ということになってしまいますので、それはそれで非常事態と言えます。抵抗が起きないということは、自分たちが守るべきものがない、つまり勝ちパターンが生まれてないということです。ですので、勝ちパターンが築かれている組織であれば、反発が生まれます。
このように、「現状を何とか維持したい」という状況の中で物事を変えていくことは難易度が高いのです。
社内人材が主人公:変化を推進する真の力
— では、どうすれば組織を変えていけるのでしょうか。
結局主人公になるのは社員なんです。外部人材は知見を持ち込んでくる、つまり異質なものを持ち込んでくる役割を果たしますが、組織のルーティンを変えていけるのは社員の方なんです。
組織を変えるには、外部人材が提案する新しい知識を自社の文脈に合わせて翻訳し、時間をかけて自分たちのルーティンの中に組み込んでいく、粘り強いプロセスが必要です。例えば、外部で使われている言葉と社内の言葉は違いますし、プロセスも翻訳する必要があります。さらに、仕事の進め方が変われば信頼関係も変化します。これらをきちんと調整していく必要がありますし、そういったことを外部人材が全て担えるかというと、それは難しいでしょう。
ですから、社員が翻訳と調整の役割を担っていく必要があるわけです。外部人材の知恵をうまく生かし、自分たちを変えていく時の主人公は、社内の人間です。
社員がその役割を担えないとうまくいかないという点は少し難しいポイントですね。 粘り強い反発の中を少しずつ進み、賛同者を増やしていくという地道なプロセスを歩むことになりますので、非常に時間がかかります。
イノベーションに必要なのは、「粘り強さ」と「政治性」

— その困難なプロセスを乗り越えるために、何が必要なのでしょうか。
イノベーションを実現するには、「粘り強さ」と「政治性」が欠かせません。たとえば、外部の知識を取り入れて成功したイノベーションの事例はいくつもありますが、それらはすべて、ある程度以上の時間をかけて取り組まれています。1ヵ月で画期的な成果が出るような事例は、まずありません。通常のプロダクト開発ですら年単位の時間を要しますし、基礎的な技術の開発となると、10年、20年という長いスパンでの取り組みになることも珍しくありません。
こうしたプロセスの厄介な点は、先がまったく見えない状態で進めていかなければならないことです。さらに、自社の常識からすれば「これはうまくいかないのではないか」と思えるようなアイデアにこそ、イノベーションのヒントが潜んでいることが多いのです。そうしたとき、納得感のある知識が提示されれば、「試してみよう」と思えるきっかけになるかもしれません。そして、それが実践へとつながっていくのです。
しかし、当然ながら、こうした取り組みには反対意見がつきものです。周囲から厳しい声を受けることもあるでしょう。それでも、粘り強く取り組み続ける人がいて、さらにそれを支える存在がいてこそ、ようやくプロジェクトは前に進みます。全員が賛成するという状況は、むしろ危険かもしれません。それは、現状の延長線上にあるということであり、変化を伴っていないとも言えるからです。
多くの反対意見がある中で、ごく少数の賛同を得ながら、地道に取り組みを進めていく。時には社内のキーパーソンに協力を求め、説得を重ね、プロジェクトを少しずつ動かしていく。そうした積み重ねが不可欠です。
また、「こういう理由があるから価値がある」「この取り組みは他の分野にもつながる」といったように、適切な理由づけを行いながら、関係性を築き、粘り強くプロジェクトを継続させる。試行錯誤を繰り返しながら、少しずつ成果へと近づいていく。そのプロセスが、結果として大きな進化を生むのです。
推進する人と、それを支える人の存在が揃って初めて、イノベーションは実現します。業界全体を揺るがすような発見や進化は、ある日突然生まれるものではなく、長い年月をかけて水面下で積み重ねられてきた努力の結晶なのです。
メンバーシップ型雇用とイノベーションにおける「時間軸」のずれ
— 今の話は、ある意味で日本の組織特性とも関連しているように思います。メンバーシップ型雇用という観点ではいかがでしょうか。
時間軸は意識した方が良いでしょう。外部人材の活用に関して言えば、多くの場合は短期的なタームで物事を考えがちです。けれども、組織そのものが変化するプロセスには、時間がかかります。つまり、外部人材を活用するタイミングと、その効果が実際に現れてくるタイミングには、どうしても“ずれ”が生じるのです。
短期で成果が出るのは、既存の構造を前提とした補完的な活用です。たとえば、自社の仕組みの一部を担ってもらう形であれば、比較的すぐに小さなリターンは得られます。けれども、「自分たち自身を変えたい」と考える場合には、話が違ってきます。
外部から得た知見を活かしていくプロセスそのものが、時間のかかる作業になります。場合によっては、外部人材が現場を離れた後も、内部での調整や浸透が続いていくわけです。むしろ、外部人材が離れた後も調整が続けられるような体制が整っていてこそ、本当の意味で外部人材を活かしたと言えるのかもしれません。
新しい取り組みには時間がかかる。だからこそ、短期間のプロジェクトだけで完結させるのは難しいわけです。その中でどうやって価値を引き出すのか。それを考えると、誰かが残り続ける体制が必要になります。
特に重要なのは、プロジェクトの中心となる人物、いわば「主人公」が、一定期間以上その場に残り続けられるようにしておくことです。そうでないと、プロジェクトが空中分解してしまうリスクが高くなります。
最近では、イノベーションの推進において「多様な人材」「頻繁なメンバー交代」が良いとされることも多いですが、それはたしかに「入口の段階」では有効です。しかし、いざプロジェクトを進めていく段階になれば、予算、体制、組織調整といった現実的な課題が次々と浮上します。
そのような場面でこそ、粘り強く推進していく人が必要なのです。多様性や新陳代謝のメリットと、継続的な関与の重要性。これらを両立させるための設計が、イノベーションの成否を大きく左右することになるのではないでしょうか。
心理的安全性とリーダーシップ──多様性を活かすチームづくりの要点

— 外部人材と社員が存在するチームにおいて、どのようなリーダーシップが求められるでしょうか。
大前提として必要なのは、心理的安全性と信頼関係です。「何を言ってもいい」と感じられる空気があるかどうか。多様性があるのはもちろん良いことですが、それが単なる属性の違いで終わってしまっては意味がありません。多様な立場や視点を持つ人たちが、互いに遠慮せず、率直に意見を言い合える土壌があって初めて、多様性は力になります。
そしてもう一つ大事なのが、「フェーズを意識すること」です。外部人材とチームを組んで何かに取り組んでいるとき、それがイノベーションのプロセスのどの段階なのか──それを把握しているかどうかで、リーダーシップのあり方は変わってきます。
多くの場合、外部人材が関わる段階は「初期フェーズ」です。つまり、アイデア出しやコンセプトの整理、可能性の探索といった段階にいることが多い。ところが、その意識がないまま進めてしまうと、「なぜこのアイデアは実現しないのか」といった誤解が生まれがちです。今はまだ入口なのだという共通認識があれば、「これをどう次の段階につなげていくか」という意識が自然と生まれてくるはずです。
その上で大切になってくるのが、当事者意識と役割理解です。外部人材と内部メンバーがそれぞれの役割を理解し、自分がどこに責任を持つべきかを把握している状態。外部の人には外部だからこそ担える領域があり、内部の人にも同様に、内部にいなければできない役割がある。たとえば、社内の稟議プロセスや組織調整、根回しといったことは、やはり内部の人でなければ進められません。どんなに外部の人が優秀で政治的に動けたとしても、そこは代替できない領域なのです。
だからこそ、プロジェクトの設計段階から、そうした役割分担を前提にしたチーム構成を考えることが重要になってきます。外部の人が「自分はここに責任を持つ」という姿勢で臨み、内部の人が「自分は社内でこの活動を支える」と腹を決めて関わる。そうした関係性が築けたとき、チームは単なる集合体ではなく、真に連携のとれた「一体の組織」になっていく。
さらに重要なのは、契約期間の終了を越えてコミットしようとする意志です。外部人材が離れた後も、内部のメンバーが「これは自分の責任でやり切る」と決意を持って取り組むことが重要です。
人的資本開示の課題:最も重要な読者は「従業員」
— 最近話題の人的資本開示についてはどうお考えでしょうか。
開示はしないよりは、した方が良い。これは間違いありません。企業という存在には常に情報の非対称性がつきまといます。だからこそ、透明性を高めるという意味でも、可能な範囲で開示を行うことには意義があると思います。
とはいえ、人的資本の情報には、少し特殊な面があります。ある種の「厄介さ」が含まれているともいえます。
というのも、人的資本に関する情報には、独自のステークホルダーが関わってくるからです。その一つは求職者です。しかし、それ以上に意識すべきなのが、社内の従業員です。これは意外に思われるかもしれませんが、実は人的資本開示における最も重要な読者は、投資家でも求職者でもなく、従業員だと考えています。
なぜなら、従業員はその会社の「中」を知っているからです。社内で日々の業務に関わる中で、制度の運用実態、人事施策の効果、職場の空気感など、表に出ない部分までを含めたリアルな情報を肌で感じている。そのため、開示された情報が“実態とずれている”と感じたとき、最も敏感に反応するのが従業員なのです。
実際、日本企業を対象にしたある研究では、「人的資本開示を積極的に行っている企業ほど、従業員のエンゲージメントが低い」という逆説的な結果が示されています。これは非常に興味深いポイントです。
もちろん、企業が嘘をついているわけではないでしょう。ただ、開示にあたって「見せたい部分だけを強調する」傾向が出てしまうことは否めません。その結果、内部の人間からすると「実態とは違う」「良いところしか出されていない」と感じてしまう。こうした印象のズレが、エンゲージメントの低下につながってしまう可能性があるのです。
従業員を起点とした経営改善

— どうすれば従業員と投資家、求職者のニーズを両立できるでしょうか。
一番大切なのは、まず良い会社をつくることです。その結果として、良い数値が生まれ、健全な開示が可能になる。この順番が逆になってしまうと、むしろ悪循環を引き起こします。
たとえば、自社の実態とはかけ離れた「良い姿」を開示してしまうと、社外の人、例えば投資家や求職者からは「この会社は素晴らしい」と映るかもしれません。しかし、内部の実情を知る従業員は冷静にそれを見ています。そこにギャップがあれば、当然エンゲージメントは下がる。すると、会社全体の状況も悪化し、開示された姿との乖離はますます広がっていく。こうしたネガティブな循環に陥ってしまうわけです。
最近では、「ストーリーを持って開示せよ」といった声もよく聞かれます。それ自体は悪いことではありません。けれど、開示の「巧みさ」を追求すればするほど、従業員との認識ギャップが大きくなるリスクがある。だからこそ、開示ありきではなく、「会社ファースト」であるべきです。
まず会社の中身をきちんと整え、その上で、それを素直に伝えていく。この順序が正しく保たれていれば、従業員にとっても誇りが持てますし、それが外にも伝わることで、さらに良い循環が生まれる可能性が高まります。この順番でアプローチできるかどうかが、成功と失敗を分ける鍵になります。
— 人的資本と従業員の幸福、そして企業価値の最大化を両立するビジョンについて、どうお考えでしょうか。
鍵になるのは、「誰を起点に経営を考えるか」という視点だと思います。投資家が知りたいのは、やはり企業の実態に関する情報です。どの企業に投資するかを判断するために、実態に近いデータが求められる。求職者も同じです。自分に合う会社かどうかを見極めるには、その企業の実際の姿を知る必要がある。だからこそ、「実態を正しく伝える」ということは、すべてのステークホルダーにとって意味があることなんですよね。
とはいえ、企業側にはどうしても「よく見せたい」というインセンティブが働いてしまいます。それ自体は自然なことです。ただ、それが行き過ぎてしまうと、実態との乖離が生まれ、特に従業員からの信頼を失いかねません。
ここで重要なのが、「従業員から入る」という考え方です。これは単に従業員を「大切にしましょう」という意味ではありません。従業員から入り、その中で投資家や求職者も大事にしていくという順番で考えるということです。
投資家も、求職者も、いずれも「外部」のステークホルダーです。しかし、求職者は将来の従業員ですし、企業が本当に持続可能な価値を生み出していくためには、やはり中で働く人たち、すなわち従業員の納得と共感が欠かせません。
実態に基づく情報を開示する。もちろん簡単ではありませんが、それをやり切る覚悟が必要です。なぜなら、情報格差をなくしていくこと自体が、企業への信頼を生み、すべてのステークホルダーにとって価値あるものになるからです。
そして、その実態を語る際、最も緊張するのは「従業員が目の前にいる場」です。この緊張感こそが、企業にとって健全なプレッシャーになります。従業員に対して語れる内容であるかどうか。それを常に意識することで、良い緊張感を生み、組織の実態を改善する動きへと発展していきます。
人・組織・事業を「一体」として見る視点を

— 最後に、人的資本経営に取り組もうとされる経営者や人事責任者に向けてメッセージをお願いします。
「人と組織と事業をきちんと見つめる」という視点を持ってほしいということです。ここから出発することで、多くの取り組みは自然とうまく進みやすくなります。
近年は、社会からの要請、競合の動向、トレンドなど、外部からのプレッシャーに基づいて施策を始めてしまうケースも少なくありません。しかし、それでは本質的な改善や変化にはつながりにくいのです。
大切なのは、自分たちの「内側」から始めること。つまり、自社の人材や組織の状態、そして事業の現実から丁寧に向き合っていくことです。「今、私たちの人と組織と事業は、どうなっているのか?」「これをもっと良くしていくには何が必要なのか?」そのような問いから経営を組み立てていく姿勢が、何より重要だと考えています。
ところが実際には、この「人・組織・事業」の関係がブラックボックスのようになってしまったり、あまり意識されていなかったりすることも少なくありません。しかし、当たり前のことではあるのですが、人と組織と事業は常に一体として動いているシステムです。それぞれが切り離せるものではなく、相互に影響しあいながら、強力なエネルギーを持って企業を動かしています。
だからこそ、そこに何か新しい施策や考えを「加えよう」とする際には、ただ追加するだけでは通用しない。そのシステムの性質や力学を理解した上で、「どこを、どう変えていけばよいのか」を見極めていく必要があるのです。
まとめ:人的資本経営の本質を見極める
人的資本経営が単なる制度設計や開示の問題ではなく、組織の本質的な変革に関わる複雑なプロセスだというのは重要な指摘だろう。
多くの企業が外部人材活用で「補完型」に留まるのは、「変革型」の困難さ故であることは明らかだ。組織の既存ルーティンは学習の産物であるからこそ強固であり、外部提案に反発を示してしまう。
真の変革の主人公は社内人材であり、外部人材は触媒に過ぎない。ここに長期的関与が可能な日本企業の強みが見えてくるともいえる。
人的資本開示では、投資家や求職者への配慮が先行しがちだが、最も重要なのは従業員の視点だ。実態と乖離した開示は組織内エンゲージメントを低下させ、企業価値毀損の悪循環を生む。
これらの洞察が示すのは、人的資本経営の成否が表面的な仕組みではなく、組織の内発的な変化への意志と能力にかかっているということだ。外部の要請に振り回されず、自社の人・組織・事業の現実から出発する重要性を考えるところがスタート地点だといえる。
関連リンク
株式会社ビジネスリサーチラボ公式HP: https://www.business-research-lab.com/