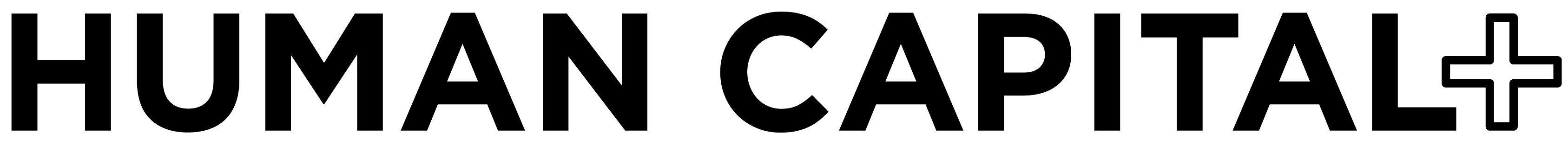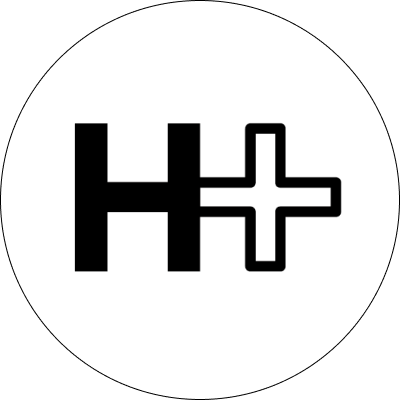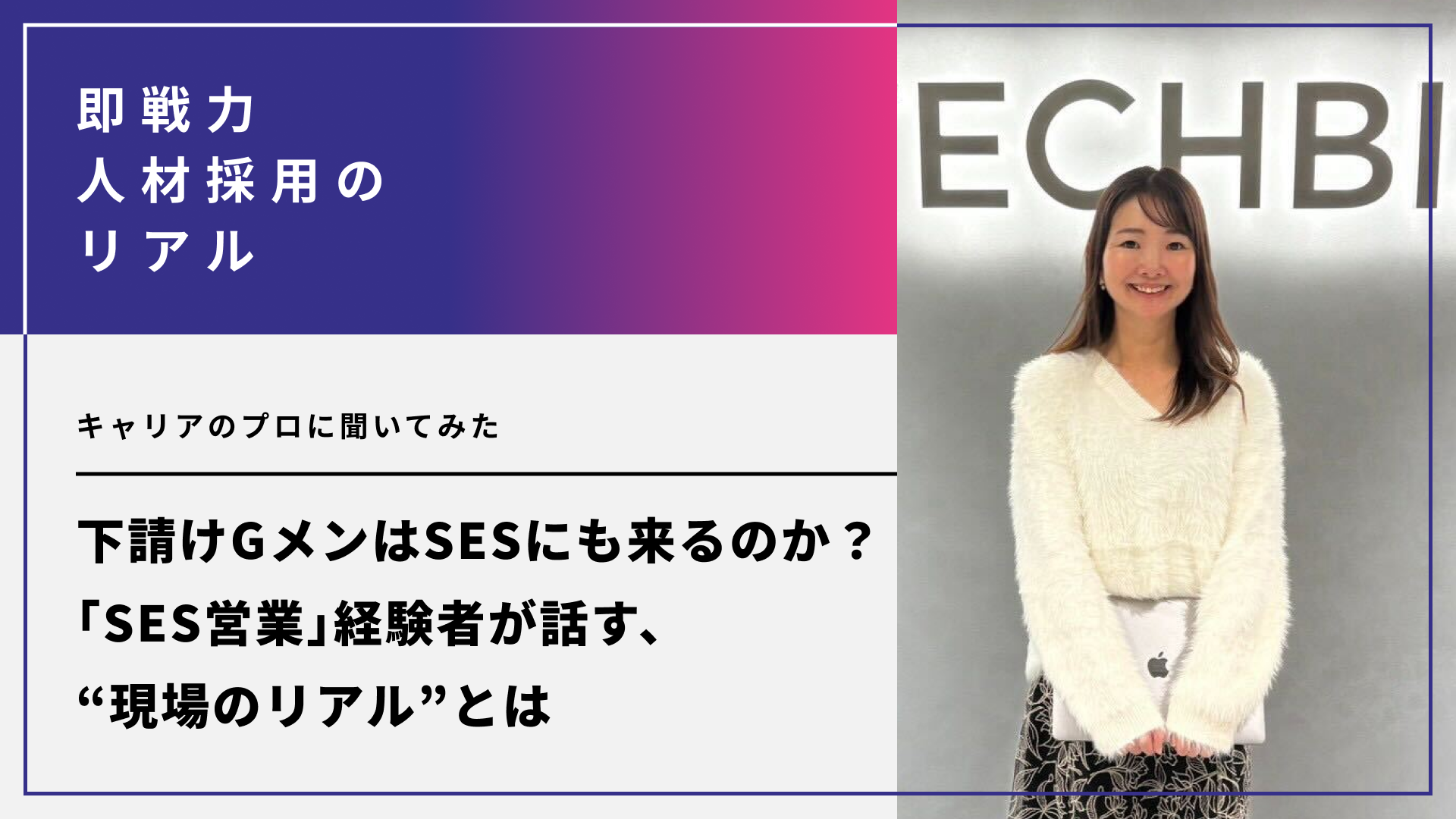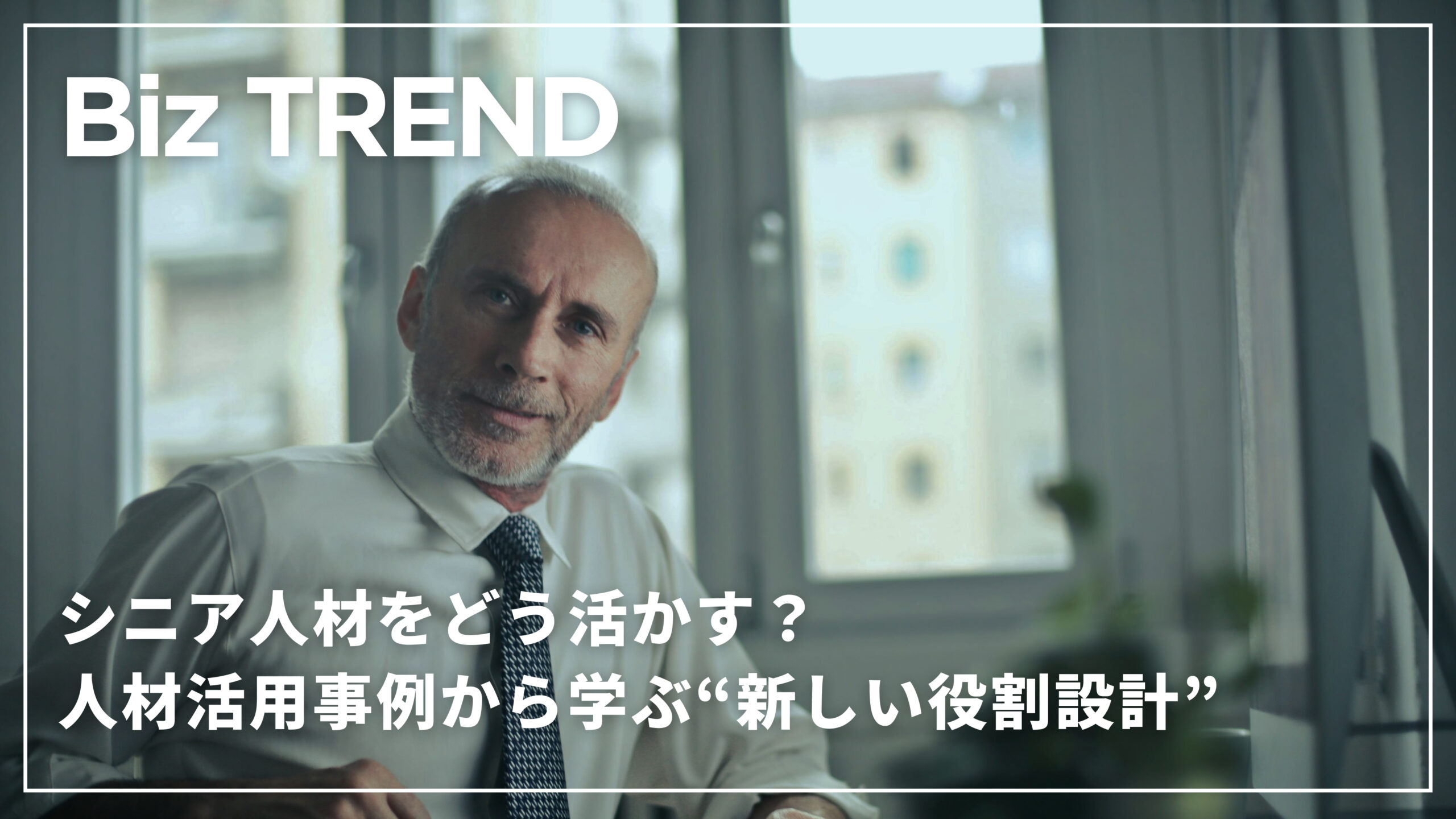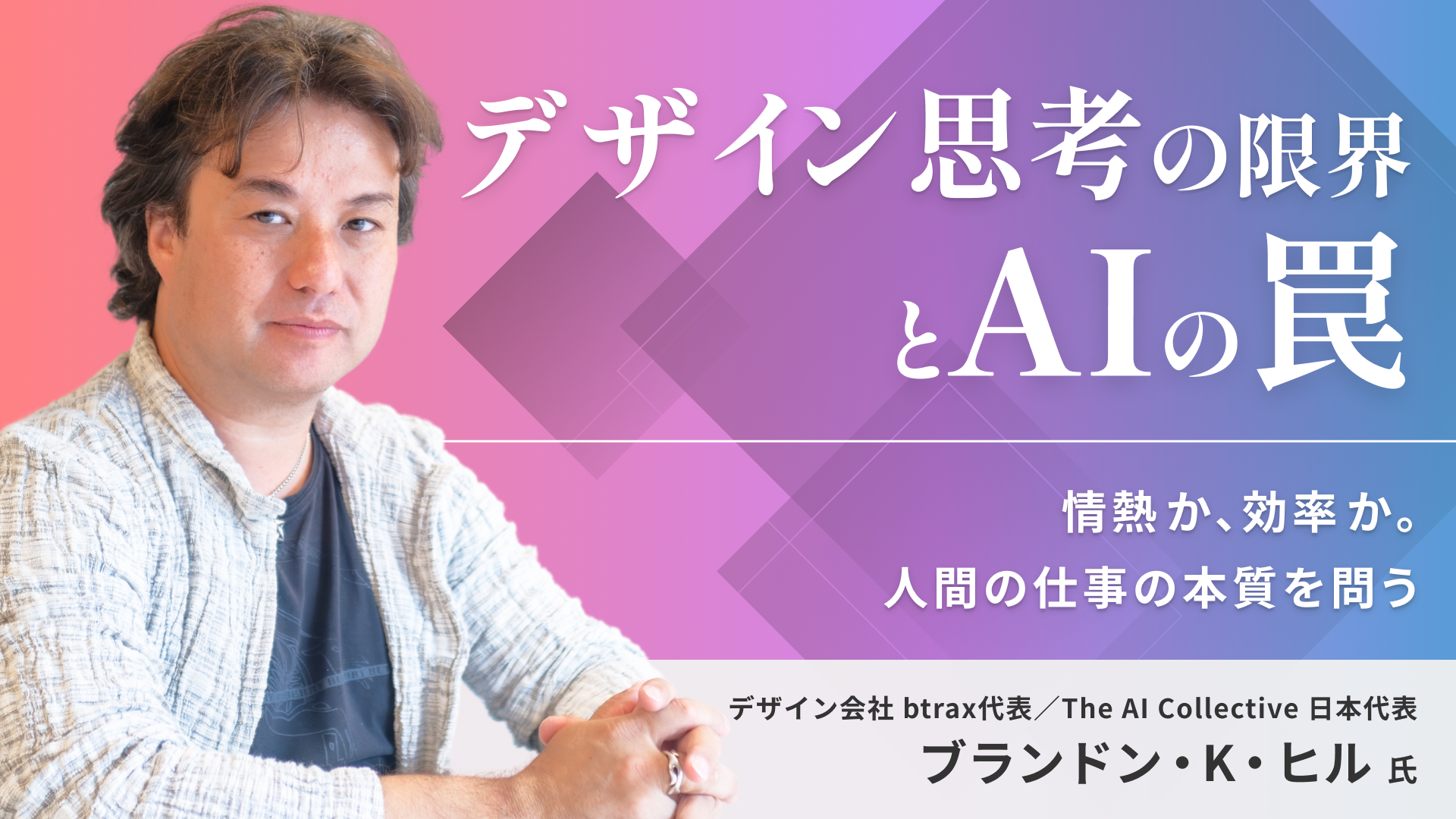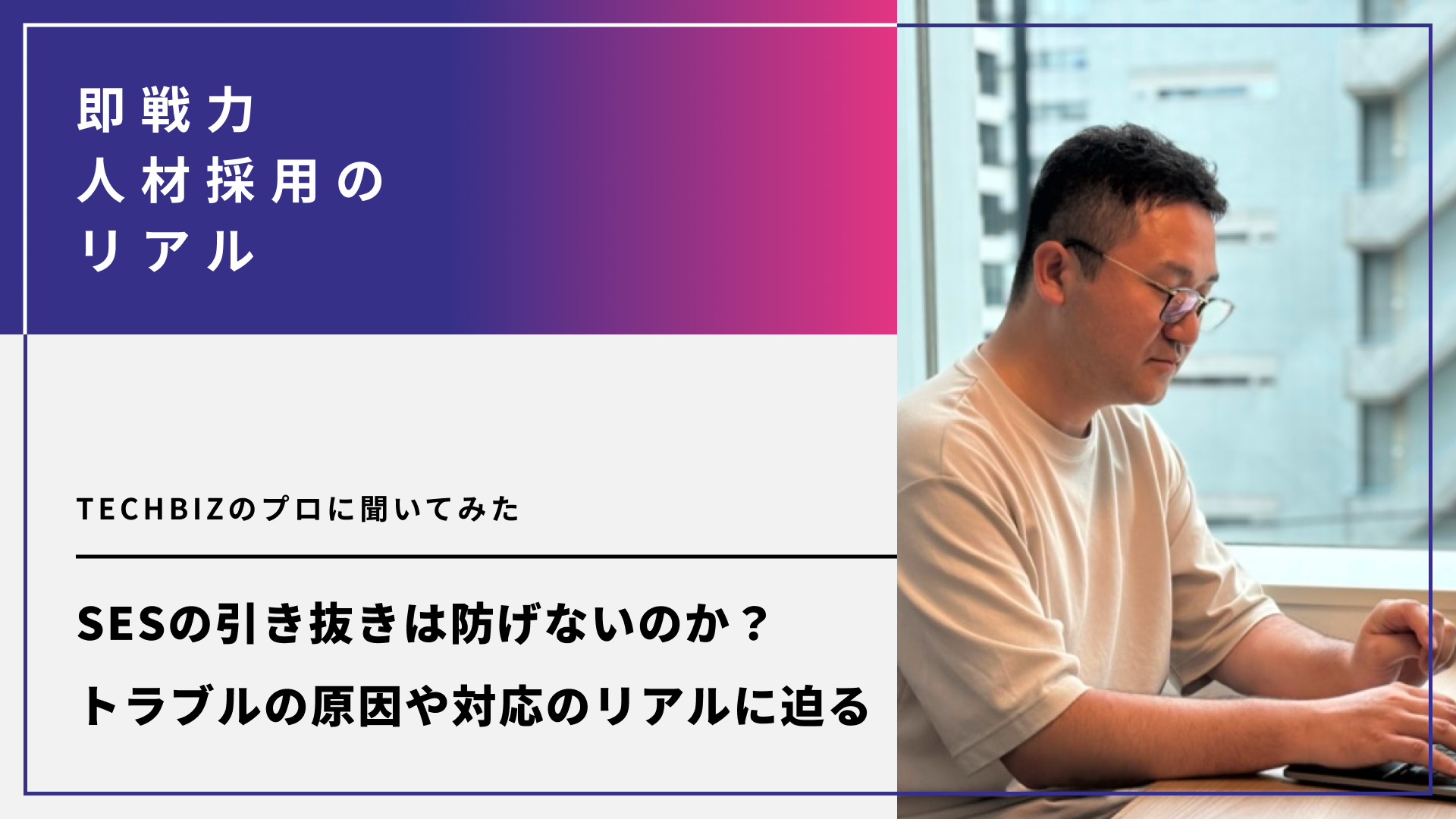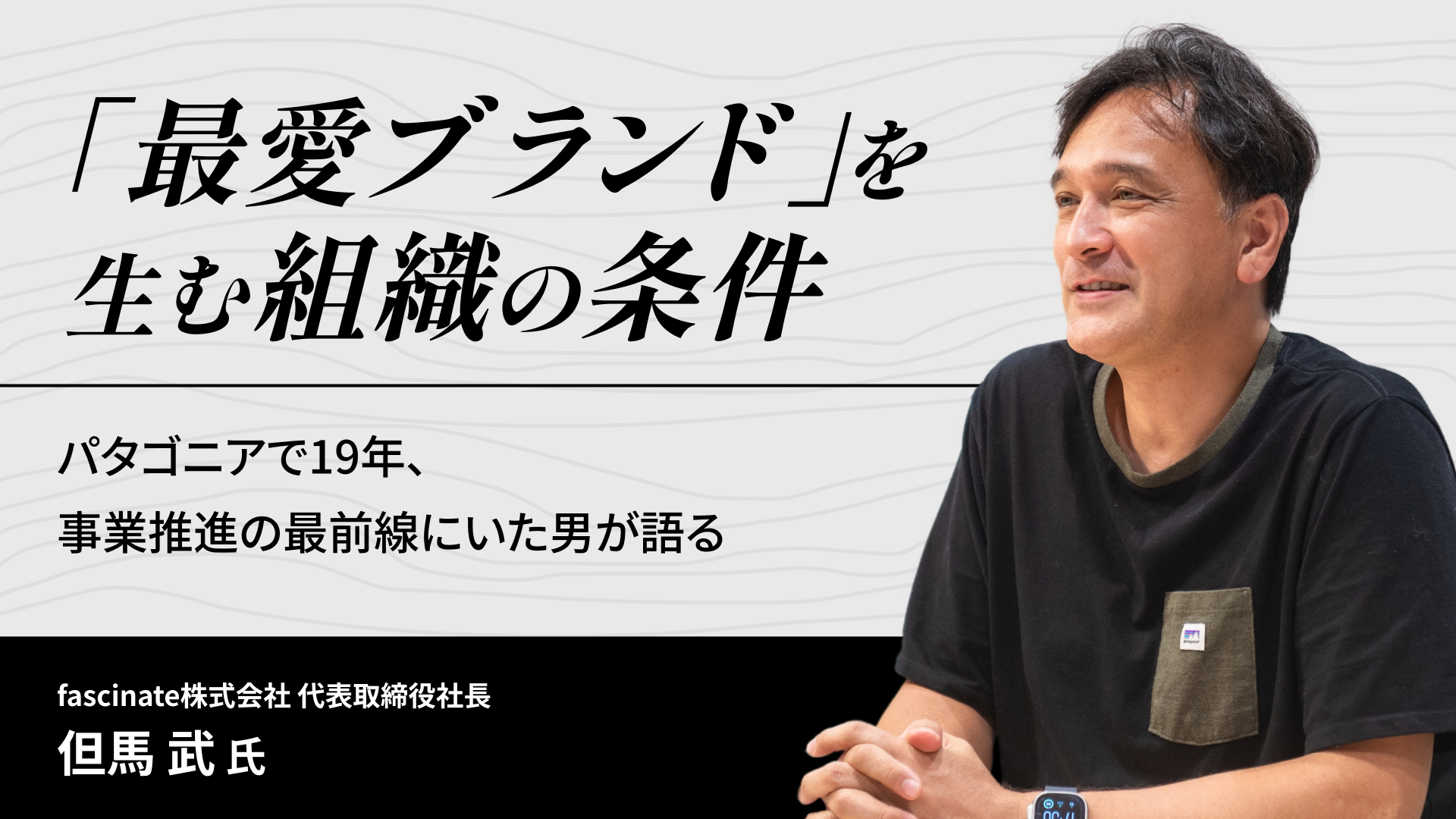HUMAN CAPITAL +
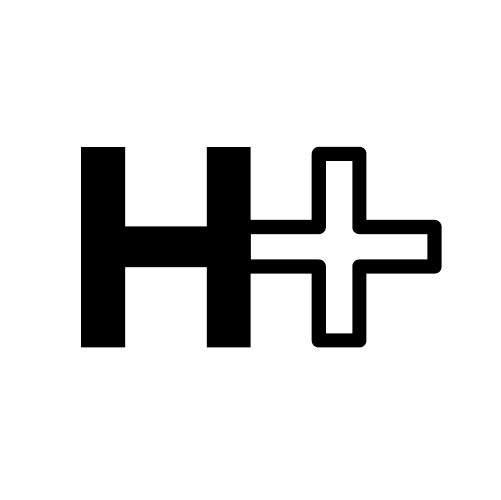
「HUMAN CAPITAL +」の編集部です。社会変化を見据えた経営・人材戦略へのヒントから、明日から実践できる人事向けノウハウまで、<これからの人的資本>の活用により、企業を成長に導く情報をお届けします。
1. DX内製化とは?重要性と企業が得られるメリット
DX内製化の定義と外部委託との違い
DX内製化とは、企業が自社のデジタル変革に必要なシステム開発、運用、保守を外部ベンダーに依存せず、自社の人材とリソースで実行することです。従来の外部委託では、要件定義から開発、テスト、運用まで全てを外部企業に任せることが一般的でした。
一方、内製化では企業が主体となって開発プロセスをコントロールし、自社のビジネス要件に最適化されたシステムを構築します。これは決して全てを自社で行うという意味ではなく、戦略的に重要な部分を内製化し、必要に応じて外部リソースを活用するハイブリッド型のアプローチも含まれます。
内製化が求められる背景と市場トレンド
企業を取り巻く環境や顧客ニーズが激変する中で、中小企業・小規模事業者においても、変化に柔軟に対応するための事業変革を進めるDX(デジタル・トランスフォーメーション)の重要性が高まっていると中小企業庁の2024年版中小企業白書で指摘されています。
特に、新型コロナウイルスの影響によりデジタル化が急速に進む中、多くの企業が外部ベンダーへの依存リスクを実感しました。開発スケジュールの遅延、コストの予算超過、そして何より自社のビジネスに最適化されていないシステムによる競争力の低下です。
さらに、AI技術の発展により、従来では考えられなかったスピードでの技術革新が求められています。この変化に対応するためには、外部ベンダーとの調整に時間をかけるのではなく、自社内で迅速に意思決定し、実行できる体制が不可欠となっています。
内製化がもたらす3つの主要メリット
コスト削減効果
内製化の最も分かりやすいメリットは、長期的なコスト削減です。外部委託では、ベンダーの利益分も含めた費用を支払う必要がありますが、内製化により直接的なコストのみで開発を進めることができます。
初期投資は必要ですが、継続的な開発案件がある企業では、2年から3年程度で投資回収が可能なケースが多く見られます。また、システムの仕様変更や機能追加の際も、外部ベンダーとの契約変更や追加費用を気にすることなく、柔軟に対応できます。
開発スピード向上
内製化により、企画から開発、リリースまでの期間を大幅に短縮できます。外部委託では、要件定義の擦り合わせ、契約手続き、開発ベンダーの社内調整など、多くの工程で時間がかかります。
内製化では、ビジネス要件の変更にも即座に対応でき、市場の変化に合わせた迅速なシステム改修が可能です。特に、競合他社との差別化が重要な業界では、この開発スピードの差が大きな競争優位性となります。
自社ノウハウの蓄積
最も重要なメリットは、開発・運用ノウハウが自社内に蓄積されることです。外部委託では、プロジェクト終了とともに技術的な知見も外部に流出してしまいます。
内製化により、システムの構造や運用方法を深く理解した人材が社内に残り、継続的な改善や新機能開発の土台となります。このノウハウは、単純な技術的知識だけでなく、自社のビジネスプロセスとITシステムの最適な組み合わせという、他社では得られない貴重な資産となります。
2. DX内製化の効果的な進め方3ステップ

Step1:現状分析と戦略立案
システム現状の把握と課題抽出
内製化を成功させるためには、まず自社の現状を正確に把握することが重要です。既存のシステム構成、外部委託している業務の範囲、社内IT人材のスキルレベルを詳細に分析します。
多くの企業では、長年の外部委託により、自社システムの全体像を把握している人材が不足しています。そのため、まずは外部ベンダーから詳細な技術文書を取得し、システムの棚卸しを行うことから始めます。
同時に、現在の外部委託費用、開発期間、品質問題の発生状況を数値化し、内製化による改善効果を定量的に予測します。この分析結果は、経営陣への提案や予算確保の根拠として活用できます。
内製化優先領域の決定
全てのシステムを一度に内製化することは現実的ではありません。自社のビジネスにとって最も重要で、かつ内製化による効果が高い領域から段階的に取り組むことが成功の鍵です。
優先順位を決定する際は、以下の観点から評価します。まず、ビジネスへの影響度の高さです。売上に直結するシステムや、顧客接点となるWebアプリケーションなどは優先度が高くなります。
次に、変更頻度の高さです。市場の変化に応じて頻繁に機能追加や変更が必要なシステムは、内製化による開発スピード向上の恩恵を受けやすくなります。
最後に、技術的な実現可能性です。現在の社内人材で対応可能な技術領域から始めることで、成功体験を積み重ね、より高度な領域への展開につなげることができます。
Step2:人材確保と体制構築
必要スキルの特定
内製化する領域が決まったら、必要な技術スキルと人材数を具体的に算出します。単純にプログラミングができる人材だけでなく、システム設計、プロジェクト管理、品質管理など、開発プロセス全体をカバーできる人材構成を検討します。
特に重要なのは、ビジネス要件とIT技術を橋渡しできる人材です。社内のビジネスプロセスを深く理解し、それを効率的なシステムに落とし込める人材が内製化成功の核となります。
採用戦略の立案(正社員・フリーランス)
日本企業は量的にも質的にもIT人材不足に陥っているとガートナーの調査で指摘されているように、IT人材の確保は多くの企業が直面する課題です。
従来の正社員採用だけでは、必要な人材を必要な時期に確保することが困難な状況が続いています。そこで注目されているのが、フリーランス人材の活用です。
フリーランス人材は、特定の技術領域に特化した高いスキルを持ち、プロジェクトベースでの参画により即戦力として活躍できます。また、正社員採用に比べて採用期間が短く、必要な期間だけ契約することで、コスト効率も向上します。
正社員とフリーランスの適切な組み合わせにより、固定費を抑えながら必要な開発力を確保する戦略が多くの企業で採用されています。
Step3:実行とPDCAサイクル
プロジェクト管理とKPI設定
内製化プロジェクトの成功には、明確なKPI設定と継続的な改善が不可欠です。開発コスト、開発期間、品質指標、顧客満足度など、複数の観点から成果を測定します。
特に重要なのは、外部委託時との比較データです。同規模のプロジェクトでの開発期間短縮率、コスト削減率、不具合発生率の改善などを定量的に把握し、内製化の効果を可視化します。
継続的な改善体制の構築
内製化は一度構築して終わりではなく、継続的な改善により効果を最大化する取り組みです。定期的な振り返りミーティング、技術勉強会、外部研修への参加など、チーム全体のスキル向上と改善意識の醸成が重要です。
また、成功事例や失敗事例を社内で共有し、他の部署や他のプロジェクトへの横展開を図ることで、組織全体のDX推進力を向上させることができます。
3. 内製化における人材確保の課題とフリーランス活用による解決策

従来の採用手法の限界
IT人材不足の現状
2030年には79万人の不足という深刻な数字が示すように、日本のIT人材不足は今後さらに深刻化することが予想されています。特に、DX推進に必要な高度なスキルを持つ人材は、大手IT企業による採用競争が激化しており、中小企業にとって確保が困難な状況が続いています。
この背景には、IT技術の急速な進歩により、従来のスキルだけでは対応できない新しい技術領域が次々と生まれていることがあります。AI、機械学習、クラウドネイティブ開発、DevOpsなど、企業が求める技術スキルの範囲が広がる一方で、これらの技術に精通した人材の供給が追いついていません。
採用期間とコストの課題
正社員としてのIT人材採用には、平均的に3から6ヶ月の期間が必要とされています。書類選考、複数回の面接、技術テスト、条件交渉など、多くのプロセスを経る必要があります。
さらに、優秀な人材ほど複数の企業から内定を獲得するため、採用競争が激化し、想定以上の高額な年収を提示する必要があるケースも増えています。年収800万円から1000万円以上の提示が必要な場合も珍しくなく、中小企業の予算では対応が困難な水準となっています。
また、せっかく採用した人材が早期に転職してしまうリスクも高く、採用コストの回収ができないまま再度採用活動を行う必要が生じることもあります。IT業界では転職が一般的な文化であり、2年から3年での転職も珍しくありません。
フリーランス活用のメリット
即戦力による開発スピード向上
フリーランス人材の最大の魅力は、即戦力として活躍できることです。多くのフリーランスエンジニアは、複数のプロジェクトを経験し、様々な技術や業界のノウハウを持っています。
正社員の場合、入社後に社内の開発環境や業務プロセスに慣れるまでに1から3ヶ月程度の期間が必要ですが、経験豊富なフリーランス人材であれば、1週間から2週間程度で本格的な開発業務に参画できます。
特に、新しい技術領域でのプロジェクトや、タイトなスケジュールでの開発案件において、この即戦力性は大きなアドバンテージとなります。
専門スキルへの柔軟なアクセス
フリーランス市場には、特定の技術領域に特化した高度な専門スキルを持つ人材が多数存在します。AI・機械学習の専門家、クラウドアーキテクト、セキュリティエンジニアなど、正社員として採用することが困難な専門人材に、プロジェクトベースでアクセスできます。
また、新しい技術トレンドに対応する際も、その分野の専門家を短期間で確保できるため、技術的な競争力を維持することができます。社内人材の育成には時間がかかりますが、フリーランス人材を活用することで、すぐに新技術への対応が可能となります。
コスト効率の改善
フリーランス活用により、人件費の変動費化が可能となります。プロジェクトの規模や期間に応じて必要な人材数を調整できるため、固定費の削減と効率的なリソース配分が実現できます。
正社員の場合、年間を通じて一定の人件費が発生しますが、フリーランスであれば実際の稼働期間分のみの費用で済みます。また、社会保険料や福利厚生費、オフィススペースなどの間接費も削減できます。
効果的なフリーランス活用のポイント
プロジェクト設計と役割分担
フリーランス活用を成功させるためには、プロジェクトの設計段階で明確な役割分担を定義することが重要です。フリーランス人材には、技術的な専門性を活かせる領域を担当してもらい、社内人材は要件定義や仕様調整など、ビジネス知識が必要な領域を担当する分担が効果的です。
また、成果物の定義を明確にし、品質基準や納期を具体的に設定することで、プロジェクトの成功確率を高めることができます。曖昧な指示や頻繁な仕様変更は、フリーランス人材のモチベーション低下や品質問題の原因となるため注意が必要です。
社内チームとの連携方法
フリーランス人材と社内チームが効果的に連携するためには、コミュニケーションツールの整備と定期的な情報共有の仕組みが不可欠です。SlackやMicrosoft Teams等のチャットツール、ZoomやGoogle Meet等のビデオ会議システムを活用し、物理的な距離を感じさせない協働環境を構築します。
また、週次の進捗会議やスプリントレビューなど、定期的な振り返りの機会を設けることで、プロジェクトの方向性を共有し、早期の課題発見と解決が可能となります。
品質管理とリスク対策
フリーランス人材との協働においても、品質管理は重要な要素です。コードレビューのプロセス、テスト工程の明確化、ドキュメント作成のルールなど、品質を担保するための仕組みを整備します。
また、フリーランス人材の急な離脱に備えて、複数の候補者との関係構築や、重要な知識の文書化とナレッジ共有を行うリスク対策も重要です。特に、プロジェクトの核となる部分については、社内人材も理解できるような引き継ぎ体制を整備することが求められます。
4. 内製化を成功させる組織づくりと運営のポイント

内製化チームの組織設計
必要な役割とスキルセット
効果的な内製化チームには、多様な役割と専門スキルを持つメンバーが必要です。まず、プロジェクトマネージャーは、技術的な理解とビジネス要件の調整能力を併せ持つ人材が適しています。開発全体の進行管理、品質管理、そしてステークホルダーとの調整を担当します。
システムアーキテクトは、技術的な設計方針を決定し、開発チーム全体の技術的な指針を提供します。この役割には、幅広い技術知識と豊富な開発経験が求められます。
開発エンジニアは、実際のプログラミング作業を担当しますが、単純なコーディングだけでなく、設計からテストまでの開発プロセス全体に対応できるスキルが必要です。
品質保証エンジニアは、システムの品質を担保するためのテスト設計と実行を担当します。テスト自動化のスキルや、様々なテスト手法に精通していることが重要です。
効果的なチーム編成
内製化チームの規模は、対象となるシステムの規模と複雑さに応じて決定しますが、一般的には5名から10名程度の規模が管理しやすく効果的です。あまり大きなチームでは、コミュニケーションコストが増大し、かえって開発効率が低下する可能性があります。
チーム内のスキルバランスも重要な要素です。経験豊富なシニアエンジニアと、成長意欲の高いジュニアエンジニアを組み合わせることで、技術継承と人材育成を同時に実現できます。
また、チームメンバーの配置については、固定的なチーム編成だけでなく、プロジェクトの特性に応じて柔軟に人材を配置できる体制を構築することが重要です。
ハイブリッド体制の構築
社内リソースと外部リソースの最適配分
内製化といっても、全てを社内で完結させる必要はありません。自社のコア業務に関わる重要な部分は内製化し、標準的な機能や専門性の高い領域については、外部リソースを活用するハイブリッド体制が現実的です。

このような戦略的な配分により、限られたリソースを効果的に活用し、内製化の効果を最大化することができます。
ナレッジ共有と技術継承の仕組み
ハイブリッド体制では、外部リソースが持つ知識やノウハウを社内に蓄積する仕組みが重要です。プロジェクト終了時の詳細な引き継ぎドキュメント作成、定期的な技術勉強会の開催、コードレビューを通じた技術共有などを実施します。
また、外部人材と社内人材がペアプログラミングやメンタリングを行うことで、自然な形での技術継承を促進できます。この取り組みにより、外部人材が離脱した後も、社内で継続的な開発と改善が可能となります。
持続可能な内製化のための取り組み
スキル向上支援
内製化を継続的に成功させるためには、社内人材のスキル向上が不可欠です。技術トレンドの変化に対応するため、定期的な研修受講支援、技術書籍の購入補助、カンファレンス参加費用の負担など、学習機会の提供を行います。
また、社内での勉強会や技術共有会を定期的に開催し、チームメンバー間でのナレッジ共有を促進します。外部講師を招いた技術セミナーの開催も、新しい技術への理解を深める効果的な手段です。
モチベーション維持施策
内製化チームのメンバーが高いモチベーションを維持できるよう、適切な評価制度と成長機会の提供が重要です。技術的な成果だけでなく、チームワークや改善提案なども評価対象に含めることで、多面的な成長を促進します。
また、開発したシステムがビジネスに与える影響を可視化し、メンバーが自分の貢献を実感できる環境を整備します。売上向上や業務効率化への貢献度を数値で示すことで、仕事への誇りとやりがいを醸成できます。
キャリアパスの明確化も重要な要素です。技術的な専門性を深める道筋と、マネジメントスキルを身につける道筋の両方を用意し、個人の志向に応じた成長支援を行います。
5. まとめ:DX内製化で競争力を高めるために
DX内製化を成功させるためには、段階的なアプローチと戦略的な人材活用が重要です。まず、自社の現状を正確に把握し、内製化する領域を戦略的に選択することから始めます。全てを一度に内製化しようとせず、成功体験を積み重ねながら徐々に範囲を拡大していくことが成功の鍵となります。
人材確保においては、従来の正社員採用だけでなく、フリーランス人材の活用を含めた多様な選択肢を検討することが重要です。特に、深刻化するIT人材不足の中では、即戦力となるフリーランス人材の戦略的活用が競争優位性の源泉となります。
組織運営では、社内リソースと外部リソースを適切に組み合わせたハイブリッド体制の構築により、限られたリソースを最大限に活用できます。また、継続的なスキル向上とモチベーション維持の仕組みを整備することで、持続可能な内製化体制を構築できます。
DX内製化は、単なるコスト削減手段ではなく、企業の競争力向上と持続的成長を実現する戦略的な取り組みです。適切な計画と実行により、自社独自の技術的優位性を構築し、変化の激しい市場環境で勝ち抜く力を身につけることができます。
ーーー
【TECHBIZ】では、DX推進に必要な専門人材のマッチングサービスを提供しております。エンジニアはもちろん、フリーランスの人事や財務経理の専門家もご紹介可能です。継続稼働率約97%の実績を持つ専任コンサルタントが、企業様のDX推進をサポートいたします。
DX推進に関するご相談やフリーランス人材の活用をご検討の際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
★「TECHBIZ」サービス詳細はこちら
即戦力人材の採用にお困りではありませんか?ハイスキルなITエンジニアをスムーズに採用できる【テックビズ】
TECHBIZでは優秀なITフリーランス人材をご紹介しています。スキルのみならず人柄も踏まえ、企業様にマッチした人材を、最短で即日ご紹介できます。即戦力人材の採用にお困りの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。