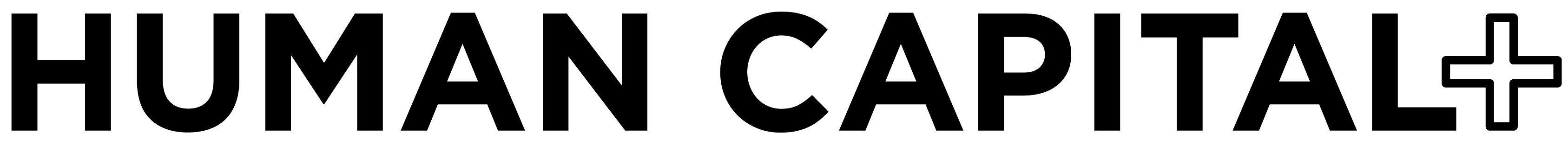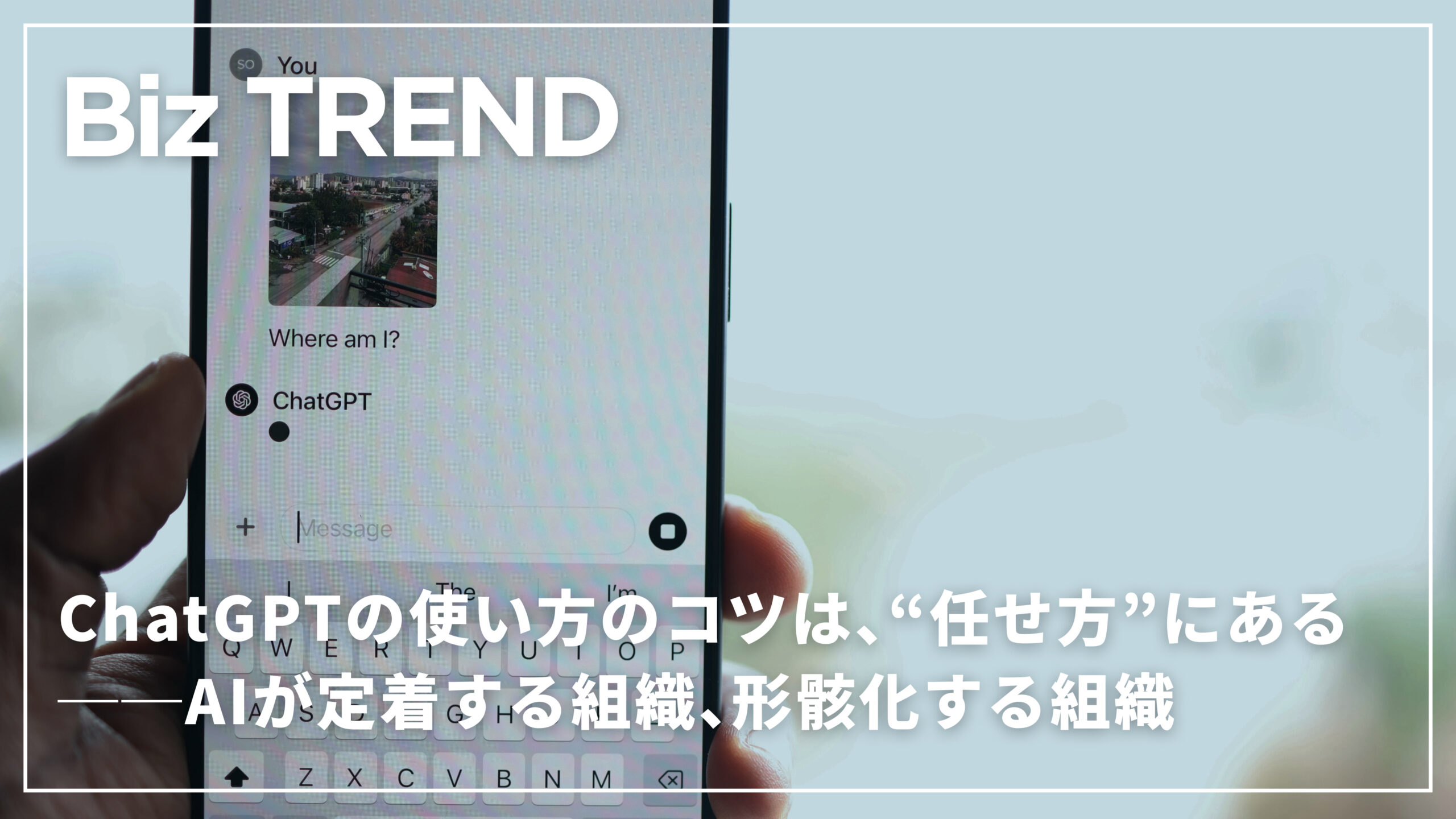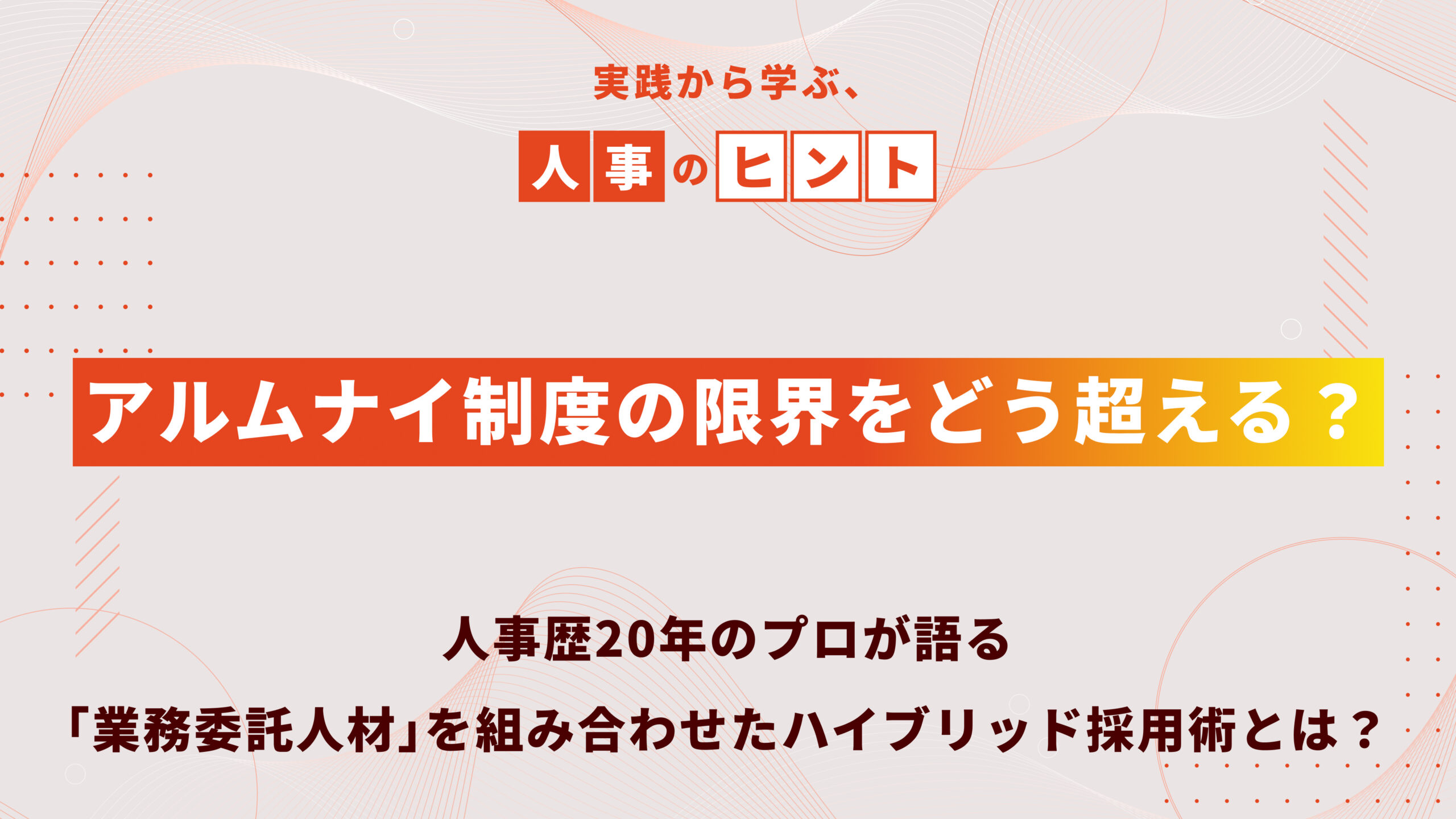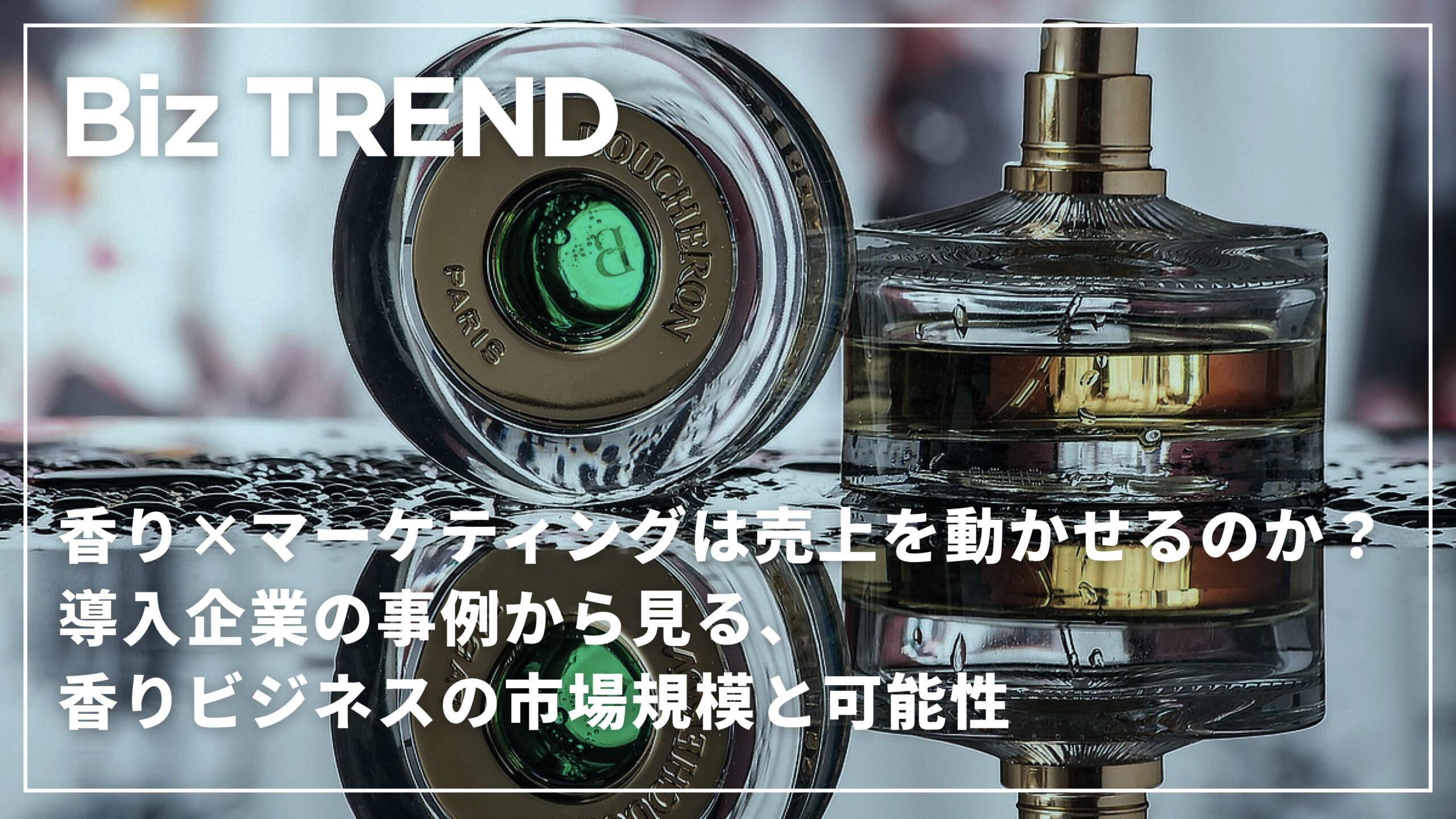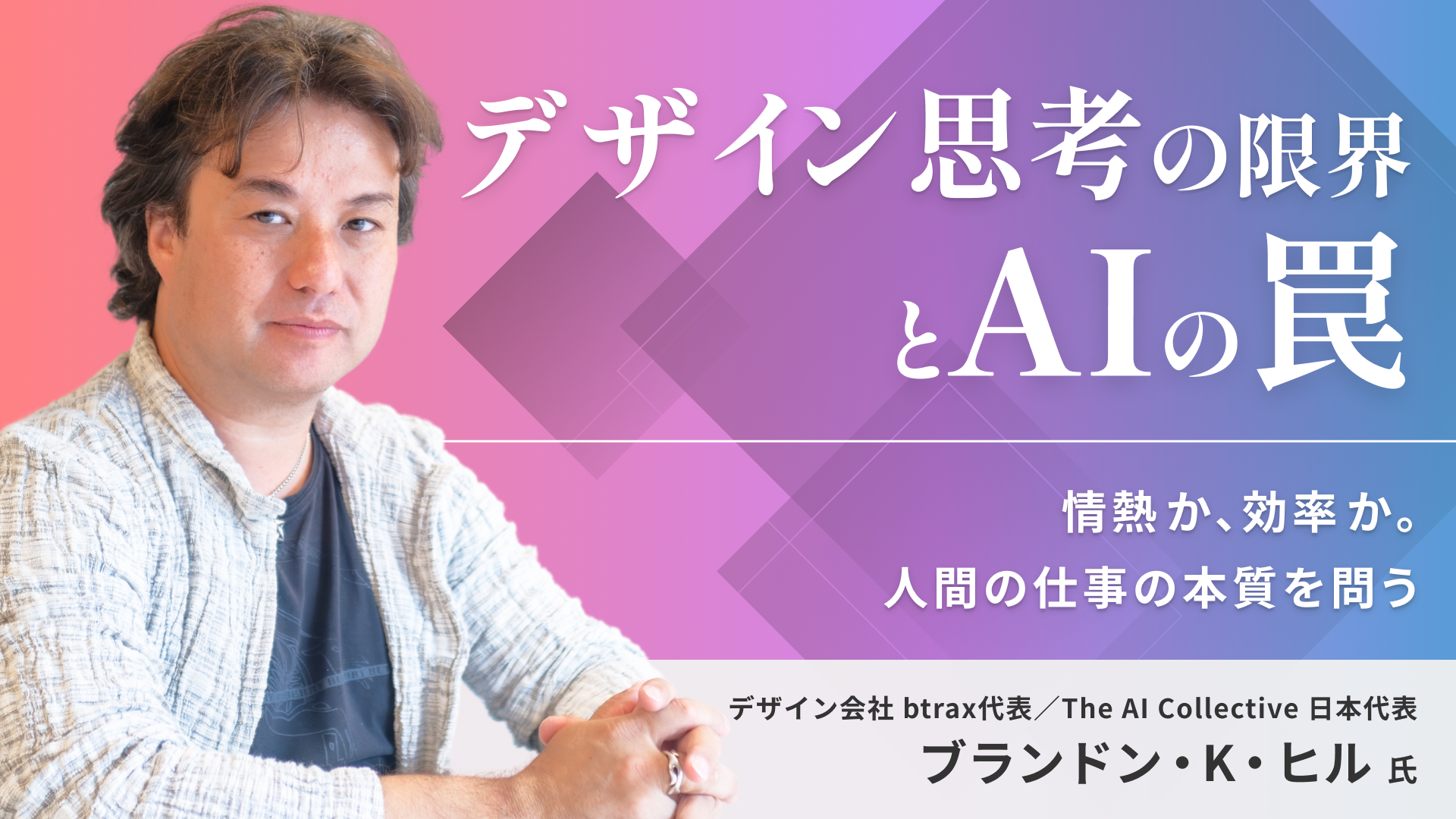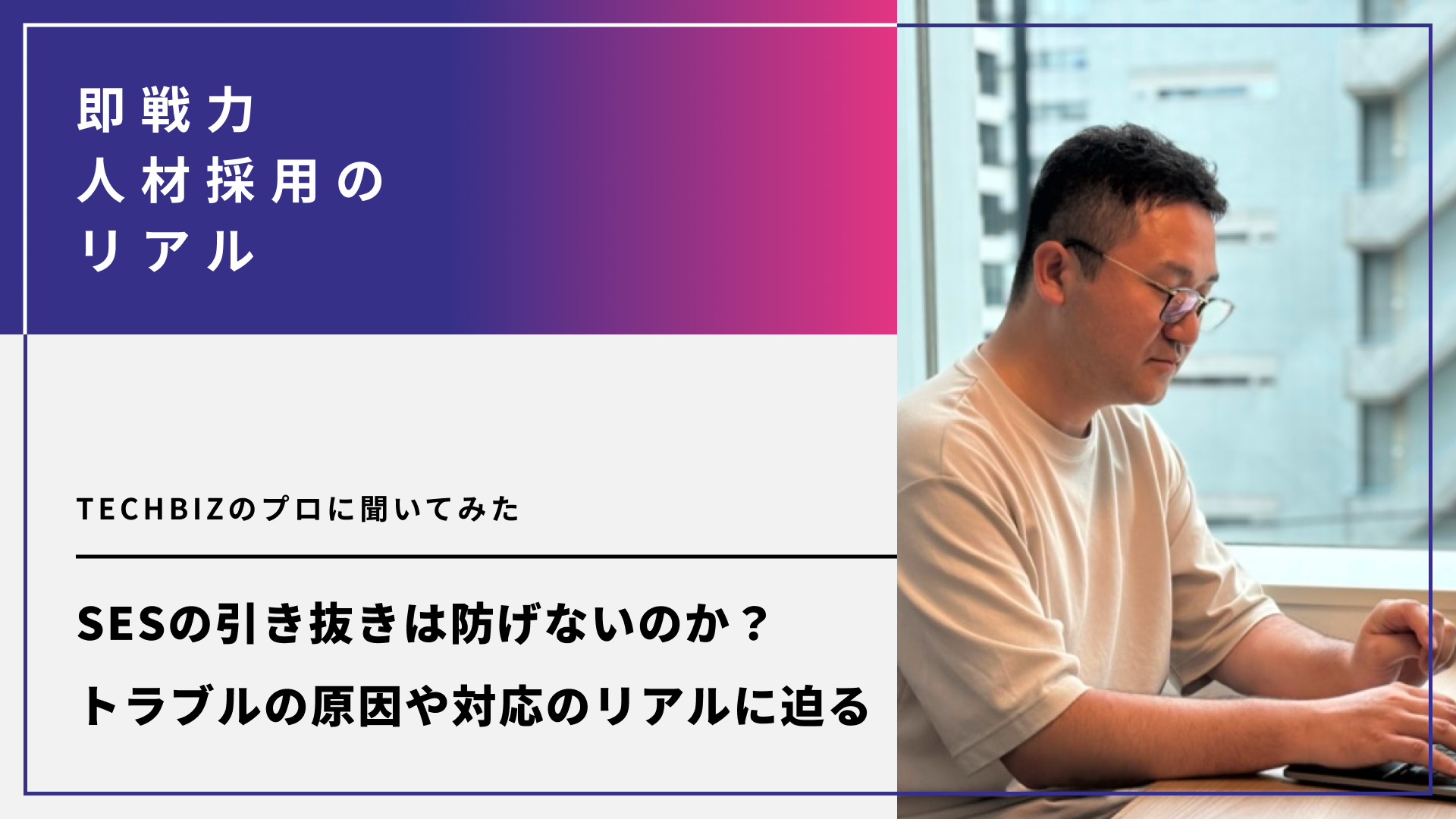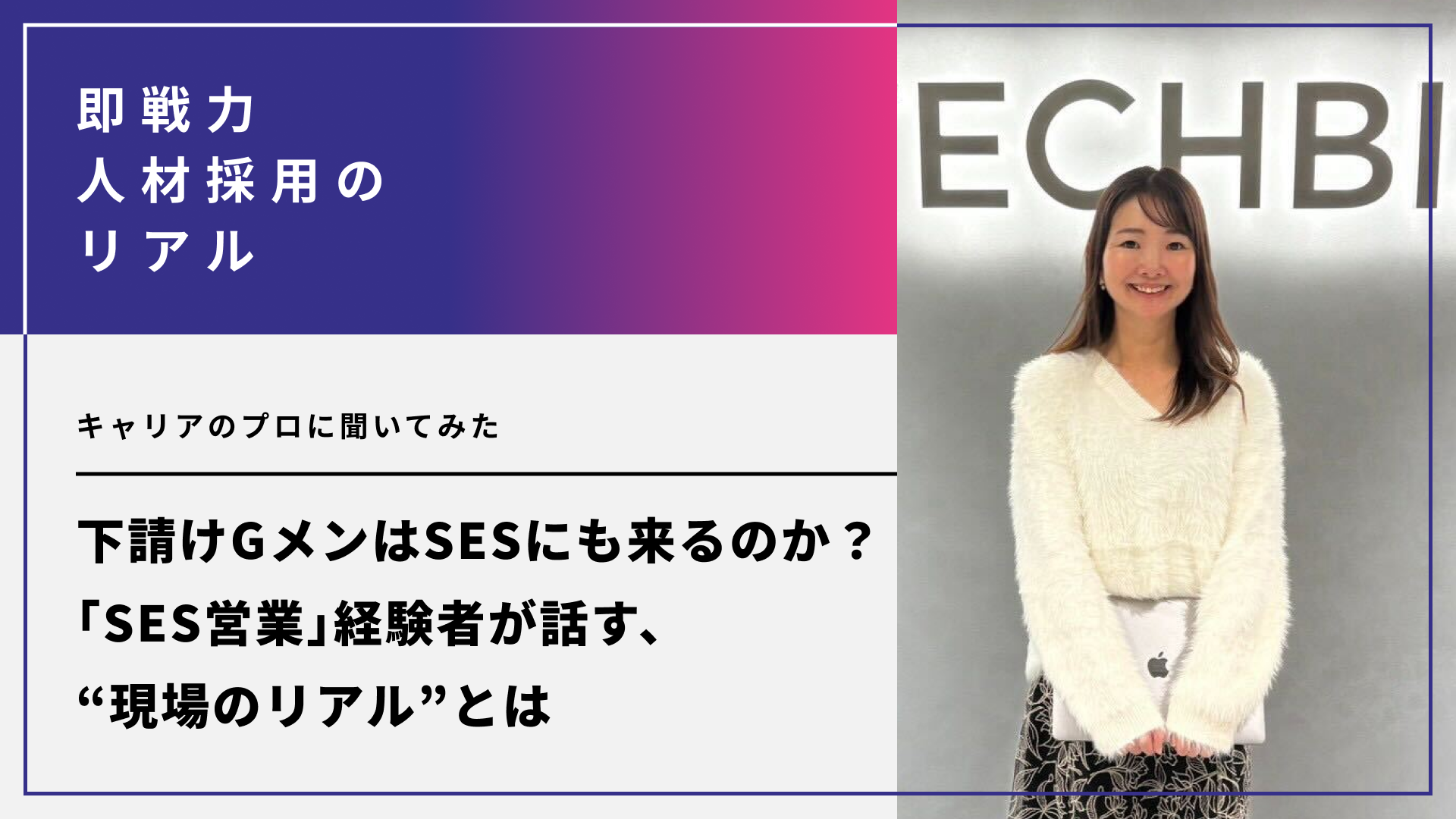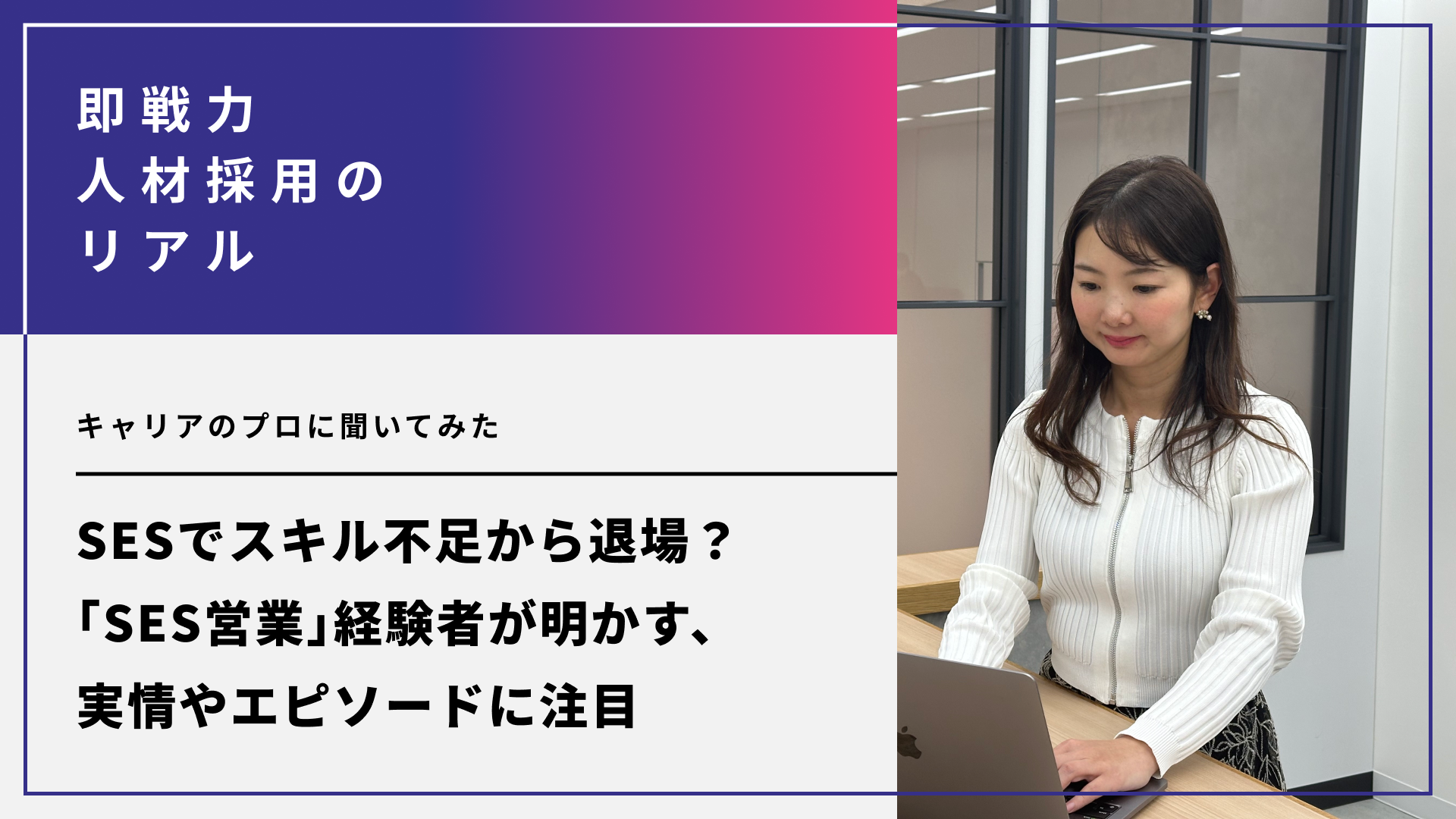生成AIの波が企業現場にも届いており、ChatGPTをはじめとするツールの導入事例も増えています。にもかかわらず、「プロンプトを考えるより、自分で作成したほうが速い」「AIに任せても思ったような回答が返ってこない」といった声も少なくありません。
これは、ただ単に“使い方がわからない”“どの業務に使えばよいか見えない”だけの話ではなかろうか。むしろ重要なのは、生成AIを「どう活用するか」よりも、「どう使われているか」を組織が問い直すことではないでしょうか。
ハイスキル・即戦力人材の採用にお困りならTECHBIZ
最短・即日で企業様にマッチした人材をご紹介【無料】お問い合わせはこちら →
ChatGPTの使い方のコツとは?熟練社員ほどAIアレルギーを起こす理由

企業における生成AI導入の動きは確実に加速しています。例えば、一般社団法人 日本情報システム・ユーザー協会(JUAS)の「企業IT動向調査2025」では、言語系生成AIを導入・準備中と回答した企業が41.2%に達したと報告されています。juas.or.jp また、矢野経済研究所の法人アンケートでは、“全社的に活用している”企業が4.0%、“一部の部署で活用している”企業が21.8%という進捗状況も明らかになっています。
このように「導入している/検討している」企業の割合は増加しているものの、“日常的に業務で活用されている”かというと、そう簡単ではないようです。たとえば、Netskopeの調査によると、日本企業の68%で従業員が生成AIアプリを「直接利用している」とされる一方、全従業員の月間アクティブユーザー率は平均1.4%にとどまるというデータも出ています。
この「導入」と「活用」のギャップが、多くの組織で見過ごされているのではないでしょうか。筆者の周りでも「プロンプトを調整しても、思った回答にならない」「結局、自分で作ったほうが速い」という経験豊富な社員からの声が多く聞かれます。なぜこのような“もどかしさ”が起きるのか――その鍵は、熟練社員の思考テンポと生成AIの対話テンプレートとのズレにあろうかと考えます。
長年、業務の流れを体得してきた経験豊富な社員にとって、AIに指示を出してから回答を得て修正を繰り返すというプロンプトを考えるプロセスは、むしろ“工程が増える”ように感じられることがあるのではないでしょうか。つまり、スキルが足りないというよりも、「自分の作業テンポのほうが速い」と感じてしまう構造。これが、AI活用が思うように広がらない背景の一つではないかと思うのです。
ChatGPTを“指示する相手”から“考える相棒”へ
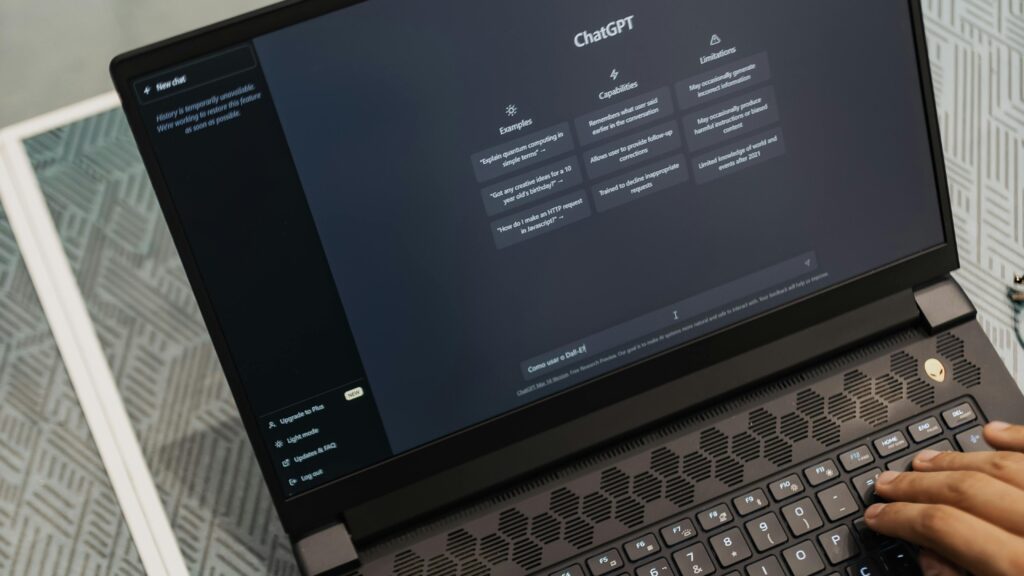
ChatGPTをはじめとする生成AIを組織に浸透させるために、多くの人が「使い方」ばかりを考えがちです。しかし、 実際には“どう向き合うか”の方が、定着の成否を左右するのではなかろうかと思います。
AIは正確なプロンプトを入力すれば理想的な回答を返してくれる——。
そんなイメージを持つ人も多いかもしれませんが、実際の現場では「試す→直す→また試す」の繰り返しです。つまり、AI活用とは“完成品を得る作業”ではなく、“共に考えるプロセス”と言ってもいいかもしれません。
たとえばAIを「ハーバード大学を首席で卒業した新入社員」と思ってください。 知識も思考力も桁違いに高い一方で、社内の業務フローや文化、判断基準については何も知りません。 そんな新入社員にいきなり「これを完璧にやっておいて」と指示すれば、戸惑うのは当然です。 AIが期待通りに動かないのは、能力の問題ではなく、上司である人間が“何をどう任せるか”を設計していないからではなかろうかと思います。
生成AIを効果的に活用している人ほど、AIを「万能ツール」ではなく、「育成すべきチームメンバー」として見ています。 仕事の背景や意図を丁寧に共有し、成果物に対してフィードバックを返す。 その繰り返しによって、AIとの対話の質が深まり、回答の精度も高まっていくのです。
つまり、AIを使いこなすとは、プロンプトの技術を磨くことではなく、「任せ方」「育て方」「信頼の置き方」を学ぶことではないでしょうか。AIを部下に見立てて対話することで、私たちは改めて“仕事を任せるとはどういうことか”を学び直せるのかもしれません。
AIとフリーランスは“組織の鏡”である
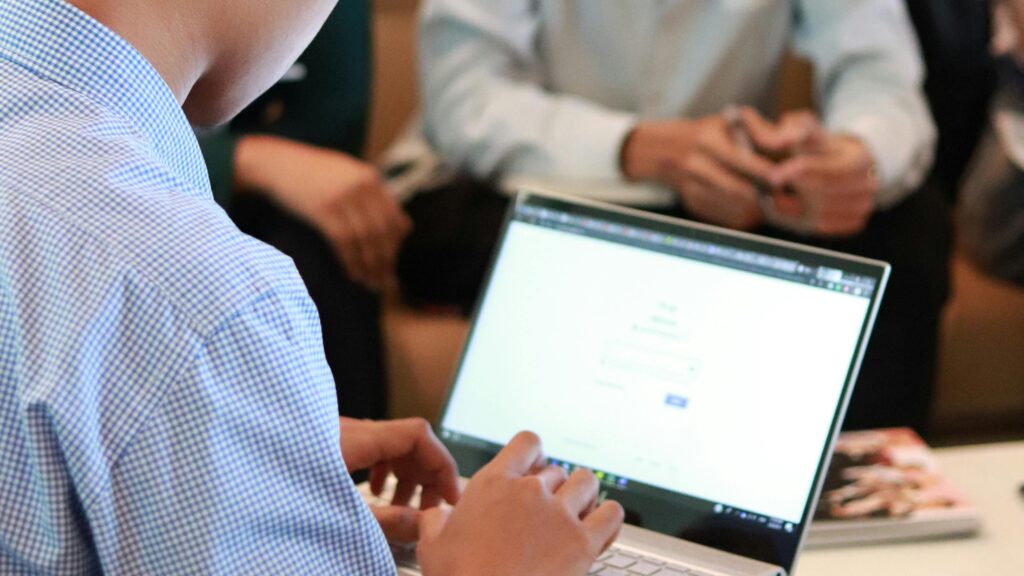
AIを上手に活用できる組織は、往々にしてフリーランスや外部パートナーとの協働にも長けているのではないでしょうか。 なぜなら両者に共通しているのは、「外部の知恵をどう生かすか」という問いだからです。AIもフリーランスも、自社の業務や文化、目的を知らない存在です。 それでも大きな成果を出せる企業があるのは、任せ方と関わり方を丁寧に設計しているからではなかろうかと思います。
たとえば、フリーランスに業務を依頼するとき。成果物を丸投げするのではなく、まず目的や背景を共有し、成果の基準をすり合わせる。このコミュニケーションの精度が、結果の質を左右します。AIもまったく同じで、「プロンプトの工夫」とは突き詰めれば、背景説明と期待値の共有にほかなりません。つまり、AI活用とは“依頼力”を磨くプロセスであり、フリーランスとの協働経験が多い組織ほどその重要性を理解しているように感じます。
また、AIや外部人材は社内ルールや“空気”に縛られていないため、時に組織の前提を問い直す役割も果たします。「なぜこの手順でやるのか」「本当にこの作業は必要か」。そうした視点はときに違和感を生みますが、その“ズレ”こそが新しい発想の源泉になります。AIもフリーランスも、組織にとっては自分たちの思考の癖を映し出す鏡のような存在なのかもしれません。
そして、優秀な外部人材を活かせる企業ほど、内部の人材も育ちやすいものです。なぜなら、任せ方がうまい組織は、信頼の置き方と成果への責任の持ち方を知っているからです。
AIも人も、適切な裁量とフィードバックを与えられて初めて力を発揮します。外部の知をどう扱うかは、内部の学びの仕組みをどう作るかに直結しているのではなかろうかと思います。
テックビズで、“外部知”を組織の力に変える
AIと同じく、フリーランスという外部の知をどう生かすかは、組織の成熟度を映す鏡です。
テックビズは、継続稼働率97%という実績を持ち、最短即日でプロジェクトに最適な人材をマッチング。契約から導入後のフォローまで一貫して支援するため、初めての企業でも安心です。
AIがもたらす変化のスピードに、すべてを内製で追いつくことは難しい時代です。 だからこそ、組織の外にある知識や経験を柔軟に取り入れ、“共に考え、共に進化するチーム”を育てることが求められています。 テックビズは、そうした企業の挑戦を支える「伴走者」になります。
最短・即日で企業様にマッチした人材をご紹介
【無料】お問い合わせはこちら編集後記:AI導入の本質は、現場に“自発性”を促すこと
これまで多くの企業を取材してきましたが、AIをうまく活用している組織にはいくつかの共通点があるように感じます。
ひとつは、特化型AIの活用です。ChatGPTのような汎用型AIは、幅広い業務に対応できる一方で、うまく使いこなすには一定のスキルやプロンプト設計のテクニックが求められます。一方で、請求処理や採用文書作成、議事録要約など、特定の業務を前提に設計された特化型AIは、UXが洗練されており、誰でも自然に使いこなせる仕様になっています。まずは特化型AIから導入することで、社員の「AIは難しい」というアレルギー反応を抑えられるのではないでしょうか。
もうひとつの特徴は、現場に“余白”をつくっていることです。 AIはものすごいスピードで進化しており、特定の部署や少人数の専門チームがトップダウンで見極めようとした瞬間に、すぐ陳腐化してしまいます。 むしろ、現場のメンバーが日常的に新しい生成AIツールに触れ、使えそうなものを試しながら横展開していく方が、結果的に効率がよいのではないでしょうか。
以前取材したある企業では、技術職一人に対して月10万円のAI予算を設定していました。
正社員・契約社員といった雇用形態を問わず、誰もが自由にAIを試せる仕組みを整えていたのです。 それによって業務効率が高まるなら、むしろ安い投資だと言えるでしょう。
AI導入の本質は、「社員を動かすこと」ではなく、「メンバーが自発的に動きたくなる組織」をどう設計するかにあるのではないでしょうか。 AIが日常に溶け込む組織とは、トップダウンではなく、挑戦の余白を許す文化を持った組織なのだと思います。
ハイスキル・即戦力人材の採用にお困りならTECHBIZ
最短・即日で企業様にマッチした人材をご紹介【無料】お問い合わせはこちら →
即戦力人材の採用にお困りではありませんか?ハイスキルなITエンジニアをスムーズに採用できる【テックビズ】
TECHBIZでは優秀なITフリーランス人材をご紹介しています。スキルのみならず人柄も踏まえ、企業様にマッチした人材を、最短で即日ご紹介できます。即戦力人材の採用にお困りの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。