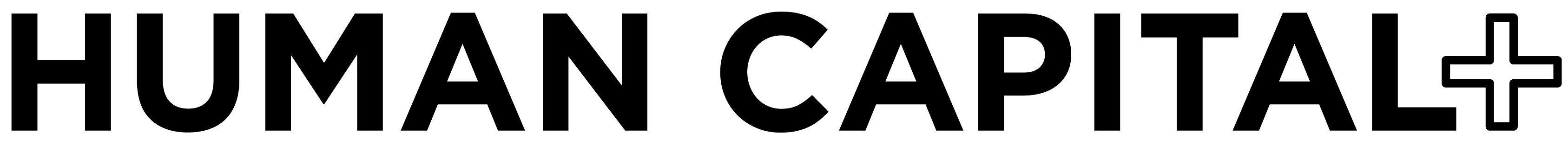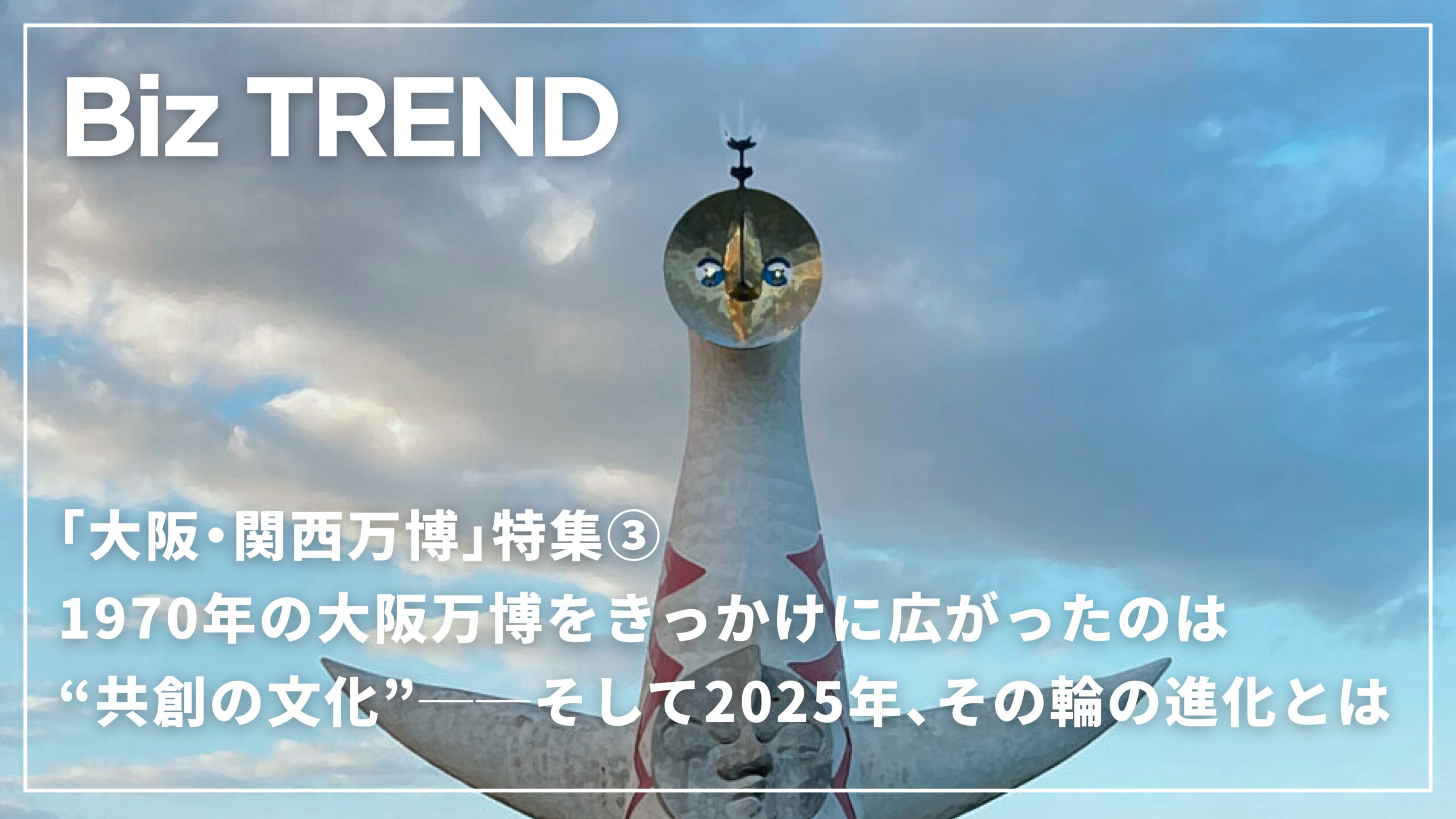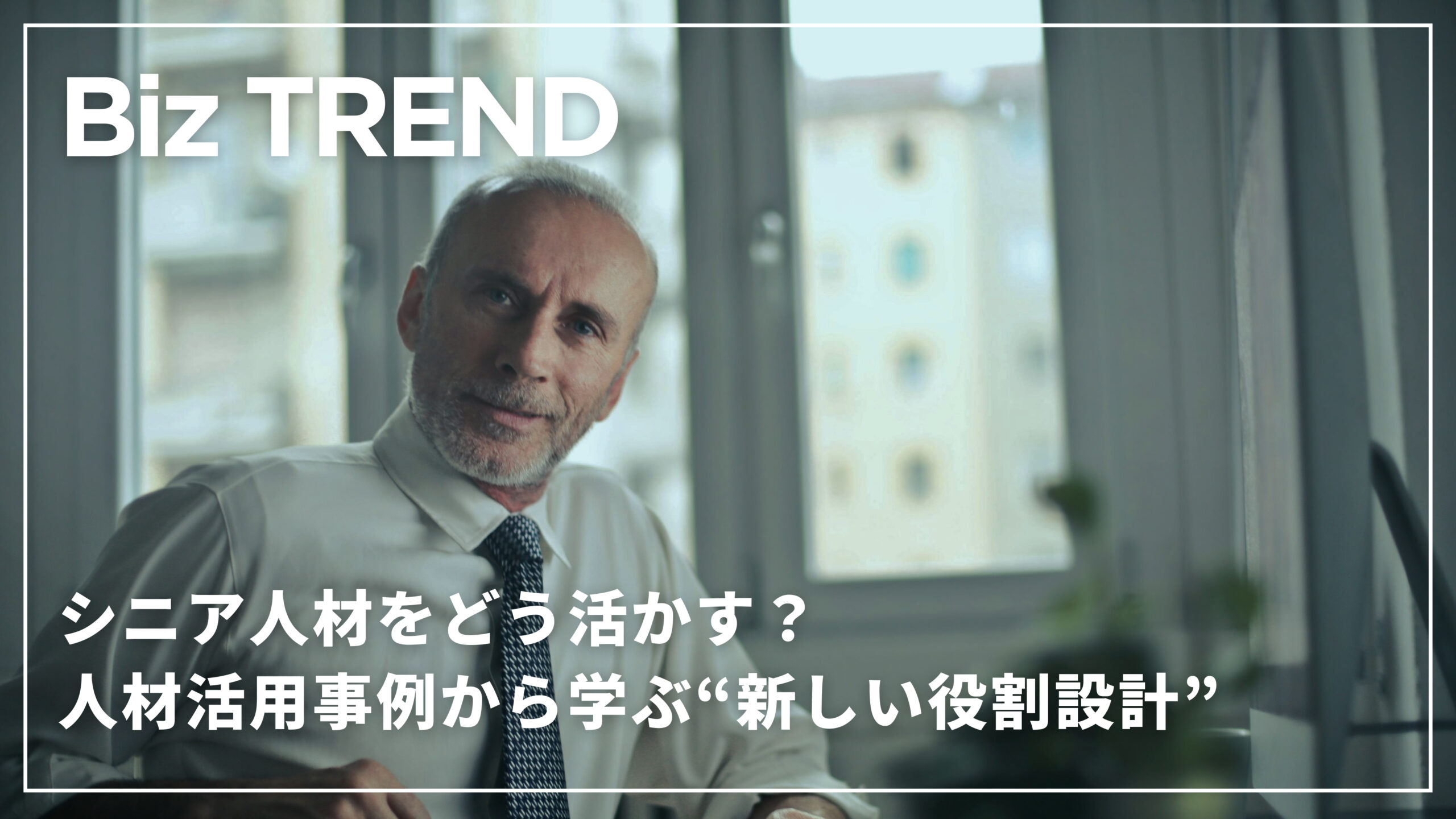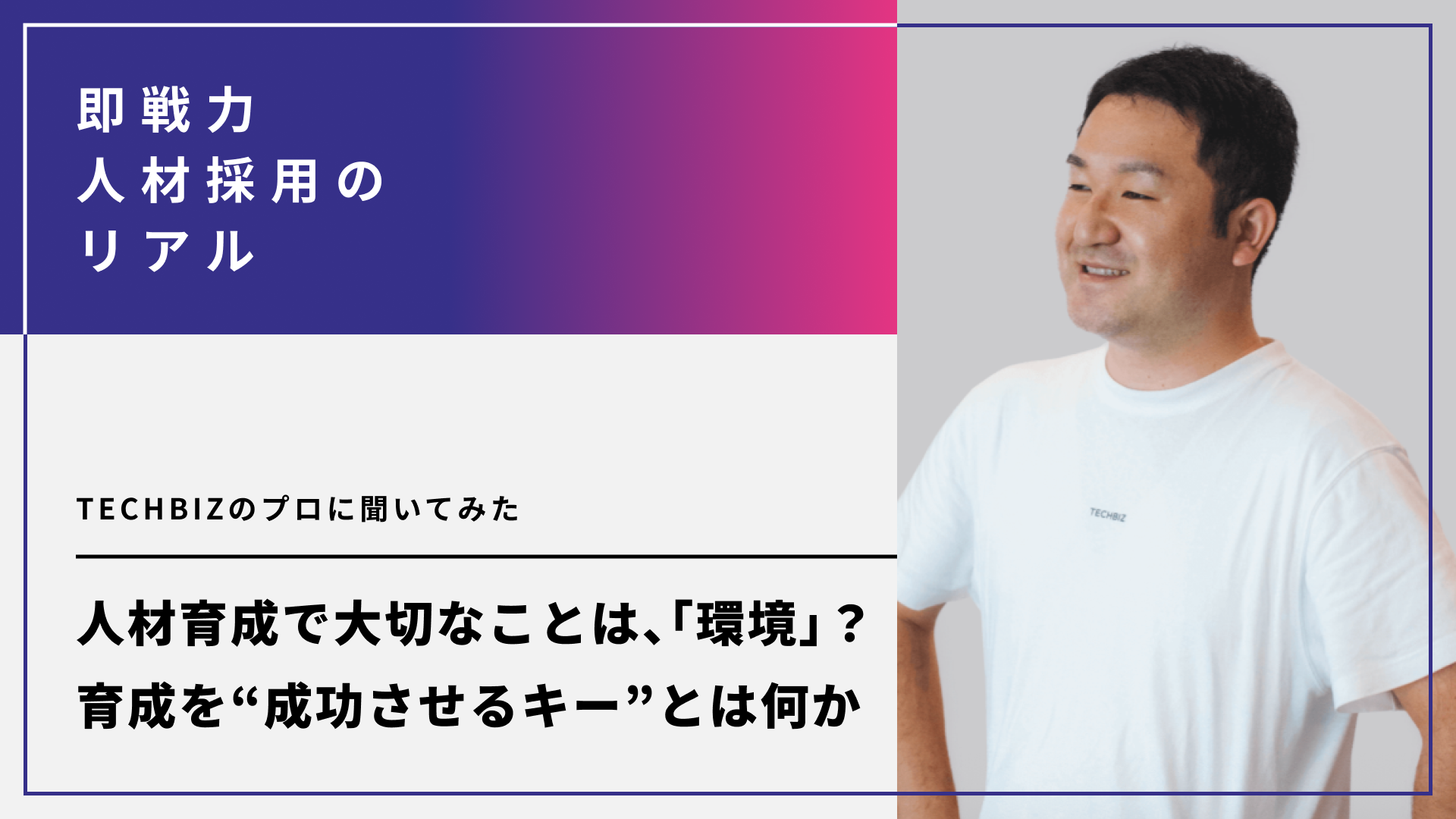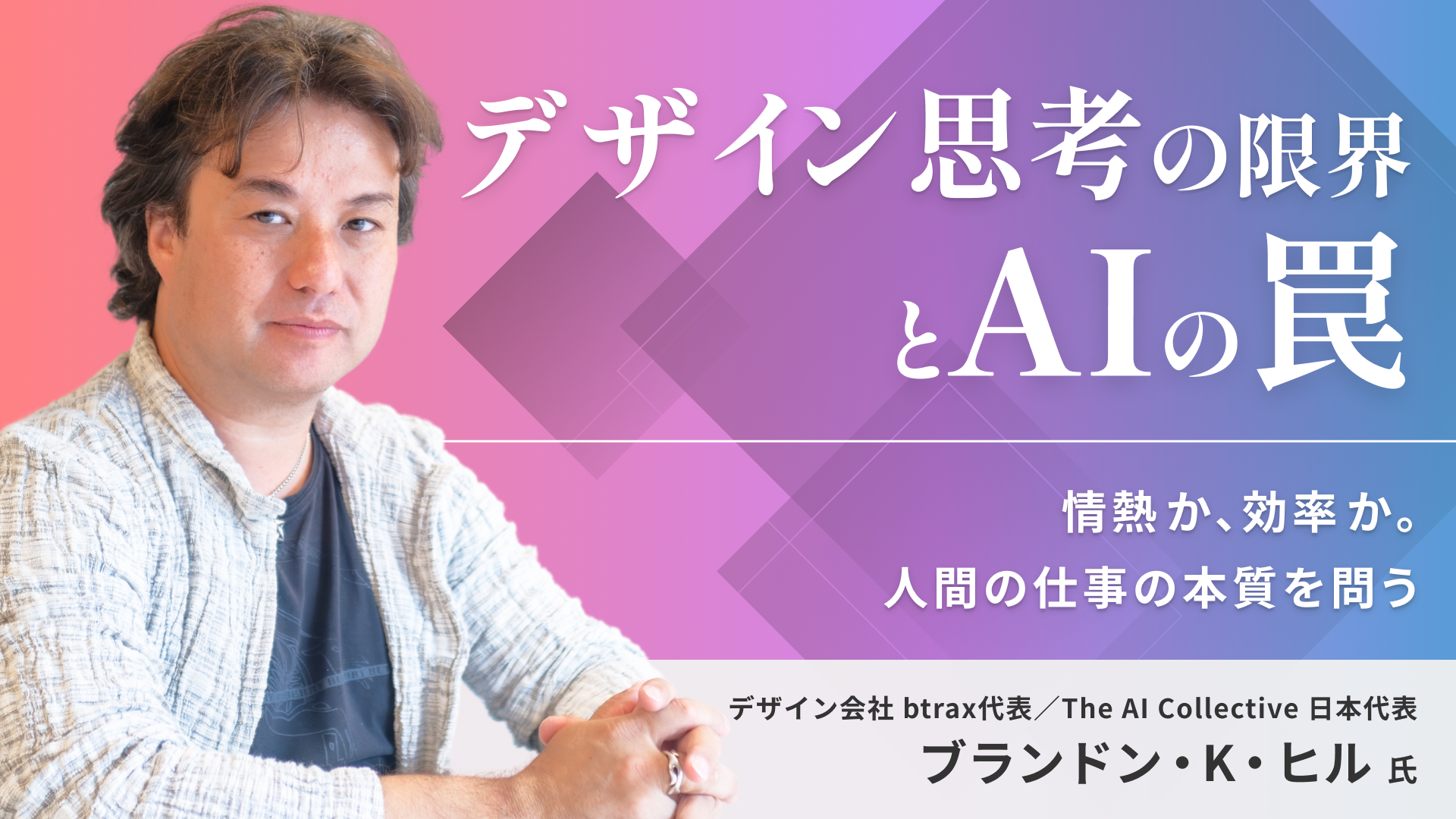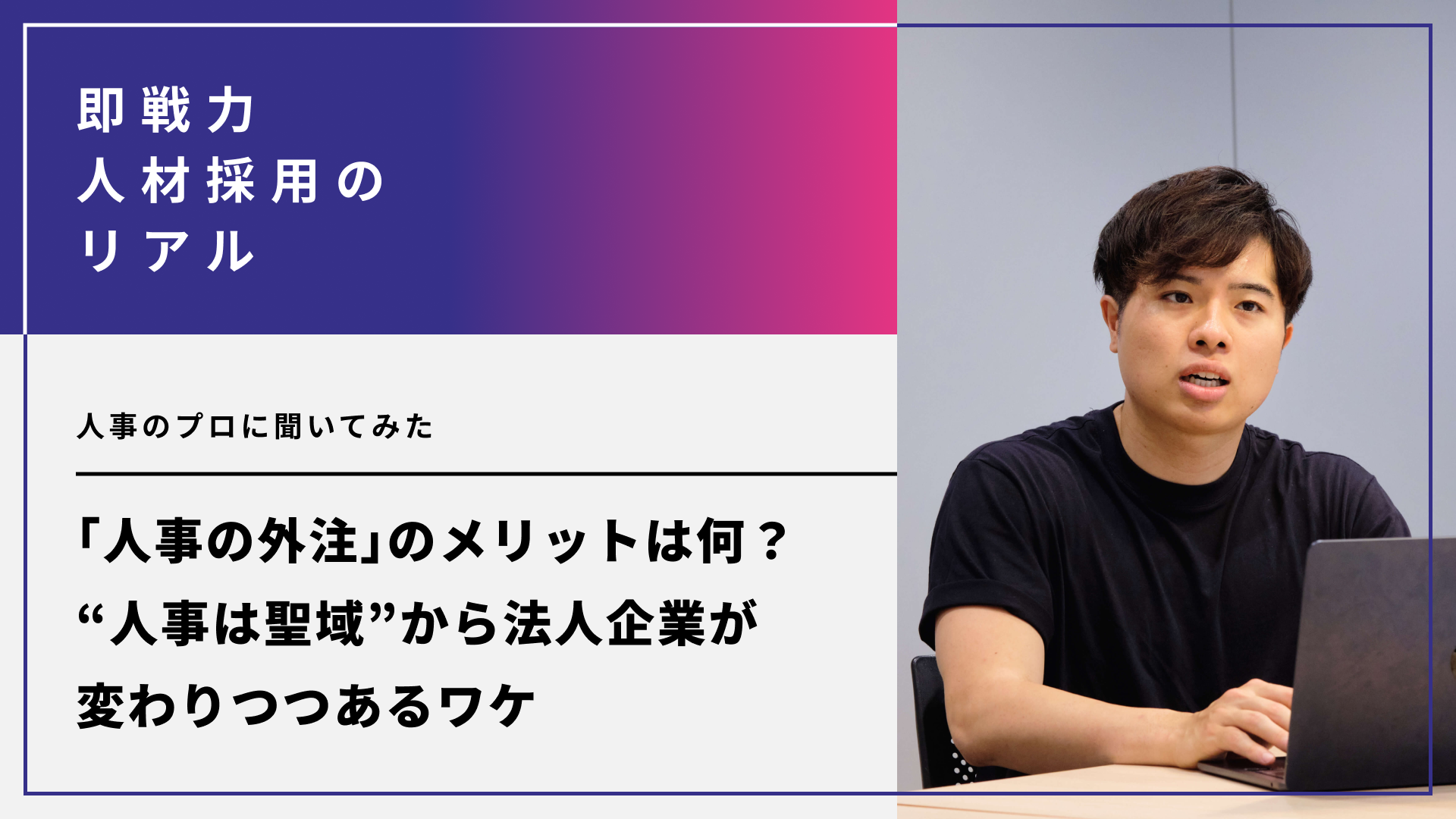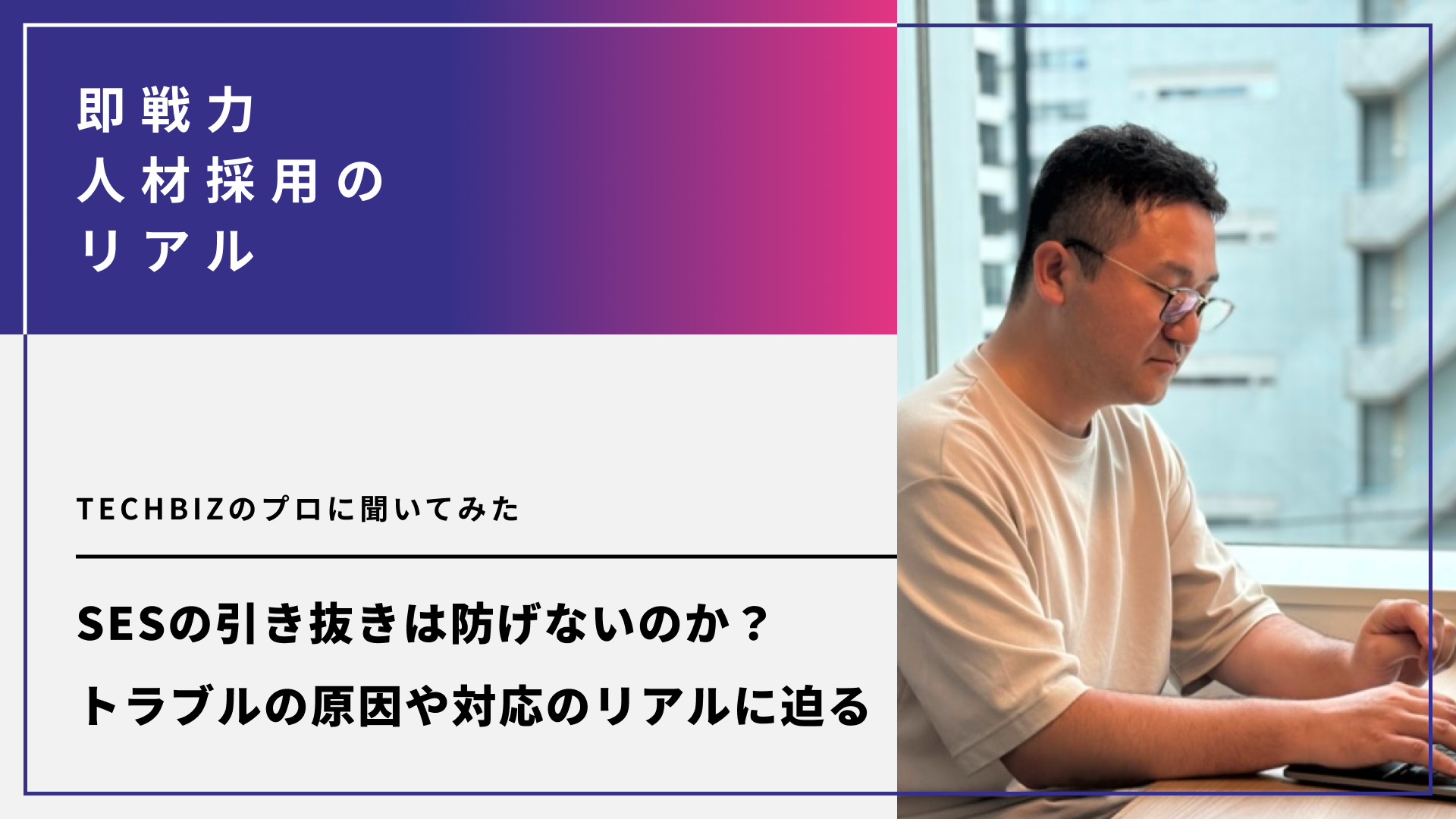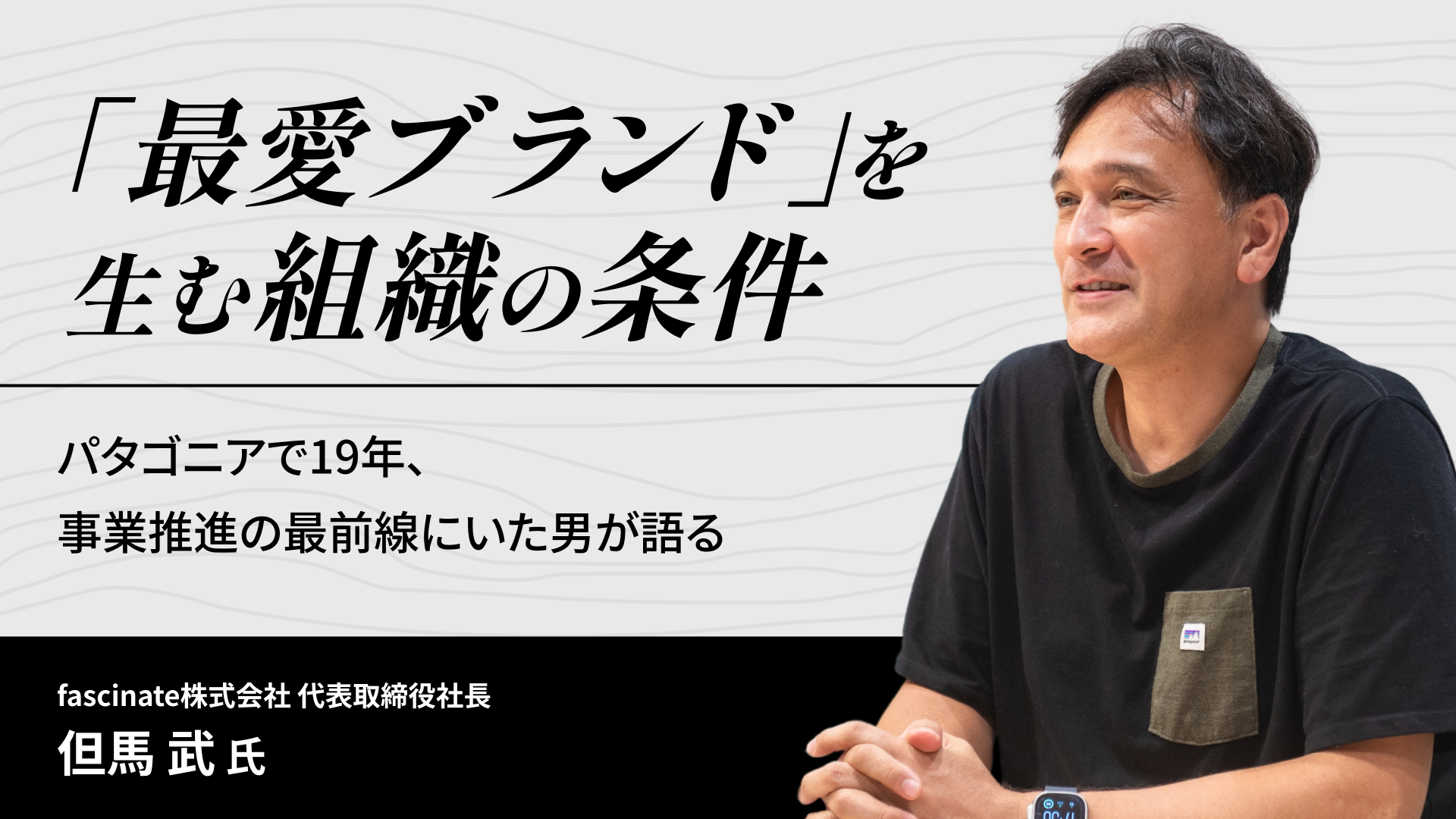2025年10月13日、ついに閉幕した大阪万博。10月7日時点で運営費収支が230億~280億円の黒字となる見通しであることを発表され、興行として成功したと言えるでしょう。開幕前には、数多く挙がった不安と心配の声も杞憂に終わりました。
無事に万博を終えた今、注目したいのは55年前。1970年の大阪万博をきっかけに広がったのは無線電話や電気自動車、情報ネットワークの構想など、今や当たり前となった技術ばかり。そして今回、注目を浴びた空飛ぶクルマや水素燃料、iPS心臓もそう遠くない未来に「新しい常識」となっていることでしょう。
しかし、今回の記事で注目したいのは技術の進化ではありません。プロジェクトの進め方も55年で大きな進化を遂げたのです。産学官の本格的な共創のはしりとなった1970年の大阪万博。2025年の万博では、共創のあり方はどう変わったのでしょうか。
ハイスキル・即戦力人材の採用にお困りならTECHBIZ
最短・即日で企業様にマッチした人材をご紹介【無料】お問い合わせはこちら →
「夢の技術」が現実に──大阪万博が描いた未来図

1970年の大阪万博をきっかけに広がったのは、単なる技術革新だけではなく、“プロジェクトのあり方”もです。日本中が高度経済成長の勢いに乗るなかで開催されたこの万国博は、世界77か国が参加し、「人類の進歩と調和」を掲げて大阪の会場が未来都市そのものに変わりました。
各パビリオンでは、当時の最先端技術が競うように展示され、そこに詰め込まれたアイデアの多くが、いま私たちの生活に溶け込んでいます。たとえば、電電公社(現NTT)が披露したワイヤレステレホンやテレビ電話。遠く離れた人と顔を見ながら話すという光景は、今ではスマートフォンやZoomで当たり前のなっています。
また、トヨタや日産が出展した電気自動車の試作展示も注目を集めました。当時は“夢の車”でしたが、いまやEVシフトが進み、街を走る日常の風景となっています。
さらに、会場の運営を支えた情報ネットワーク管理システムは、来場者数や電力、動線を集中制御する仕組みとして稼働しました。この構想は、半世紀後のスマートシティやIoTに直結する発想です。そしてアメリカ館や丹下健三氏による大屋根パビリオンなど、軽量素材や膜構造建築の挑戦は、いまのドーム型スタジアムや環境建築の原点になりました。
注目したいのは、こうした技術の多くが産学官の協働から生まれた点です。 日本政府や万国博協会がテーマを提示し、大学が研究を担い、企業が試作を形にする――。 この一連の流れは、まさに国家規模の共創プロジェクトだったのです。1970年の大阪万博を振り返ると、実際に広がったのは“新しい技術”だけではありません。
異分野の人々が集まり、一つの目的に挑む「プロジェクト型の働き方」――その文化こそが、 現代につながる“共創の原点”だったと言えるのではないでしょうか。そしてその精神は、2025年に再び大阪の地で開催される次の万博にも、確かに引き継がれました。
未来を共につくる──生活者が主役になった2025年万博

2025年の大阪・関西万博の特徴は、技術の進歩だけでなく、“誰が未来をつくるのか”という構図そのものが変わったことです。かつての万博が「国家と企業による未来のショーケース」だったとすれば、2025年は「生活者が共に未来を動かす実験場」へと進化しています。
実際、日本国際博覧会協会(万博協会)が運営する「共創チャレンジ」には、1,500を超えるプロジェクトが登録されました。日本政府や万博協会だけでなく、スタートアップ、大学、NPO、地方自治体、そして一般市民までが、自らテーマを立て、行動を起こしているのです。
たとえば、大学と地域が連携して健康増進を促す取り組み、企業と学生が協働する環境プロジェクト、地域の子どもたちがまちの未来を描くアート活動など――その一つひとつが「誰かに見せる展示」ではなく、「自分たちが参加する未来づくり」です。
会場では、水素社会やデジタルツイン都市、ウェルビーイング・モビリティなど、未来の暮らしを体験できるパビリオンが並びます。しかし重要なのは、それらが“技術を見せる場”ではなく、“技術をどう生かすかを考える場”になっている点です。
来場者は単なる見学者ではなく、共創の一員としてアイデアを投じる存在。オンラインでもリアルでも、誰もが社会課題の解決に参加できる仕組みが用意されています。
つまり、1970年の大阪万博をきっかけに広がったのが「産官学の共創」だったとすれば、2025年の万博で広がるのは「産官学+生活者による共想」。
技術や制度が中心だった“見せる万博”から、人が主役の“動かす万博”へと変わりつつあるのです。経営の視点で見れば、この変化は示唆に富みます。
社会課題を前に、企業が単独で価値を生み出す時代は終わりました。必要なのは、社員や顧客、地域や個人を巻き込んだ「共創の設計」です。2025年の大阪・関西万博は、その未来の組織モデルを、リアルな社会実験として見せてくれるはずです。
共創を日常に──フリーランスが動かす“現代の協働モデル”
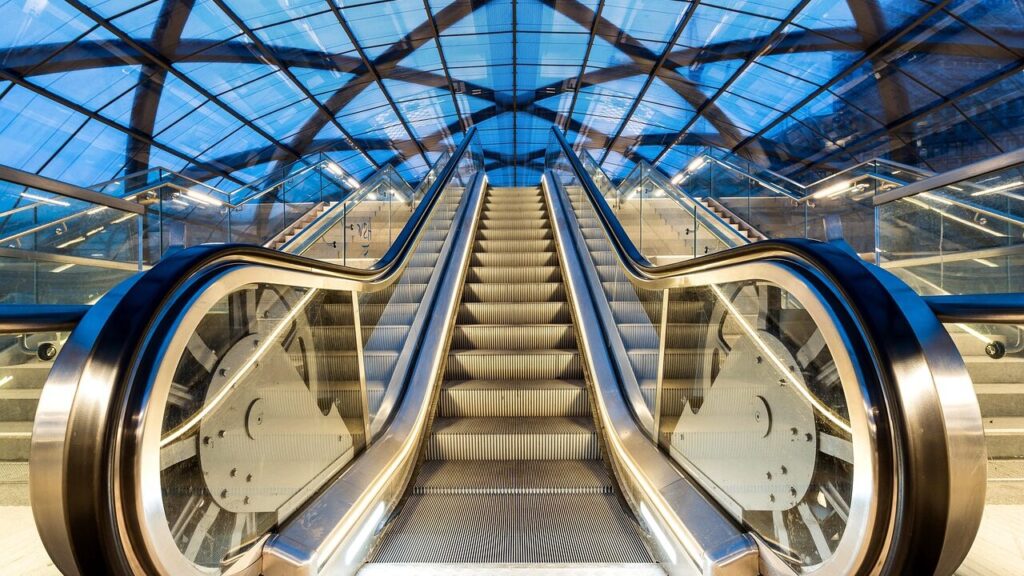
1970年の大阪万博をきっかけに広がったのは、産官学が一丸となって未来を描く「共創のはじまり」でした。そして2025年の大阪・関西万博では、その輪の中に生活者や個人が加わり、“誰もが未来づくりのプレイヤーになれる”という新しい共創のかたちが生まれています。
この流れは、ビジネスの現場にも確実に波及しています。企業が新しい価値を生み出そうとする時、必要なのはスピードと多様性。しかし、組織の中だけで完結するには限界があります。
そこでいま注目されているのが、専門スキルを持つフリーランスとの協働です。特定分野に強みを持つ個人を、プロジェクト単位で柔軟にチームに迎え入れる。まさに、期間限定で多様な専門家が集まる万博のパビリオンのように、“目的中心の共創チーム”を企業が自らデザインする時代が来ています。
実際、フリーランスの活用は単なる「外部委託」ではありません。デジタル化やAIの進展に伴い、企業の課題はより複雑化・専門化しています。だからこそ、個人の知見をスピーディーに取り入れ、外の視点で組織の課題を再定義できるチーム設計が求められています。それは、万博のように一人ひとりの専門性や創造性をつなぎ合わせる営みに近いのです。
さらに、フリーランスの存在は“働き方の民主化”という点でも象徴的です。1970年は企業が主役だった時代。2025年は生活者や市民が社会課題を共に解く時代。そしてこれからは、個人のスキルが社会を動かす時代です。企業の外にいる一人ひとりが、共創のエコシステムを構成する“現代の万博メンバー”と言えるでしょう。
つまり、フリーランス活用とは、 企業が共創を「一過性のイベント」ではなく「日常の経営構造」に取り込むこと。社外の知をチームに呼び込み、目的に応じて形を変える柔軟な組織へと進化することです。異なる専門性が交わる場所にこそ、新しい価値が生まれる。
その姿は、半世紀前に大阪の地で始まった“共創のDNA”が、いま働き方の形として生き続けている証なのかもしれません。
テックビズで、フリーランス活用を“共創の資産”に変える
共創を日常化するには、適切なパートナーを見つけることが何より重要です。しかし実際には、「どんなフリーランスと組めばいいのか」「探し方がわからない」と悩む企業も少なくありません。そんなときに頼れるのが、テックビズです。
テックビズは、継続稼働率97%という高い実績を誇り、最短即日でプロジェクトにマッチする人材を紹介します。契約から導入後のフォローまで一貫してサポートしてくれるため、初めての企業でも安心して始められます。
ハイブリッドな働き方が当たり前になった今、フリーランスは“外部リソース”ではなく、知識と経験を循環させる共創のコアメンバーです。テックビズは、その出会いと仕組みづくりを支え、企業の未来を動かす“共創のプラットフォーム”を実現しています。
最短・即日で企業様にマッチした人材をご紹介
【無料】お問い合わせはこちら編集後記:お客様は神様ではない。退職者は裏切者じゃない
共創の重要性が高まる今、企業にとって大きな課題は「いかに外部にパートナーをつくるか」にあります。その相手は、同業他社だけとは限りません。業界の外にいる企業かもしれないし、自治体や大学かもしれません。閉じた組織の中だけでイノベーションを起こす時代は、もう終わりに近づいています。
これまで多くの企業を取材してきて、私が特に注目している共創相手が二つあります。
一つはユーザーです。従来、企業とユーザーは「価値を提供する側」と「享受する側」という一方通行の関係でした。しかし実際には、ユーザーこそがサービスや商品の価値と課題を最も深く理解している存在です。 ユーザーコミュニティを活用して商品開発やリニューアルを進める企業も増えています。
たとえばBASE FOOD(ベースフード)のBASE FOOD Laboでは、ユーザーを“Labo研究員”として募集し、定期的な食のフィードバックや新メニュー試験・意見交換を実施しています。“お客様を神様にする”のではなく、“パートナーにできるか”――それがこれからの企業の競争力を左右するのではないでしょうか。
もう一つの共創相手が「アルムナイ(退職者)」です。かつては会社を離れた人材を“裏切り者”と見なす風潮もありましたが、 今やアルムナイは社内事情を理解しつつ、社外で新たな経験を積んだ貴重な存在です。
彼らと上手に関係を築くことで、組織の“外の知”と“内の文脈”が交わる瞬間が生まれます。社内を知り、社外で新しい経験を積んだアルムナイだからこそ、プロジェクトのリカバーや橋渡し役として、共創を支える存在になり得るでしょう。実際にアルムナイコミュニティを組織し、共創を進める企業は着実に増えています。ときにプロジェクトに直接参加し、ときにハブとなって企業と社会をつなぐ。 社内を知る彼らだからこそできる絶妙な調整が、共創の潤滑油になるのです。
1970年の大阪万博で始まった“共創の文化”は、2025年を迎える今、 ユーザーやアルムナイといった“個人の力”へと拡張しようとしています。未来をつくるのは、企業でも行政でもなく、人と人とのつながりそのものなのかもしれません。
ハイスキル・即戦力人材の採用にお困りならTECHBIZ
最短・即日で企業様にマッチした人材をご紹介【無料】お問い合わせはこちら →
即戦力人材の採用にお困りではありませんか?ハイスキルなITエンジニアをスムーズに採用できる【テックビズ】
TECHBIZでは優秀なITフリーランス人材をご紹介しています。スキルのみならず人柄も踏まえ、企業様にマッチした人材を、最短で即日ご紹介できます。即戦力人材の採用にお困りの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。