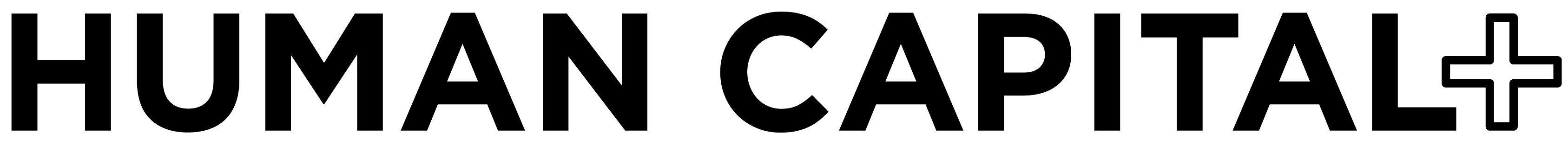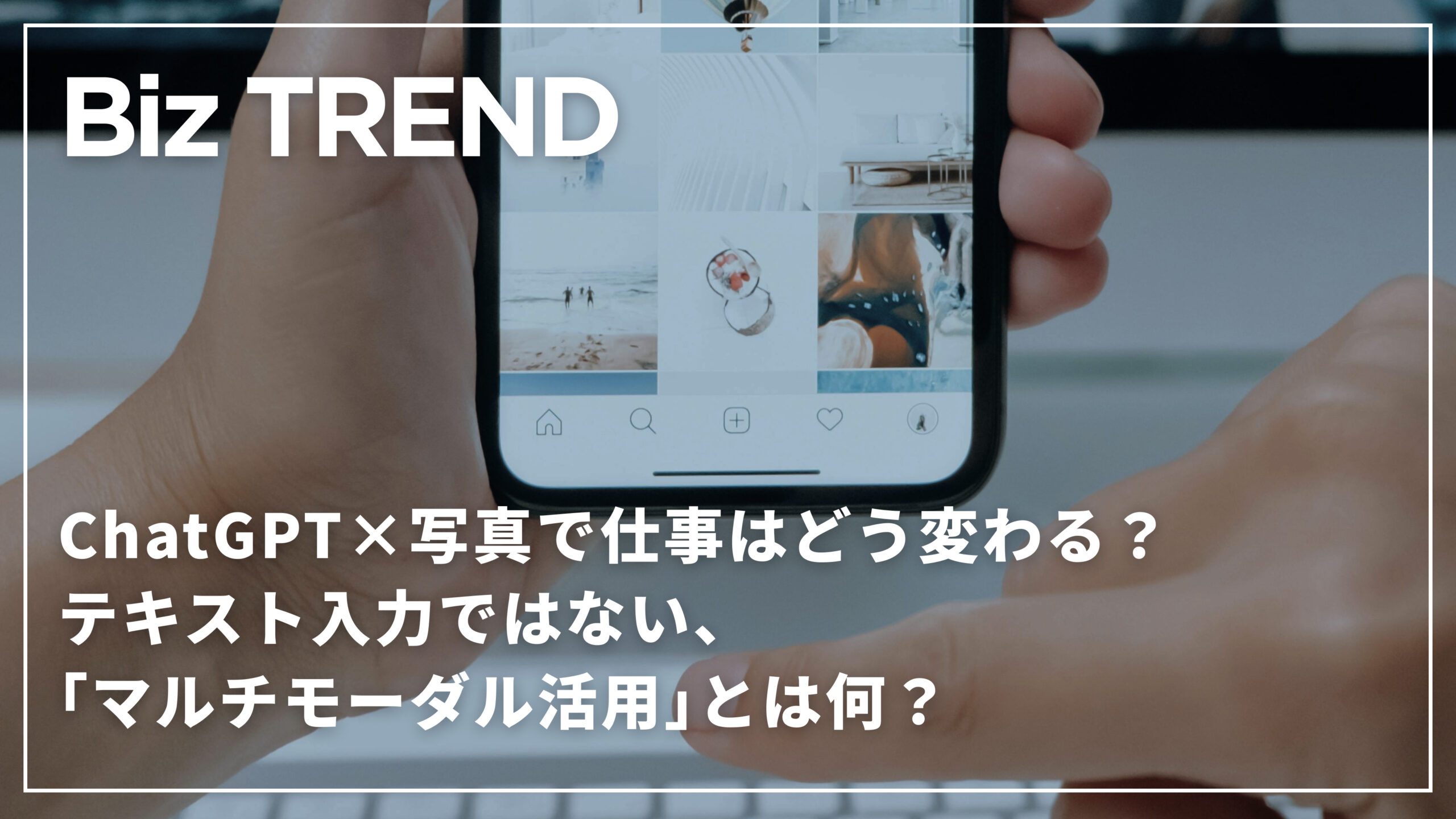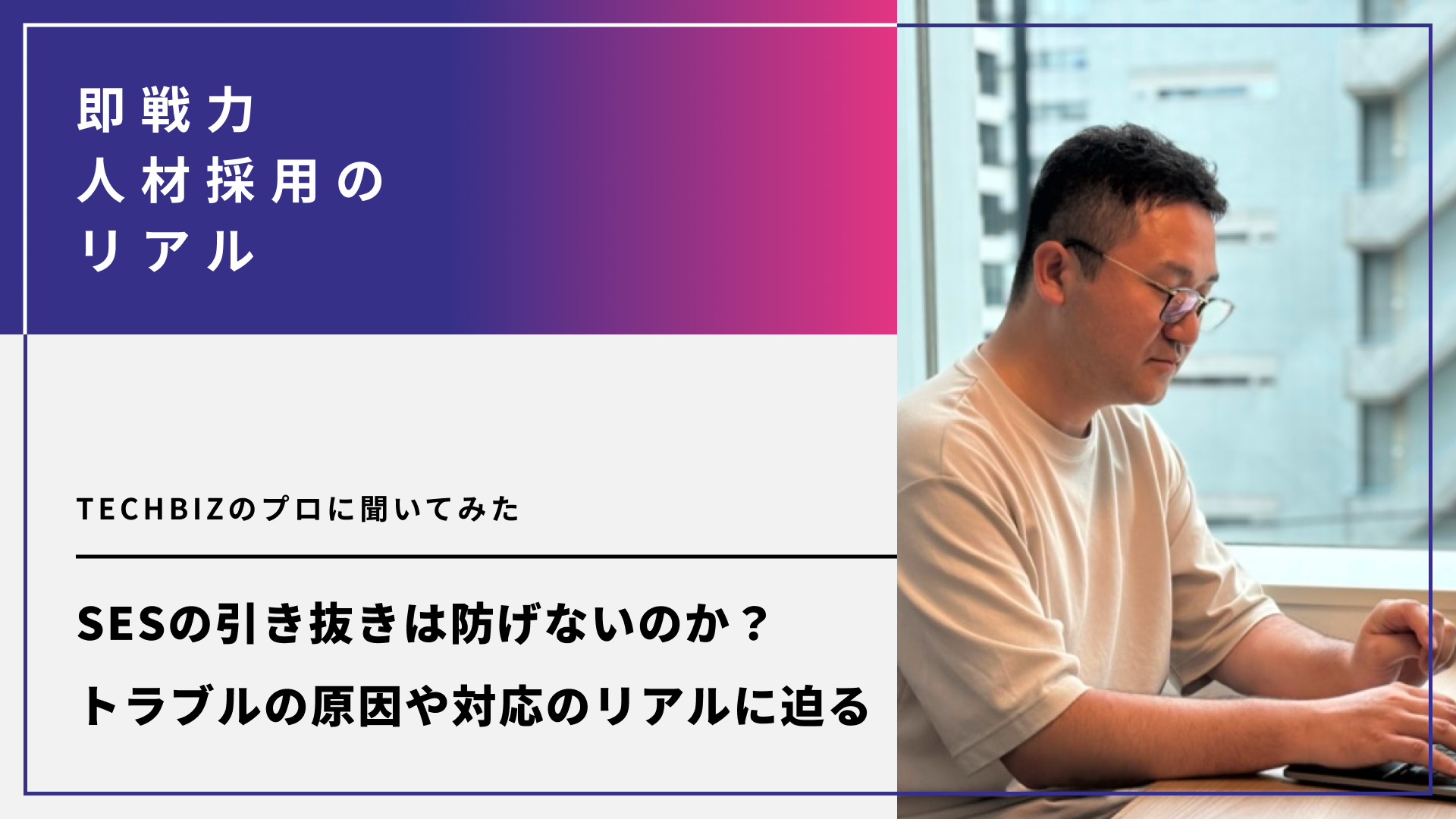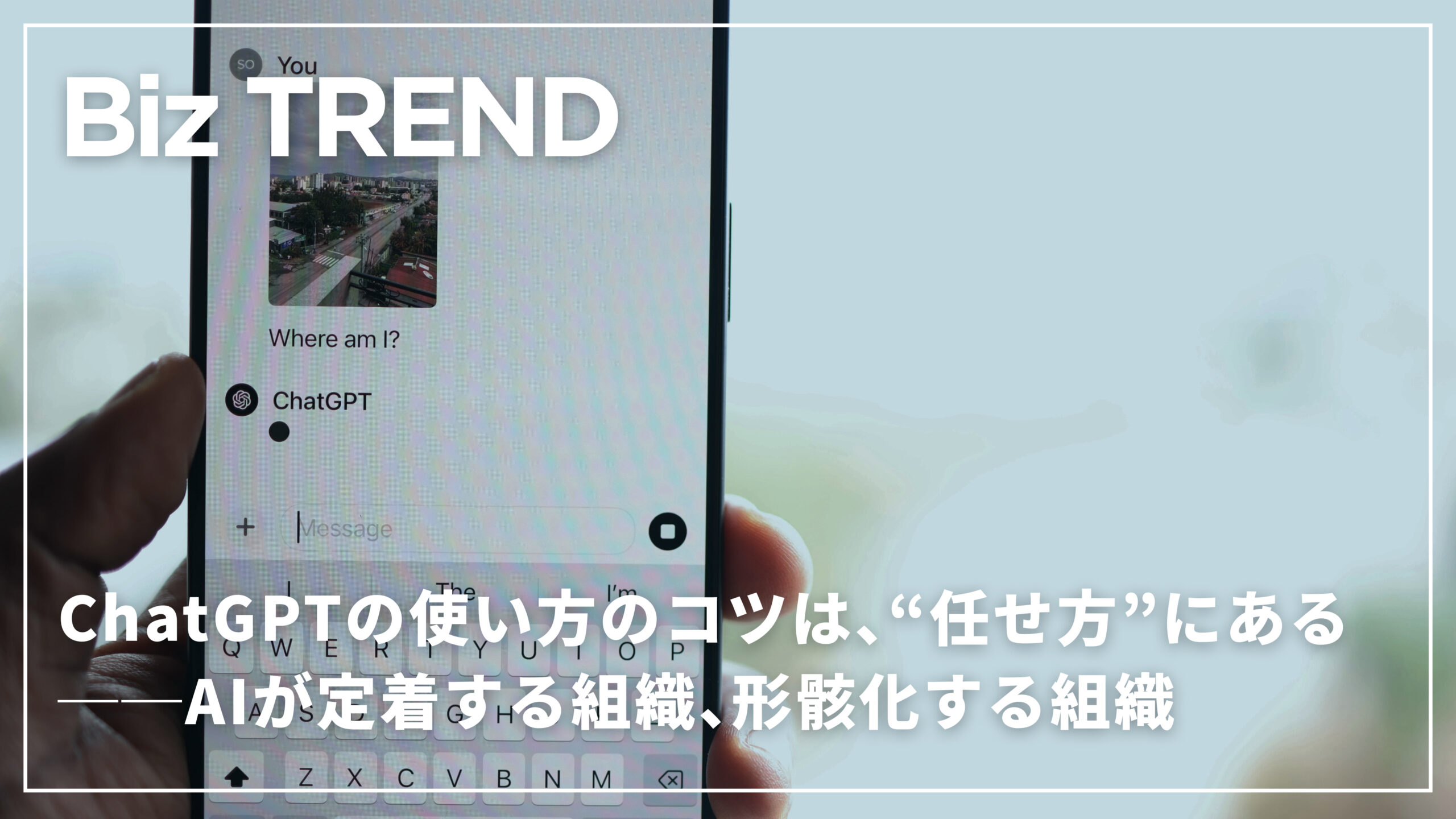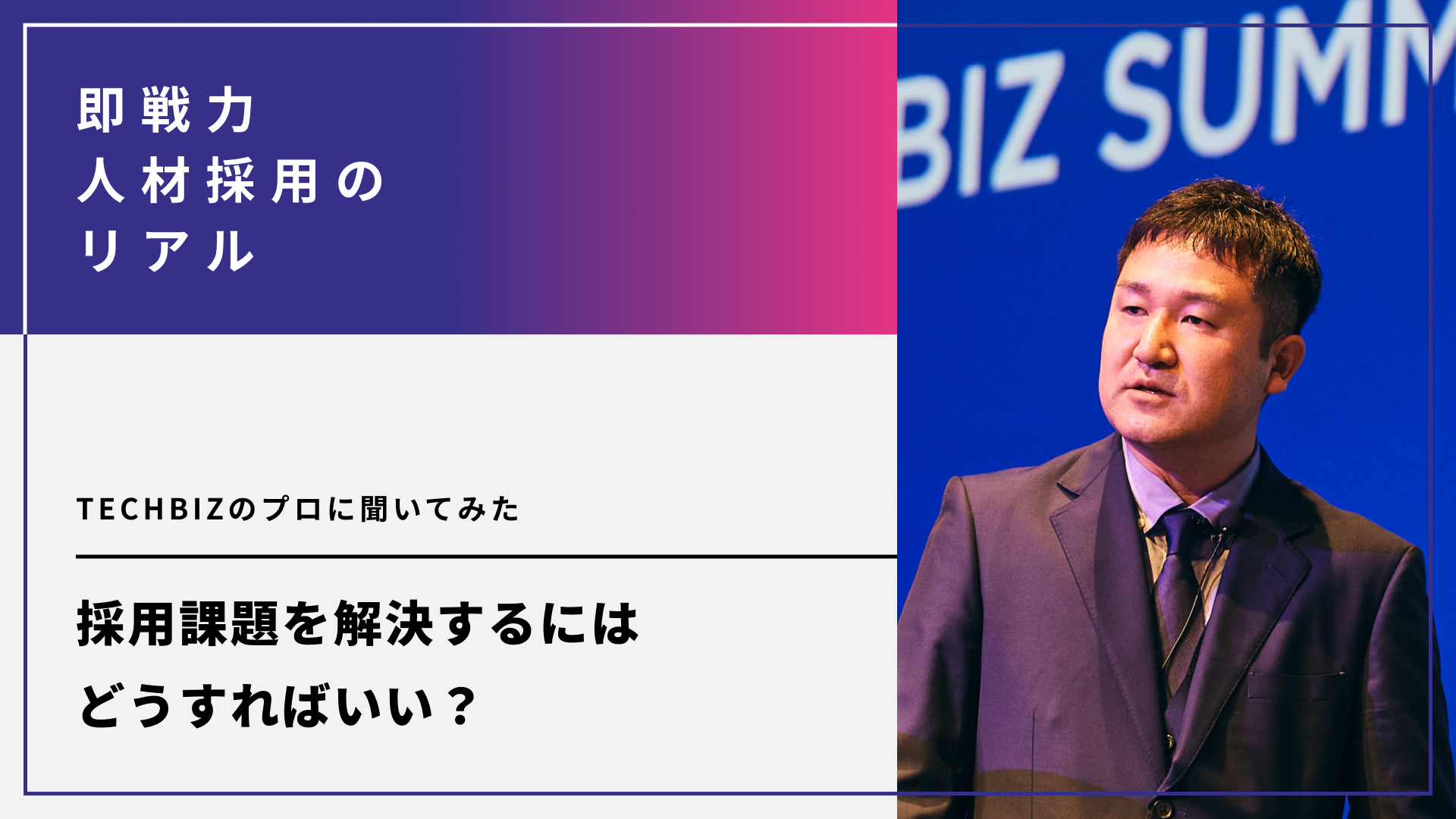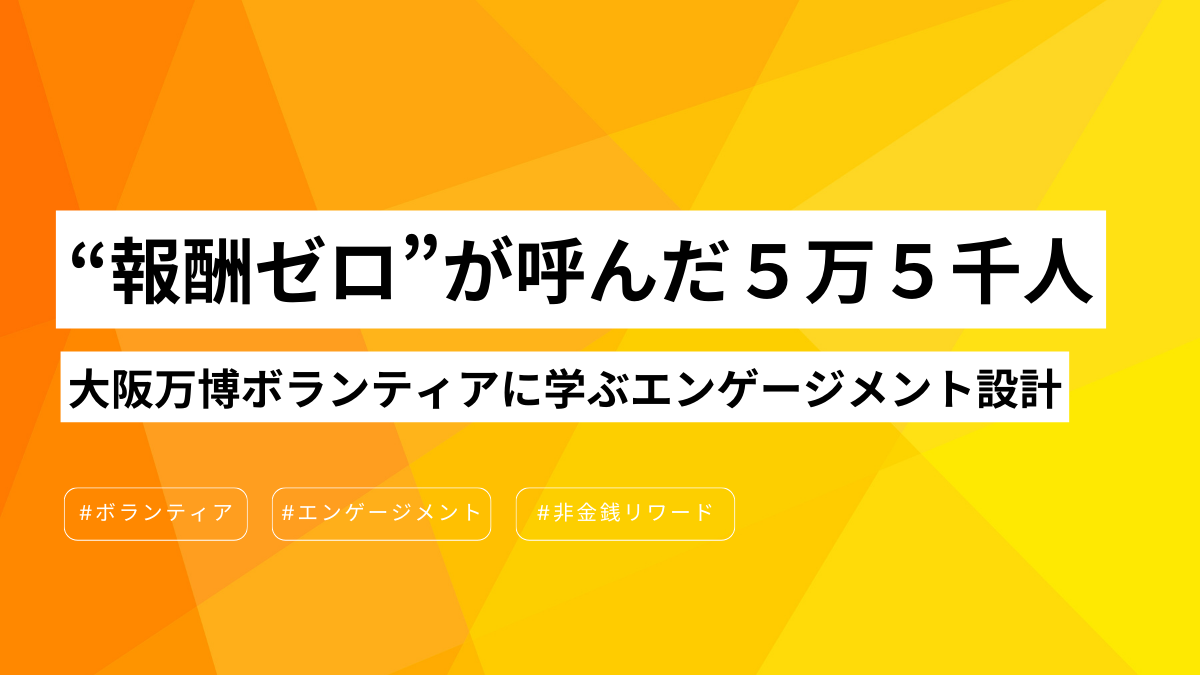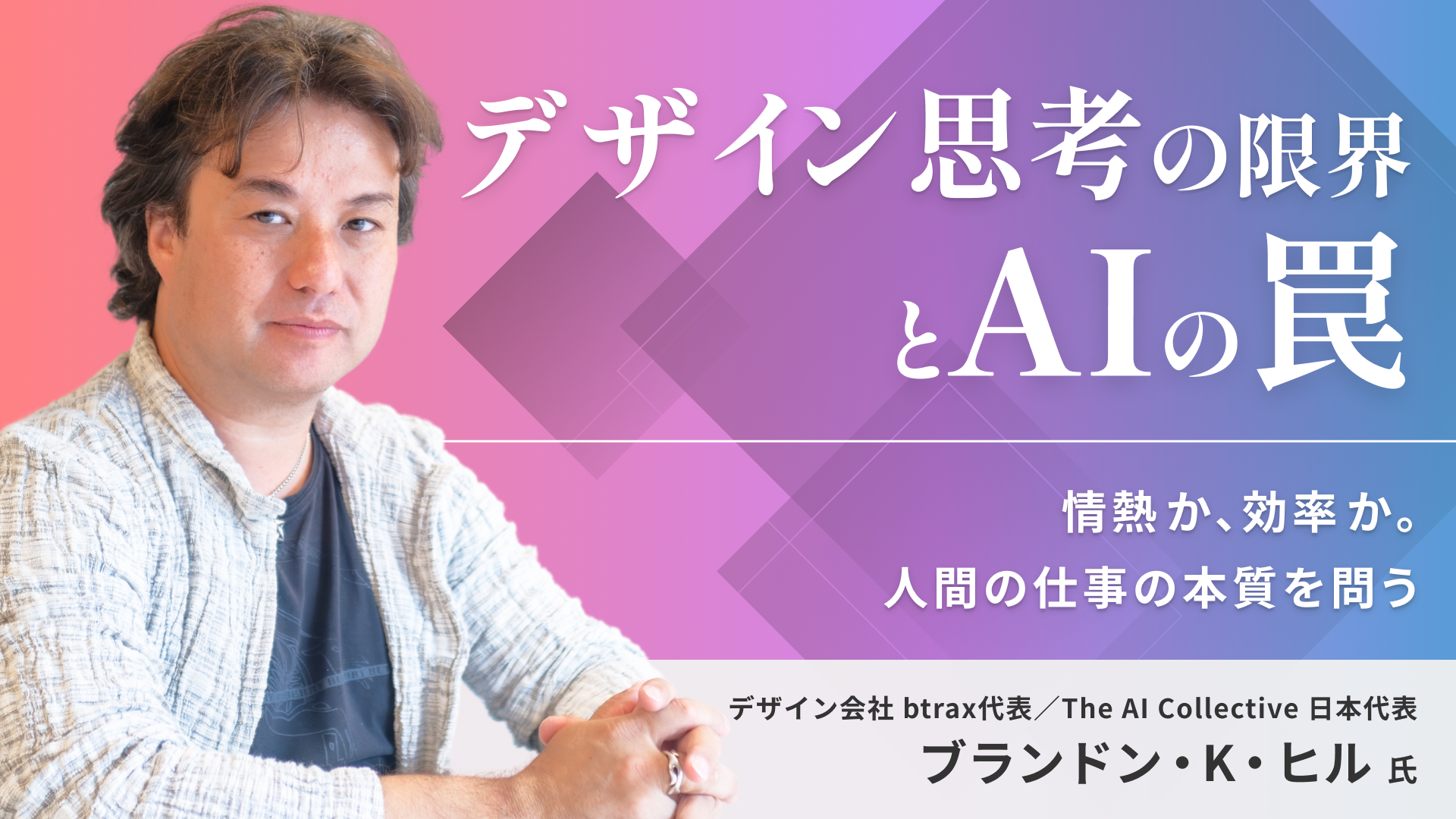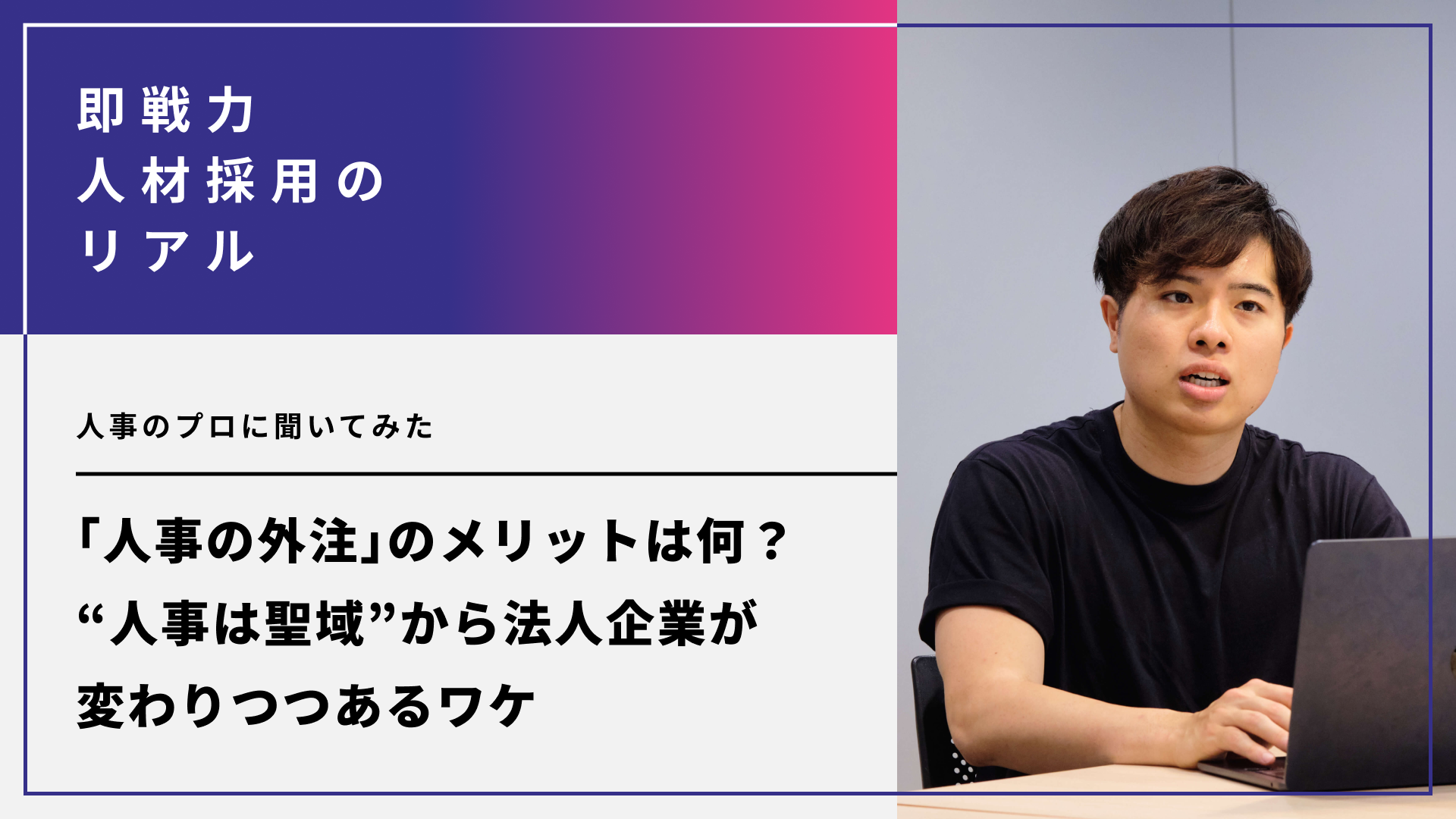「チャッピー」が流行語大賞に選ばれ、生成AIとしてのChatGPTがますます注目を集めています。文章を作る“テキストのAI”という印象が強いかもしれませんが、実は画像や写真を読み込んで状況を分析することもできます。
テキストだけのプロンプトでは伝わりにくい内容でも、写真を使えばAIの制限を補い、より深く理解してもらえるのです。今回は、あまり知られていないChatGPT×写真の活用法と、そこから企業が得られる示唆を紹介します。
ハイスキル・即戦力人材の採用にお困りならTECHBIZ
最短・即日で企業様にマッチした人材をご紹介【無料】お問い合わせはこちら →
ChatGPT×写真で変わる、企業の新しいAI活用とは?
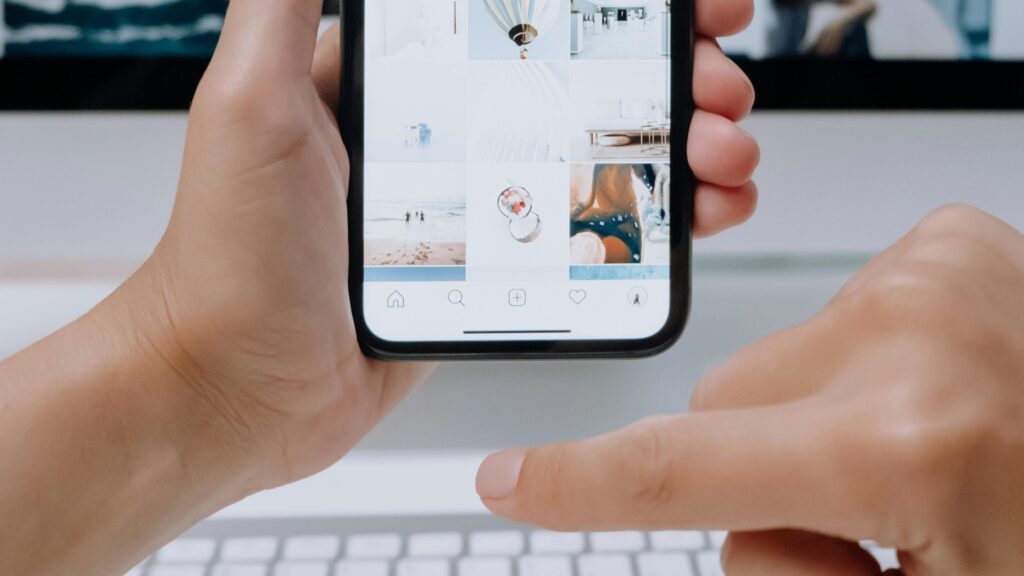
企業でAIを活用する流れが広がる中で、「思ったほど効果が出ない」という声も聞こえてきます。その理由のひとつは、AIに渡している情報のほとんどが“文章だけ”だという点かもしれません。報告書や議事録といった整ったテキストは扱いやすいものの、実際の仕事の多くは、写真、現場の配置、手書きメモ、ちょっとした空気感など、言葉にしにくい情報に支えられています。
最近、海外でも「画像+テキスト」を組み合わせてAIに読み込ませる「マルチモーダル活用」が広まり始めています。たとえば、ユーザーが送ってきたスクリーンショットをChatGPTに読み込ませて不具合の原因を特定したり、売場の写真をアップロードして改善ポイントを整理したりする例が紹介されています。写真を素材にすることで、文章だけでは見えなかった問題の“背景”や“理由”に触れられるようになるのです。
ChatGPTの画像入力機能は、まさにその流れを支える技術です。写真を読み込ませると、AIが「ここは動線が詰まりやすいかもしれません」「この作業の順番に特徴があります」といった形で、状況の中にあるヒントを拾ってくれます。これは、AIがすべてを判断しているというより、人間が気づくきっかけをそっと差し出してくれているような感覚に近いかもしれません。
こうした気づきが増えていくと、ベテランが当たり前のように行っていた工夫や判断の理由が少しずつ言葉になっていきます。「なぜそうしているのか」をチーム全体が共有できるようになると、仕事のやり方に再現性が生まれ、組織としての学び方も変わっていきます。
これまでのAI活用は「どんなプロンプトを入力するか」に目が向きがちでしたが、これからは「AIに何を見せるか」が同じくらい大切になっていくはずです。
参考:https://skimai.com/5-ways-your-enterprise-can-use-chatgpt-vision/?utm_source=chatgpt.com
「 ChatGPT×写真」には“伝え方の本質”が詰まっている

AIをうまく使うには特別な技術が必要だと思われがちですが、実はそのヒントは、人間どうしのコミュニケーションの中にあります。チャットだけで説明されると分かりにくいけれど、図や写真を使われると「なるほど」と理解が深まることがありますよね。これはAIも同じで、文章だけよりも、写真や画像を見せたほうが正しく理解しやすくなります。
たとえば、会議室のレイアウトを文章だけで説明されてもイメージしづらいですが、写真が1枚あるだけで一気に状況が伝わります。
ChatGPTに写真を読み込ませるのは、まさにそれと同じことです。AIに「言葉だけで説明しきれない部分」を補いながら伝えることで、誤解が減り、答えの精度も自然と上がっていきます。
つまり、ChatGPT 写真 の活用は、AIの能力を伸ばすというよりも、人間側の“伝え方の質”を高めるための方法だと考えることができます。プロンプトの工夫も大事ですが、それ以上に「どう言えば伝わるか」を考える力のほうがずっと重要です。
そして面白いのは、AIにわかりやすく伝える練習をするほど、人間どうしのコミュニケーションもうまくなるという点です。ChatGPTに説明して伝わらないことは、往々にして人にも伝わっていません。逆に、写真や図を交えてAIに伝わる説明ができれば、社内の共有や部下への指示もぐっと分かりやすくなるでしょう。
ChatGPTとフリーランスが、企業の“伝える力”を映し出す

AIをどう活用するかを考えるとき、実は鍵になるのは“伝わる説明”です。そしてその力は、フリーランスのような外部の人と働くほど鍛えられていきます。
長く同じ組織で働いていると、互いに前提を共有しているため、説明を省略しても仕事が回ります。これは効率的ですが、同時に「説明しなくても通じてしまう」状態が当たり前になり、気づかないうちに説明の質が落ちていきます。
その影響は社外の顧客との会話にも表れます。丁寧に伝えているつもりでも、言葉が足りず、意図が正確に伝わらない——そんなズレが起きやすくなるのです。
外部のフリーランスと協働することは、この“見えないズレ”を明らかにします。文脈を共有していない相手だからこそ、曖昧さや言い回しのクセがそのまま通用しません。何を、どこから、どう説明すべきか。外部の視点を通すことで、説明の骨格があらためて見直されていきます。
これはChatGPT 写真の活用とも本質的には同じです。文章だけでは伝わりきらない背景を、写真や図解を添えることで補い、理解の精度を高める。AIに「伝わる」説明は、人にも伝わりやすい説明です。
つまり、ChatGPTと外部人材はどちらも企業の伝える力を磨く“試金石”になるのです。
AI時代の組織には、技術より前に「伝え方の上手さ」が求められます。社内だけで閉じた環境ではその力は育ちにくい。外部の専門家と協働しながら、相手の前提を丁寧にたどり、必要な情報を選び取り、分かりやすい形に編集して伝える。この積み重ねが、そのままAI活用の精度にも跳ね返ってきます。
テックビズでコミュニケーション力をアップデート
外部視点を取り入れたい企業にとって、信頼できるパートナーがいるかどうかは大きな差になります。テックビズは、継続稼働率97%という実績を持ち、最短即日で最適なフリーランスをマッチングします。
契約から導入後のフォローまで一貫して支援してくれるため、初めて外部の力を取り入れる企業でも安心です。変化のスピードが速い今こそ、外の知恵を柔軟に取り入れながら、組織のコミュニケーションをアップデートしましょう。
最短・即日で企業様にマッチした人材をご紹介
【無料】お問い合わせはこちら編集後記:AIが進化するほど、人の“考える力”が問われる
ChatGPTのようなAIを使いこなすには、プロンプトのテクニックよりも、“本質的に考える力”や“伝える力”のほうがむしろ問われる場面が多いと感じます。テキストだけでは伝わりにくいことを写真や図で補ったり、AIが返してきたアウトプットに違和感があれば、その理由を言語化して突っ込んでみる。こうした姿勢は、実は普段の仕事の中でも欠かせないものです。
これまで多くのAI専門家に取材してきましたが、「これから人間に求められるものは?」と尋ねると、返ってくる答えの多くは“好奇心”や“モチベーション”でした。
AIによって私たちは、これまで以上に簡単にプロダクトを作り、新しい知識にアクセスできるようになります。しかし、そもそも学ぼうとする動機や、知らない世界に触れたいという好奇心がなければ、その力を引き出すことはできません。
スキルはAIによってどんどん民主化されていく一方で、「なぜ学びたいのか」「どこまで深く知りたいのか」という、人間の内側から生まれる動機の差はむしろ広がっていくのかもしれません。 AIと向き合う今の時代は、自分の好奇心やモチベーションをどう育てるかを問い直すチャンスでもあります。
AIが当たり前になったこれから、人間の“思考の深さ”や“知りたいという力”こそが、私たちの大きな武器になるはずです。
ハイスキル・即戦力人材の採用にお困りならTECHBIZ
最短・即日で企業様にマッチした人材をご紹介【無料】お問い合わせはこちら →
即戦力人材の採用にお困りではありませんか?ハイスキルなITエンジニアをスムーズに採用できる【テックビズ】
TECHBIZでは優秀なITフリーランス人材をご紹介しています。スキルのみならず人柄も踏まえ、企業様にマッチした人材を、最短で即日ご紹介できます。即戦力人材の採用にお困りの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。