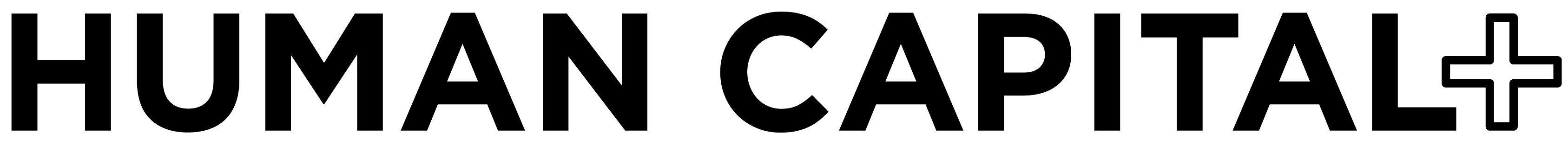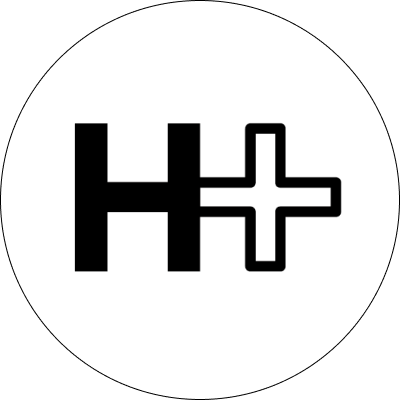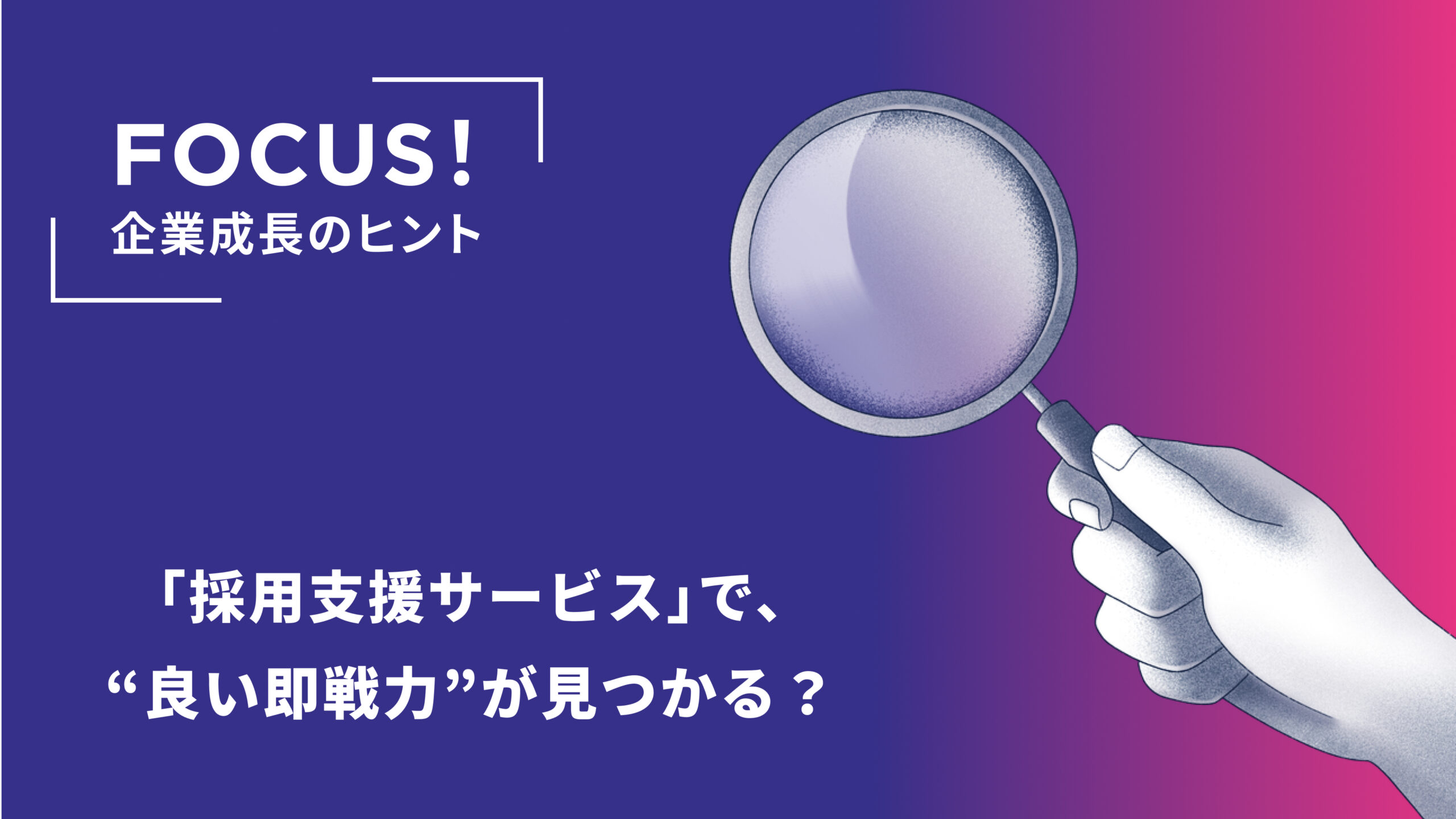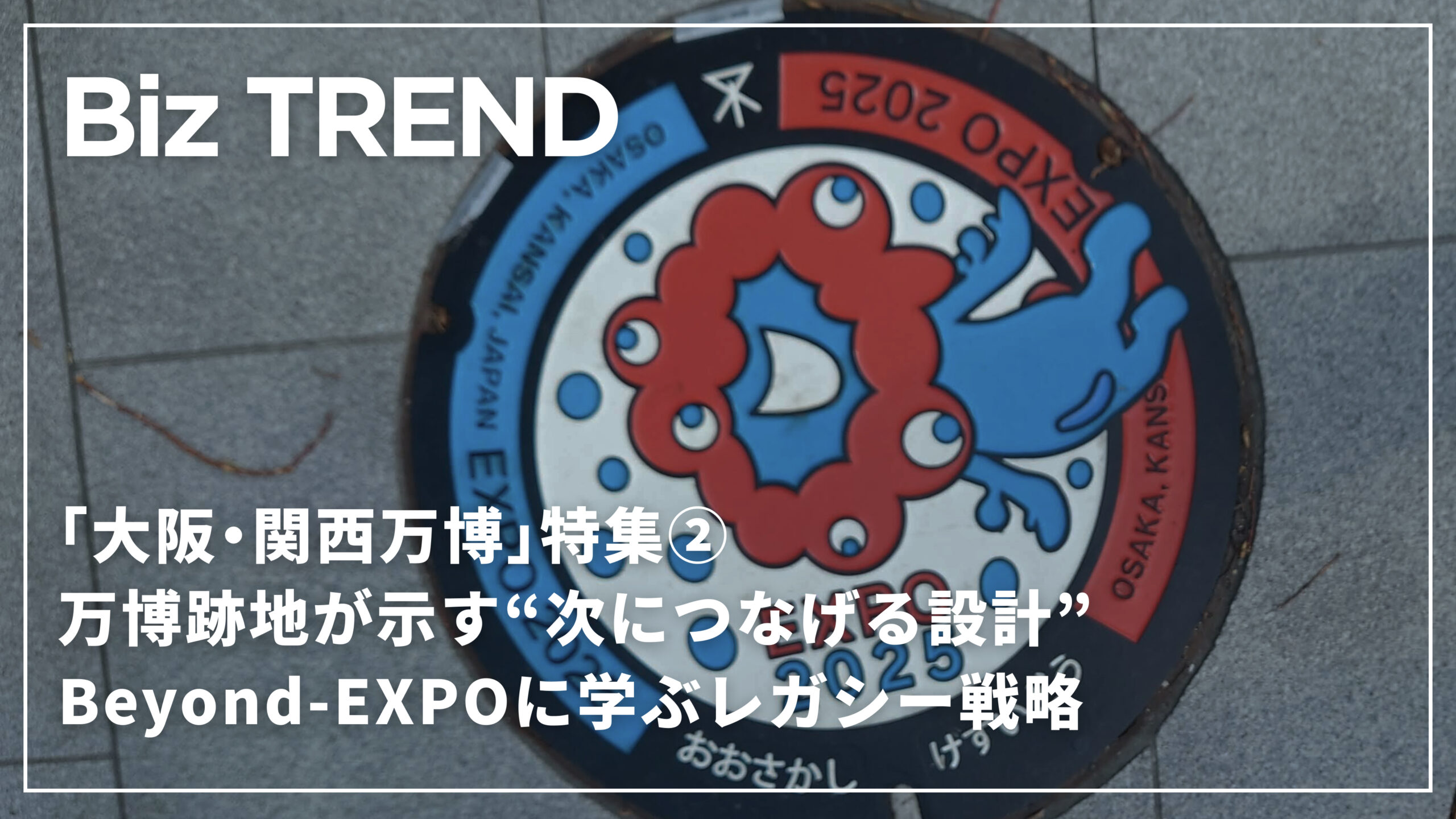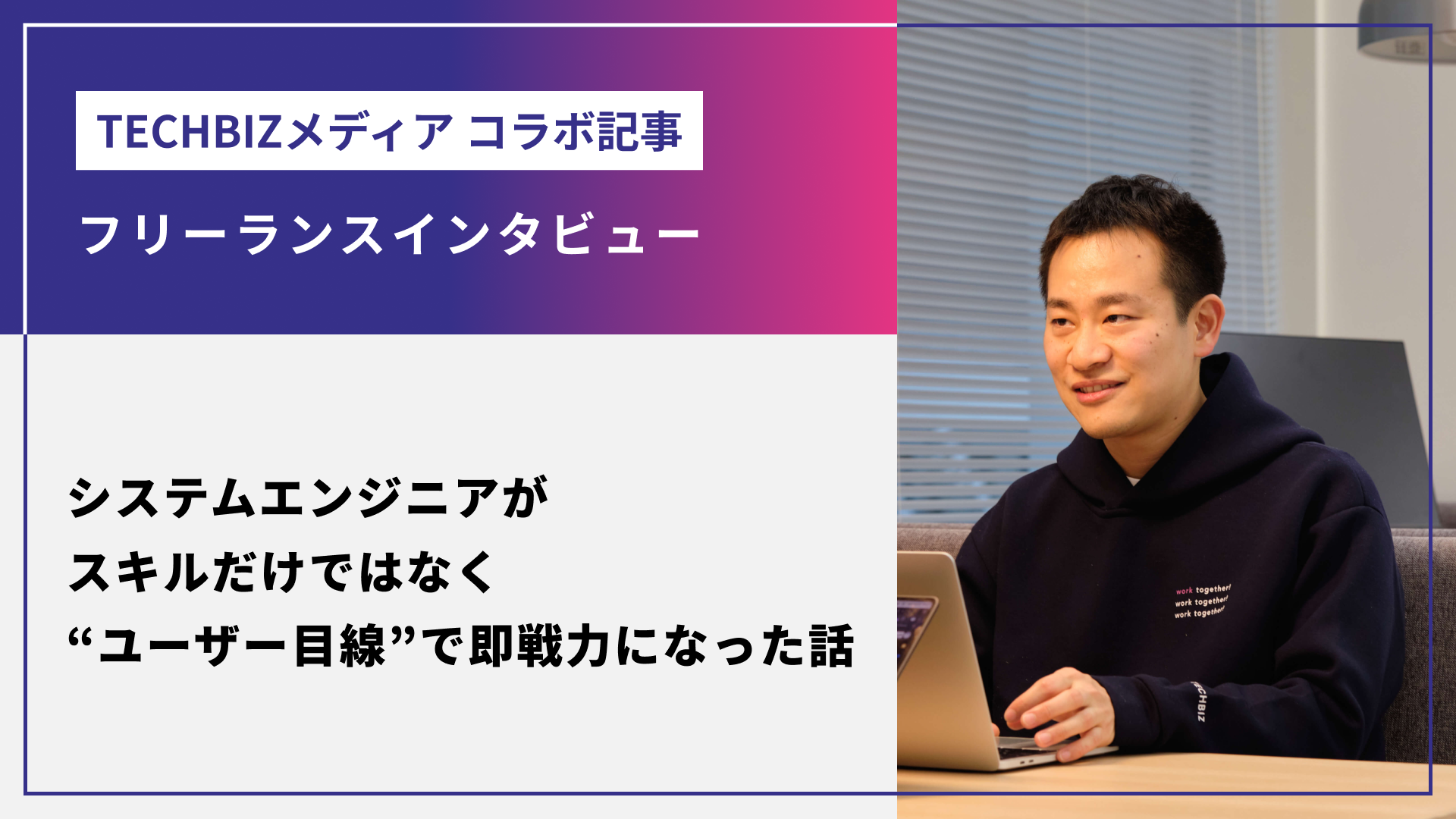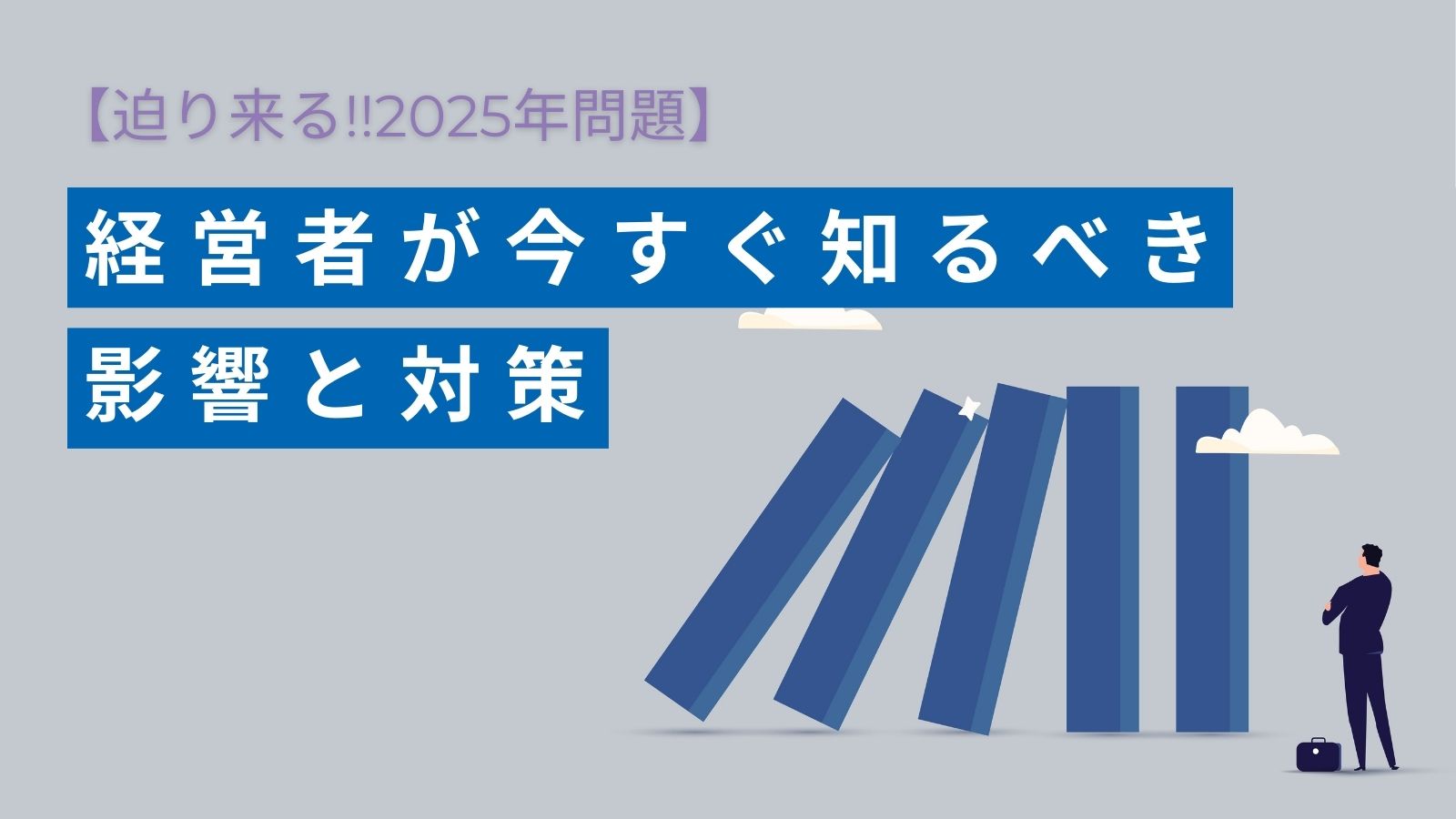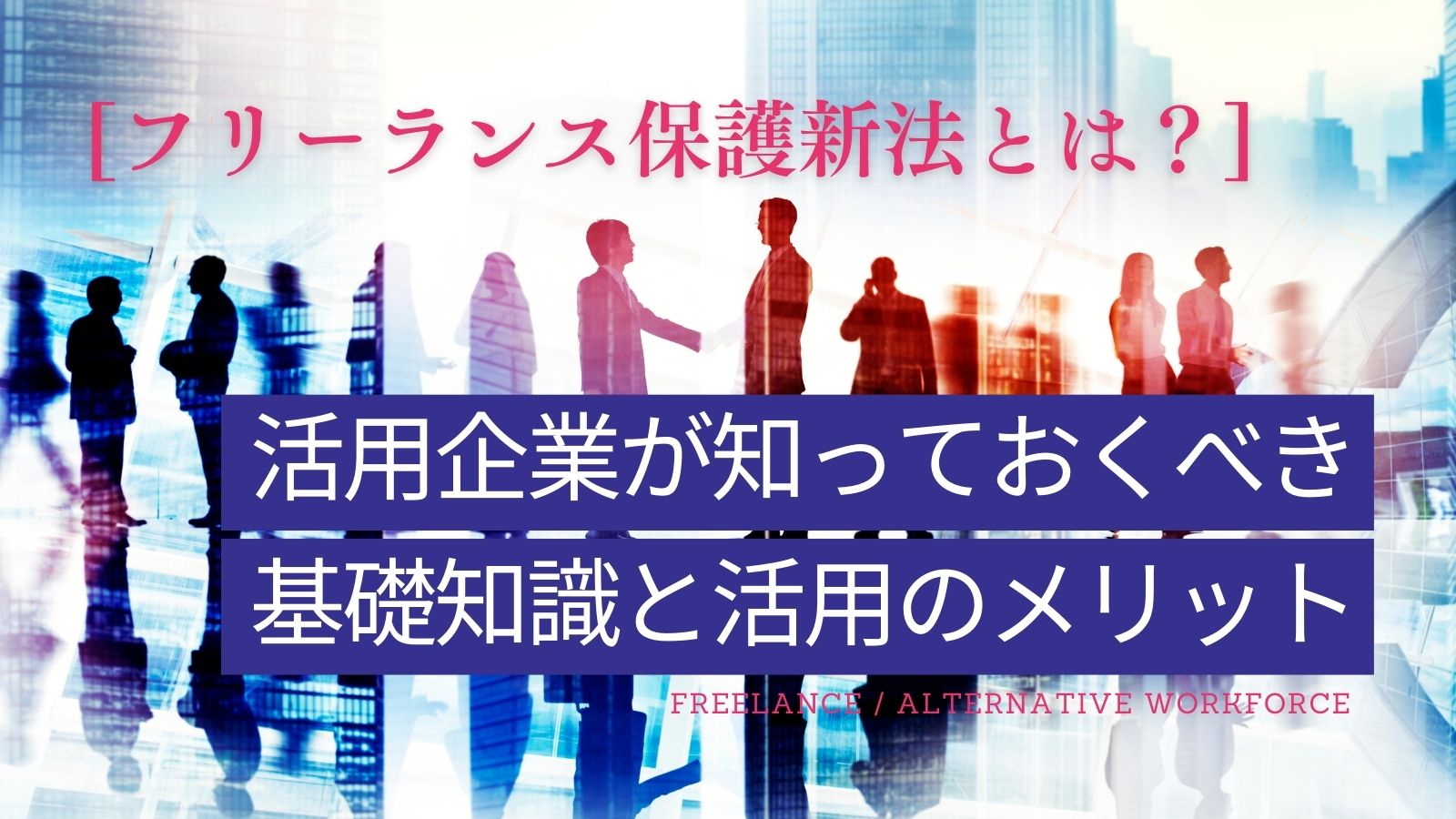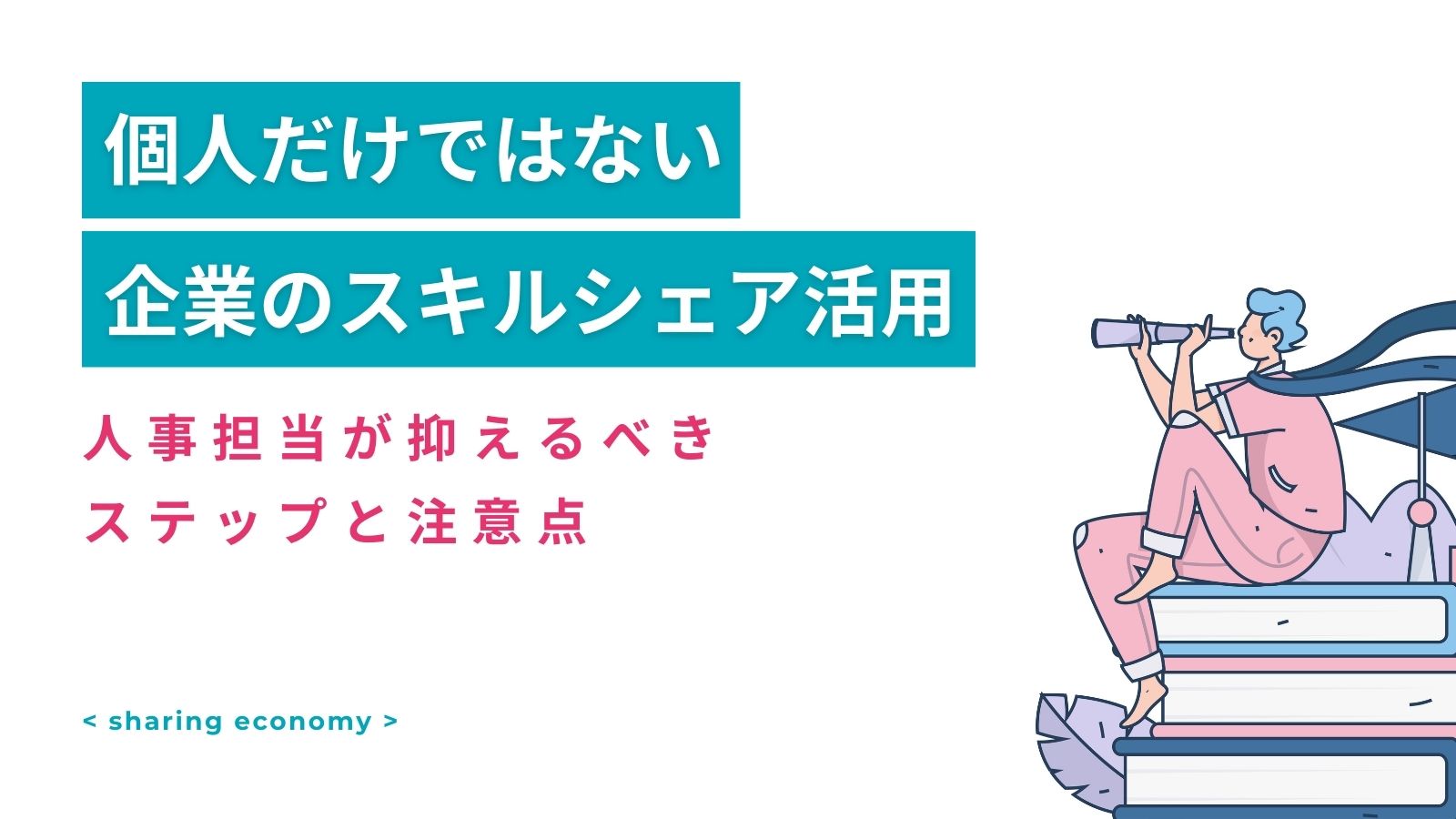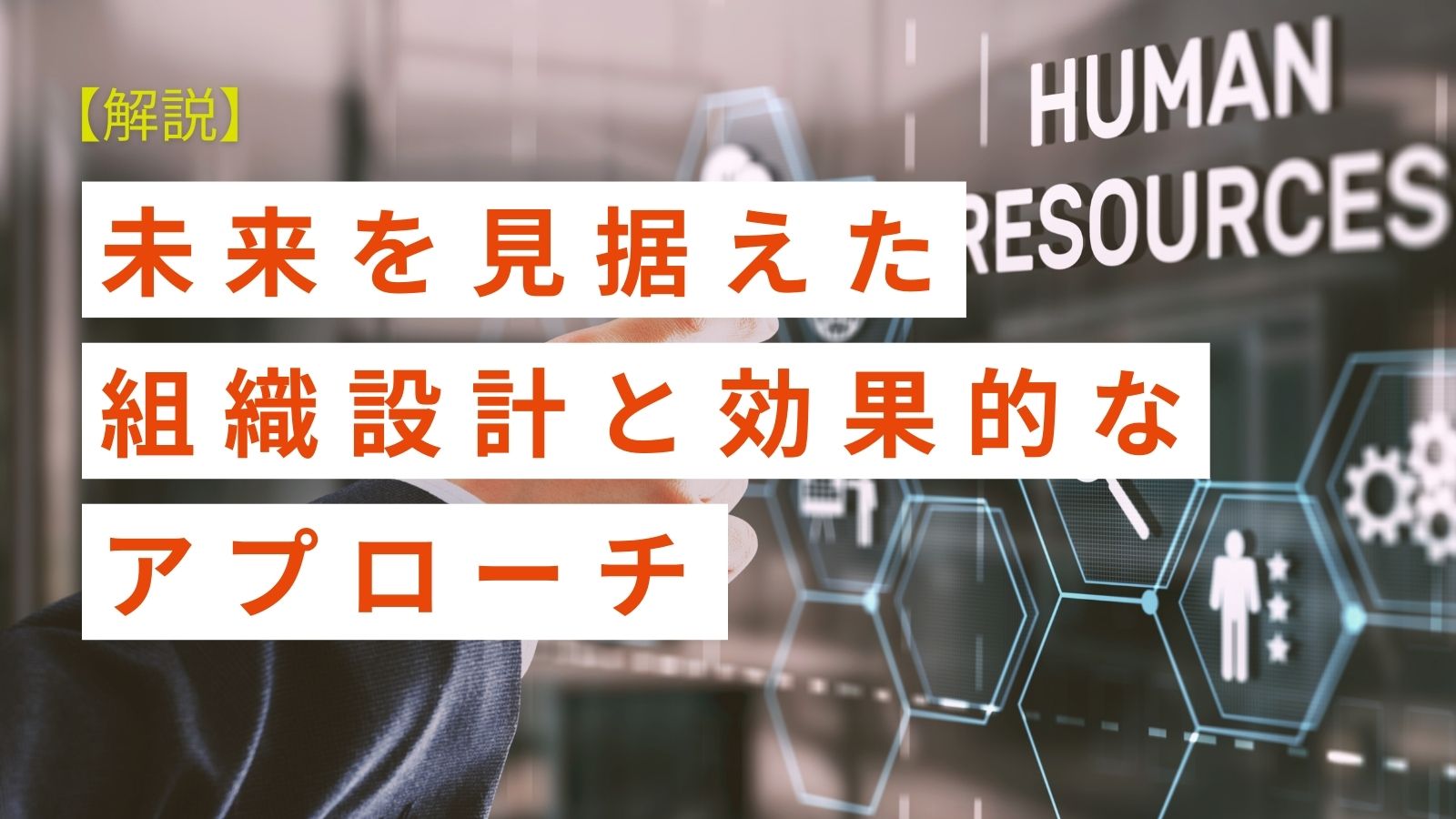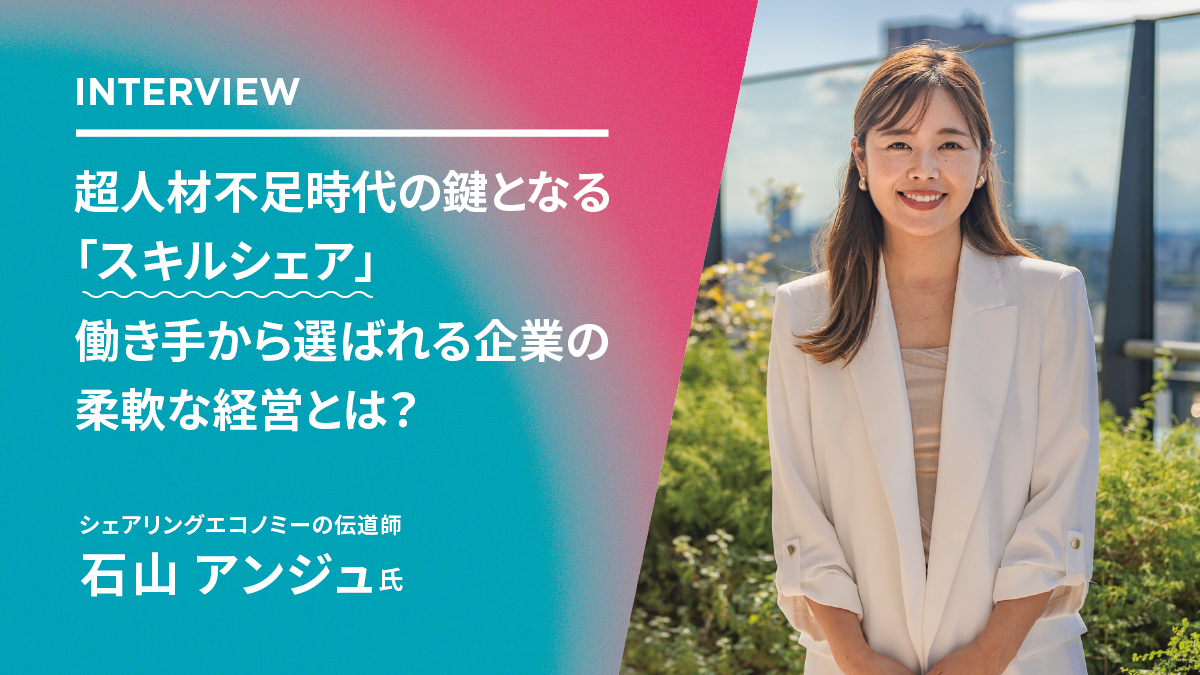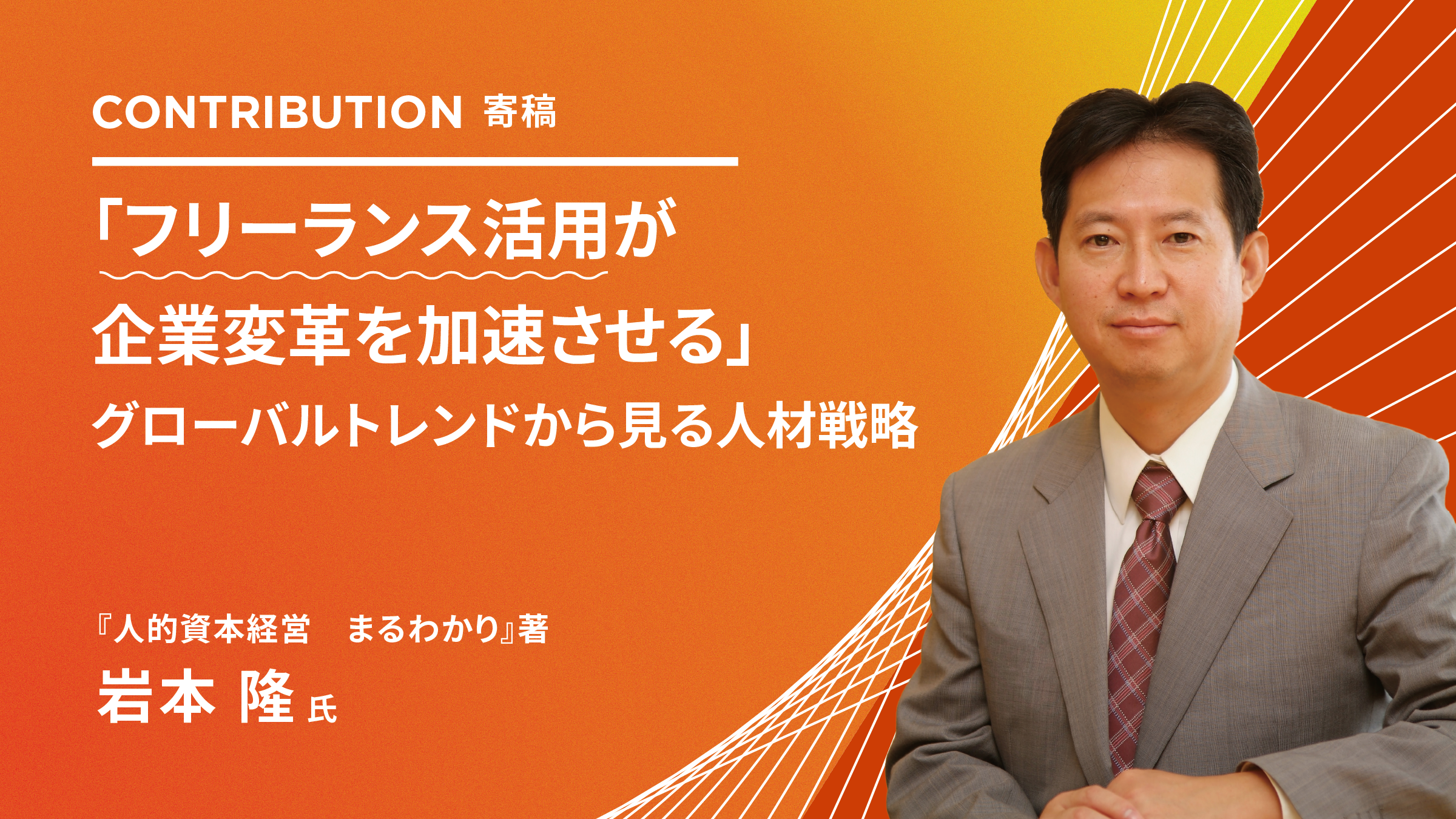リモートワークの普及によって、地方在住のエンジニアを採用する選択肢が広がっています。母集団を広げることはもちろん、地方でのフルリモートならではの特性を理解した上で活用することで、採用戦略全体を見直す機会にもなります。本記事では、母集団形成から定着までを一気通貫で整理し、エンジニア採用担当者が戦略を描く際の指針となるポイントを解説します。
エンジニア採用にお困りならHRBIZのプロ人事と解決
上流から下流まで、実績豊富なプロ人事がサポート。【無料】お問い合わせはこちら
エンジニア採用は、多くの企業にとって大きな課題のひとつ。求人広告や紹介会社にコストをかけても応募が集まらず、ようやく採用できても数年以内に離職してしまう──そんな状況に直面している人事・採用担当者の方も少なくありません。
一方で、リモートワークの普及によって、都市部のエンジニアに限定せず、地方在住のエンジニアを採用する選択肢が広がっています。母集団を広げることはもちろん、地方ならではの特性を理解した上で活用することで、採用戦略全体を見直す機会にもなります。
本記事では、フルリモートでの地方エンジニアの活用を前提に「母集団形成から定着まで」を一気通貫で整理し、人事・採用担当者が戦略を描く際の指針となるポイントを解説します。
関連記事として「【地方エンジニア活用】採用コストを最適化する3つの戦略とは?|都市部 vs 地方の比較」や「【地方エンジニア活用】フルリモート環境でのマネジメント実践法『3Vフレームワーク』で課題を”見える化”」も併せてご覧ください。
なぜエンジニア採用は難しいのか
1. スキルの見極めが難しい
人事担当者がスキルを正確に見極めるには、現場エンジニアの協力や選考設計そのものに専門性が欠かせません。
たとえば同じJavaエンジニアでも、金融系システムに強い人とWebアプリ開発に強い人では、実際に活躍できるフィールドがまったく違います。さらにクラウド(AWSやGCP)、AI、モバイルなど、トレンドごとに必要な知識や経験が細分化されています。
現場では、「履歴書にはReactと書いてあるけれど、実務ではほとんど触ったことがない」「クラウド経験ありとあったが、オンプレ環境での補助的な経験だった」といったケースもあり、特にエンジニア経験のない採用担当にとっては、正確なスキルの見極めは難易度が高くなります。
2. 市場が圧倒的な売り手市場
優秀なエンジニアほど、複数の企業から同時に声がかかっています。特に都市部では、大手やメガベンチャーが「ネームバリュー+成長機会+好条件」を武器にして採用を有利に進めています。
新卒や20代の若手エンジニアは「研修制度が整っている」「キャリアアップが見込める」といった理由から志望度が上がる傾向があります。一方、中堅層は「給与条件」「労働環境や働き方」への不満が転職理由となり、より魅力的な環境へと流れてしまう可能性が高まります。
結果として、中小企業や名前の知られていないスタートアップは母集団形成の時点で不利になったり、せっかく採用できても短期間で競合に人材が流れてしまうといった課題が顕著に現れます。
参照:
・『「研修・教育制度を知ると志望度が上がる」と回答した学生が9割に迫る。「研修が充実している企業は、社員を大切にしていると思う」「スキルが身につく企業に就職したい」の声/2024年卒対象アンケート』by 株式会社学情|PR TIMES
・『転職理由ランキング【最新版】 みんなの本音を調査!』by doda
3. 採用後の関係構築が不可欠
エンジニア採用は「入社して終わり」ではなく、そこからが本当のスタートです。たとえば、せっかく採用できても「スキルアップが叶わなそう」「評価基準が不透明」「リモートで孤立してキャリアが見えない」といった理由で数年以内に離職してしまうケースは後を絶ちません。
逆に、キャリア支援や成長機会が明確に設計されている企業では、エンジニアが社内の「ファン」になり、リファラル採用に自主的に取り組む好循環が生まれます。これは単なる人事施策ではなく、組織文化づくりそのものに直結する要素です。
🔎関連記事
【6/20開催イベントレポート】リファラル×認知科学で描く!新時代の組織デザイン
“自律的に成長する組織とは何か”を参加者とともに考える場となりました。
つまりエンジニア採用は、スキルの多様性 × 市場の競争激化 × 定着の難しさ が同時に絡み合う点で、他職種と比べて圧倒的に複雑なのです。だからこそ「採用戦略」が必要であり、地方エンジニア活用はその戦略の一つとして有効になり得ます。
母集団形成の戦略(地方エンジニア編)
地方のエンジニアを採用するために、そもそもどのようにして母集団を作ればよいのでしょうか。
都市部では採用イベントや勉強会、転職フェアなど候補者と接点を持てる場が多い一方、地方ではそもそものコミュニティが少なく、従来のやり方では応募者が集まりにくいのが現実です。だからこそ、地方の候補者特性を理解したうえでのアプローチ が欠かせません。
1. 採用ブランディングを強化する
「都市部に比べて学習機会や横のつながりが少ないのでは」といった、地方在住のエンジニアが抱える不安を解決していきましょう。企業側が採用広報で「最新技術へのキャッチアップを支援」「全国のチームと協働」「リモートでも孤立しない環境」といった点を打ち出すことが効果的です。
加えて、「地方にいながらトレンドの案件に携われる」「スキルを活かしつつ生活基盤は地元に置ける」といった働き方の魅力を示すことも、応募の動機付けにつながります。
2. 新卒市場と中途市場でアプローチを分ける
新卒採用:地方の大学・高専・専門学校との関係構築が鍵になります。キャリアセミナーやインターンシップを通じて「地域課題に取り組む企業」という姿勢を見せることで、早期から学生との接点を持つことが可能です。
中途採用:先述したように、「地方に住みながらも活躍・キャリアアップが可能な環境」を明確に打ち出しましょう。ライフスタイルとキャリアの両立をサポートできる体制を示すことがポイントになります。
3. 社員を巻き込んだ母集団形成
母集団形成は人事だけの役割ではなく、社員総出で行うことができます。
たとえば、すでにフルリモートで活躍している社員のインタビュー記事を公開すれば、働き方の解像度が高まり、「自分も同じように働けそうだ・こういう雰囲気なら働いてみたい」と感じてもらえます。
あるいは、社員が自発的にブログやSNSを運用したり、オンライン勉強会に参加・登壇したりできるような環境を整えることで、自然と会社の存在感が高まり、母集団形成につながります。
特に地方のエンジニアコミュニティは、都市部に比べてまだ活発とはいえません。だからこそ、企業やイチ社員が積極的に関わり、成功事例や働き方のロールモデルを示すことで、採用市場での差別化ポイントをアピールできます。
選考設計とスクリーニング
母集団形成の次は「活躍できる人材」を見極めましょう。特にエンジニア採用ではスキルの幅が広く、また、フルリモート前提の場合はその適性を判断しづらいため、選考設計そのものに工夫が必要です。
1. 技術スキルを客観的に評価する仕組み
履歴書や職務経歴書だけではスキルレベルが掴みにくいのがエンジニア採用の難しさです。以下のような仕組みを取り入れることで、ミスマッチを防ぎやすくなります。
- コーディングテストや技術課題をオンラインで実施し、コードの品質や問題解決力を確認する
- GitHubやQiitaなどのアウトプットをチェックし、実務に近い成果物を見て判断する
- 面接には現場エンジニアを同席させ、具体的な課題や技術ディスカッションを行う
こうした客観的評価の仕組みと現場メンバーによるスクリーニングがあれば、入社後のスキルのミスマッチを防ぐことができます。
2. リモート適性の見極め
地方在住のエンジニアはフルリモート前提となるケースが多いため、スキルだけでなくリモート適性を見極めることが重要です。
- 自律的にタスクを進められるか
- オンラインでのコミュニケーションに慣れているか
- セキュリティや業務環境を整えられるか
こうした要素は、スキルと同じくらい定着や活躍に直結します。選考段階で「具体的にどのようなリモート環境で働いているか」を確認する質問を設けると効果的です。
例:
- 自律性:「どのように日々のタスクを管理していますか?」「進捗が遅れた場合はどのように共有しますか?」
- コミュニケーション力:「過去にフルリモートやハイブリッドで働いた経験はありますか?」「オンラインでの意思疎通で工夫していることは?」
- 業務環境の整備:「自宅のネットワーク環境やセキュリティ対策はどうされていますか?」「業務用PCやツールは会社提供か自己準備か、どちらを希望しますか?」
こうした質問を交えることで、候補者がリモートに適した働き方を実践できるかどうかが具体的に見えてきます。
3. 選考プロセスを「透明化」する
候補者にとって不安が大きいのは、「どれくらい選考が続くのか」「結果はいつわかるのか」が見えない状態です。特にフルリモート採用では、温度感が伝わりにくいため、選考や稼働後の評価基準をフラットに共有することが重要です。
- 「面接は最大3回、合否は1ヶ月以内に確定」など、スケジュールを最初に提示する
- 「成果は週次で進捗確認、四半期ごとに評価」といった、稼働後の評価プロセスを説明する
- 候補者からの質問にもオープンに答え、「選ぶ側」だけでなく「選ばれる側」である姿勢を示す
オンボーディングと定着支援
優秀な地方エンジニアを採用できても、短期で離職してしまえば採用・育成にかけた時間とコストが無駄になってしまいます。
特にフルリモート環境では、出社前提の仕組みをそのまま適用すると「稼働実態が見えない」「評価に不公平感が出る」「孤立して帰属意識が育たない」といった問題が起こりやすく、定着率に直結します。
こうした課題を解決するには、オンボーディングからキャリア支援までを一貫して設計することが欠かせません。具体的には、初期1か月でのオンボプランの明確化、定期的な1on1や心理的安全性を保つ仕組みづくり、そしてアウトプット基準での評価・キャリアパスの提示などです。
『フルリモート環境でのマネジメント実践法『3Vフレームワーク』で課題を”見える化”』では、実務経験と企業支援の知見をもとに、地方エンジニアをフルリモートで定着・活躍させるための”型”を整理しています。
”3つの見える化”をキーワードに、地方エンジニアが安心して力を発揮できる環境をつくるための実践法を紹介していますので、併せてご一読ください。
- ✔ Visualization of Performance: 成果の見える化
- ✔ Visualization of Collaboration: つながりの見える化
- ✔ Visualization of Future Career: キャリアの見える化
🔎関連記事
フルリモート環境でのマネジメント実践法『3Vフレームワーク』で課題を”見える化”
リモートワークの普及により、都市部だけでなく地方在住のエンジニアを採用する企業が増えています。しかし「成果が見えない」「チームに馴染みにくい」「キャリアの未来が描けない」といったフルリモート特有の課題が、定着や活躍を阻む要因になりがちです。本記事では、3つの”見える化”をキーワードに、地方エンジニアが安心して力を発揮できる環境をつくるための実践法を紹介します。
まとめ|戦略的に「地方エンジニア活用」を進めるためには
地方エンジニアの活用は、採用戦略を広げるチャンスになります。ただし、母集団形成から選考プロセス、オンボーディング、定着支援までを一貫して設計しなければ、せっかく採用しても短期離職や再採用に繋がり、結果的にコストがかさむリスクもあります。
また、都心部での採用や入社後フォローと同じ戦略をとっていると、フルリモート特有の課題に気付けず、候補者の目に魅力的に映らなくなったり定着や活躍を阻む要因になったりします。
- 母集団形成が思うようにいかない
- スキルの見極めに自信が持てない
- 採用してもすぐに離職してしまう
といった課題に心当たりがある場合は、ぜひ一度HRBIZにご相談ください。エンジニア採用に精通したプロ人事が、要件整理から母集団形成、採用広報、面接設計、入社後のフォローまで伴走します。
エンジニア採用にお困りならHRBIZのプロ人事と解決
即戦力の人事プロを、柔軟かつスピーディーにご紹介!【無料】お問い合わせはこちら
即戦力人材の採用にお困りではありませんか?ハイスキルなHR人材をスムーズに採用できる【HRBIZ】
HRBIZでは優秀なHR人材をご紹介しています。スキルのみならず人柄も踏まえ、企業様にマッチした人材を、最短で即日ご紹介できます。即戦力人材の採用にお困りの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。