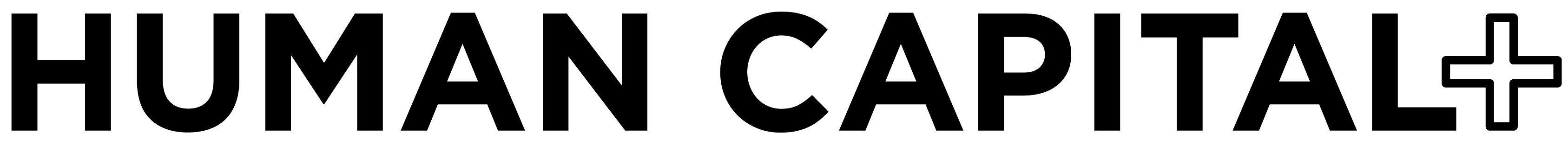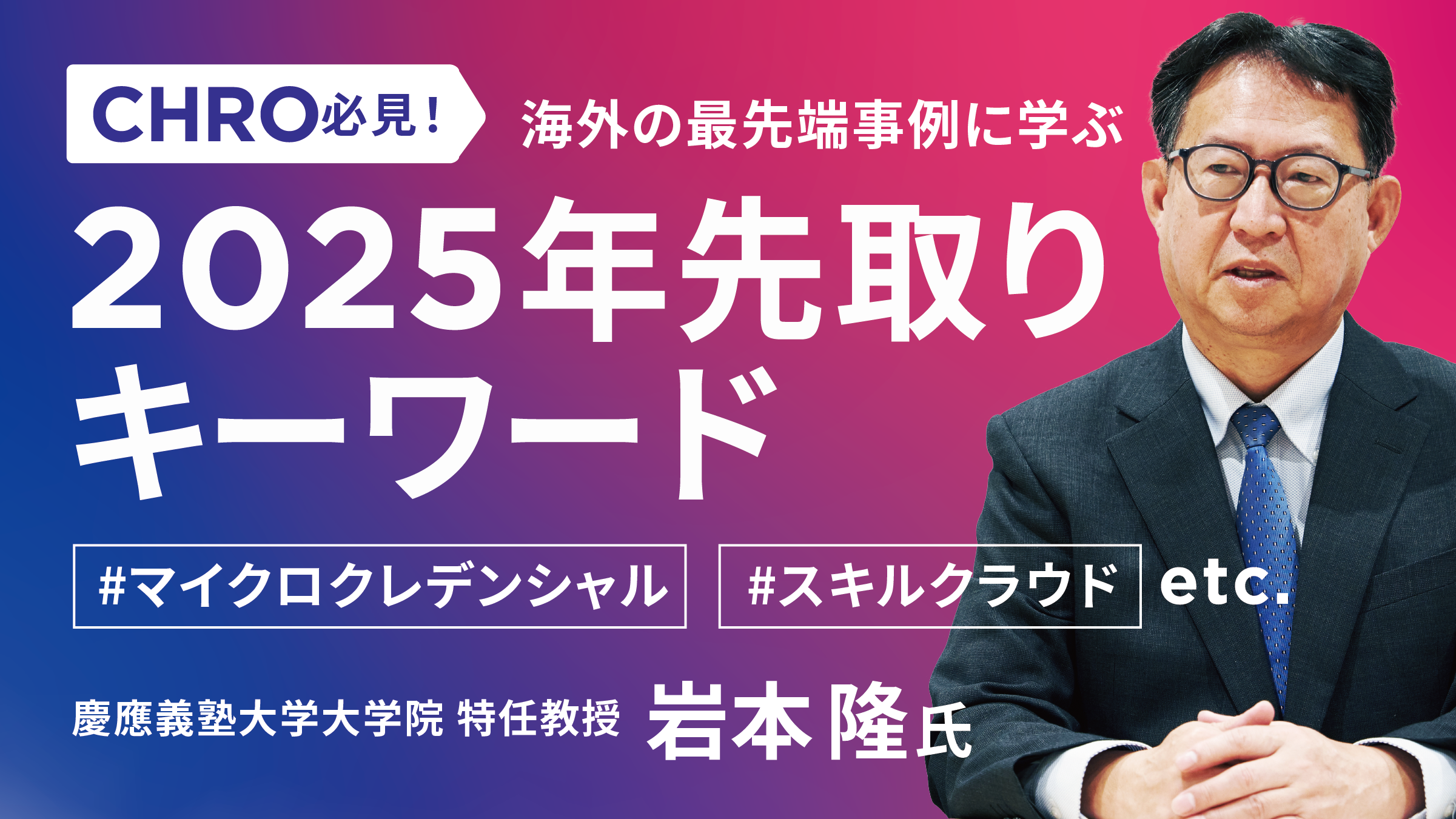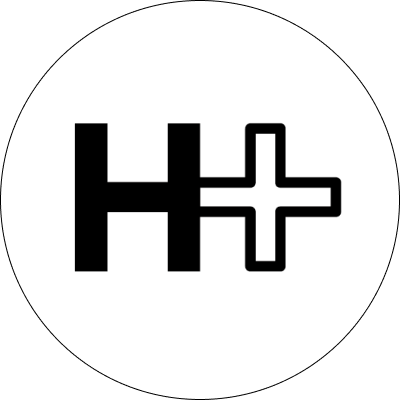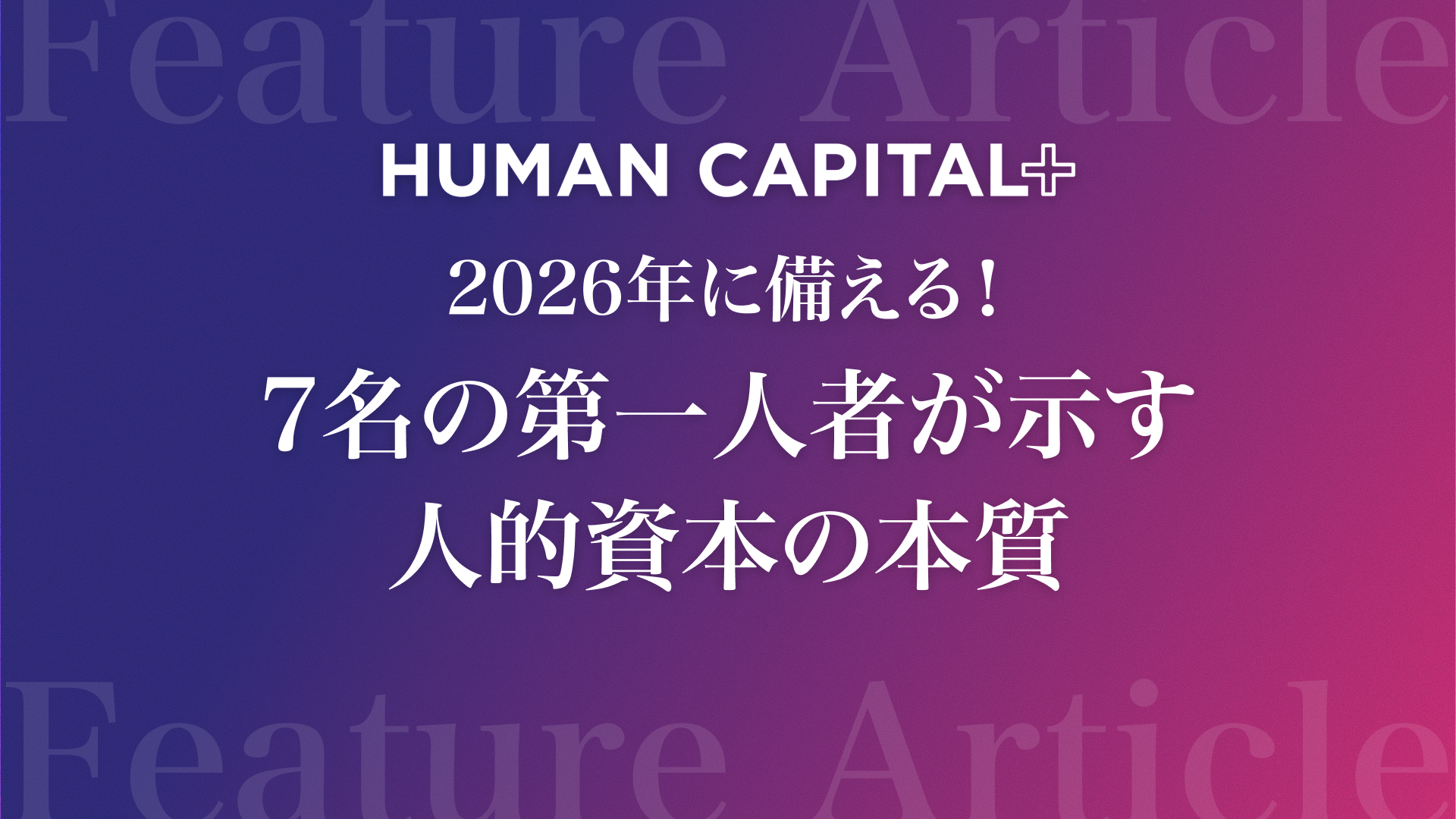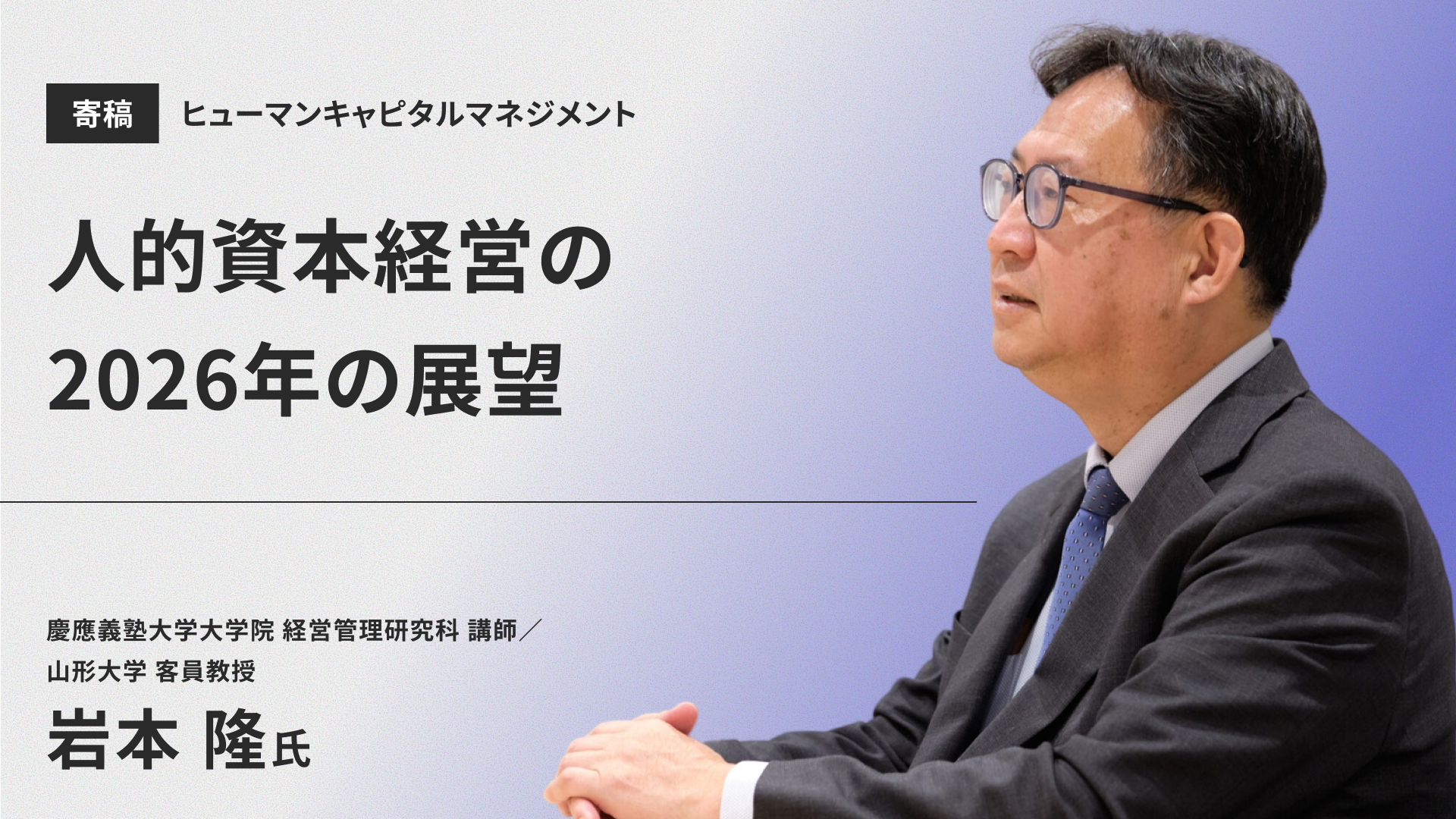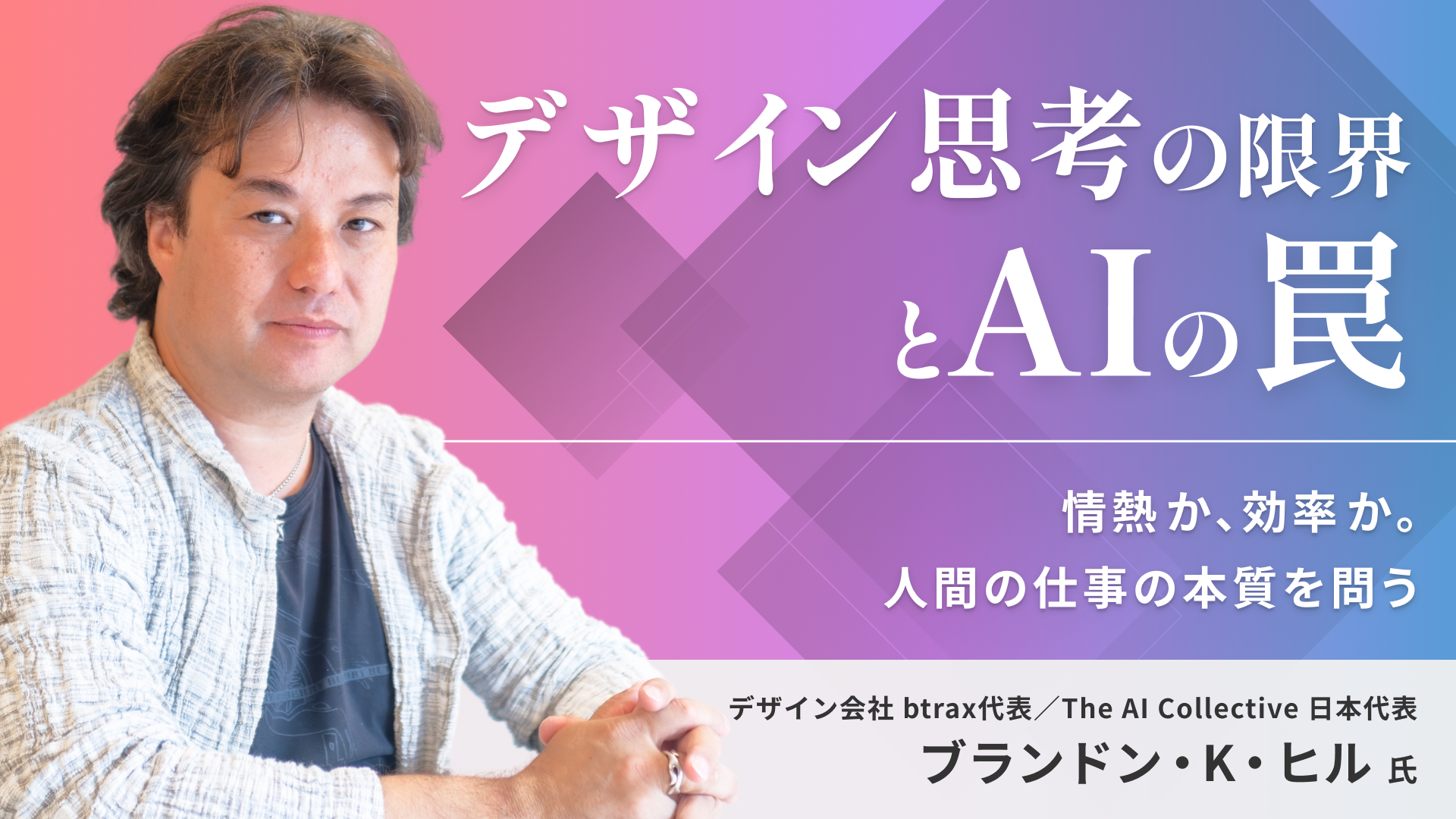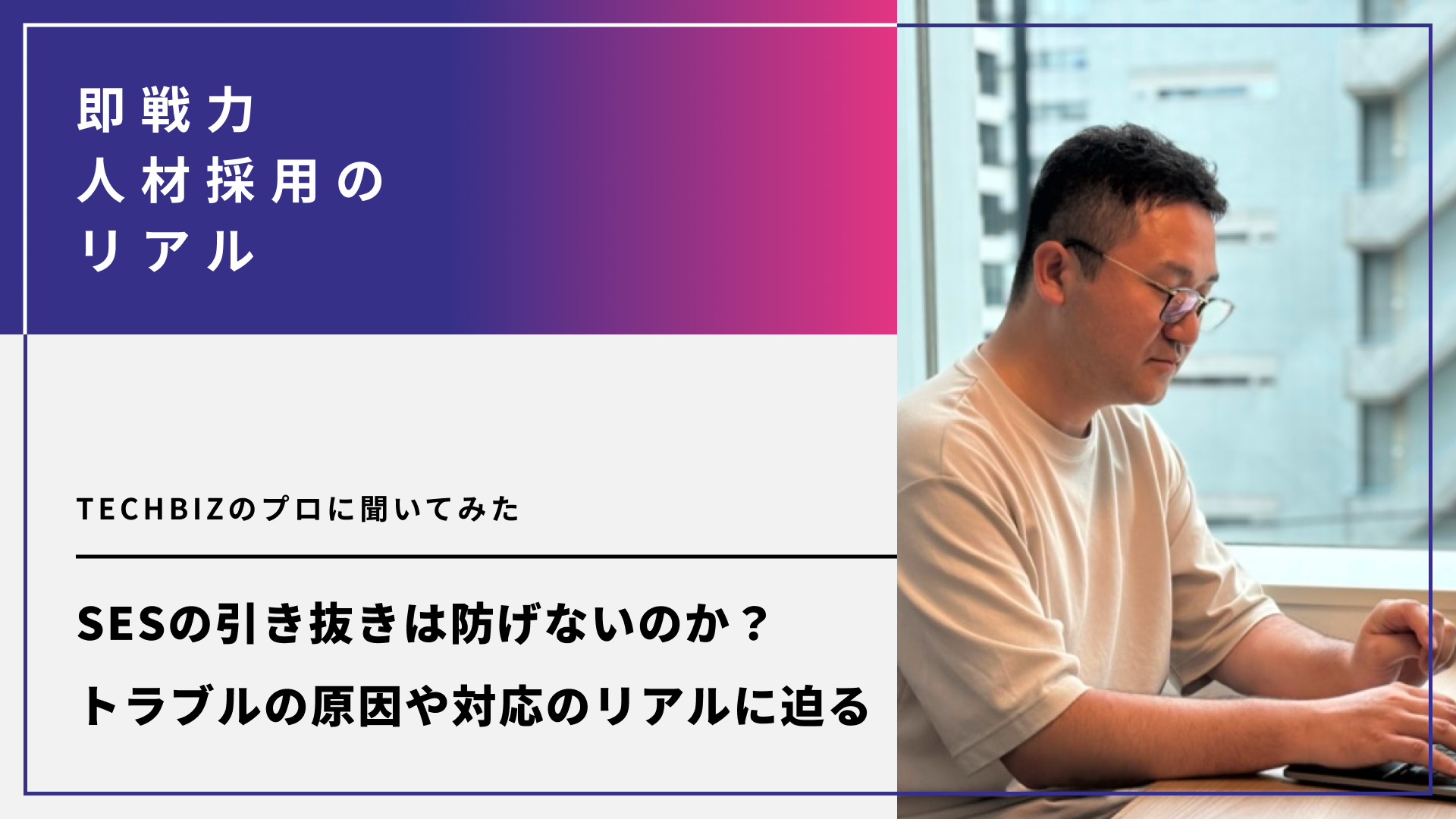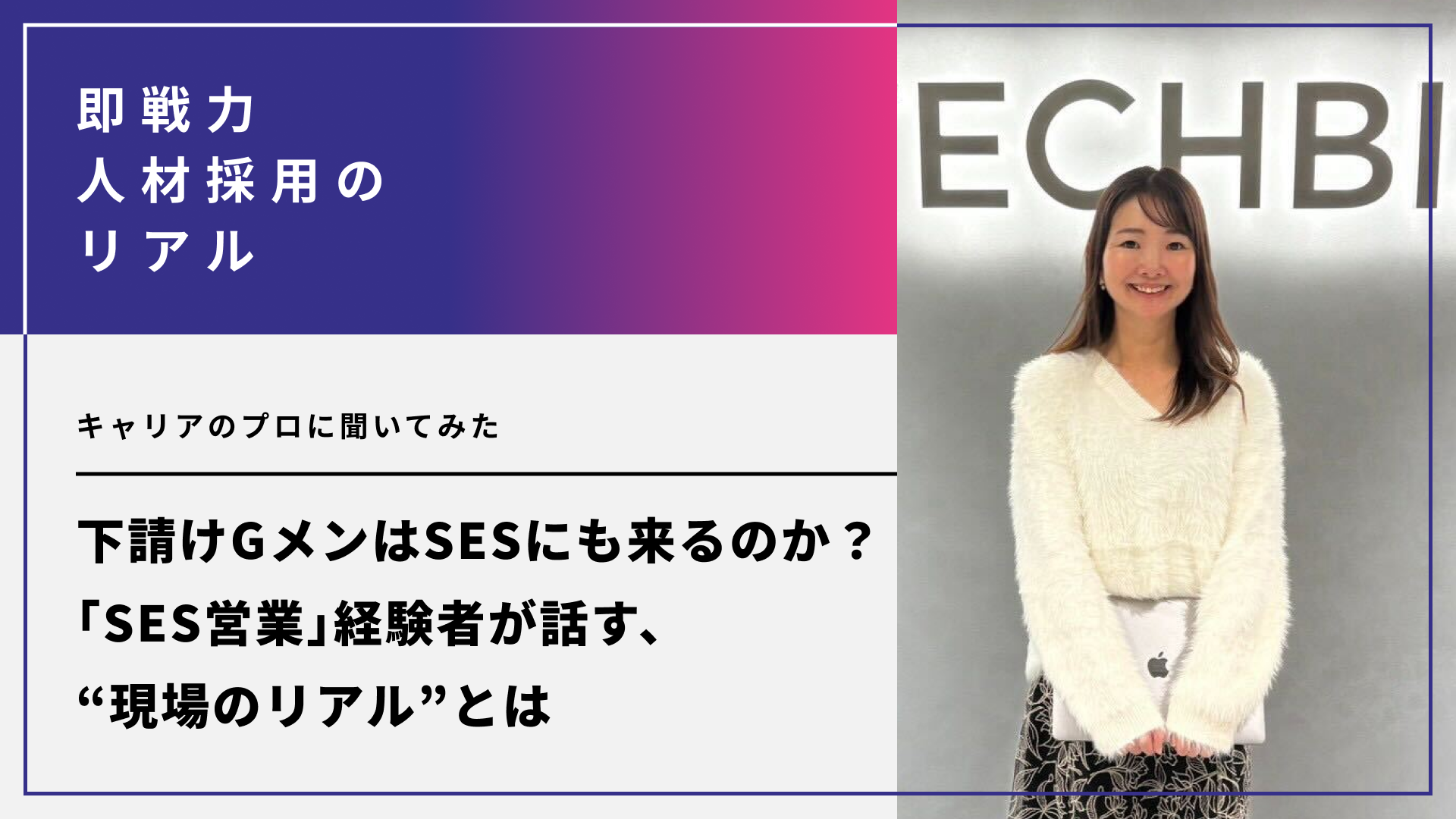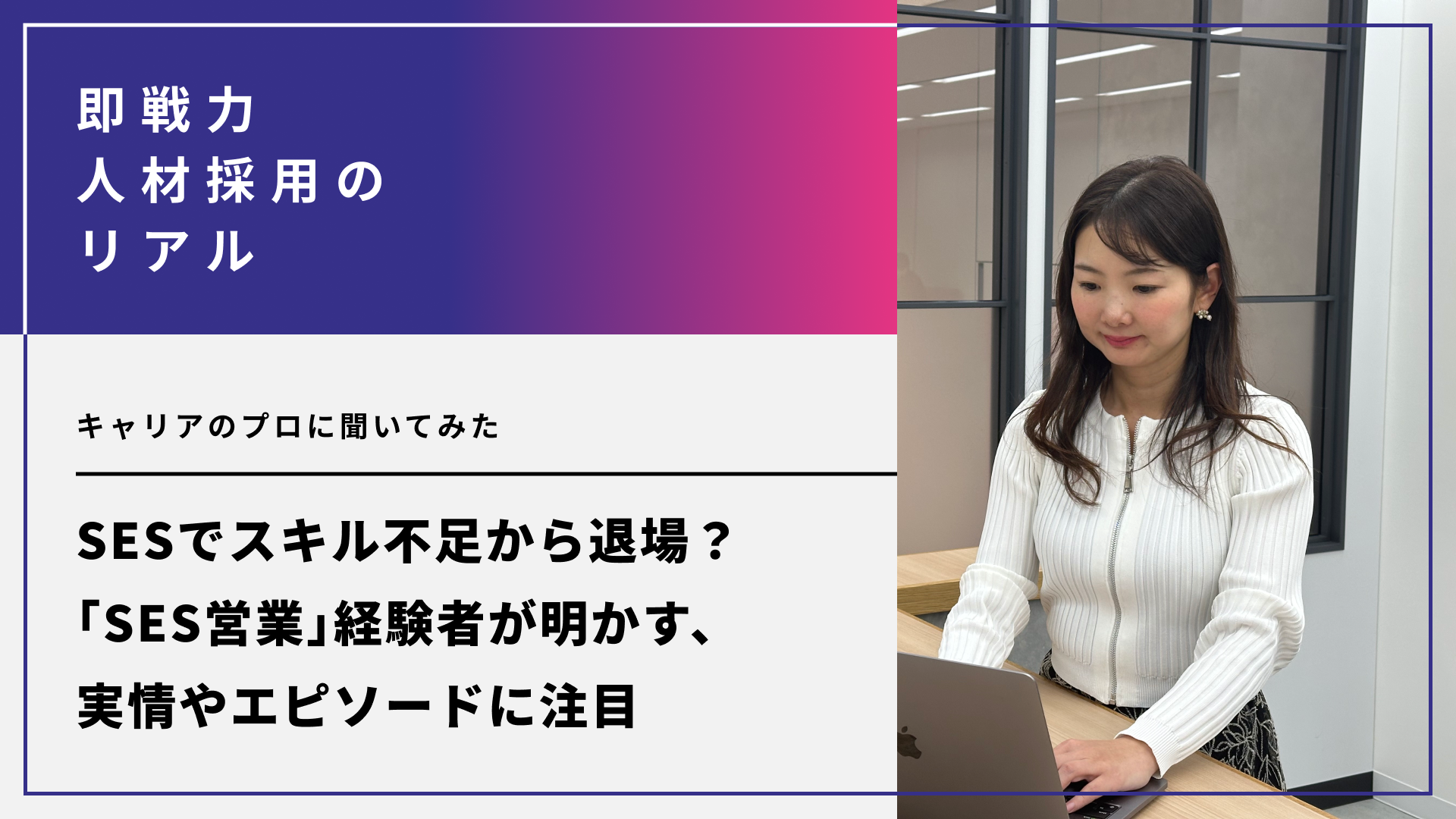今回は、過去にもご寄稿をいただいた人的資本経営の第一人者である岩本 隆先生に、2024年の総括と、それを踏まえた海外、そして国内における2025年の人事トレンドを予測の上でお話いただきました。
岩本 隆氏プロフィール

東京大学工学部金属工学科卒業。カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)大学院応用理工学研究科マテリアル理工学専攻Ph.D.。日本モトローラ(株)、日本ルーセント・テクノロジー(株)、ノキア・ジャパン(株)、(株)ドリームインキュベータを経て、2012年6月より2022年3月まで慶應義塾大学大学院経営管理研究科特任教授。2018年9月より2023年3月まで山形大学学術研究院産学連携教授。2022年12月より2025年3月まで慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授。2023年4月より慶應義塾大学大学院経営管理研究科講師、山形大学客員教授。 (一社)ICT CONNECT 21理事、(一社)日本CHRO協会理事、(一社)日本パブリックアフェアーズ協会理事、(一社)SDGs Innovation HUB理事、(一社)日本DX地域創生応援団理事、(一財)オープンバッジ・ネットワーク理事、ISO/TC 260国内審議委員会副委員長などを兼任。
Q.1 様々な変化があった2024年について、どのように振り返られますか?
A.1 「人的資本経営」と「ジョブ型雇用」の2本柱を実現するために多くの取り組みが広がった一年でした
今年は「人的資本経営」が本格的に進んだ年だと評価しています。統合報告書を開示する企業はいよいよ1000社を超え、約1,300社ある大企業の大半が人的資本について開示するようになりました。多くの企業が人的資本をコストではなく投資だと認識し推し進めてきた結果が表れているものと思います。
もう一つ見逃せないトレンドとしては「ジョブ型雇用」の推進です。内閣官房が8月に「ジョブ型人事指針」を公表したのも大きな引き金となりました。この指針の中では三位一体の労働市場改革とジョブ型人事指針の意義を説明することから始まり、導入事例として20社の先進的な取り組みを紹介しています。
そしてこれらのトレンドに応えるように、様々な形で個人のスキルの可視化が進んできました。経営戦略に連動した人材戦略に則り、「スキルマップ」という形で将来の人材ポートフォリオを策定する企業が増えています。
「スキルマップ」と合わせて普及し始めたのが、「マイクロクレデンシャル」の導入です。学習内容をより細分化した単位ごとの履修証明を指し、個人が持つスキルやケイパビリティをより細分化して証明ができるようになるものです。2024年は「マイクロクレデンシャル元年」とも呼べる転換点で、「オープンバッジ」と呼ばれるスキルのデジタル証明の国際規格が活用され始めています。私が審査委員長を務める「オープンバッジ大賞」というアワードも今年で2回目を迎えましたが、昨年よりも多くの先進事例がノミネートされ盛り上がりを実感しているところです。

Q.2 国外に目を向けたとき、2025年は世界でどのようなトレンドが予測されるでしょうか
A.2 「The War of the Skills Clouds」とも呼べるスキルベースでの組織マネジメントのさらなる盛り上がりが起こるでしょう
日本と比較したとき、欧米を中心とした国外においてはスキルベースでの組織マネジメントが進んでいます。欧米では古くからジョブ型雇用の形式をとっており、そのために個人のスキルやケイパビリティを可視化し評価する体制が構築されてきました。
そんな「スキルベース先進国」である欧米諸国ならではの動きがすでに想定されています。たとえばEUではCSRD(Corporate Sustainability Reporting Directive)と呼ばれる指令により、サステナビリティ報告の一貫性を高め、金融機関や投資家、一般の人びとが比較可能で信頼できるサステナビリティ情報を利用できるようにする動きが出てきています。これはEU域内で事業を行う企業に人的資本や環境に関する情報を開示することを義務付けるものであり、日本企業も例外ではありません。
また、日本に影響の大きいものでいえば企業の人的資本報告の国際的ガイドラインISO 30414の改訂版が2025年春に発行される予定です。さらに人材マネジメントシステムの新しい国際規格「ISO 30201」が開発中で、発行されるとISO 9001やISO 14001のような認証規格になる可能性があります。
フリーランスに関わるトピックも見逃せません。国際サステナビリティ基準委員会(ISSB)の人的資本研究プロジェクトにより優先順位の高い人事施策について深掘りして議論がなされていますが、ここでも「Alternative workforce」と呼ばれる「代替的労働力」がホットなトピックになっています。これまで正社員の補助的な役割として充てられることが多かったフリーランスをはじめとする代替的な労働力を、いかに主体的に裁量を持たせながら活躍してもらうかが競争力を高める上で欠かせないポイントになっている証左です。

Q.3 ここまでお話いただいた2024年と世界のトレンドを踏まえ、2025年の日本企業はどのような対応を迫られるでしょうか
A.3 ジョブ型雇用の実装が求められるとともにスキルベースの組織マネジメントが進行し、指標と目標を設定した上でロジックを通すことがますます求められるようになるでしょう
これまでメンバーシップ型雇用を採用する企業が多かった日本においても、激化する企業間競争に生き残るために本格的にジョブ型雇用の実装が求められる時期に差しかかってくると考えられます。そのためにスキルベースの組織マネジメントが進行するでしょう。
人的資本経営では、「インプット→アクティビティ→アウトプット→アウトカム」のプロセスにおいて指標と目標を設定してロジックを設定することが求められます。従来は、どのような人的リソースを投入するかという「インプット」、もしくはどんな企業活動を行うかという「アクティビティ」までしかせいぜい求められませんでした。
しかし、これからはどのような結果を生んだかという「アウトプット」、さらにはそれがどのような事業上の成果につながったかという「アウトカム」まで求められるようになります。「論理性」があることに加えて指標と目標が設定されて「定量性」があることや、腹落ちするナラティブにすることで「納得性」があることも人的資本経営を実践する上で重要なポイントです。
人手不足が深刻化する時代の人的資本経営の実践においては、内部人材に加えて外部人材の活用も経営戦略上欠かせないものになってきます。具体的にはフリーランスを筆頭に、アルムナイと呼ばれる過去に退職した人材や副業の人材も活用し、事業を加速させることが求められるようになるでしょう。この外部人材の戦略的活用のためにも、スキルベースの組織マネジメントに基づき必要なスキルを定義した「スキルマップ」は不可欠です。
また昨今トレンドにもなっているリスキリングの文脈でも同様の「スキルマップ」の定義と、それに対応した「ラーニングマップ」の作成が有用です。この動きも先述した「オープンバッジ」による「マイクロクレデンシャル」によって促進されることが期待されます。こうした活用人材の多様化と必要リソースの明確化に伴い、リーダーシップにおいてはますますピープルマネジメント力を高めることが必要になるでしょう。AIの台頭によってテクニカルスキルは代替されていく一方で、ヒューマンスキルは相対的に価値を高めていくはずです。