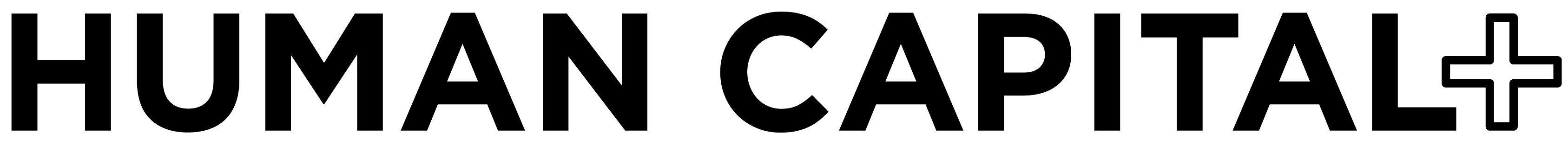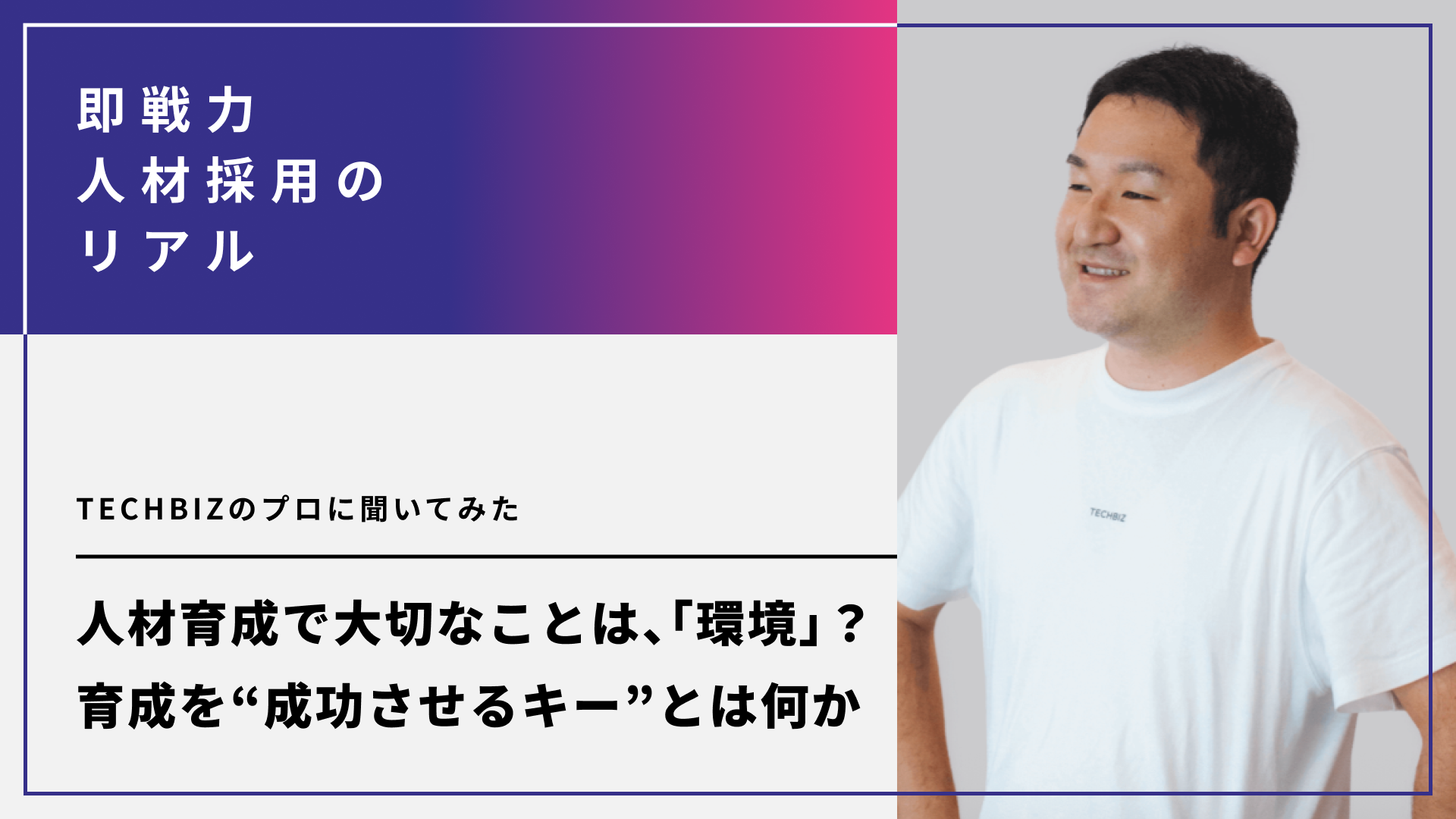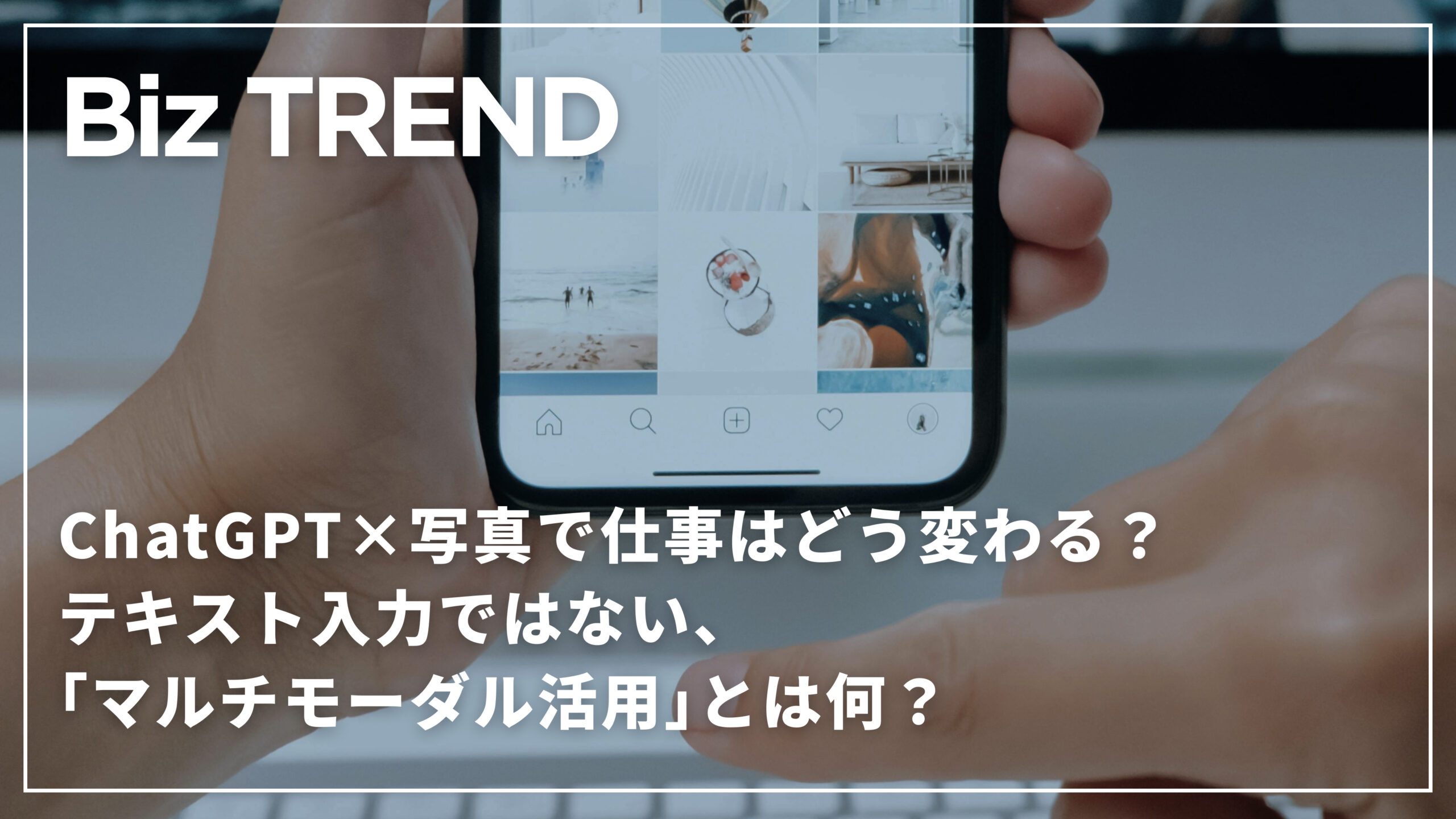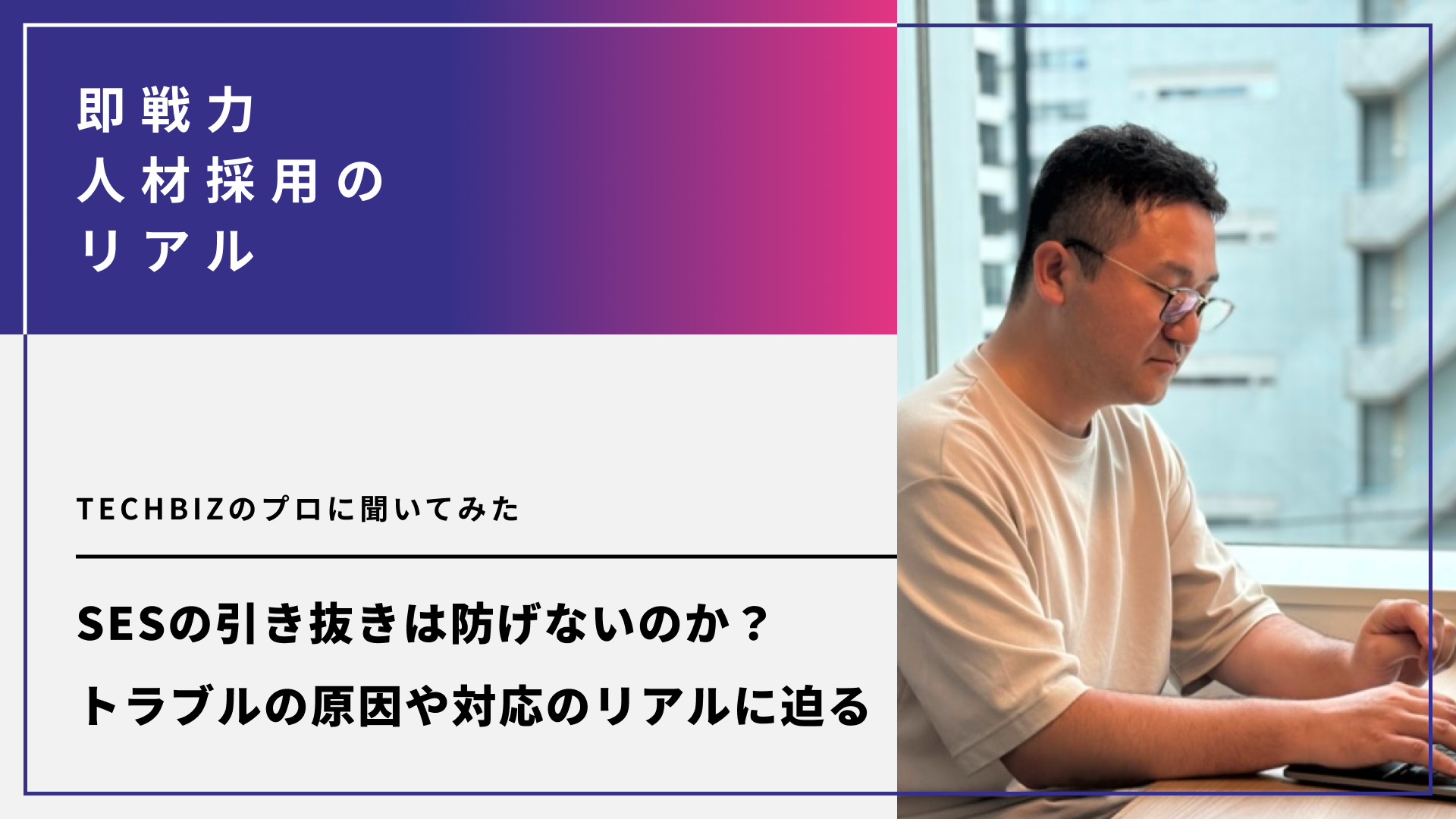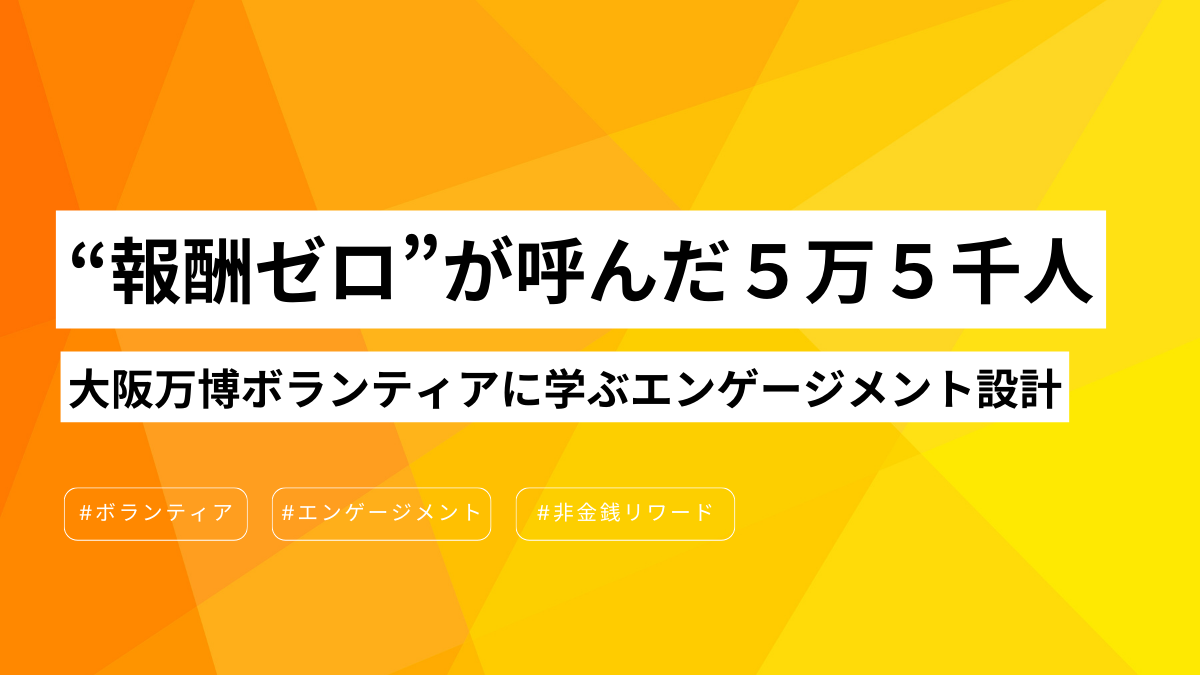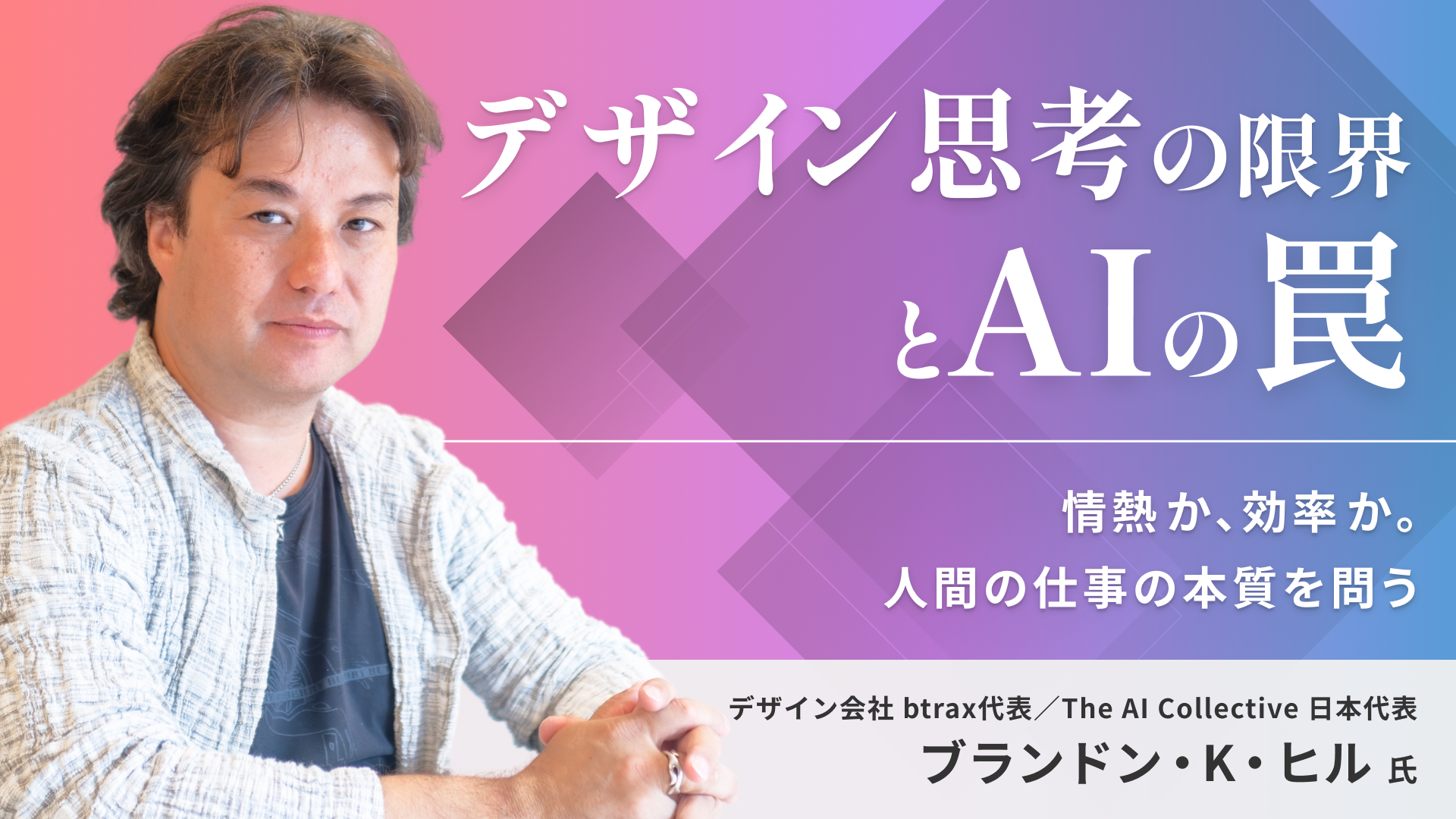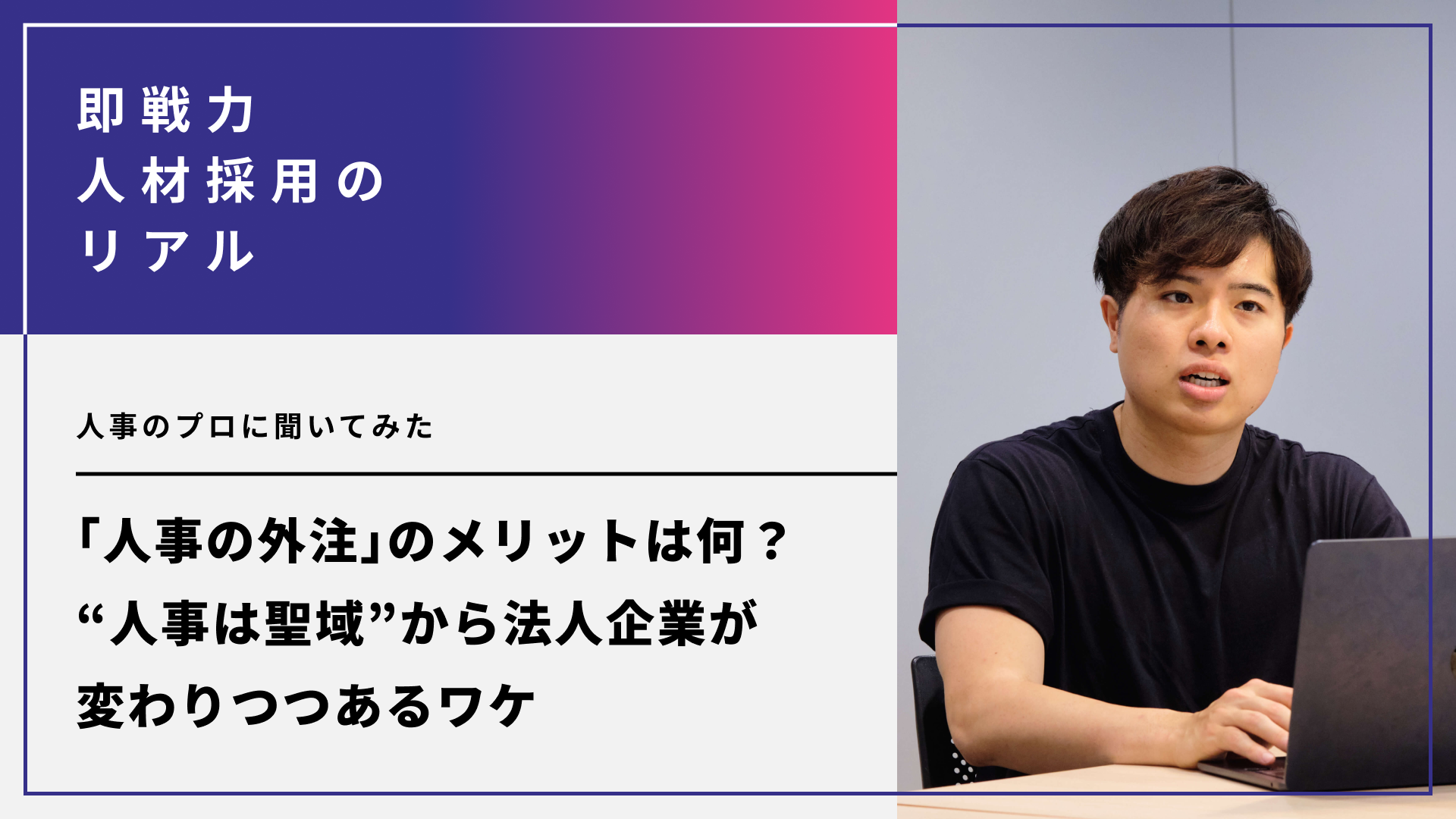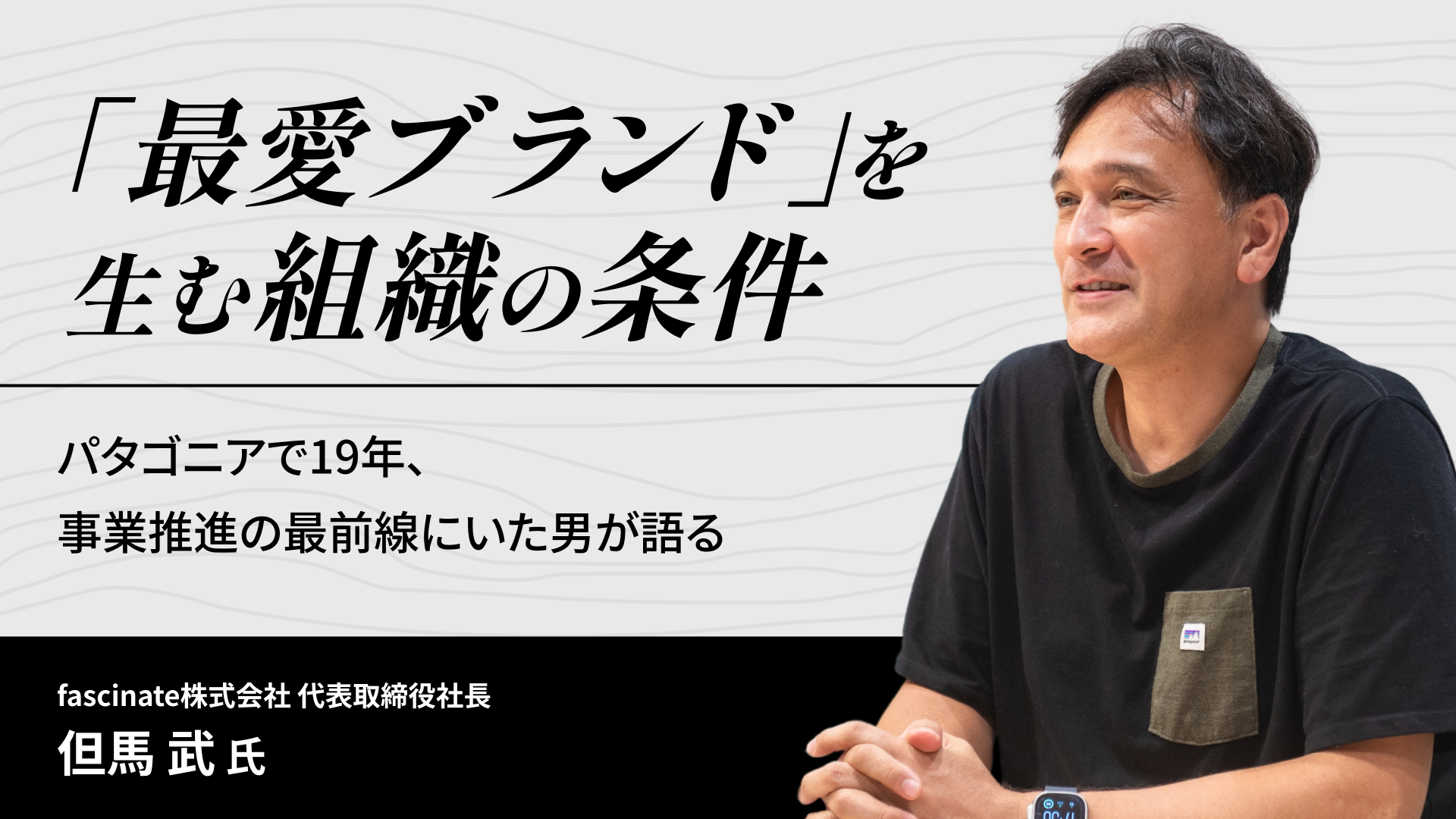HUMAN CAPITAL+では11月の間、「AI」に注目し、AIやChatGPTに関する記事をBizTRENDにて計3本公開していました。
現在も日々進化を続けるAIですが、近年では企業の人事評価にも導入され始めています。そこで気になるのが、人事評価とAIのシナジーです。
本記事ではプロライターが取材を通して知った、人事評価とAIに関する意見や実態、向き合い方などを分かりやすくまとめています。ビジネスや組織での運用のヒントになるかもしれないので、最後までチェックしてみてください。
HUMAN CAPITAL +
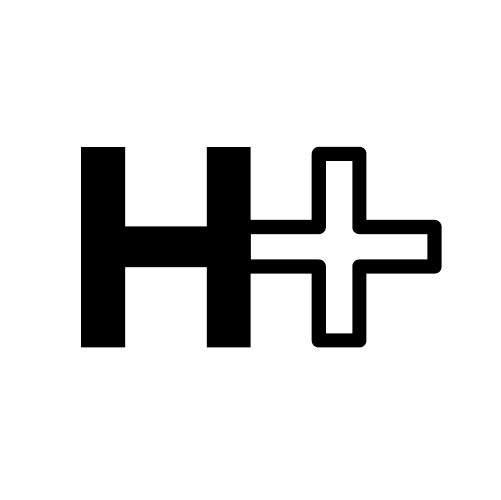
「HUMAN CAPITAL +」の編集部です。社会変化を見据えた経営・人材戦略へのヒントから、明日から実践できる人事向けノウハウまで、<これからの人的資本>の活用により、企業を成長に導く情報をお届けします。
ハイスキル・即戦力人材の採用にお困りならTECHBIZ
最短・即日で企業様にマッチした人材をご紹介【無料】お問い合わせはこちら →
人事評価の時期になると、頭を抱える人は少なくないのではないでしょうか。最近はAIを使った人事評価の活用が少しずつ広がり、データをもとに評価を支える「人事評価×AI」という取り組みも注目され始めました。
ただ、導入が進む一方で、実際にどこまで役立つのか、自分たちの働き方にどう影響するのかは意外と語られていません。そこで今回、この流れをあらためて整理してみたいと思います。
人事評価×AIで、HRの仕事はどう変わるのか?
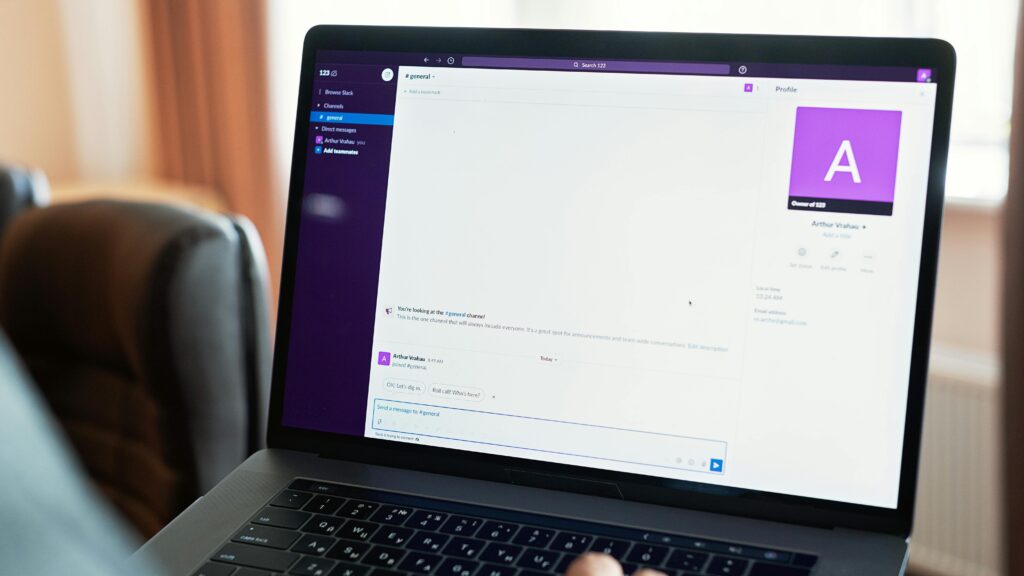
近年、AIの活用はマーケティング、営業、カスタマーサクセスといった領域で急速に発展してきました。しかし2024年以降、世界的には「HR領域にもAI導入が一気に広がっている」と指摘されています。Gartnerの“HR Technology Trends 2024”でも、生成AIを活用する人事部門が前年から大きく増加し、とくに「パフォーマンスマネジメント(人事評価)」が最も利用が進む領域のひとつと報告されています。
海外だけでなく、日本でもこの流れは顕著です。ここ数年、タレントマネジメント系サービスや評価クラウドの多くが「AIによる評価コメント生成」などのAI機能を相次いで実装し始めました。つまり、人事評価はもはや“人の主観だけで行うもの”ではなくなりつつあります。
この背景には、技術の進化だけでなく働き方の変化もあるでしょう。リモートワークが広がり、管理職が直接部下の働きぶりを把握しにくくなったことで、「ログや成果データを整理し、評価に必要な情報をAIが整える」というニーズが高まりました。
さらに人的資本開示が進んだことで、企業は“評価の透明性”を外部に示す必要が生まれています。評価プロセスをデータ化し、一定の基準で判断することは、もはや企業の責任とも言えそうです。
人事評価×AIは、人事の役割を再設計できるのか?
人事評価AIの価値について考えたいのは、ツールの導入をゴールにしないこと。これまで私が取材してきた中でも「日本企業はツール導入をゴールにしてしまうから、DXが進まない」という話を幾度となく聞いてきました。
「紙をシステムに置き換える」「Excelをクラウド化する」といった“デジタイゼーション(置き換え)”にとどまってしまう企業が多いのです。確かにデジタル化によって効率化が進むかもしれませんが、それは本来のDXとは言えません。本質は、既存のプロセスにテクノロジーを乗せることではなく、仕事のあり方そのものを再設計することです。
その点、HUMAN CAPITAL+のシリーズ「即戦力人材採用のリアル」の過去記事で解説されていた「人事の仕事は“設計”と“運用”に分かれる」という話は、非常に示唆的です。設計の質が変わらなければ、AIを入れても評価の質は上がりません。これまで人が使っていたデータをAIに読み込ませても、人の仕事は楽になるかもしれませんが、本質的に人事評価という業務を再設計したことにはならないのです。
なぜ人事評価をするのか、そのためにどんなデータが必要になるのか、そこからどんなアクションを提案するのか。そうしたプロセスを経て、初めて評価AIを組みこんだ人事DXと言えるでしょう。
これらのことを踏まえて考えるべきことは、DXとは「いかにAIに人の仕事をさせるか」と考えることではありません。テクノロジーによって仕事の役割を変えることだと思います。
たとえばAIの登場で、教師の役割は大きく変わりつつあります。今や、わからないことはAIのほうが正確かつ分かりやすく答えてくれますし、むしろ“AIのほうが緊張しないで質問できて学習効果が高い”という話すらあります。だからこそ、教師の役割は「教える」から、「生徒の個性を受け止め、モチベーションを引き出す存在」へ変わりつつあるのではないでしょうか。
企業の中でも、人事や上司の役割は同じ流れの中にあるように思います。仕事の手順を教えることよりも、社員のやりがいをどうつくり、どんなチャレンジを後押しできるか。その“支援の質”が、これからのマネジメントの本質になっていくのかもしれません。AI時代におけるリーダーシップを、あらためて見つめ直すタイミングが来ているように感じます。
人事評価AIによってフリーランス活用も効率化する

人事DXとは「仕事をAIにまかせる」ことではなく、「仕事の役割を見直すこと」だと先述しましたが、これは人事の仕事に限った話ではありません。様々な仕事をDXするために、その価値や特性を見直していくと、社内の人がやるべき仕事と、社外のプロに頼った方がいい仕事が見えてくるはずです。
たとえば、戦略づくりや組織づくりのように、長期の視点や深い関係性が必要な仕事は、どう考えても社内に軸があったほうがよい。一方で、専門知識が必要だったり、期間限定でリソースを増やしたい領域は、社外のプロのほうがスピード感も精度も高い場合があります。
評価AIが進むことで、この“社内でやるべき仕事”と“外部の力を借りるほうが良い仕事”の境界線が、自然と浮かび上がってくるようになるはずです。
そう考えると、フリーランスや外部プロ人材の活用は、単なるコスト削減策ではなく、組織が自分の得意領域に集中するための合理的な選択肢として位置づけられていくのかもしれません。コア業務は自社社員で担い、ピンポイントで高度なスキルが必要な部分は外部と組む。そんな柔軟な働き方が、AIによって後押しされていくでしょう。
実際、外部人材を活用している企業では、社員が本来やるべき役割に集中できたり、事業の変化に合わせたスキル補完がスムーズになるケースが多いようです。評価AIによって“仕事の輪郭”がはっきりしてくるほど、外部の専門家と協働するメリットが際立つのかもしれません。
AIが作業負荷を減らしてくれることで生まれる余白を、どのように活かすか。その一つの答えとして、外部プロ人材との連携がより一般的になっていくでしょう。
テックビズでAIドリブンに強い組織へ
テックビズは、継続稼働率97%という実績を持ち、企業が求めるスキルや課題に応じて、最短即日で最適なフリーランスを紹介します。契約から導入後のフォローまで一貫して支援してくれるため、初めて外部人材を活用する企業でも安心して依頼できます。
AIによる効率化で生まれた余白を、専門家との協働にあてる。そんな“柔軟な組織づくり”を実現したい企業にとって、テックビズは心強いパートナーになるはずです。
ハイスキル・即戦力人材の採用にお困りならTECHBIZ
最短・即日で企業様にマッチした人材をご紹介【無料】お問い合わせはこちら →
即戦力人材の採用にお困りではありませんか?ハイスキルなITエンジニアをスムーズに採用できる【テックビズ】
TECHBIZでは優秀なITフリーランス人材をご紹介しています。スキルのみならず人柄も踏まえ、企業様にマッチした人材を、最短で即日ご紹介できます。即戦力人材の採用にお困りの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。