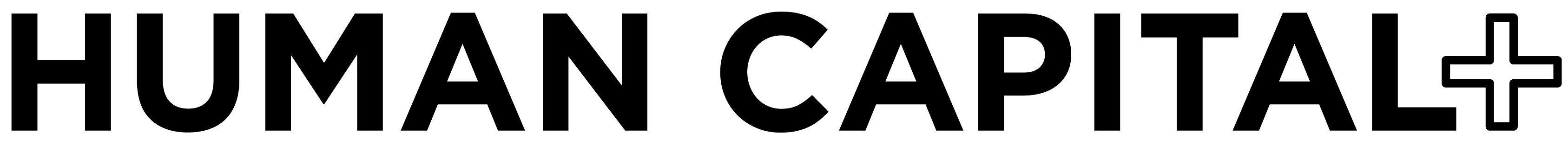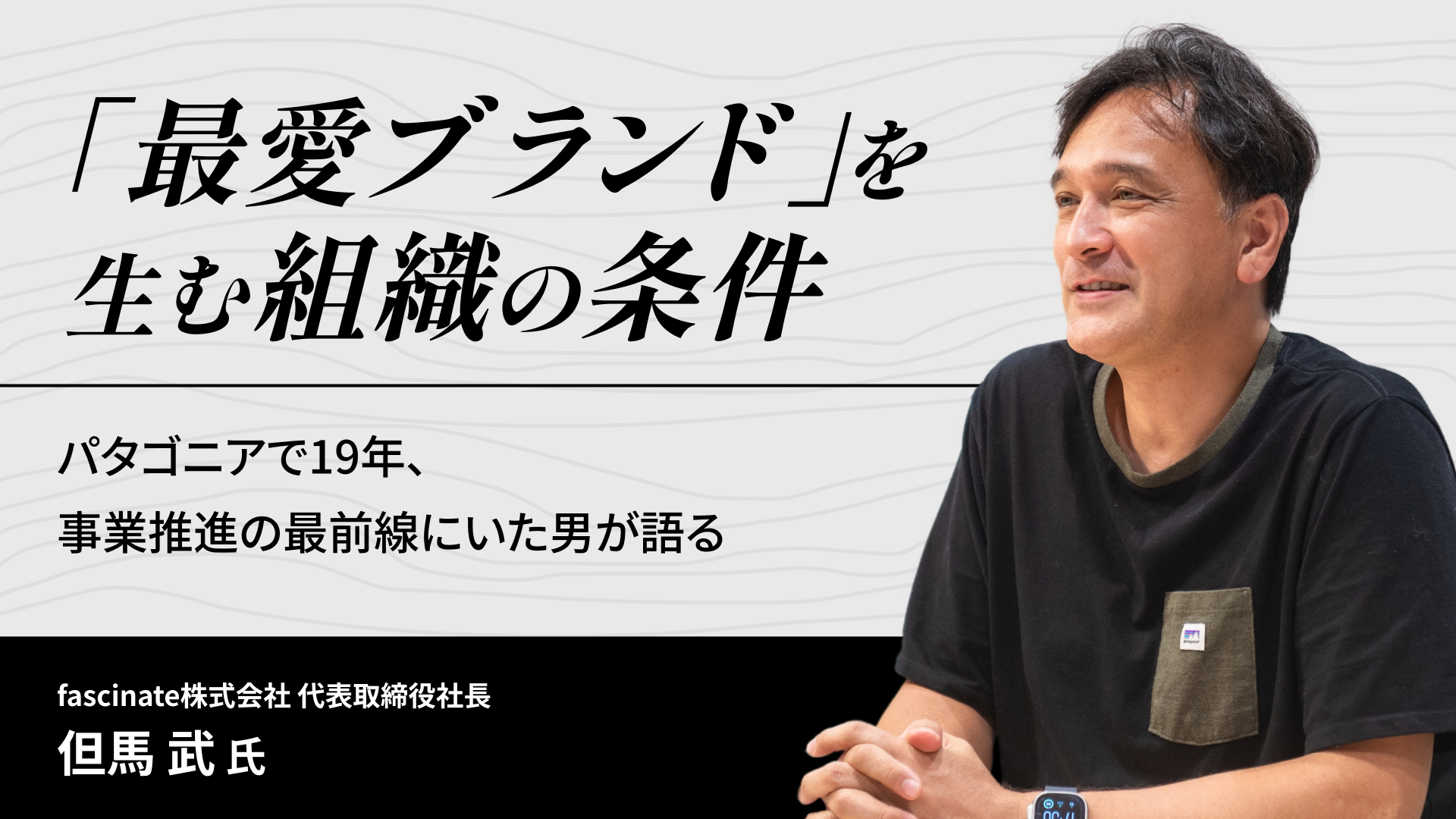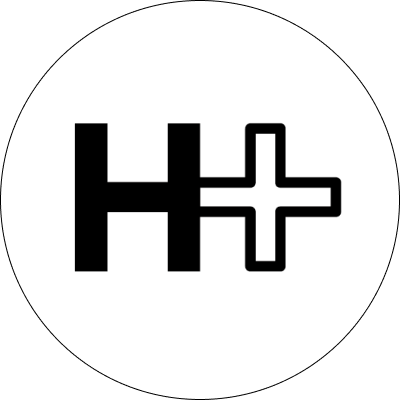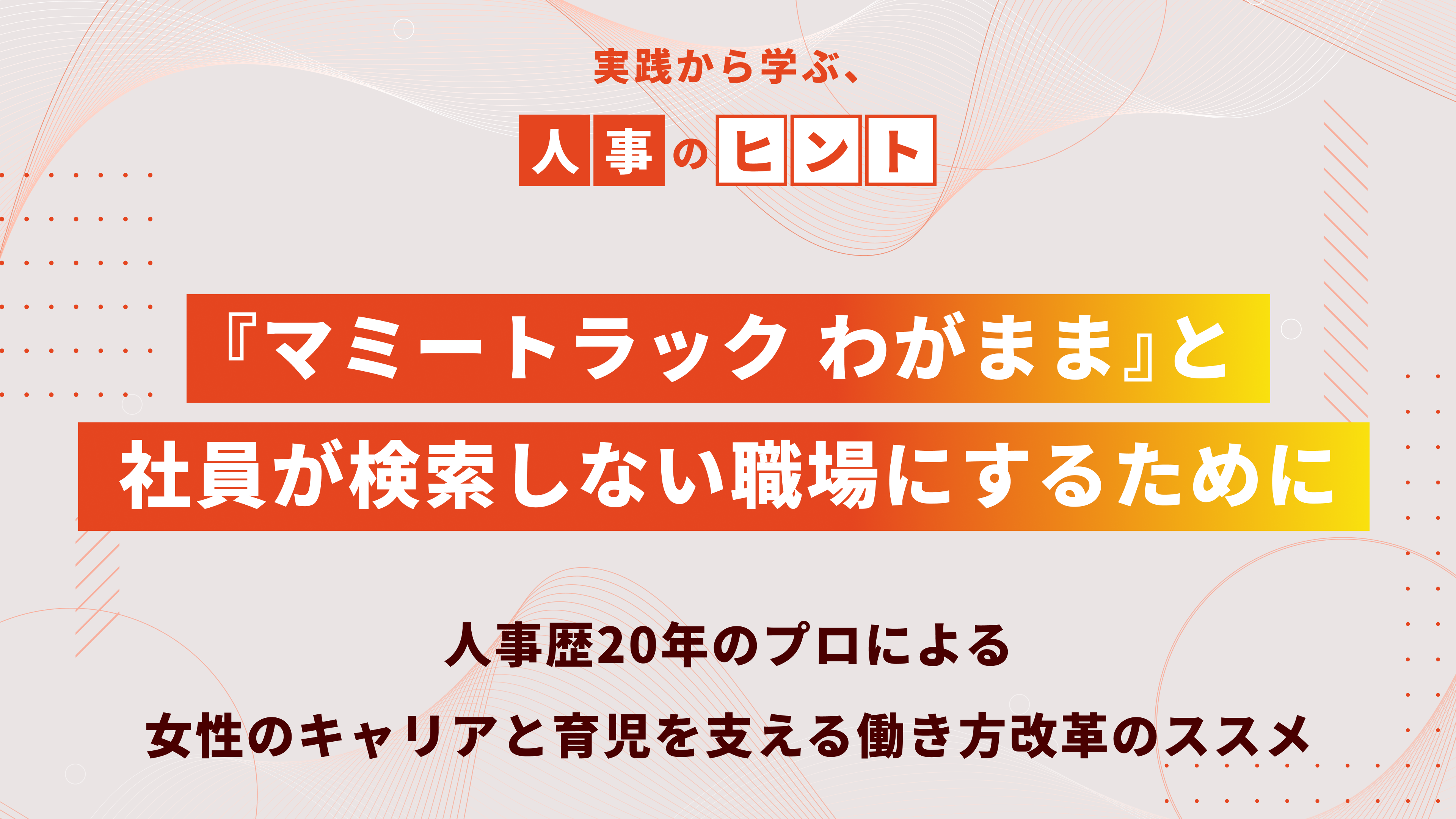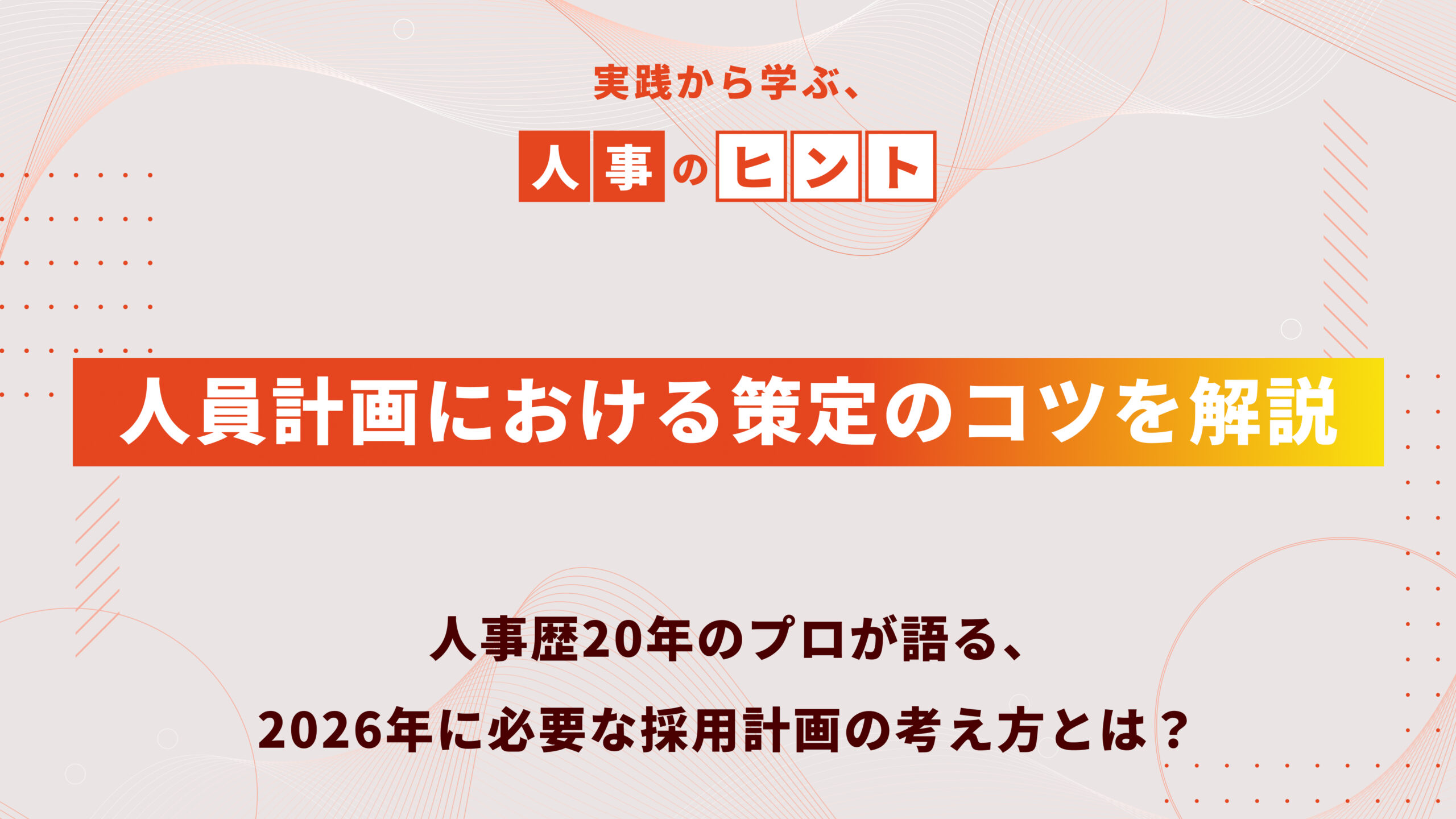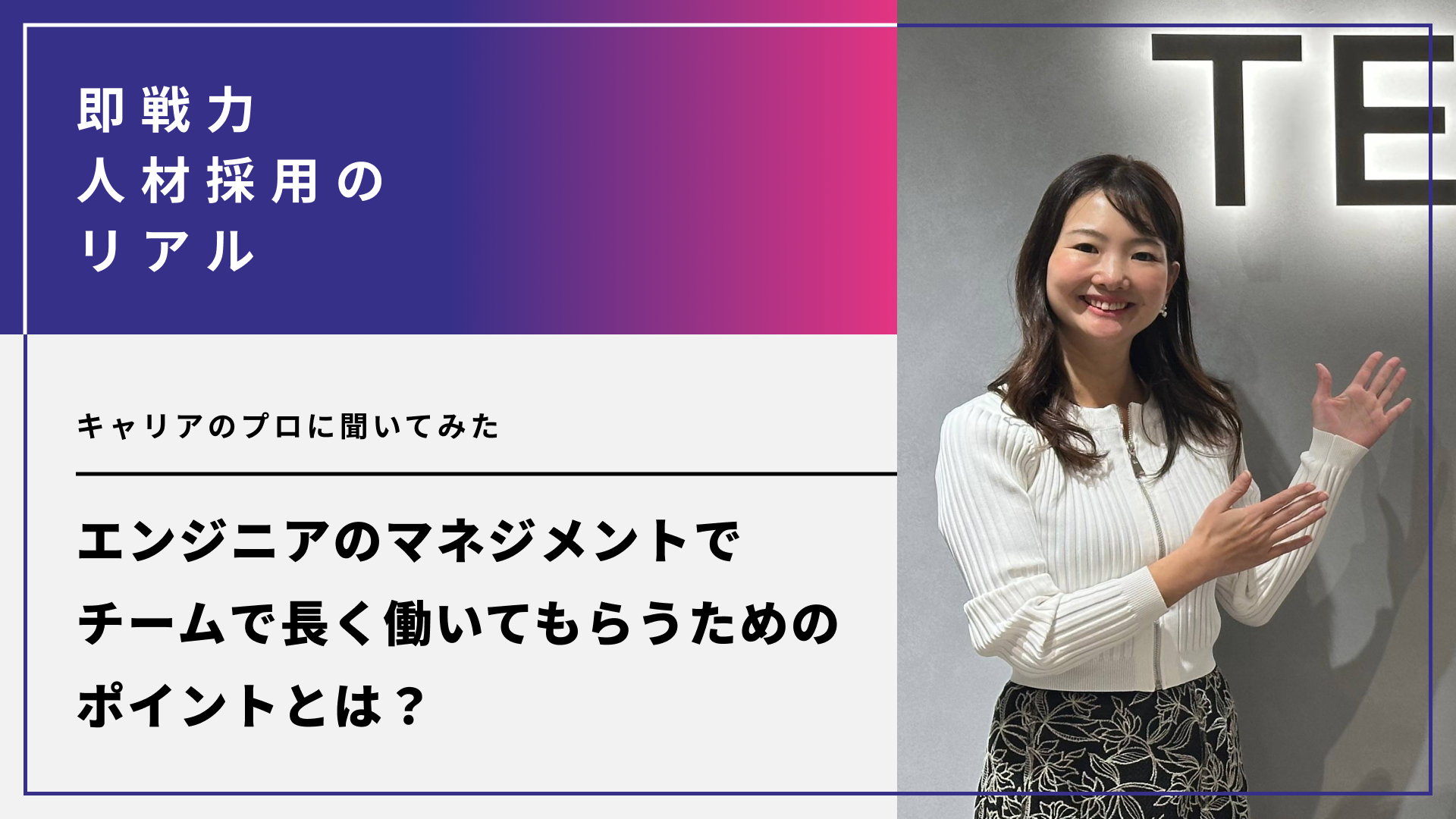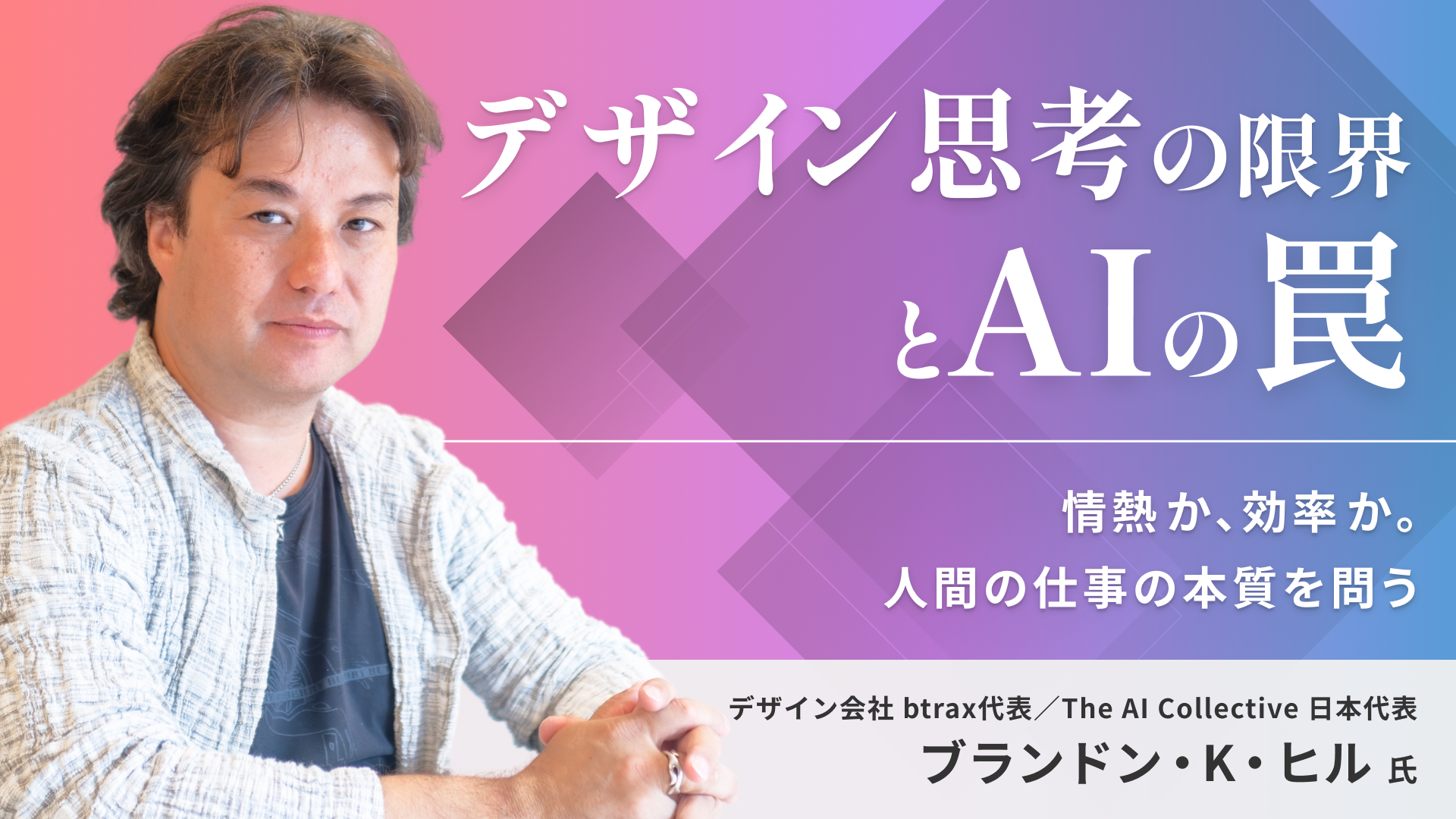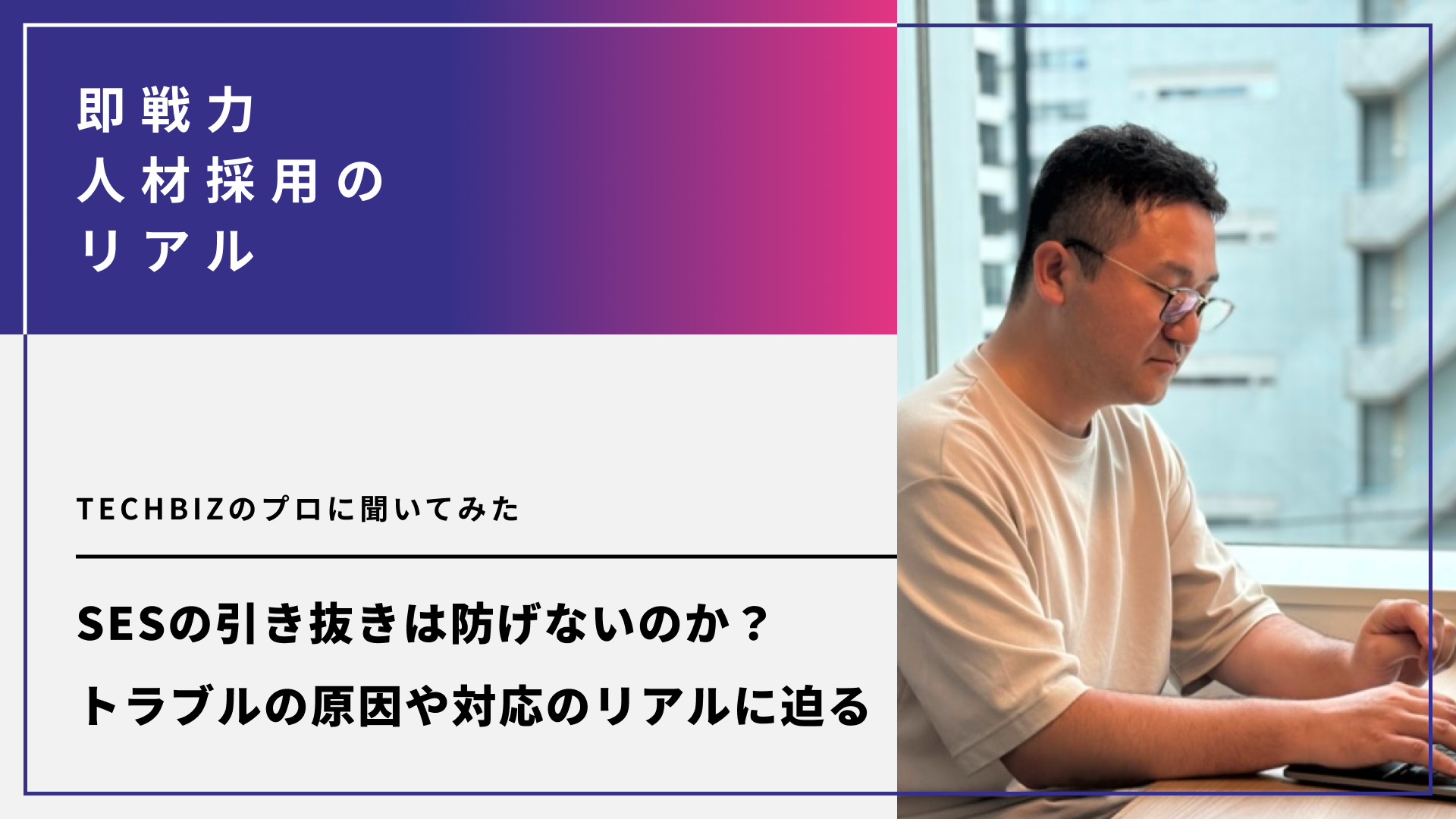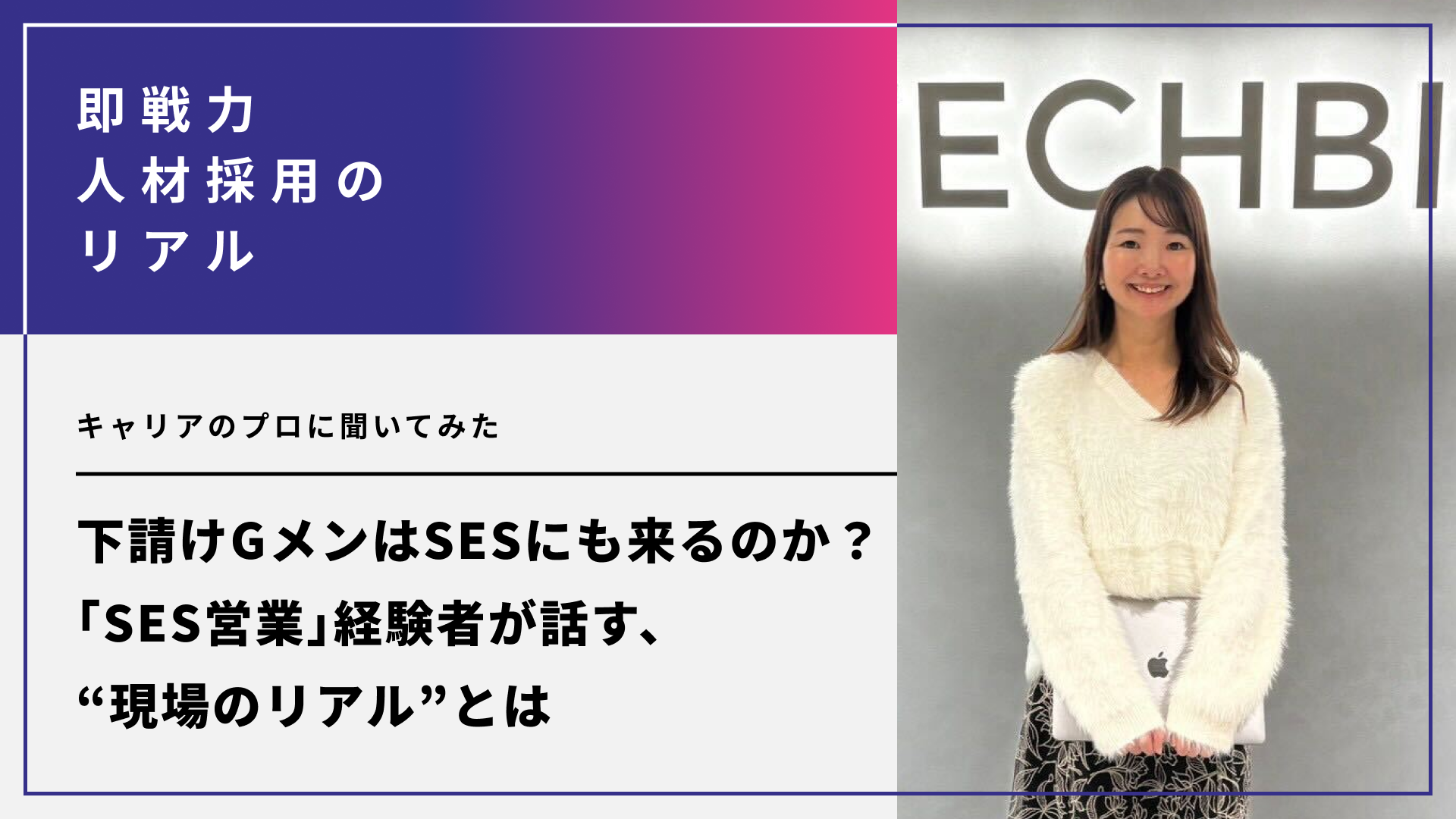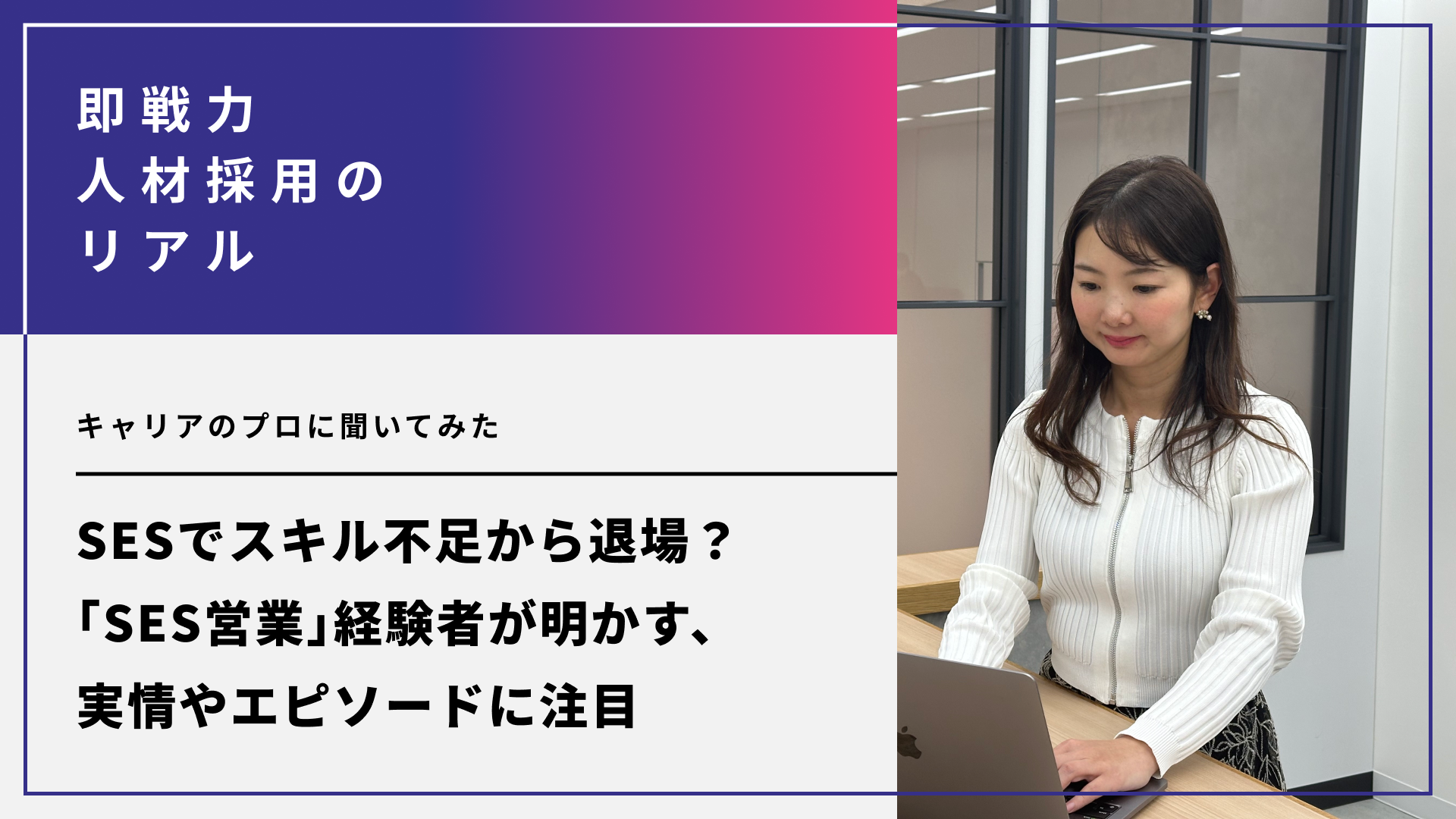fascinate株式会社代表・但馬武氏。パタゴニア日本支社で約19年間、eコマース事業の立ち上げから経営陣まで経験し、現在は「最愛ブランド戦略構築家」として組織開発から事業開発、ファンベースマーケティング構築支援に携わる。
「強さで頼られ、弱さで愛される」という独自のリーダーシップ観は、どのような原体験から生まれたのか。経営層・人事責任者に向けて、組織づくりの本質を語っていただいた。
但馬武氏プロフィール

パタゴニア日本支社にてダイレクトマーケティング部門統括を中心に19年勤務。2017年よりエーゼロ株式会社を経て、一般社団法人RELEASEに参画。2018年に愛される企業「LOVABLE COMPANY」のためのブランド戦略を構築するfascinate株式会社を創業。顧客及びスタッフエンゲージメントの観点から組織づくり、事業構想、マーケティング戦略づくりに伴走型で支援している。
ルーツと原体験 – 「違和感」が導いた道

――但馬さんの現在の活動は、パタゴニアでの経験が大きく影響していると伺っています。まず、そこに至るまでの原点からお聞かせいただけますか。
生まれは東京で、母がポルトガル人なんです。当時の日本は、いわゆるハーフである自分にとって少し生きにくい時代でした。幼少期から「外人だから」という理由で地元のお祭りに入れなかったり、見た目で判断されたりすることが日常的にあって。国籍は日本なのに、そういう経験を重ねていくと、日本社会の中でどう生きていったらいいのか、ずっと考え続けていましたね。
母はラテン系で非常に陽気な人で、「長いものに巻かれろ」を一切許さない。そういう母の下で育ったので、「個性を抑え、みんなで仲良く」という日本の行動様式とは常に葛藤していました。自分の意見を言えば孤立する。そんな経験を小中高と繰り返していたと思います。
――その環境が、現在の「本音で語る」というスタイルにつながっているのでしょうか。
そうかもしれません。ただ当時は、周りの目を気にしながら生きていたので、自分が本当に何をしたいのかに向き合えていなかったんです。大学になると個性を発揮できる瞬間も増えてきましたが、社会に出る時には「何をしたいのか」が見えなくて。ただ漠然と「人に必要とされたい」という思いだけがありました。
それで新卒では、当時で一番忙しそうな携帯電話会社に入社したんです。ちょうど携帯電話サービスがリリースされるタイミングだったのもあって決めました。ただ、最初から3年で辞めようと決めていました。社会を見るにはちょうどいいかなと思って。
――実際には2年9ヶ月で退職されたそうですね。その理由は?
命が燃えてない感じがしたんです。当時の携帯電話は今でいうAIのような熱い分野でした。でも自分の中では「所詮、携帯電話でしょう」という感覚があって。しかも典型的な日本企業で、ヒエラルキーも強くて「会社ってこういうものか」と心が折れました。
ちょうどその頃、父が脱サラして福島県猪苗代でコテージを始めたんです。実は父は、僕がサラリーマンの世界で生きていけない人間だと思って、逃げ場としてコテージを始めてくれたんですよ。実際自分は無理だなーと思ったこともあり退職届には「ピザ職人になる」と書いて辞めました(笑)。
――ピザ職人、ですか(笑)。
当時の上司たちは「他社への転職はともかく、ピザ職人って何だ? 大丈夫か?」と心配してましたね。でも僕の中ではもう「ピザ職人なんだ」と。今思えば、おかしくなっていたんでしょうね。
それで12月31日に福島に引っ越して、1月1日にコテージで目を覚ましたんです。その夜、雪が降る中で山の途中まで行って、森の中から下を見たときに、猛烈な虚無感に襲われました。「俺、単に逃げてきただけだな」「負けたんだな」って。
――その虚無感が、次のステップへのターニングポイントになったと。
そうです。「命を懸けて生きているのか」「持って生まれた意味は何なのか」と、真剣に考えました。幼少期から、時折そういう虚無感に陥ることはあったんですが、あの時が一番大きかった。そんな虚無感から抜け出すようにスキーばかりをしていました。そんな中、いまの妻と付き合い始め結婚したい!と思い4月には東京に戻りもう一度挑戦しようという気持ちが沸き起こってきたんです。
パタゴニアでの19年 – 組織と向き合い、学んだこと

――そこからどのようにパタゴニアとの出会いがあったのでしょうか。
3月下旬に東京に戻る準備をしているなか仕事を考えていたのですが漠然とアウトドア業界にいきたいなーとは思っていたんです。先輩から勧められて購入したパタゴニアのウェアを利用していました。まだまだ日本では目白と鎌倉にしかお店がなかったのですが、直感的に「パタゴニアで働くっていいかな」と。
当時はインターネットもほとんど普及していない時代です。それで福島から4月1日に東京に戻って、翌日に目白店に行ったら、ちょうど「コールセンタースタッフ募集」の求人が出ていたんです。すぐに履歴書を送りました。
――面接はどうでしたか。
スーツを着て行ったんですが、環境問題のことをすごく聞かれて。当時は環境問題について何も知らなかったので、正直戸惑いました(笑)。
それで家に帰ってからいそぎパタゴニア米国本社のウェブサイトを見てみたら「パタゴニアという会社は環境問題のことをやってるんだ」と分かって。その時、強く「俺はこの会社で何かやりたい」と思ったんです。
すぐに手紙を書き送ったのですが、何を書いたか全く覚えておりません。何かしたい!とだけ書いたんでしょうが当時日本支社の代表だった矢村さんという方がその情熱を買ってくれて無事採用されました。
――1997年、アルバイトからのスタートでしたね。
はい。5月1日からアルバイトとして通信販売部門のコールセンタースタッフとして働き始めて、たしか4ヶ月後に社員になりました。当時、部門は10人ちょっと、パタゴニア日本支社全体でも50人ぐらいの規模でした。
当時の日本支社はそれまでのメンバーによる経営から米国本社からのミッション「環境危機に警鐘を鳴らし、解決に向けて実行する」を実現するんだという方針のもと、組織の大きな変革の始まりのタイミングで、良い意味で自由、悪い意味で混沌としていました。
――その状況をどう打開されたのですか。
個人的に動きながらもモヤモヤしていたなかで米国本社が新しい日本支社長を決めたのが1998年。ジョン・ムーアが着任早々時間をもらってこうしたほうがいい、ああしたほうがいいと提案したのですが、「分かった。お前がやれ」と。
当時まだ27歳ぐらいで社員になってから1年経過していない時期でしたが若かったですし、見様見真似で取り組みました。若かった頃にはほんと多くの方々に御迷惑をおかけしてしまい申し訳なく思います。
――その後、ビル・ワーリン氏が日本社長として着任されます。
ジョンは2年ほどいてその後新しい日本支社長が着任します。ビルは米国アウトドア業界の重鎮で、実質的にノースフェースを大きくした人物でした。彼の下で10年ぐらい働いて、グローバルでの仕事の進め方を本当に学びました。
最初の3年間は大変でしたよ。あまりにも僕のスキルが低すぎて英語も出来ないし力不足と判断されていましたのでアタリが強かったです(笑)。やりたいことを実現するにもまずはスキルと経験だと必死に食らいついていきました。チームをまとめる力や数字を読む力、ビジネスを構築する力には自信がありました。
いよいよ厳しいぞと思ったときに認められたのは、本社側のバイスプレジデントでした。真摯に取り組んでいれば誰かが見てくれていると。
――それがターニングポイントになったと。
既に日本支社の経営陣には入っていたのですが、ビルのもとでマネジメントについて多くのことを学ぶことができました。上司には恵まれ続けたと思います。、通信販売部門でもeコマース事業も立ち上げて売上は毎年伸び続け最終的には僕が入った時と比べて、部署の規模は15倍ぐらいになりました。
――一方で、葛藤もあったそうですね。
そうですね。38歳くらいまではビジネスとアウトドアスポーツ、そして環境問題と取り組み続け自分のなかでの成果というか実感を積み重ねていきました。その中で感じたのはまたいつも通り「自分の命が喜ぶ取り組みをできているか?」という問いでした。
アウトドア・スポーツも楽しいしビジネスもそう。ただ環境問題については知れば知るほどその根深さをしり、パタゴニアを通じて変革をしていけるんだ!という確信はあったものの実感できるほどには変化もなく、ずっとモヤモヤとしていました。
米国では民主主義が浸透していることもあって、正しさによっての社会変革がパワーあるのですが、日本ではそれよりかは「楽しさ」で巻き込んでいくことが大事なんだということに気づいたんです。
――その経験が、現在の活動にどうつながっていますか。
メンバーも60名を超えて自分の力の限界も感じ、沢山のご迷惑をかけ、挫折を感じたなかで、「自分が本当に取り組みたいのはイノベーションを起こしていく必要があるにもかかわらず、他者に遠慮して個性を発揮できない企業のありかたなんだ」と気付き、2014年からパタゴニアで働きながら他社へのコンサルティングを始め2016年にパタゴニアを退職。その後岡山県西粟倉にあるエーゼロを経験したあとに2018年から愛される企業を増やしていくというfascinateを創業しています。
最愛ブランド戦略とは – 強さで必要とされ弱さで愛される

――現在の「最愛ブランド戦略」という考え方について、詳しく教えてください。
企業がとる戦略にはいくつも選択肢があります。最高な製品をつくったり最低価格で勝負したり最速で届けたり。そのなかで最も愛されることを考える戦略があるんじゃないかと。まさにパタゴニアがそうですよね。
顧客から愛されるためにはそこで働くスタッフも同様です。なので、愛される形も様々なのでその企業のコンディションに合わせて数年かけて「最愛ブランド」になっていくプロセスをデザインし伴走します。それは組織開発であり事業開発でもあるんです。
最初の取り組みはやっぱり組織内の関係性に着目して取り組むことが多いなあと思います。企業理念をみなで考えたり話しやすい関係性を社内でつくっていったりしていきます。
――「強さで必要とされ、弱さで愛される」というお話もされています。これはどういう意味でしょうか。
そもそもはロバート・キーガンの著書「なぜ弱さをみせあえる組織は強いのか」にあるのですが、簡単にまとめると人は弱さを弱点として捉えて他者にはみせないようにします。
でも実際はどうでしょうか?ひとの不完全な要素をみたときに私達は手を差し伸べ一緒に考えようとするんです。世界は複雑でひとりの創造力や努力で変えることができるわけではありません。他者との協力関係があって創発がうまれます。
ここで難しいのは弱さを認め他者に開示するという勇気を持つことなんです。
――組織では、弱さを見せることを避ける傾向がありますよね。
そうなんです。これは日本のみならず海外でもある傾向だと思いますが、特に儒教の影響が強い日本では「リーダーは強くあるべき」「先輩は答えを持っているべき」というような思い込みが強くあります。しかし、実際には弱さをみとめ開示しそれを得意と感じている他者の能力を借りて創発を起こしていくことが組織の発展につながり事業にもつながっていくんです。
僕自身、パタゴニア時代に学んだのは、完璧なリーダーなんていないということです。自分自身もその弱さを認めることができず大変苦労し大きな失敗を何度も繰り返してきました。。
大事なのは、議論でもなく対話です。それは他者との対話もそうですが、自分自身との対話を進めていくこと。そして本音で他者と語らいつながり、その会社の目的も考えながら常に変化進化する姿勢をもつことです。そういう姿勢がチームを強くします。
――実際の伴走では、どのようにアプローチされるのですか。
まずは企業理念の理解を深め組織づくりを行っていくことから始めます。そこからその深められた事業の目的に沿って今後の事業展開を考え、ファンベースマーケティング戦略を構築していく流れです。
具体的には私はプロセスをデザインしファシリテーターとして一緒に関わりながら変革をすすめていきます。プロジェクトチームをつくり定期的なミーティングを通して理解を進め、定期的に全社への発信を実施。
そのプロセスを通じて徐々に本音で話せるような関係性をつくっていくんです。
大事なのは組織のなかだけの内向きな視点なのではなく、社外つまり顧客やステークホルダーからの視点もいれながら進めていくことです。ひとは弱さを内包していますが、その根っこにはものすごくエネルギーがありそれを引き出すことができると想像を超える発想やエネルギーがうまれてくるんです。
それには自分を信頼し仲間を信頼し、未来をつくれるんだという効力感がとっても効果的だと思っています。
――その結果、組織はどう変わっていくのでしょうか。
パタゴニアはフレデリック・ラルーが書いたTeal組織にも取り上げられているのですが、自分がやりたいことがあり、そして仲間を信頼して挑戦を続ける。そうすることで驚くような事業がうまれ熱狂的なファンがささえてくれる。
その目的に対して自律的に動ける組織になっていくので、メンバー一人ひとりが主体性を持つようになります。「言われたことをやる」のではなく、「自分で考えて動く」ようになる。
そして、組織全体の創造性が上がります。本音で語り合えるから、新しいアイデアが生まれやすくなる。失敗を恐れずにチャレンジできるようになる。
最終的には、その組織や企業が、顧客からも、メンバーからも社会からも「愛される」存在になっていきます。
これからの働き方

――人口減少やAIの台頭など、働き方の大きな変化が起きています。但馬さんは、これからの「働くこと」をどう捉えていますか。
日本は戦後荒廃した国土を先人たちの努力によってとっても豊かな国になってきました。一定の豊かさを享受できているいま、次の豊かさをつくっていくのは私達の責務だと思っています。
AIが発達すればするほど、人間らしさが問われる時代になると思います。AIにできることはAIに任せて、人間は人間にしかできないことをやる。
じゃあ、人間にしかできないこととは何か。それは「夢をえがくこと」「他者とつながること」だと思うんです。そのベースとなる信頼関係を構築すること、そしてそれが共感、協働へとつながっていく。そうして想像を超えていく。こういったことは、AIには代替できません。
――経営者や人事責任者に、何かメッセージはありますか。
時代をみると常に世界は変化していますしその変化にあらがうのではなく変化を起こしていく側になることが楽しいと思うんです。人類がいままさに活用しきれていない資源の最大のひとつは人が持つ創造力だと思っています。
その創造力を解放する組織のありかたこそが愛される企業で得られる効果効能だと信じているんです。世界にはそのような組織があり、それらを真似ることから始めてもいいのでぜひ一歩変化を起こしていく側に踏み出してくださるとうれしいなと思います。
リーダーシップとは何もジャンヌ・ダルクのように私のあとについてこい!という姿のことではなく、自分の境界線を超えていく勇気のこと。「強さで頼られ、弱さで愛される」。このバランスを取れるリーダーが、これからの時代を作っていくと思います。
――最後に、今後のビジョンを教えてください。
fascinateを創業して8年が経過してやっとどうやったらパタゴニアのような企業がうまれ進化していくのかのステップを解明できたという確信を持っていえるようになりました。
この知識とか経験はまさにこれまでの先人たちの探究や知識経験をベースにしていますのでまさに「巨人の肩にのって」ここまでこれたように思います。
なので、自分自身もこの経験を多くのひとに届けていくのがこれからの役割です。
具体的には、関わる企業も増やしていきたいですしそのようにできるひとも増やしていきたいと考えています。
欲しい未来のつくりかたは様々な手法がありますが、仲間をつくり事業を進めファンとともに未来をつくる、そんな愛される企業が1社でも多く増えていくことにとりくんでいきたいなと思います。
編集後記
インタビューを通じて印象的だったのは、但馬氏の一貫した姿勢です。ハーフとして日本社会で感じた違和感、パタゴニアでの葛藤、そして現在の活動。すべてに共通するのは、「本音で語り合える関係性」への強いこだわりです。
「弱さで愛される」というメッセージは、一見すると逆説的に聞こえるかもしれません。しかし、現代の組織が直面する多くの課題——心理的安全性の欠如、イノベーションの停滞、メンバーのエンゲージメント低下——は、まさにリーダーが「強さ」だけを求められ、「弱さ」を見せられないことから生じているのではないでしょうか。
但馬氏の言葉は、経営者や人事責任者に、組織づくりの本質を問い直すきっかけを与えてくれます。完璧なリーダーを目指すのではなく、人間らしいリーダーであること。それこそが、これからの時代に求められているのかもしれません。
即戦力人材の採用にお困りではありませんか?ハイスキルなフリーランス人材をスムーズに採用できる【テックビズ】
テックビズでは「ITエンジニア」「人事HR」「経理ファイナンス」領域にて優秀なフリーランス人材をご紹介しています。スキルのみならず人柄も踏まえ、企業様にマッチした人材を、最短で即日ご紹介できます。即戦力人材の採用にお困りの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。