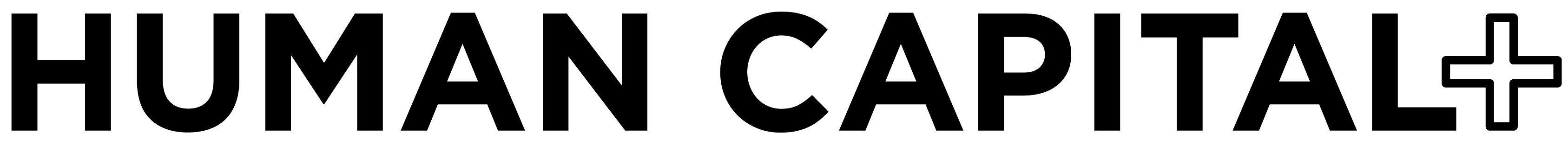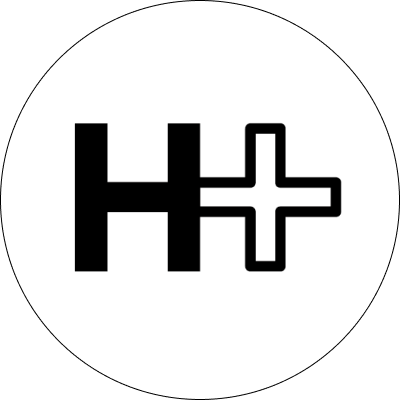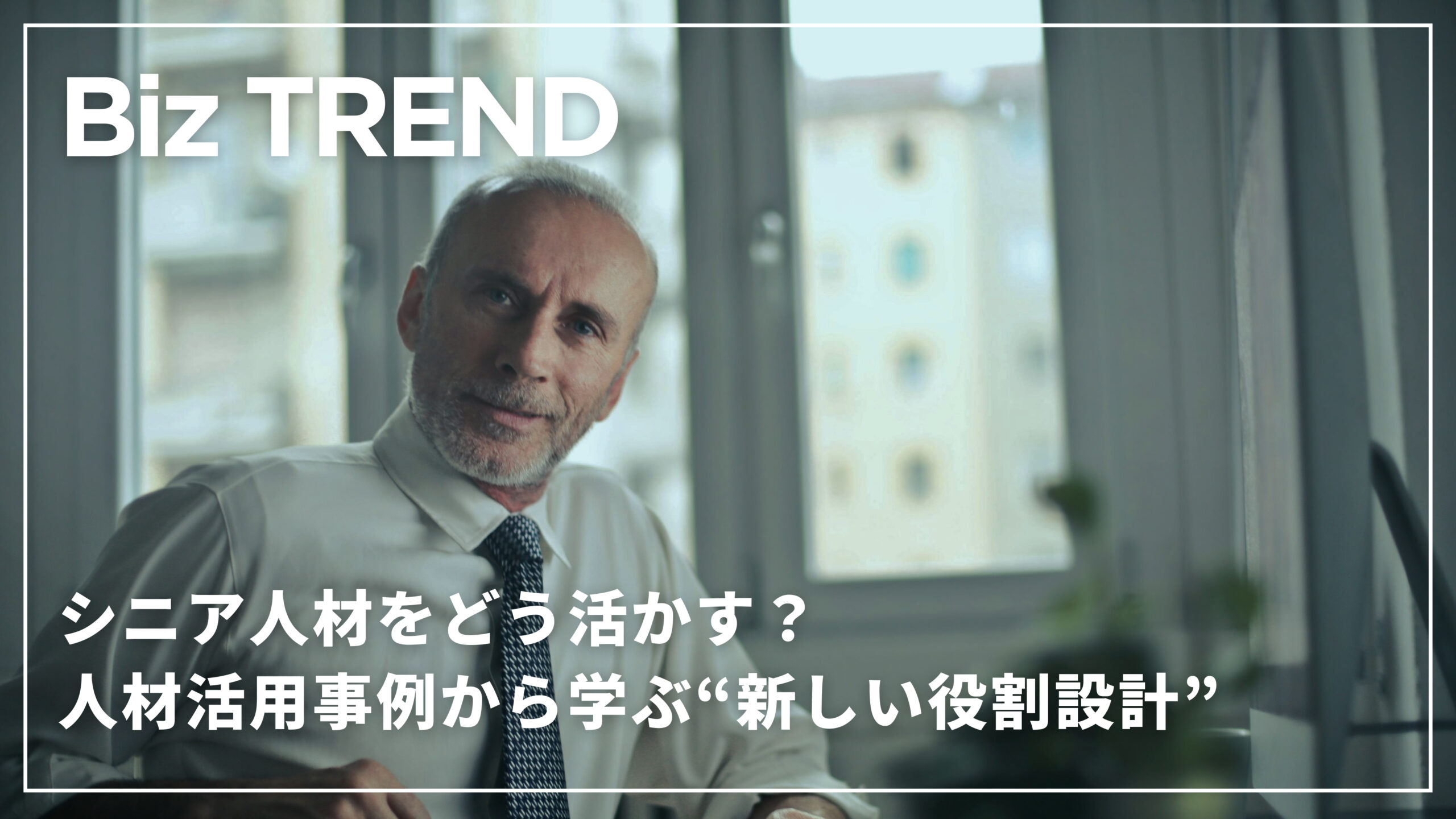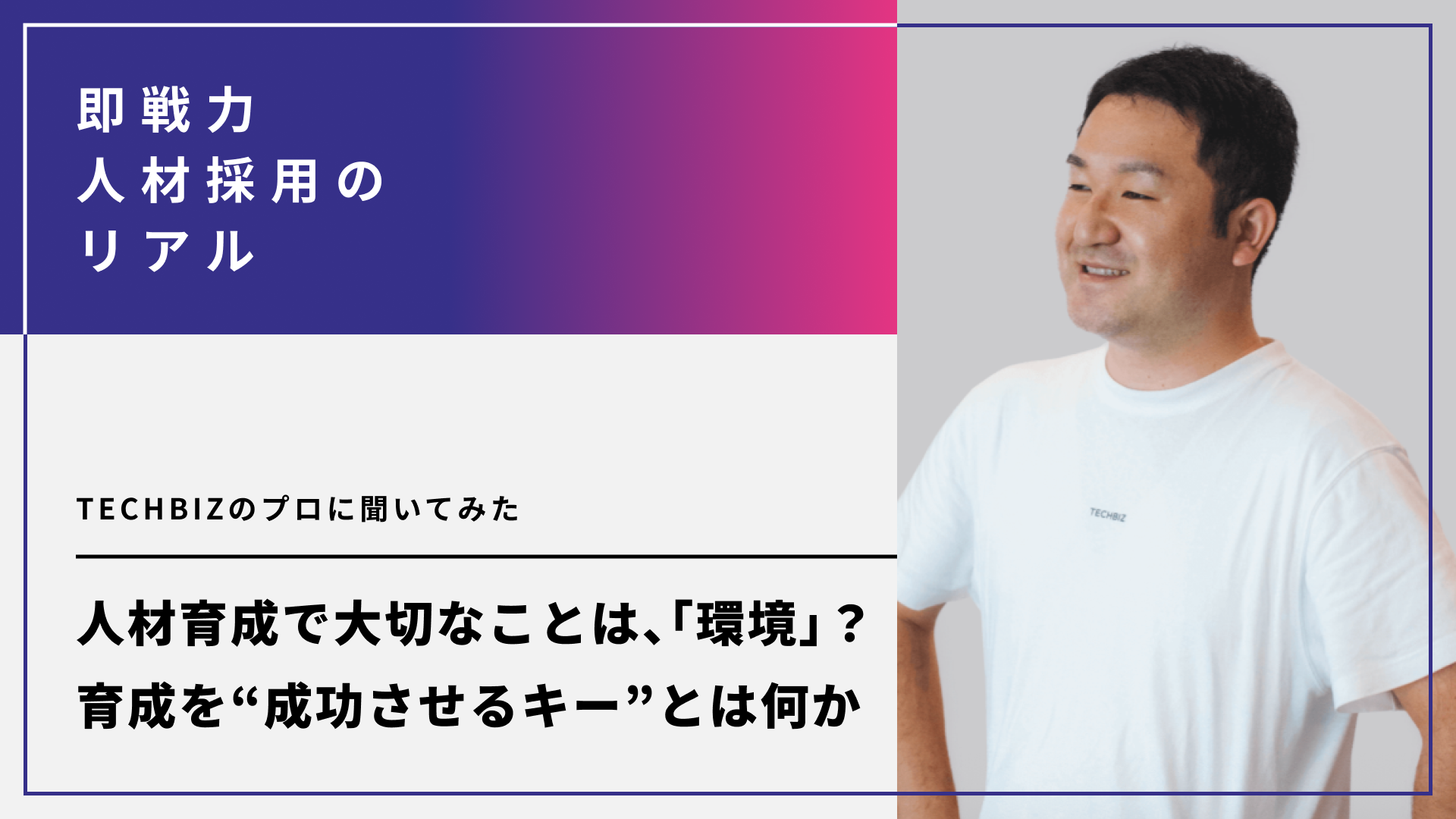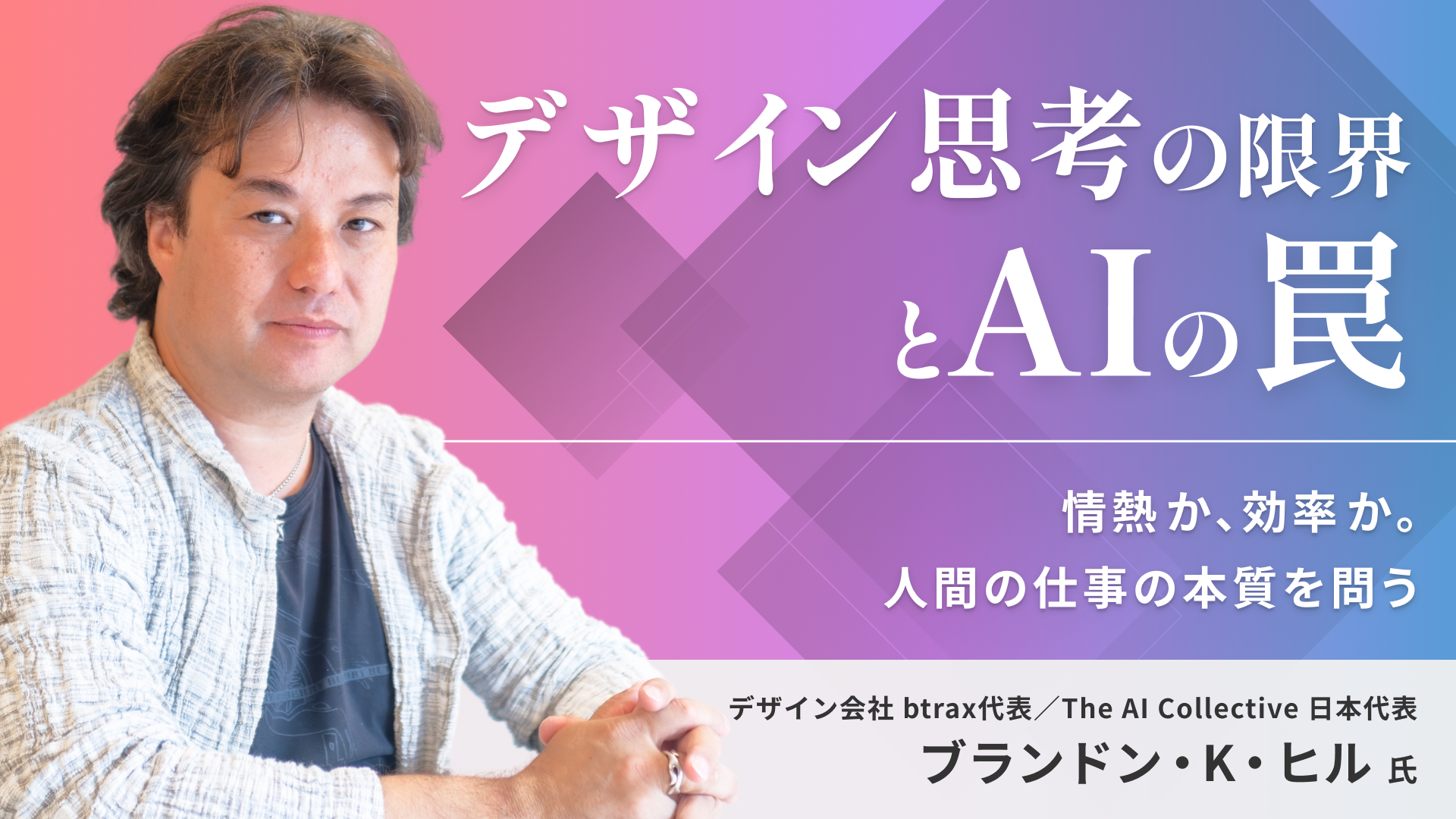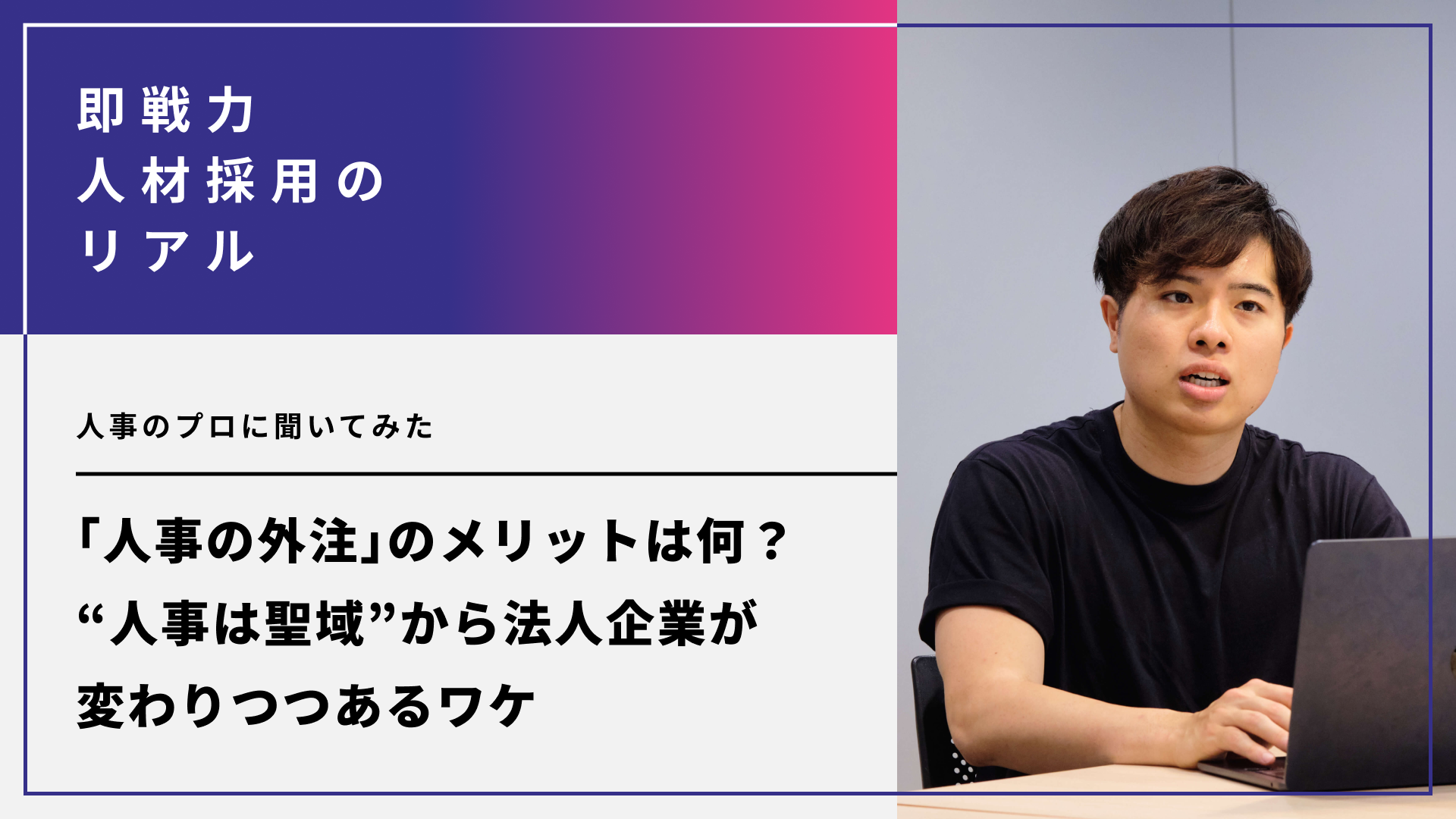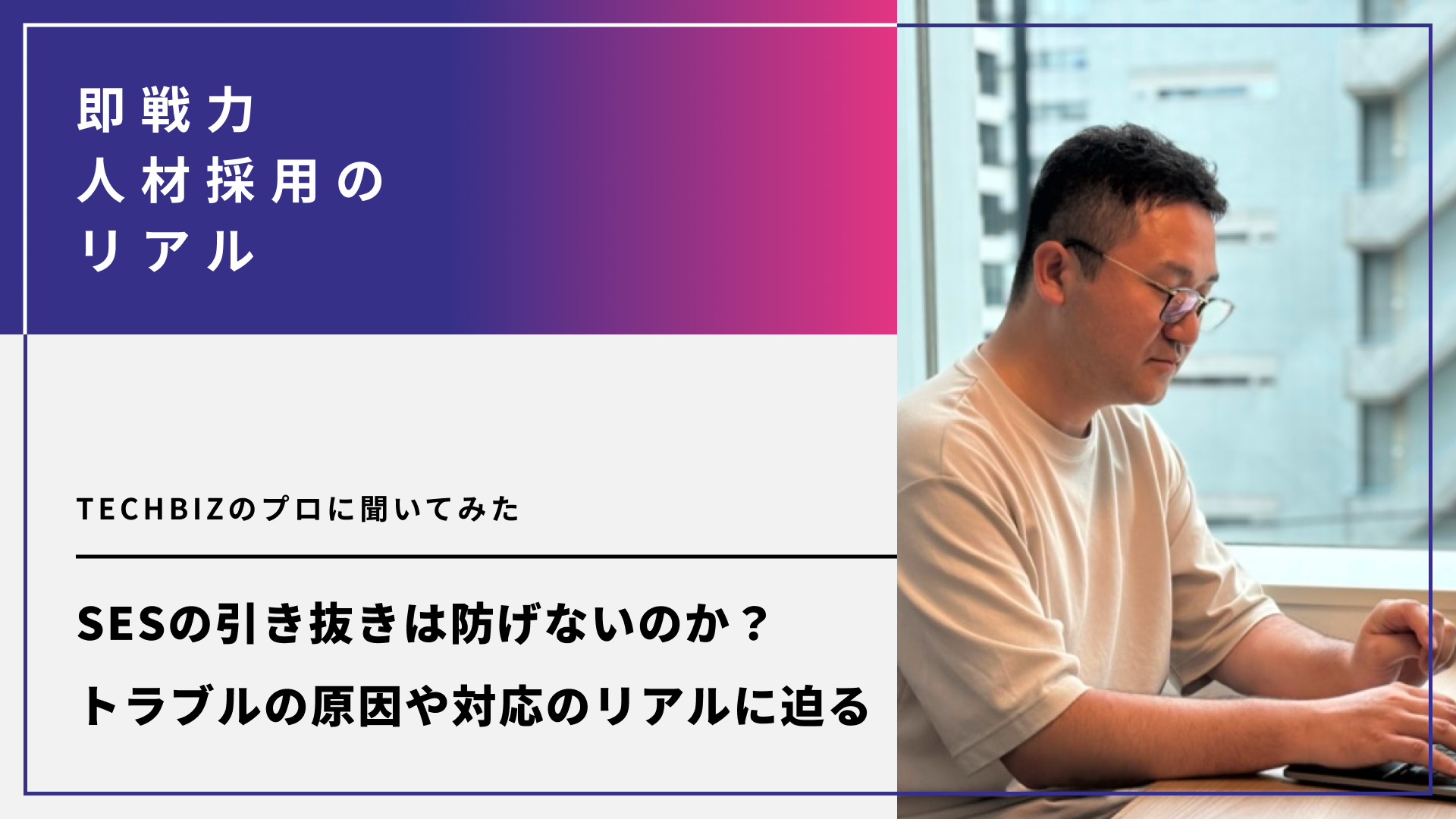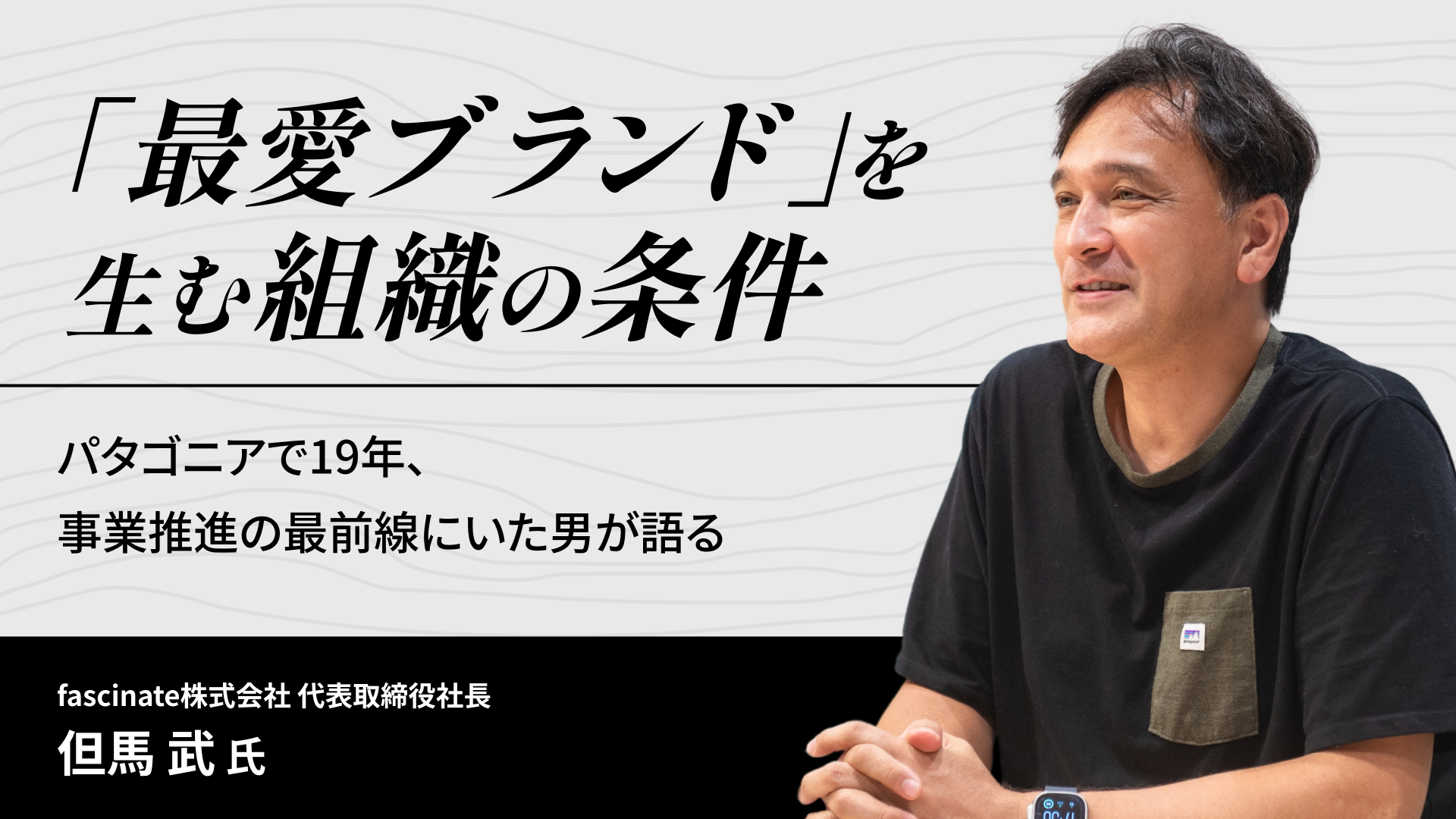エンジニア採用の遅れは人事課題ではなく経営課題。DX・内製化の波があらゆる産業に広がる中、エンジニア不足が事業成長のブレーキとなり、採用の遅れが経営課題として顕在化しています。一方で、採用市場は圧倒的な売り手市場。転職・独立が当たり前の時代に、企業の採用力が試されています。本記事では、「採用の外注」を経営の武器に変えるための実践的な視点と、成果を最大化するパートナー選定のポイントを解説します。
エンジニア採用にお困りならHRBIZのプロ人事と解決
上流から下流まで、実績豊富なプロ人事がサポート。【無料】お問い合わせはこちら
エンジニア採用の遅れは「人事課題」ではなく「経営課題」
近年、「IT業務の外部委託をやめて内製化へ」という潮流が加速しています。
しかしエンジニア採用は圧倒的な売り手市場。IT部門の内製化を進めたくても、採用が追いつかない・採用できても早期離脱してしまう、といった問題が、様々な企業で顕在化しています。
これらは単なる人事部の課題ではありません。
事業計画や組織開発そのものが遅延し、新規サービスリリース・開発リードタイム・競合優位性に直結します。特にスタートアップや新規事業部では、1人のエンジニアが事業KPIを左右するケースも珍しくありません。
経営戦略において「採用計画=実行計画」であり、採用の遅れは経営の停滞を意味します。
内製の限界|エンジニア採用が難しい3つの理由
1. 人事がエンジニアリングを理解しきれない
人事担当者の多くは、エンジニアリングそのものを日常的に扱うわけではないため、技術トレンドや採用マーケットの変化に追いつくのが難しいのが現実です。
新しいプログラミング言語やクラウド技術が次々と登場し、スキルセットの定義が常に変化する中で、人事が単独で最適な採用要件を設計するのは非常に難しいといえます。
こうした知識のギャップを埋めないまま採用活動を続けると、候補者との温度差が広がり、ミスマッチや辞退が増えます。結果的に採用スピードが落ち、採用コストだけが増えていく構造が生まれてしまいます。
候補者からの質問に答えられない、面接官によって評価軸がバラバラ、技術課題や開発環境の説明が曖昧──こうした“粗さ”は、優秀なエンジニアほど敏感に察知します。
2. IT人材の転職・独立志向の高さ
もう一つの難しさは、IT業界は人材が流動的で、転職や独立を前向きに考えている人材が多い、という点です。
採用に成功しても、給与水準や評価制度、スキルアップ機会に不満を持つと、早期離脱してしまうケースも少なくありません。また、フリーランスとして複数企業と関わる働き方が一般化しつつあることで、ひとつの会社に長くいるという前提そのものが崩れつつあるのが現状です。
その結果、採用活動が「採る」だけでは完結せず、どうつなぎとめるかがより重要なテーマとなっています。
特にエンジニアの場合、「どのような技術に触れられるか」「誰と働けるか」「プロダクトの影響力」など、モチベーションの源泉が多層的です。
人事だけでこの複雑な期待値を満たすのは難しく、採用後の定着・成長支援を含めた「長期的な関係構築」が求められます。
3. 大手や有名ベンチャーに人材が流れてしまう
ブランド力、報酬水準、福利厚生、開発環境など、大企業や話題のスタートアップには圧倒的なアドバンテージがあります。
彼らは大型プロジェクトに携わる機会・最新技術に触れられる環境を提示でき、採用マーケットでの魅力の総量が根本的に違います。
一方で、知名度の低い企業がその差を条件面で埋めようとするのは現実的ではなく、待遇やブランドでは勝負にならない土俵で戦っている現状があります。
この採用格差に直面しながらも、具体的な打開策を持てずにいる、という企業が多いのではないでしょうか。
「採用の外注」という選択肢が、経営の武器になる理由
先述したとおり、エンジニア採用を取り巻く環境は、社内人事の努力だけでは限界が見え始めています。
こうした中で、「採用の外注」=プロへの業務委託・採用代行(RPO)という選択肢が、改めて注目を集めています。
しかし現実には、「既存業務を他の人に任せる」という発想で止まっているケースが多いのが実情です。
スカウト送信や面談調整といった作業をアウトソースしても、根本的な採用課題、つまり『なぜ採用が進まないのか』という戦略的問題には手が届いていません。
採用の外注を経営の武器に変えるためには、単なる委託ではなく、戦略と知見を併せ持つパートナーを選ぶことが不可欠です。この前提を踏まえた上で、ここでは「”正しい”採用の外注がなぜ経営の武器になるのか」を解説します。

1. 客観視による根本的な改善
外部パートナーの最大の価値は、採用活動を客観的に見直す視点を持ち込めることです。
社内チームだけでは気づきにくい「前提のズレ」「非効率な慣習」「競合から遅れをとっている制度や施策」などを、第三者の立場から分析・是正できます。
たとえば、採用要件の粒度が曖昧・業務内容に対する報酬が市場と合っていない・評価制度が古い、など。これらの課題は、客観的視点がないと、社内では問題として認識されにくいのです。
外部パートナーは、他社事例や市場データを踏まえてプロセスを俯瞰することができ、「なぜ採れないのか」を構造的に可視化する役割を果たします。
2. 専門知見とスピードを同時に得られる
近年の人事部は業務量が多く、採用に避けるリソースが足りない上、エンジニアリングを取り巻く環境について学習し続けることは現実的に困難です。
その点、エンジニア採用を専門とする外部パートナーは、最新の市場動向・報酬相場・技術職の転職行動に常に接しており、実践知が豊富です。
母集団形成やスカウト戦略だけでなく、「どのようなメッセージが刺さるのか」「どんな要件で応募が増えるのか」を即座に提案できます。
つまり、外注=プロの知見を成果として取り込む手段、と捉えましょう。社内にゼロからノウハウを蓄積するよりもはるかに早く、精度の高いエンジニア採用を実現できます。
3. 経営リソースを「採用運用」から「採用戦略」へシフトできる
外注によって採用実務を手放すことで、経営層や人事責任者は“本来の仕事”に集中できます。
限られた社内リソースを、スカウトや候補者対応といったオペレーションではなく、組織設計・人材ポートフォリオ・報酬戦略などの上流領域に再配分できるのです。
これは単なる時間の節約ではなく、「外部パートナーが運用を担うことで、採用を経営レベルの意思決定に引き上げる」ための“構造転換”です。
成果を最大化する採用のパートナー|選定する際の4つのTo-Do
エンジニア採用は、一般的な採用代行のテンプレートでは機能しません。オペレーション業務の丸投げだけでは、根本的な課題「なぜ採れないのか」「なぜ離職するのか」を解決できないからです。
成果を最大化するためには、エンジニア採用の知見を持ち、人事・経営戦略と現場の両方を理解したパートナーを選ぶ必要があります。
ここでは4つの視点に分けて、外部パートナーを選定する際のコツをお伝えします。

1. 「安さ」や「実績数」ではなく、“エンジニア採用特化”で選ぶ
複数のパートナーを比較検討する際、多くの企業が「価格」と「導入実績数」だけで選定しがちです。しかし、エンジニア採用においてはこの2つだけでは成果は測れません。
なぜならエンジニア採用は、一般職のように“数を集めて選ぶ”モデルではなく、個々のスキル・志向・価値観のマッチング精度が最も重要になります。
たとえば、営業職の採用に強いRPOが、同じ手法でエンジニアを採用しようとしても、技術的な文脈を理解できません。その結果、「技術がわかっていない企業」と見なされ、候補者からネガティブな印象を持たれるリスクがあります。
したがって、「エンジニア採用の専門知識を持つ人事コンサルタントが在籍しているか」を確認することが、最初の重要なチェックポイントです。
2. 単純業務の代行ではなく、上流戦略から共に見直せるかをチェックする
採用業務の一部を外注しても成果が出ない最大の理由は、戦略レイヤーが抜け落ちていることにあります。本来、成果を出す採用業務の委託とは、単なる“作業の代行”ではなく、
- 採用要件や人材ポートフォリオの整理
- 現場・経営層を巻き込んだ戦略設計
- 候補者体験(CX)やアトラクト設計の改善
までを包括的に支援できるパートナーです。つまり、「手を動かす人」ではなく、「思考を共にする人」を選ぶことが大切。
エンジニア採用に強いパートナーであれば、スカウト文面一つをとっても、技術・市場・候補者心理に基づいた提案ができるはずです。ここに踏み込めるかどうかが、“長期的に成果を出すパートナー”と“作業代行”の分岐点です。
3. 社内の情報を「数字」「プロセス」「制度」レベルで共有できる状態にする
どれだけ優れたパートナーを選んでも、社内の情報がブラックボックスのままでは成功しません。
特にエンジニア採用では、採用要件・報酬設計・評価制度・開発体制など、情報の非対称性が多く、外部から見えにくい構造になっています。
外注を効果的に機能させるためには、まず社内の現状を整理し、
- 各フェーズのKPI(応募・通過・内定・定着など)
- 採用フローとボトルネック
- 報酬・評価制度・育成方針
を共有できる状態をつくることが前提です。
採用代行を“正しく使いこなす”ためには、まず自社の採用活動をデータで可視化し、共通言語で議論できる環境を整えることが必要です。
4. “発注”ではなく“共創”のマインドを持つ
外部パートナーへの委託で成功率を左右する最後の要素は、企業側のスタンスです。
「採用業務を任せたら終わり」という発注思考ではなく、「一緒に採用を作る」という共創マインドが重要になります。
特にエンジニア採用では、事業フェーズやプロダクト開発状況によって必要な人材像が常に変化します。その変化に対応するには、パートナーと継続的に情報を交換し、施策を“共に改善していく”関係が欠かせません。
採用を単にアウトソースするのではなく、採用力そのものを共に育てる。これが真に成果を出すパートナーシップの形です。
まとめ|エンジニア採用の外注、選ぶべきは“知見と実績のある伴走者”

エンジニア採用の外注を、経営レベルの施策として機能させるには、「知見×実績×伴走力」を兼ね備えたパートナー選びが重要です。
エンジニア採用特有の課題を理解し、現場目線で改善策を設計できるか。
客観的に課題の根本原因を発見し、経営層とも対話できるか。
そして、単発ではなく中長期で“採用体制を強くする”視点を持っているか。
採用を外に任せるということは、経営の中枢機能の一部を共同運営するということです。だからこそ外部の知見を活かし、自社の強み・弱みを再定義しながら、「どうすれば優秀なエンジニアが集まり、活躍し、定着するのか」を戦略的に考えることが大切です。
- 母集団形成が思うようにいかない
- スキルの見極めに自信が持てない
- 採用してもすぐに離職してしまう
といった課題に心当たりがある場合は、ぜひ一度HRBIZにご相談ください。エンジニア採用に精通したプロ人事が、要件整理から母集団形成、採用広報、面接設計、入社後のフォローまで伴走します。
エンジニア採用にお困りならHRBIZのプロ人事と解決
即戦力の人事プロを、柔軟かつスピーディーにご紹介!【無料】お問い合わせはこちら
即戦力人材の採用にお困りではありませんか?ハイスキルなHR人材をスムーズに採用できる【HRBIZ】
HRBIZでは優秀なHR人材をご紹介しています。スキルのみならず人柄も踏まえ、企業様にマッチした人材を、最短で即日ご紹介できます。即戦力人材の採用にお困りの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。